「聴こえざるを聴き、見えざるを見る」|清水高志×松岡正剛|『続・今日のアニミズム』|TALK❷|前編
人類学者・奥野克巳と哲学者・清水高志による共著『今日のアニミズム』の出版を記念する対談篇。第二弾となる今回は、清水高志が編集者で文人の松岡正剛と語り合う。
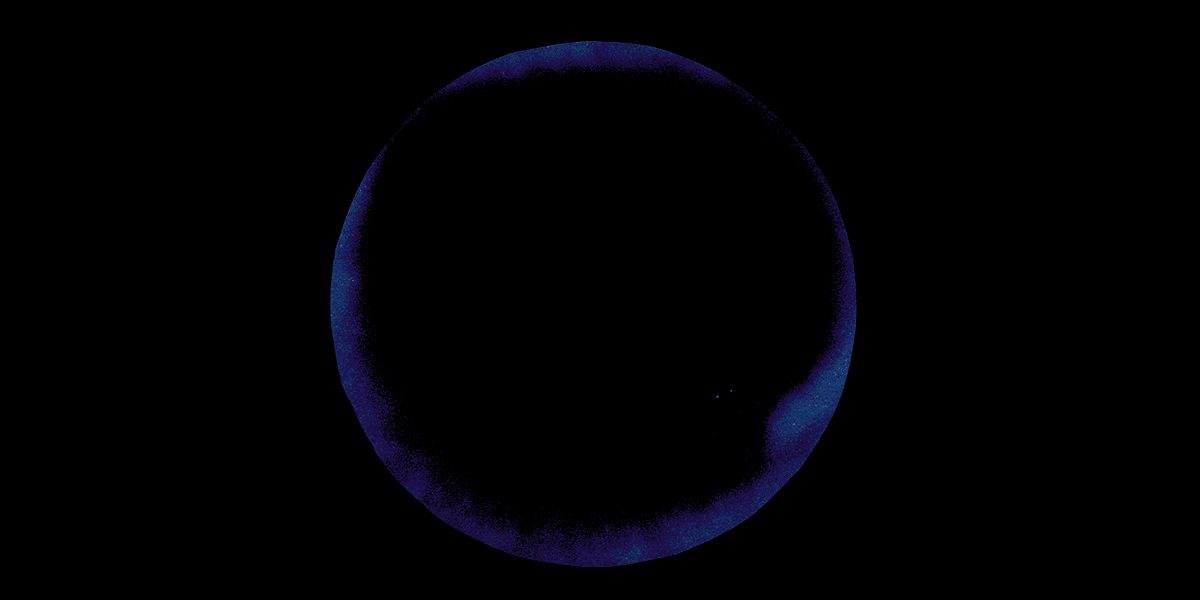
<<「死と刺青と悟りの人類学──なぜアニミズムは遠ざけられるのか」|奥野克巳 × 大島托|『続・今日のアニミズム』TALK❶
アニミズムと仏教思想と西洋人文知を貫通し、古くて新しい知の展望を切り拓いてみせた話題の書『今日のアニミズム』。その共著者である奥野克巳と清水高志がそれぞれ異なるゲストと際会して行う対談シリーズの第二弾、今回は哲学者の清水高志と編集者で文人の松岡正剛が初となる対談を行った。
松岡正剛が主宰するISIS編集学校事務所の本楼を舞台に行われた、あたかも知とイメージの濁流のような本対談の話題はインド哲学、仏教思想、西洋近代哲学、現代思想、果ては文学、国学、民俗学にも展開し、極めて多岐にわたっている。不世出の碩学たちによる曼荼羅模様のように複雑に入り組んだ全3万字に及ぶ対談を、前後編に分けてお届けしよう。
聞き手・文/辻陽介
はじまりのニューエイジャー
松岡正剛(以下、松岡) (ISIS編集学校事務所にて)やぁ、やっとお会いできましたね。
清水高志(以下、清水) はじめまして。松岡さんは在野の知の巨匠なので、学会などで気安くお目にかかることが出来ない。いい機会がないかとずっと以前から思っていたんです。実は、僕は昔から松岡さんのファンの一人なんです。
松岡 へえ、そうなの? 昔というと……
清水 タモリと対談していた頃から知っています。(笑)僕が見たときはさすがに古本になっていましたが。松岡さんが監修したテレビの『極める』も見ていましたし、その後、2000年前後に『日本流』、『山水思想』、『フラジャイル』といった著作が、連峰をなすように出てきたときにも影響を受けましたね。
松岡 『今日のアニミズム』では、仏教とか、もちろんアニミズムもそうだけど、だいぶ日本の話が出てきましたよね、禅も出てくるし。清水さんは、あんまりそういうの書いてなかったんじゃないのかな。
清水 結局、イン哲(*インド哲学)が僕は好きなんですよね。最初から好きなんですよ。中学に入った頃から好きなんです。
松岡 へえ、早熟だなぁそれは。
清水 僕はニューエイジャーなんですよ。中沢新一さんとか松岡さんには青年期にニューエイジの波が来たと思いますけど、子供の頃にそれをもろにかぶったんですね。
松岡 そうすると、ニューエイジってことはパンクやニューウェイブとか?
清水 僕はむしろすっかりインドに傾倒してましたね。行動はパンクでしたが。(笑)
松岡 インドか。シタールのラヴィ・シャンカールとか?
清水 僕は書物からですね。阿部知二さんが翻訳した『ラーマーヤナ』、あれにガーンとやられて。あれは練達の名訳ですよね。当時は異星のまったく違う文明とか、人類学っぽい設定のSFが流行った時代でもあって、僕もル・グィンなんかを読んだりしていたんですが、次第にもはや現代人が描いたフィクションですらないものに強く惹かれていったんです。
松岡 そうか。あっちは? 土取利行が音楽をやっていた…
清水 ピーター・ブルックの芝居『マハーバーラタ』。あれはずっと後で大学生の頃でしたが、もちろん大興奮で観にいきました。『ウパニシャッド』を読んだり…、『バカヴァッド・ギーター』を読んだのが中一の九月くらい、あれにも相当感化されましたね。それで神隠しにあったように、変な世界に行ってしまったような感じです。(笑)
松岡 なるほどねぇ。じゃあ、ミシェル・セールとかは後から?
清水 セールは20歳の頃からです。サーンキヤ学派が好きだったり、自分で理論を作ろうとしていたんですが、インド哲学の用語で語っても、誰にも分かってもらえないだろうと思ったんです。それで概念や素材をヨーロッパに寄せていこうと。
松岡 僕はサーンキヤとヴァイシェーシカに憧れた。木村泰賢の『印度六派哲学』が最初です。イン哲は取り違えられやすいし、当時だとオカルトに捉えられたりするよね。あんまりパンパン書くと。
清水 書きようもないんですけどね、まぁ中学二年とかだから(爆)。それで、最初はショーペンハウアーやニーチェのいるドイツの方に寄せようと思ったんですが、インドとドイツでは全然違うぞと思った。生に対する肯定というものがまるで違うと。
松岡 それは確かにそうですね。
清水 むしろ向かうべきはフランスなんじゃないかと思ったのが10代半ばくらいです。そこから色んな試行錯誤があって、セールに出逢いました。ところで僕は育ちは名古屋なんですけど、母方は香川なんです。
松岡 じゃ、空海だ。
清水 そうなんですよ。なんとなく空海にはずっとシンパシーがあって、それで仏教に関心が強いところもありますね。
松岡 そこからセールに辿り着いたのが面白いね。煙草吸っていいかな? (と、優雅に紫煙をくゆらせ始める)
清水 それでセールをやり出したんですけど、彼はそうそう手をつけられない謎の人じゃないですか。学部、修士とずっと研究し続けて論文も書いてましたが、やっとちゃんと論じられると思えるようになったのは、27くらいのときでしたね。西田幾多郎につながる京都学派的な解釈でライプニッツを読み直し、西田、ライプニッツ、セールと並べて補完し合うように読解していく、というスタイルになったんです。今でも僕は大体そういう手法ですね。
松岡 それも大事な着眼点だし、あんまりやれる人はいなかったよね。ライプニッツは、僕も下村寅太郎さんのところに通うようになって、工作舎から『ライプニッツ著作集』を出させるようにしたんですが、僕自身にとってもライプニッツは大きかったですね。僕の場合はセールではなく、ホワイトヘッドから錯交する形でライプニッツにいったんですけどね。
交錯する内と外――『声字実相義』と唯識の認知哲学
清水 松岡さんは若い頃から、仏教やイン哲にも関心を持たれていましたよね。
松岡 そこらへんへの関心は最初からちらちらあったんですよ。イン哲や仏教は言語観とか価値観がまったくヨーロッパの哲学とは違うので、それこそショーペンハウアーのミットライト・ペシミズム(*共苦、厭世主義)が届かない何かを最初から持ってるんですよね。それと、今いわれたライプニッツとか西田とか。ただ、僕は西田に対してはずーっと、いまだに不満があるんです。
清水 表現やスタイルといった点についてですか?
松岡 いや、彼の生き方は好きですね。悩み方も好きなんですが、ただ西田の場所論が果たして完成しているのかという点にはずっと疑問がある。僕としては西田には絶対矛盾的自己同一とかの解明にもっといってもらいたかったんですよ。好意はすごく持っているんだけど、どうも物足りないんです。もっと「無の場所論」に向ったほうがよかった。中沢くんも一時田辺元(*西田の弟子で京都学派を代表する哲学者の一人)に行ったね。
清水 そうですね、最近それで西田とか華厳にも触れられるようになりましたね。今回の僕の本にも、西田の影響がやはりあるんです。西田が語っていたようなことを形を変えて語っているところがある。西田は西洋哲学をガーッと吸収した上で華厳へと向かったじゃないですか。ただ、僕はそこをもう一歩進めて密教まで向かいたいという欲求が昔からずっとあって。
松岡 それは一番いいコースだね。華厳から密教へというのは明恵上人が辿った道でもある。ただ、意外に現代哲学や現代思想ではその道があまり追われていない。
清水 どうもそうですね。
松岡 法蔵(*華厳宗第三祖)とか澄観(*華厳宗第四祖)以降、禅もそうで、華厳から禅と密教が二つながら出てくる、これを捉える人があまりいない。中国でもいないんですよ。ヨーロッパでは仏教学や東洋学が今は大したことなくて、アメリカン・スピリチュアリズムにみんないっちゃってるけど、そこはぜひやられた方がいいです。
清水 僕はアニミズムと華厳的なものを接続していくことが、その道を復元していく一つの方法になるんじゃないかと思うんです。ただダイレクトに空海とかに接続するのが難しいのは、空海は彼なりにサイエンスというものを肯定しようとしているんですが、その肯定しようとしているサイエンスが古代のものなんですよね。だから今日の我々からするとちょっと分かりにくい。
松岡 それは仕方ないよ。当時は錬丹術とかの時代ですから。丹生(にゅう、水銀を含む鉱物)を煎じて服餌するとか、硫化水銀をちょっとずつ吸って仙人になるとか、そういう術でしかなかった。サイエンスと言っても錬金術的な錬丹術です。でもそれはしょうがないよね当時は。中国の葛洪(かっこう)の錬丹術に近いものを空海や玄昉(げんぼう)や、役行者のような連中はやっていたわけです。神農主義というか本草学ですね。それが少しロジカルになり、サイエンティフィックになるのは、三浦梅園や稲生若水(いのうじゃくすい)とか、江戸時代の国学が起こった裏側でやっている中国的サイエンスがおこり、それに加えて志筑忠雄のようにヨーロッパのものを入れている人のころになると、サイエンスがぐっとでてくる。梅園の反観合一の条理学なんてのは、けっこうロジカルで、かつアナロジカルです。空海や玄昉の時代では無理です。ただ、ライプニッツとかのもっと奥にあるプロティノスとか、グノーシスなんかを見てみると、あれもサイエンスと言えばサイエンスなんだよね。そういうものを取り出していけば空海についてももっと書きようがあるかもしれない。
清水 僕は空海は『声字実相義(しょうじじっそうぎ)』から分け入っていくのがいいんじゃないかと思ってますね。空海の中ではあれが最も華厳っぽい。
松岡 ああ、いいですよ。『吽字義』とともにね。
清水 華厳には「主伴依正」のような思想があるじゃないですか。ディペンダントなもの(依)とインディペンダントなもの(正)が、相互に立場を入れ替えるという。道元だと「身心依正」、あるいは『声字実相義』だと「内外の色は互いに依正にして」なんていう言葉も出てきますね。最澄なんかは、この「依正」という語を輪廻転生における「正報」と、その拠りどころとなる環境「依報」の二つの略語であるとして解釈しているようで、「依正」という言葉に注がつくと必ずそれがでてきて分かりづらくなってしまう。輪廻がどうとかではなく、これは唯識から相互入れ子の華厳が出てくるあたりの論理を密教的に展開してるところですね。そして空海も『声字実相義』では、それを内と外が入れ替わるという風に表現しているんです。
これは松岡さんの関心とも近いですよね。今回、対談前に松岡さんの『擬』という本を読み直したんですが、多和田葉子のエクソフォニー(*母語の外に越境した言語のあり方を考える)という主題に触れつつ、内と外の問題がやはりしっかり語られていた。ここは大きな問題なんだろうと思うんですね。
松岡 大きいですね。『声字実相義』というと、あれは書き方もすごいよね。スタイルをパッパッと切り替えて変化していく。がらっと偈に入ったり頌に入ったり。突然スローガンが「五大にみな響きあり」という風にでてきたり。普通の仏教学ではない。
清水 面白いですよね。空海は地・水・火・風・空の「五大」に識大も並べて「六大」としているわけですけど、「識」のようなものがマテリアルなものと同列に並べられているんですよね。これは深い。
松岡 認知哲学です。
清水 そうなんです。それで言うと、唯識思想は色んな人が研究されていて、僕も好きでよく読むんです。すごく面白いですね。唯識においては識の中に「見分」と「相分」という区別があって、主体と対象らしきものがある。「見分」は主体側、つまり見ている側なんだけど、そこには眼識とか耳識とか鼻識とか五感に相当する前五識というものがあり、それによって「相分」である対象に関与しているとされる。また、それをさらに第三者的に包摂しているものがあり、それが自証分である、と言うんですね。古くはこの「三分」で「識」の構造を考えた。そして、その「識」もまた相互入れ子的に他の誰かの相分になっていく。そこから華厳的なネットワークが出てくるわけですよ。
共に、合流する――偶有性について
松岡 華厳も出てくるし、一方に阿頼耶識(あらやしき)の方へ向かっていく道もあります。阿頼耶識についてはまだ誰もちゃんとやれていないんじゃない?
清水 踏み込んでやってないですね。比較思想学会なんかでは、ベルクソンと結びつけて阿頼耶識を論じている人なんかがいますね。ただ、そういう話になるとイン哲の先生たちが「じゃあ輪廻はどうするんだ」という風に食いついてきて、ぶち壊しちゃう。(笑)ああいうのを見ると、僕はちょっと違う方向に向かいたくて、この本でも仏教にラトゥールを接続したりしてるんです。
ラトゥールの議論というのは要するに、研究者のさまざまなアプローチのような、複数の主体のエージェンシーがあって、ある一つの軸に向かって競合していくと、それに対するフィードバックの繰り返しによって科学の対象というものが立ち上がってくる、というものですよね。唯識で、眼識とか耳識とかをずらっと並べて「相分」との間のフィードバック・ループで考えるというのと発想としては近いんです。ただ、ラトゥールはセールから出てきた人で、僕は好きなんだけども彼が見ていたのはそこまでで、それはあくまでもネットワークの網の目の一部に過ぎないんです。仏教で言ったら唯識から華厳に行く展開がない。
松岡 そんな感じがあるよね。僕もラトゥールには不満があった。
清水 そう。だからラトゥールのような形だけじゃなく、あれをもう一回、全体構造に戻していかないといけないと思うんです。セールが『ヘルメス』の中で考えていたように全体的な網の目を作っていく必要がある。その際、主体が対象を作り出すということを否定的に考えてはいけないと思うんですね。今日では主体が対象を作るという考えに対し人間主義的だという批判が寄せられますが、それは違っていると思う。
たとえば松岡さんがよくご存じの日本的な美学においても、「用の美」なんてことを柳宗悦がいうわけですよね。これは道具や対象を人が様々な形で用いること、弄くりまわすことによって、逆に対象のエージェンシーが際立って、人間臭さが脱色されたものが出てくるという話だと思うんです。茶器なども多くの人が玩弄し、売り買いしているうちに作者が意図しなかった効果がでてくるのを有り難がる。
主体がいっぱい関与することで出来上がったものは作られたもの(対象)なんだけれど、それがまた折り返してまた別の結節点に向かっていくというか、作る側になっていくというモーメントがある。これをセールは『ヘルメス』の中で「主体-対象的段階」の次にくる「対象-対象的段階」と呼んでいます。華厳の四法界説で、理事無礙のあとに事事無礙が来るような展開ですね。
松岡 ふうむ。そのこと、書けばよかったのに。(笑) 当っているよ。
清水 実はセール本人と会った時にそういう話をしたんです。色んな話を三時間くらいして。彼が「僕は前置詞の哲学というのを考えているんだけど、日本にはそういうのはないのか?」とも聞いてきて、困ったんですが「否定の接頭詞の哲学ならある」と答えました。(笑)阿はサンスクリットで否定の接頭辞だけど、密教には「阿字本不生(あじほんぷしょう)」のように、そこに「不生不滅」とか、空の思想を読み取っていく思想があるので。
松岡 八不、ナーガールジュナですね。主体が積極的に関与している、ということを主体主義、人間主義と思わないほうがいい。そこを日本がうまくやってきたというのは、そうなんですね。おそらく日本の場合だけではなくて、そういう考え方はエージェント思考なんですよ。主体をエージェントに代行させている。「見立て」とか、「寄物陳志」(物に寄せて思いを述べる)とか、「物」だとか「事事」、「理事」というふうに託していく。そこから枯山水のように岩や砂を山水に「見立て」たりする方法も出てきます。それはヴァーチャルに代行したエージェントなんだけれど、その時にオブジェクトとサブジェクトが内外一緒の相依・相即状態であることを想定しているわけです。そういう例はもう万葉の歌の中にもいっぱいあるので、そこが前置詞の問題というより、「係り結び」になるわけです。そういう「代行性」による見立ては、その後ずっと歌舞伎だとか俳諧だとか、世阿弥などにも出てきますね。そうした「見立て」的なエージェントの思想が、ヨーロッパの思想には、それこそライプニッツからセールに至るまで、まだまだ足りないような気がするんです。
代行できる物が、ブラウザのように、アプリのように、ソフトウェアのように外へ出ていくという手法がちょっと足りない。たとえば楽器を打つとか、声を出したときとかに、松なら松、梅なら梅がそこに「うつる(移る、映る、写る、うつろう)」わけです。もちろんドラッグの力を借りることもあれば、あるいは奥義のようなものによる場合もあるけれど、そのときずっとその作用が、主体によるものだとは思ってはいないと思うんです。変化し続けていくものだと、日本の「見立て」の思想では考えられている。ただ、きちんとそれが思想化はされていない。柳宗悦じゃないけれど、「下手物にも何かがある」とか言い続けるだけで終わってしまっている。
それともう一つ、そこに僕はコンティンジェンシー(*偶有性。con-tingencyは、語源的にconは「共に」tingentは「合流する」という意味を持つ)というものがあると思うんです。物に代行させてエージェント化したときに、こっち(主体)側からもコンティンジェントな、ダブル・コンティンジェントなものが合流するように出てくる。
さっき清水さんが言ったような、イン哲とか華厳から密教への推移があったときに、そうしたものもバッと出てきていた感じがします。
清水 おそらく今日、松岡さんが偶然性(偶有性)の話をされるだろうと思って、僕が過去に訳したセールの『作家、学者、哲学者は世界を旅する』という本を持ってきたんです。

松岡 ああ、それはまだ読んでないですね。
清水 この本の最後の方でセールは同じことを二回言うんですよ。「もろもろの関係(Relations)があるなら、その理由(Raison)がある。もし現実(Réel)が合理的(rationel)であるなら、諸関係(Rapports,Ratio)がそれをいっぱいに満たし、それを基礎づけ、それを堅固にしている。ところで、あらゆるものが予測可能なものではない。偶然なもの(Contingent)が存在する。もし現実が結びつけられた(relié)、関係的な(relationnel)、宗教的な(religieux)ものであるなら、現実を貫いてあらゆる種類の結びつき(Liaisons,re-ligare)があり得る」、これですよね。
松岡 まさにその通りだね。
清水 ここは絶対に松岡さんのツボだろうと思ってたんです(笑)
松岡 その通りだ(笑)
清水 コンタンジャンスには「共に合流する」という意味がありますよね。それは偶然的なる物に合流するんです。ライプニッツもそこを踏まえていたと思いますね。ライプニッツは「観念とは何か?」という論文で代数的関係の話をしているじゃないですか。
松岡 代数というのは代わりだから。
清水 ギリシアにおいてもロゴスというのはもともと分数や比が表わすものですよね。でも比を体現しているのはモノだったりする。ピラミッドとその影、杖とその影がどちらも1:1とか。その時刻にピラミッドの影の長さを測ってピラミッドの高さを推定したというのは有名な話ですよね。ライプニッツにとって、比や関係はいくらでも操作できるんです。何等分するというような代数的操作は、有限のなかで無限にできる。しかし、それをいくら足していっても、ゼノンの「アキレスは亀に追いつけない」パラドックスのように、全体はけっして構成されないというのが、ライプニッツの連続体合成の問題ですね。むしろ物が全体としてまずあって、そうした代数的観念を無数に含み、体現している。それらの観念が、物に合流しているというのが、「観念とは何か?」でライプニッツが主張したことだった。――ピラミッドと杖をつなぐ。それがRelation、個々の物を超えてそれを含む関係であり、それが予測ということを可能にする。それもあるけど、物がまた全体としてそれらの関係を含んでいる。そこに相互包摂や対象ということが出てくると思うんですよね。コンタンジャンだし、対象が「うつる(映る、うつろう)」ということ。
松岡 これはちょっとあらためて読んでみないといけないね。「うつる」は移るであって、写る、映る、感染するですからね。
バックミラーに見える未来
清水 松岡さんの思考でいくつか、僕は気になっているところがあるんです。日本論でもバイナリー(二項対立)を非常に効果的に出してきますよね。日本人が偏愛する、独特の「対の思考」というものに着目する。また松岡さんが『擬』で挙げられていた蕪村の句、「凧(いかのぼり)きのふの空のありどころ」、あれはすごく分かる。すごくいいですね。あそこに松岡さんの思考の核心がある。
松岡 そうですね。
清水 今回の本では岩田慶治の話もしているんですが、岩田は『木が人になり、人が木になる』という本で、白地に柿がいくつか描かれた図を描いてるんですよね。この図の余白の部分はどこかと言ったら、普通はその白地の部分だと思うわけだけど、岩田はその柿の部分を絵から切り抜くと、そこに開いた穴以外の全てが余白になると言うんです。白地はその余白の一部でしかない。つまり、普通なら二次元の平面で捉えてしまうんだけど、それを挟んでいる三次元の空間があるというんですね。これはまさに「凧(いかのぼり)」ですよね。そこを切り抜いてしまうと、海中を覗き込むタコ眼鏡みたいに、時空を超えて色々なものが出てくる。
松岡 そうそう、タコ眼鏡なんだよ、タコ・ブラウザというか。岩田さんはそういうところを、パッと見抜く目をもっていました。ユクスキュルの「抜き型」みたいなね。
清水 編集工学のディマケーション(分景)という手法も、ひとつ開けたところから見えてくる世界についてのものですよね。僕はその抜いた穴から、ある意味空間的な「一即多」の関係がでてくると思ったけど、松岡さんはそこに時間を超えた、「きのふの空」とか、「日本の文化」を眺めている。僕にとってもそこがツボなんです。これは道元で言ったら「現成公案(げんじょうこうあん)」の話ですよね。鳥がいて魚がいて空があり水がある。その主客が一体となったところから全機現へ、つまり鳥や魚が環界と溶け合って躍動するひとつのあり方が、あらゆる世界の万象にそのまま通じて一体であるということが、「現成公案」では謳われている。松岡さんもまさにそういう話をしているんだけれど、それを文化的な話のヴァリエーションとしてどんどん展開していけるのがすごい、と。(笑)
松岡 まあ、僕は無責任だからね(笑)。それともう一つは、禅で言う「朕兆未萌(ちんちょうみぼう)の自己」のような、《まだ私にならない自分》が思索するということにずっと焦点を置いているせいもありますね。確立した自己というものをあまり想定していないんです。確立したら終わりだとは思わないけど、大変になる。蕪村なんかもそうだし、芭蕉にもそんなところがある。「よく見れば 薺(なずな)花咲く垣根かな」という句があるけど「それ、見えてるじゃん!」と。(笑)つまり、視野を移動させて、自分の中の「未熟な自己」を上手く使うんだね。未熟で未成で未萌な、いまだ萌えていない自分が、今これによって萌えている。この「萌」の状態を哲学の奥にしまいこんでいるところが蕪村の句のうまいところだし、そういうのは俳諧にもあるし、世阿弥にもあるね。「残念な」(*妄念を残した)もの、失敗して何かを失ったものとしてのシテがワーッと橋懸かりから出てくると、現実を主体的に見ていた「旅の僧」が、移り舞の状態に変移、転換していく、という風に。
清水 未萌、つまり未到来でもあるし、過ぎ去っているんだけれど残ってもいる、両方あるという感じですね。
松岡 その通りです。バックミラーで後ろを見ているから、過ぎ去ったものも変化するし、いっぽうで未来もまた見方が変わるわけです。過去・現在・未来、三つ全部があるんですね。仏教では三世実有とか過未無体といいます。
清水 この、「うつ(移、映)っている」というところが勘所ですね。たとえばライプニッツが円錐からその切断面としての円錐曲線の観念を引っ張ってくるというとき、一部それを観念として取り出せば十分なんですよ。代数的な無限の操作というのは有限の物やモジュール、記号操作のうちにある。よくライプニッツはイクノグラフィ(平面分解図)ということを言うんですが、平面分解図をひとつ取り出してきただけで、立体を作っただけの意味がある。それがあれば立体を「作れる」からです。ライプニッツもまた、そうしたものを取り出そうとしている。
松岡 それは面白い。清水さんは随分といろんなことに気がついてるね。あんまりいないよ、そこまで気がついている人は。
清水 (笑)ありがとうございます。
プラトンからプラトンへ
清水 最近僕は、あらためてプラトンを読んでいるんです。以前松岡さんが千夜千冊でセールについて書かれたとき(1170夜)に、プラトンの『国家』についての記事にもリンクがあって、そこでプラトンの『パルメニデス』を読まれて立ち往生されたと書かれているのを見たんですが、僕も去年『パルメニデス』を読んでうわっとなったんですよ。あの本は後半でほとんどわけがわからなくなっていく。僕は『今日のアニミズム』で「一と多」の問題を考えるためには、その他の何種類かの二項対立を同時に考え、またそれらどうしの関係性を変えていく必要があるということを書いたんですが、実はプラトンもそれをすでにやっているんです。『パルメニデス』でも「一と多」の問題が語られているわけですけど、「一と多」というバイナリーには違うバイナリーが組み合わさっていて、それを認めずに単独で「一」や「多」そのもののイデアを語ろうとすると、何も語れないことになって破綻する、ということが論証されているように思うんです。
松岡 僕はプラトンはそれを分かっていながら、やっていないのではないかと思ったんだけど…、やってるかな?
清水 やってるように僕は思いましたね。最近、山内志朗さんがスコラ学者、プラトン学者としてのドゥルーズという本を書いていたんですが、目から鱗で。プラトンは『ソピステス』が非常に重要なんですよね。あそこに核心がある。
松岡 そこは、さっきの華厳と密教の間ぐらいというのと同じだよね。
清水 プラトンだと重要なのは、『パルメニデス』、『ソピステス』、『ティマイオス』、のラインですね。『ソピステス』は40、41の終わりあたりが特に大事なんです。たとえば『パルメニデス』では、若いソクラテスがパルメニデスにめちゃくちゃに論破されちゃうじゃないですか。『ソピステス』はその意趣返しとして読めるんです。パルメニデスは、すべてを包摂する「一なるもの」だけがあり、そしてそれだけが「有るもの」なんだということを言った人ですよね……。『ソピステス』では「エレアからの客人」というのがわざわざやってきて、師のパルメニデスの説を否定する論証をする。――どんなものかと言うと、「有るもの」の対立項は「非有」ではない、つまり「無」ではないということを主張するんです。そこには「~であらぬ」というものがくるんだ、と。「~であらぬ」とはつまり、「異なるもの」ということですね。「~がある」と「~であらぬ(異)」は、同じ「being」なんだけど違う。「~であらぬ(異)」は述語であって、本来「~がある」を包摂する側のはずなんですよね。パルメニデスは、一方的にすべてを包摂する「一なるもの」に固執して、それ以外のあらゆるものを否定していったんですが、「~であらぬ(異)」ものが「有る」ということは言えるんだと「エレアからの客人」は主張する……。
つまり述語の否定形が、もう一度主語の位置に置かれることによって、『ソピステス』では包摂関係が循環構造になって、無効化されているんです。「一なるもの」だけがあるのではなくて、「異なるもの」がどんどん循環構造のなかで増殖する、そういう論理が、ここではっきり出ている。これはもうヨーロッパの弁証法そのものなんですよ。スコラ学のドゥンス・スコトゥスなどもみんなそうなっている。二元論をこの構造に繰り込んで、「being」の二重性によって繋いだ回転仕掛けの中をずっと回っている。ドゥルーズの『差異と反復』もそうですよ。このロジックで彼が、現代のものまで読み込んでいるというのがすごい。このプラトンが扱った問題のしつこさというものには本当に驚きますね。
松岡 しつこいだけではなくて、さまざまな思考の萌芽を含む表現方法に気づいたというのもあるでしょうね。対話篇にしているのもそうだし、洞窟の比喩を筆頭に、あらゆることを表象する方法に気がついたというのはすごいよね。エイドーラ(イドラ=偶像)にピンときてたんだろうね。だから確かにそれがまだドゥルーズにもあるのかもしれない。
清水 ヨーロッパのロジックというのは排中律を前提としているんですけど、あれはある個物がより一般的なものに含まれている場合に、判断として言えることですよね。「薔薇は植物である」とか。このとき薔薇はけっして動物には含まれない。しかし逆に、イデアのような一般的性質が個別のもののうちに含まれるんだったらどうか。『パルメニデス』で、若きソクラテスが言っているのもそういうことです。つまり、含まれる、属するというのには個別が一般を含むか、一般が個別を含むかの二種類ある、と。後者の場合は排中律が成立してしまうけど、前者の場合は一般概念への個物の分類ではないので排中律があてはまらない。だからソクラテスはあえて「大きさそのもの」「小ささそのもの」という一般概念、つまりはイデアを立てて、個物がそのイデアを分有すると考えたらどうかと提案した。そうすればあるものが「大きくかつ小さい」ということも成りたつようになる。「大は小である」とか、「小は大である」のような矛盾したことをいっているわけではなくなる、と。
しかし、これはパルメニデスによってボコボコにされちゃうわけですね。もしイデアを分有するというのなら、それはその部分の分有に過ぎないだろう、と。それとは別にその部分を含み込んだ「一なるもの」としてのイデアそのものがあるはずだろう、と。この包摂関係を循環的にしようとしたのが『ソピステス』だし、『ティマイオス』まで読み進めてみると、二項対立的なものがそれらの性質を合わせ持つ第三項的なものによって調停されるという話が繰り返しでてくる。さらにはこの第三項の位置を一巡させるということを、比例式を操作しながら考えたりしてますね。エンペドクレスの水火風土、あるいはそこから派生した熱と冷、乾と湿という二項対立も、もともとはそうした操作のなかで考えられていたようなんです。どうも当時、イタリアの方に住んでいた奴らの方がソクラテスよりも二、三段階、進んでいて、それが隠されていたのか、よほど素朴な連中をあいだに挟んでしか伝わってなかったんじゃないかとも思えるんですよね。
松岡 とすると、プラトンもイタリアに対しては思うところがあったんだ。ピタゴラスとかね。
清水 そう思いますね。自分たちよりももっと優秀な人たちがいたはずだという、何かそういう思いがあるから、『ティマイオス』ではアトランティス神話を語ってみたりするんじゃないか、と。多分、そういう状況のなかで、ヨーロッパを駆動している論理が祖型的に一気に展開されていたんだと思います。
松岡 それは大きな見方だね。プラトンの読み直しか。清水さん、その話をちゃんとやった方がいいよ。
清水 やりたいですね。翻訳の直しみたいなことばかりしてますけど(笑)
同時通訳的思考――「主語化以前」を可視化する
松岡 清水さんはなんでそんなに翻訳をするの? 400も注を付けたりして。大変でしょう?
清水 僕はセールが表現のレベルでもまともに翻訳されたのは、これまであまりないと思っていたんですよね。だから絶対自分が納得のいくような形に訳したかったんです。
松岡 語学に負担感がないんだ?
清水 いや負担はあるんですけどね。ただ、ずっと若い頃からセールを読んでいるから、日本語でセールのように表現したいと思っていたんです。
松岡 僕もかつて10年間くらい同時通訳のグループを預かっていたんですよ。英日・日英、露日・日露、それから仏日・日仏。イタリアはチームに入っていなかったけれど、外に天才がいた。通訳というのは英語的なものやロシア語的なものやフランス語的なものを、日本語にしていかなきゃいけない。しかも同時通訳だから相当に速くやらないといけないんだけど、すると日本語の力を思い切って上げておかないと、いくら英語が上手かったりフランス語が上手かったりしても通訳になりません。その日本語の錬磨は松岡さんだろうということで、付き合うことになったんです。
その時によく分かったんだけど、トランスレートというのは読むとか、解釈するとかの基本です。しかも通訳的なものになるとシャーマン的でアニミスティックになってくるので、たとえば「この志野の茶碗は」、「備前は」と言ったときに、どうやってこれを通訳すればいいのか。「志野」っていうのも説明しなきゃいけないし、いやいや「備前は」ってことも言わなきゃならないし、「焼き」は、「焼き成り」は、「景色」は、といった言葉はほとんど英語とかフランス語にはないので、そこも補わなければならない。だから、それを近似的に言うための範囲を彼らが設定していたんです。それが日本語的にどうなのか、僕のほうで説明して修正するということをずっとやっていたんですね。
だから、清水さんがセールの訳をここまでやられているのを見ていると、非常に面白いんです。大変なんだけど、同時通訳的にやっている。日本語の責任を清水さんはきちんと取っているよね。
清水 ありがとうございます。そうなんですよ、セールを原書で読み始めたのは21のときかな……。セールを日本語に訳すために、幸田露伴を読むとか、ボキャブラリーを増やさないと駄目なんですよね。
松岡 露伴読んだの? 露伴をそこで読んだというのは大正解だね。だから 『声字実相義』もそれですよ。空海は半分以上を向こうの翻訳、通訳をしながら当時の日本語に切り替えていくんです。その切り替えのインターチェンジ、トランジット・ポイントが非常に空海の場合は天才的ではあるけれど、基本の作業は同じです。それにしても、よく気がつくね、露伴でいいって。露伴は江戸語を明治語に翻訳したのだけれど、そのことを示唆したのは淡島寒月です。
清水 (笑)日本語を豊かにしていかないと、とにかく太刀打ちできない。セールには独特の言い回しがあるんです。たとえば「炎の舌のように」とか。これは至るところランダムに盛り上がったり、窪んだりする感じ、空海の『十住心論』だったら沖まで続く海の波頭の揺らめきで表現するような、海印三昧みたいなイメージですね。普通には通じないだろうという言い方をいっぱいしてくるんですが、それが阿吽の呼吸で分かるようにならなければいけない。たとえばセールはよく「Voila!」(*ほら、など多様なニュアンスがあるフランス語)という語を用いるんですが、その「Voila!」がどういう「Voila!」なのか。それこそピカチュウが「ピカチュウ!」って言っているだけなのに、すべて阿吽の呼吸で察して分かってあげるくらいの、ポケモンマスターのようになっていないといけないんですよね(笑)
松岡 そうだね。あとは、表意文字ってものが気になるよね。西洋の人たちにとっては、文字は綴りですよね、それとグロッサリー(*用語辞典)。それに対して空海や蕪村たちには表意文字が見えていますよね。「山」とか、阿字観の「阿」とか。ああいうものに僕はまだ手をつけられていないんですよ。東洋を扱うとき、最後はフォントではなくて文字霊というか、文字魂、そういう文字のアニミズムというものが不可避なんだけど、まだちょっとうまく言えないなぁ。清水さんは表意文字と表音文字の違いはあまり感じない?
清水 いや、そこはとても大きいですよね。インドのあのガチガチに練り上げられたロジックが、いったん中国を通るとどこかモヤっとしてしまうんです。それはなんでなのかと考えてみると、文字の問題だと思うんですよ。表音文字にすると中国だと言語に地域差があるので、スペイン語とポルトガル語のように言語が分裂してしまうと思うんですよね。そこを表意文字でふわっと繋いでいるから、言ってみれば手話のようなもので、そこで抽象度が下がってしまうんです。
松岡 その手話っぽいというのは面白いね。表意文字っていうのは仮に「止められる」んだよね。綴り字の世界は語根からずっときてスペルになっていて、その言葉のこれはというところをずっと継続できるんですが、東洋の表意文字というのはそこが良い意味でも「止まる」し、悪い意味ではスタティックになる。デリダみたいなフォネー(*音、声の特権性)についての議論は、表意文字側からは出しにくい。ちょっと、そこは僕は不如意なんですね。
清水 サンスクリット語だと、たとえばどういう動詞とか様態を表わす言葉から主語が逆に作られたかということが看て取れますよね。
松岡 中村元さんなんかがそういう話をしていますね。中村さんからは、クマーラジーヴァ(鳩摩羅什)の翻訳力の凄さをいろいろ教えてもらいました。
清水 だんだんそれが、英語みたいに後から整備された言葉になると、主語は主語であって、その主語が述語としてどうだという形になる。それが実はループしているということが、サンスクリットだと分かりやすいんですよ。もともと述語であるはずの「~である」ものが主語になって、だからそうした様態や動作の原因であるということになるんですが、これはナーガールジュナがすごく批判したことですね。「去るものが去る」というのはおかしいだろうと『中論』に書いています。
そうしたショートサーキットと主語の増殖がさっきのプラトン弁証法でも出てくるし、パルメニデスはあらかじめそれを封じるかのように「一なるもの」をどかんと突きつけていたわけです。本来述語側であるはずの、「包摂するもの」が主語化した究極の例が、パルメニデスの「存在者としての一者」なのかも知れないけれど、むしろ東洋では述語的なものが、多様なかたちでお互いを相互包摂することで、主語的なものに原因を帰さない、ショートサーキットを肥大させない論理をうまく作っていった。主語が包摂される場所、コーラ(χώρα)の側から主語化を否定する構造を考えたり、体用論(*現象、様態としての「用」と、その本体としての「体」についての仏教の議論)を考えたりしてるんですよね。
松岡 そうだね、東洋と西洋とではショートサーキットの作りが違う。うーんなるほど。西田がもうちょっと深められたんじゃないかというものそこです。場所、コーラの問題。
清水 西田を、述語の論理からさらに進んで、ただ最大限の包摂者としての場所を構想したんだ、という風に読んでいる解釈がすごく多い。そうした一方向的な話ではなくて、あれはあくまでも相互包摂の話として読まないといけないのに、一般的に誤読されていると思いますね。晩年の西田はライプニッツに近づいていくんですが、ライプニッツを西田研究者で読める人が少ないので、どうしてもヘーゲルとかに寄せて読まれがちなんですよね。
僕は西田は場所論のあとに、またもうひとつ進歩したという風に感じています。鎌倉に行ったあと、昭和八年から始まると思っているんです…。
松岡 ああ、家族を亡くしてからだね。「無の自覚的限定」なんかも面白かったね。
清水 面白いですよね。西田は中期がごちゃごちゃしている。むしろジェイムズの話をしている初期のものとか、最晩年の「絶対矛盾的自己同一」とか、ああいうものが面白いですね。
✴︎✴︎✴︎
清水高志 しみず・たかし/1967年生まれ。哲学者。東洋大学総合情報学科教授。主な著作に『セール、創造のモナド──ライプニッツから西田まで』(2004)、『来るべき思想史 情報/モナド/人文知』(2004)、『ミシェル・セール──普遍学からアクター・ネットワークまで』(2013)、『実在への殺到』(2017)、『脱近代宣言』(2018/落合陽一、上妻世海との共著)、『今日のアニミズム』(2021/奥野克巳との共著)など。
松岡正剛 まつおか・せいごう/1944年、京都生まれ。編集工学研究所所長、イシス編集学校校長、角川武蔵野ミュージアム館長。70年代にオブジェマガジン「遊」を創刊。80年代に「編集工学」を提唱し、編集工学研究所を創立。その後、日本文化、生命科学、システム工学など多方面におよぶ研究を情報文化技術に応用し、メディアやイベントを多数プロデュース。2000年「千夜千冊」の連載を開始。同年、「イシス編集学校」をネット上に開講し、編集術とともに世界読書術を広く伝授している。
✴︎✴︎✴︎
〈MULTIVERSE〉
「あるキタキツネの晴れやかなる死」──映画『チロンヌプカムイ イオマンテ』が記録した幻の神送り|北村皆雄×豊川容子×コムアイ
「パンク」とは何か? ──反権威、自主管理、直接行動によって、自分の居場所を作る革命|『Punk! The Revolution of Everyday Life』展主宰・川上幸之介インタビュー
「現代魔女たちは灰色の大地で踊る」──「思想」ではなく「まじない」のアクティビズム|磐樹炙弦 × 円香
「生死観」としての有機農業 ──エチオピアで学んだ生の豊穣|松下明弘
「病とは治療するものにあらず」 ──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践
「俺たちはグレーな壁を生き返らせているんだ」──1人の日本人がまなざしたブラジルのストリート|阿部航太×松下徹
「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝
「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話
「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー
フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介
「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄
「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生
「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美
「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介
「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く
「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎
「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰
「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義
「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志
「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾
「死と刺青と悟りの人類学──なぜアニミズムは遠ざけられるのか」|奥野克巳 × 大島托





















