私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね? ──エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
移民と出稼ぎが多く流入するエチオピアの農村においては、家と家との垣根が低く、システムに多くを頼ることのない、自律的で相互浸透的な生が営まれているという。90年代末よりエチオピアの農村をフィールドワークしてきた文化人類学者・松村圭一郎氏に話を訊いた。

現代社会の生きづらさを、政治や社会、法律やルールなど「システム」のせいにして語ることは、とても簡単だ。あるいは人類学の本などを読んで、その本が記述する「遠く」の人々の暮らしをロマンチックに憧憬し、あたかもそこがユートピアであるかのように賛美した上、そうなってはいない自分たちの暮らしを社会のせいにして失望することもまた、同様に簡単だろう。もちろん、そうした見方にも一理はある。しかし、それはともするとシステム依存的な見方であり、少なくともそこには、自分たちの暮らしを自分たち自身でマネージするという「自治の精神」が欠落している。
1990年代末よりエチオピアの農村社会のフィールドワークを続けてきた文化人類学者の松村圭一郎氏は、こうしたシステム依存的なものの見方に対し「我々の行為の中にこそ政治があり、私たちがここでどう他者と関わるかが福祉の問題であって、格差の問題でもある」と強調する。松村氏によれば、エチオピアの農村社会においては、家と家との垣根が低く、多様な人々が密接に関わり合いながら、デヴィッド・グレーバーが言う「基盤的コミュニズム」を彷彿とさせる社会関係を築いているそうだ。しかし、それは決してエチオピアの農村がプリミティブな理想郷であるということを意味しない。現代のエチオピアには近代化、グローバル化に伴うさまざまな社会問題が山積しており、むしろ、彼らの協働的な暮らしとは、そうした不安定な現代社会を自律的にサバイブするための日々の実践によってこそ作られているのである。
エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神から僕たちが学ぶべきこととはなにか。4月に編著『文化人類学の思考法』(世界思想社)を上梓したばかりの松村氏に話を訊いた。
エチオピアの農村の相互浸透的なコミュニケーション
HZ 松村さんへのインタビューは約一年半ぶりでしょうか。前回は著書『うしろめたさの人類学』(ミシマ社)についての話が中心でした(『STUDIO VOICE』vol.412所収)が、その時、松村さんがお話されていたエチオピアの村における相互扶助についての話は、僕にとって非常に興味深いものでした。そこで今回も再びその話から聞いていきたいのですが、まずは前提として、松村さんがこれまでにエチオピアでおこなわれてきたフィールドワークの内容について、あらためて教えていただけますでしょうか。
松村 エチオピアをはじめて訪れたのは、1998年です。学部の3年を終えたあと1年休学して、友人2人と行きました。海外ならどこでもよかったんですが、ゼミの指導教員がエチオピアの専門家だったので、長期滞在のためにいろいろと便宜をはかってもらえたんです。その10ヵ月あまりの経験がとても衝撃的で、そのあと大学院に進んで、これまでほとんど毎年のようにエチオピア西南部の村を訪ねています。ジンマという町から40キロほどの場所で、コーヒー栽培が盛んな地域です。元国営のコーヒー農園がすぐ近くにあります。最初は、農民が誰の土地をどうやって使っているのか、換金作物のコーヒーと自給用のトウモロコシなどの富が誰の手に渡っているのか、といったテーマで調査しました。それで博論をベースに最初の単著『所有と分配の人類学:エチオピア農村社会の土地と富の力学』(世界思想社)を書きました。ポイントは、ある土地や富が誰かのものになる「所有」ってなに? という問いです。「私のものは私だけのもの」という私的所有権の考え方を相対化する試みでもありました。
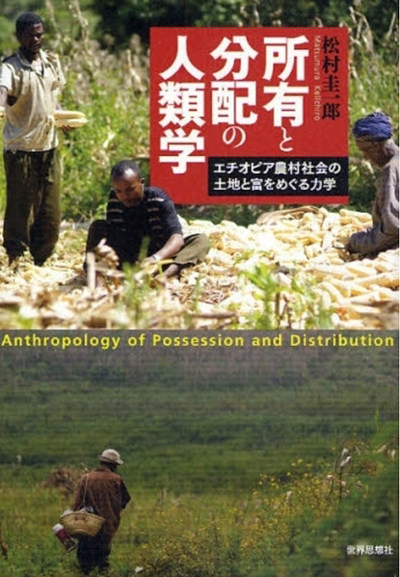
『所有と分配の人類学:エチオピア農村社会の土地と富の力学』(著・松村圭一郎/世界思想社)
HZ ありがとうございます。私的所有権の相対化というテーマは、松村さんの前著『うしろめたさの人類学』にも引き継がれていますよね。『うしろめたさの~』においては、エチオピアの村落においていかに村民同士が緊密に絡み合い、かつ相互扶助的な関係性を作り上げているかということにより力点を置いた記述がなされているわけですが、僕がとりわけ面白いと感じたのは、そうした相互扶助的な生を営む彼らが地縁や民族性によって強く繋がった原始共同体的な存在ではない、という点でした。むしろ、農村には移民も多く、多文化が混在した中で共生している、と。
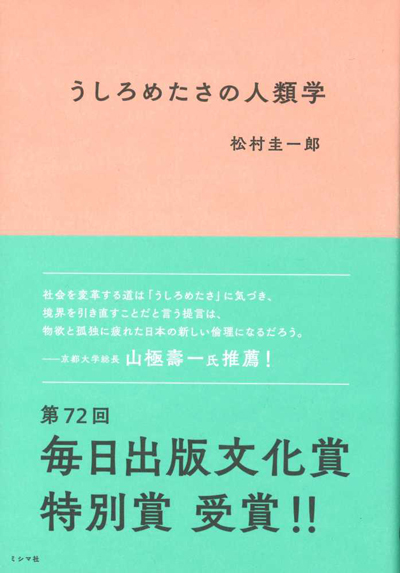
『うしろめたさの人類学』(著・松村圭一郎/ミシマ社)
松村 そうですね。僕が滞在したエチオピアの村には、古くからのカチっとした共同体があったわけではない。よそから移り住んだ人も多くて、宗教や民族も多様でした。いわゆるかつての伝統的で均質なムラ社会のイメージとはかけ離れているんです。コーヒーという換金作物があるので、その富を求めて出稼ぎや移民がくる。すごく現代的で流動的な農村だけど、そうした多様な人びとのあいだでコミュニケーションの回路が開かれているんです。
HZ それぞれが異なる信仰や慣習を持つ人々にも関わらず、個人主義的にではなく、相互に深く関わり合いながら暮らしている。ここに驚いたんです。実際のところ、農村内ではどのようにして人間関係が築かれているんでしょうか。
松村 まず言葉については、アフリカの多くの地域でもそうなんですが、みんなふつうに二言語くらい話すので、あまり問題になりません。エチオピアでは、村でも町でも、その土地のローカルな言語だけでなく、多くの地域で広く話されているアムハラ語など、複数の言語を話せないと生きていけない。そして、文化的差異に関しては互いに尊重し合うことがごく自然になされています。たとえば、僕が面白いなと感じたのは村の人が亡くなった時です。
普通、葬儀というと最も宗教性の違いが色濃く出そうな場面ですよね。しかし、彼らは村民みんなで墓掘りをするんです。亡くなった人の宗教に関係なく、キリスト教徒も、イスラム教徒も一緒に。最後はその人の宗教のお祈りが捧げられますが、あとはみんなそれぞれのやり方で弔意を示す。遺族は一週間、喪に服します。その間、宗教も民族も関係なく同じ集落の人が入っている葬式講が遺族の食事から薪や水の手配まで全部、面倒を見る。遺族はただ、喪に服すための仮設の家で何もせずに過ごすわけです。そこに、村中の人が弔問に訪れます。しばらく黙って座っているだけの人もいれば、ずっと長い時間、遺族とともに過ごす人もいます。とにかく遺族だけにしない。これは、エチオピアで広く見られる習慣ですが、よそから来た異民族も、違う宗教の人も、こういう場で垣根を越えたコミュニケーションを重ねていく中で、多様な人びとの社会関係が築かれていくのだと思います。
ほかにも、家でコーヒーを飲むときは必ず隣近所の人を呼ぶ、というのも村の習慣です。そこでも、宗教や民族は関係ありません。キリスト教徒の祭日には、イスラム教徒の人も「おめでとう」と言いに隣人の家を訪ねる。そういう配慮がごく自然とできている。おそらく、昔はもっと均質的だったと思うんですが、移民が増え、多様化していく中でもそうした協働性がつくられ、維持されているところが、面白いんです。

Photo by Keiichiro Matsumura
HZ 均質性という点で言えば、エチオピアの農村の住人はたまたま寄り集まったもの同士に過ぎないわけで、これは日本の都市の状況ともそう変わらないですよね。あるいは、具体的な信仰を持っている人があまり多くないという点では、日本の都市の方が均質性は高いかもしれない。喧嘩や衝突のようなことは起きないんでしょうか?
松村 喧嘩はしょっちゅうしてますよ(笑)。だから、「相互扶助」という日本語のイメージとはちょっと違うんです。仲がいいから助け合っているわけではない。小学校とかで「みんな仲良く、助け合いましょう」とか言われるのとは対極の世界です。愛憎が交錯する密着した人間関係のなかで、互いに手を差し伸べ、配慮せざるを得ない状況にある、と言ってもいいかもしれません。でも、一方でその関係は閉じていなくて、すごく流動的でもあります。このあたりをうまく伝えるのが難しいんですが。
この前まで一緒にコーヒーを仲良く飲んでいたと思ったら、次の時には、仲違いしてもう一緒に飲んでなかったりする。でも、物理的には近い場所にいるので、たとえば集落の人が亡くなるとか、別のことがきっかけで仲直りするチャンスもたくさんある。関係の回路がコーヒーを飲むだけでなくて、宗教的なものや日常のモノのやりとりなど、つねに複数あるんですね。限られた回路で人間関係が固定することなく、つねに複数の潜在的な可能性のなかで動きながら均衡しているようなイメージなんです。
HZ なるほど、小さな人間関係自体はつねに組み替えられながらも、村全体としての協働関係は維持されているというようなイメージでしょうか。先ほど葬儀の際の慣習の話がありましたが、村の内部にはそうした協働関係を維持していくための決まりごとのようなものが他にも多くあるんですか?
松村 いえ、明文化された「ルール」のようなものはほとんどありません。村内の特定の人物が絶対的な権威を持っていることもなく、困ったら村の年長者たちが相談に乗ったり、喧嘩を仲裁したりします。単純に言うと、みんなとても緩い(笑)。その場その場で臨機応変に問題に対処しているように見えます。
たとえば、村内では、子供がどこの家でご飯を食べようが、どこの家で寝ようが基本的に自由なんです。親と喧嘩して関係が悪くなったりすると、近所の親戚や友達の家に何日もいたりする。家族がそれぞれの単位で完結して暮らさないといけないという考えではなく、流動的で相互浸透的なんですね。
もちろん、まったくの無秩序ではなくて、基本は家族を単位として暮らしています。でも、日中は家同士で人の往き来が絶えなくて、そこで遊んでいる子どもが誰の子なのか、一緒に家事をしている人が家族のメンバーなのか、近所の人なのか、分からないくらい。まあ夕飯時になると、自然に戻っていくんですが、そこにも明確な決まりがあるわけではなくて。コミュニケーションの積み重ねで、いろいろなことが定まっていく感じです。

Photo by Keiichiro Matsumura
HZ 移民が多いということは核家族も多いということですよね。たとえば育児や家事など、そうした家庭内労働はどのように行われているんでしょう?
松村 そこに関しても家族が相互浸透的なんです。つまり、家と家との垣根が非常に低い。たとえば、1歳に満たない赤ちゃんのいるお母さんが、その赤ちゃんを脇にポイッと置いて家事をしている。すると最初は年の離れたお兄ちゃんが赤ちゃんの面倒を見ているんですが、お兄ちゃんも子供だから飽きてどっか行ってしまう。するといつのまにか現れたおばあちゃんが面倒を見ている。やがて、おばあちゃんがいなくなってしまうと、今度は通りがかった近所の人が赤ちゃんをあやしはじめる。こうしてその場にいて手が空いている人が赤ちゃんの世話をする。もちろん、あらかじめ決められたタイムスケジュールや役割分担があるわけじゃありません。
ようするに、家族はこのメンバーで、子育ては母親の仕事といった固定的な役割意識が薄い。「私だけのもの」という領域意識が幅をきかせていない。私の子だからって、私だけが面倒を見る必要ないよね? と問われている気がします。この融通無碍な垣根の低いコミュニケーションは、ずっと観察していると芸術的にさえ思えます。できる人ができることをやり、必要な人が必要なものを受け取る。まさにデヴィッド・グレーバーが『負債論』に書いていた「基盤的コミュニズム」が、エチオピアの村ではいろんな場面に見られるんです。

Photo by Keiichiro Matsumura
僕たちはすでにコミュニズムを生きている
HZ いまグレーバーの名が出てきましたが、グレーバーがいう「基盤的コミュニズム」とはなんなのか、少し説明していただけますでしょうか。
松村 グレーバーは、『負債論』のなかで、負債による人間関係が全面化するような状況を批判しています。負債は、交換のなかで返済が完了していない一時的な状態で生じているだけで、借りたものは返さないといけないといった原則も、絶対的なものではない。人間のモラリティには、そうした交換だけでなく、もっと別の複数の様式が関わっていると論じました。ひとつはヒエラルキーで、明確な上下関係があると負債なんて生じないでしょ、と書いています。たとえば、お金持ちの社長さんからお昼ご飯をおごってもらって、それを返すべき義務のある負債だとは思わない。むしろ、「社長、今度は私がおごります」とか言ったら、失礼になる。もうひとつが、コミュニズムです。これは共産主義という意味ではなくて、どんな資本主義の権化みたいな大企業のなかでもみられる日常的な行為。「それぞれの能力に従って与え、それぞれの必要性に応じて受けとる」と定義されています。たとえば、「そこのハサミとって」とか、「タバコの火、貸してもらえますか?」みたいなやりとり。こうした行為も、返済すべき負債とはみなされない。家族のなかだとほとんどがそうだし、町で知らない人から道を聞かれるとか、ふつうにどこにでもある行為ですね。グレーバーはそれを人間の社会性の根底にあって、社会を可能にする土台だという意味で、基盤的コミュニズムという言い方をしています。

『負債論』(著・デヴィッド・グレーバー/以文社)
HZ グレーバーの議論を踏まえて、松村さんのお話を聞くと、エチオピアの村における基盤的コミュニズムを前提とした関係性は対岸のユートピアの話ではない、ということをあらためて強く意識させられます。ともすると、現代社会の生きづらさや個人主義社会ゆえの孤独などについて、政治や社会に全て責任がある、あるいは近代化や都市化に根本の原因があるという風に考えてしまいがちですが、実はそうではないんですよね。そもそも、エチオピアの農村は前近代的な空間などではなく、近代化を経て世界市場にも取り込まれた、流動的な世界であるわけですし。
すると気になるのは、なぜ日本では基盤的コミュニズムのような行為が、ここまで制限されてしまっているように感じられるのか、ということです。負債が入り込まない行為の範囲がとても狭い。家と家との垣根が非常に高い。端的にいうと、共同体がない。逆にエチオピアの農村において「僕は一人が好きなので近所付き合いはしません」みたいな人は現れてこないんですか?
松村 周囲の評判を落として孤立してしまう人は、たまにいます。ただ、エチオピアで孤立するって、日本で孤立するのとはわけが違う。単純にしんどい状況になるわけですよ。不安定な生活で、病気とか不作とか、いつどんな災いに見舞われるかわかりません。社会保障のサービスもないので、誰かと関わっていないと、身の危険になりかねない。だから、基本的に一人で過ごすことは極力、避けられる。たとえばご飯を一人で食べている人は、村では非常に珍しい。私が部屋で一人で本を読んでいると、こっちにきてみんなのところで読め、と言われてしまいます(笑)

1999年、学生だった松村氏が最初にエチオピアを訪れて半年ほどが経過した頃の一枚。
HZ なるほど。その点に関して言えば、たとえば東京などは、良くも悪くも一人ぼっちで生きていてもとりあえずは安全だ、と言える状況になっているのかもしれませんね。いたるところにコンビニもあるし、自動販売機だって無数にある。交通の便もよく、公共サービスも相対的に充実している。誰かと協働せずとも一人で生きていけると思い込むことができるだけの環境は整っていると言えます。
松村 そうですね。しかし結局はみんなで首を絞めあってるところがあるようにも感じます。人に頼らず、何でも自分でこなしていくためには、コンビニは24時間あいてないといけないし、電車は遅れてはいけないし、機械が間違うようなこともあってはならない。でも、実際のところ機械は誤作動するし、システムは簡単に乱れます。東京で停電があったりすると大混乱じゃないですか。みんな不平満々になる。しかし、本当はこんな複雑なシステムが回っていることの方が驚異的で、恐ろしいことでもあると思うんです。そのシステムを支えつづけるのも人間なので、それを維持するために現場はものすごく疲弊していて、ちょっとのミスも許されないようなストレスフルな環境に置かれているわけですから。
HZ おひとりさまでも安全かつ快適に暮らせる便利な世の中を維持するために、むしろ苦労の総量は増えてしまっているという。さらに、そうした便利さが当たり前のものになったことで、なるべく他人に頼らず、なるべく他人に干渉しないことが、あたかも美徳であるかのように考えられている節もあります。おっしゃる通り、これは首を絞めあっているように感じますね。
松村 たぶんそういう日本のシステムを前提にしたときの人間像がエチオピアとはだいぶ異なっているんだと思います。人間って不完全で、自分ひとりの力だけでは生きられない。エチオピアの村人はそれをあたりまえだと思っている。そう考えると、他人に迷惑をかけることも、他人にお節介を焼くことも、ごく自然なことですよね。誰もが「私だけのもの」に頼っていては、生きていけないので。日本では、システムに頼りながら、自分ひとりで、あるいは家族単位で、人に厄介にならずに生きていけるような人間像がデフォルトになってしまった。だから、相互に瑕疵がないかを見張りあいつつ、できるだけ他人と関わろうとしない。その結果、作り出されているのが、一人一人が誰の世話にもならず誰にも迷惑かけず生きていける社会というのは、どこか倒錯的ですよね。
HZ システム依存と言ってもいいのかもしれません。自分自身、多くをシステムに頼ってしまっているという自覚があります。たしかにその方が楽な面もありますから。
松村 私も日本だと、とても気楽だと感じます。電車もすぐ来るし、どこでも短時間で移動できて便利だし、快適だなと思ったりしますよ。ただ、そこに慣れきってあたりまえだと思ってしまうと、システムが止まった途端に大変なことになる。3.11の震災の時もそうでしたね。僕たちの生活を支えているシステムの脆弱性がむき出しになった。あれから10年と経ってないのに、早くもそれがなかったことのようにされている。システムに依存しすぎる怖さにあの時にみんな気づいたはずなのに、不思議な話です。
私たちは思っている以上に綱渡りの怖いことをやって生きている。日本で、もしいま全システムが機能を停止したら、と想像することがあります。たとえば東京駅で、あれだけ人があふれているなか、水はどこで確保できるのか、食料はどうすれば? と想像を巡らしてみる。 おそらくお店にある商品はすぐなくなりますよね。警察や消防だって機能しないかもしれない。じゃあ、その環境でどうサバイブできるのか。
そんなことを考えて東京を歩いている人って、ほとんどいないと思うんです。そういうサバイブのための思考というのはシステムが健全に動いている状態が日常化すると失われてしまう。だから、まずはそのシステムに依存しすぎることの危うさを少しは意識しなければと思いますね。いざというとき、ちゃんと近くにいる人に頼れることも大切な能力になる。もちろん、それは災害などが起きたときのため、というわけではなくて、この世界への向き合い方、あるいは人間ってそもそもどんな存在なのか、という問いとして意識しておくべきなんじゃないかと。
HZ 海外に出てみると日本の治安の良さを感じることが多く、またそれを美点として誇る文脈もありますが、そこにもアンビバレンツがありますよね。夜道を一人で歩いても平気な環境においては、自衛のための自治の意識、ありていに言えば身を守るためには群れなければならないといった意識が、忘れ去られてしまいがちです。効率だけを求めるなら日々の人間関係の煩雑さを、ルールや制度にアウトソージングしてしまった方がたしかに楽なんですが、これはやっぱり危うい。
松村 ルールとか制度というものは、それをマネージする別の権力を必要としますから。違反者を取り締まり、誰がそれに適合するかを登録し、それによって利益を得たり、サービス提供者を限定したりするシステムが、こうして形成される。さらに悪いことは、そうした権力のようなものを、物事の解決の唯一の手段だと思い込んでしまうことです。ただ、これは錯覚なんですよ。
エチオピアではそうしたシステムや国家というものが、そもそも信用されていない。だからほとんどのことは自分たちがコミュニケーションレベルで解決するしかない。村では、揉め事が起きると、時には裁判沙汰になることもありますが、できるだけ避けるべきとされています。基本的にはみんなに信頼される年長者が同席のもと、当事者が延々と話し合って解決策を見いだしていく。年長者という固定的な資格や役割があるわけじゃなくて、なんとなく村で分別のある人たちが問題を抱えた双方の当事者から依頼を受ける。じつは年齢もまちまちです。その仲介役の人たちが、どちらかを弁護して依頼者に有利な交渉をするのではなく、両者の言い分を聞きながら妥協点を探るんです。
なぜそのような方法を選ぶかというと、たとえば裁判に頼ってしまうと「あなたが有罪」といったように白黒つけられてしまう。しかし、村の中だとその後もそこで一緒に生きてくわけですから、どっちが勝った、どっちが負けたといった明確な答えを出すと、その後の関係に亀裂を生み出してしまう。だから、ぼんやりと妥協点を探るほうが、関係を持続していく上では重要なんです。それは、日本の昔の寄り合いのやり方とほとんど同じです。

Photo by Keiichiro Matsumura
HZ まさにグレーバーがいうところのアナキズムですよね。エチオピアの話を聞いていると、自分たち自身による暮らしのマネージがいかに大切か、つまり、自分たちが本来できるはずなのにできていないことが多くあるということを、はっきり感じさせられます。
松村 はい。日本に生きる私たちも、じつはエチオピアの村で暮らしている人と同じ世界を生きています。彼らが特殊な能力をもっているわけではない。むしろ人間はずっとそうやって生きてきた。世界的にみても、今の日本のようにシステムへの過剰な信頼が共有されているほうがじつはめずらしい。ヨーロッパやアメリカなどでも、日本からみればいい加減だな、と思うこと多いですよね。でも、そこにはシステムなんてそんなもので、自分たちでなんとかするもんだという意識がある。人間には、かならずしもシステムや制度がなくても、自分たちでこの世界をマネージしていく能力がある。今それができていないんだとしたら、私たちにはそういう能力や可能性があることを忘れてしまっているだけなんじゃないかと。いま、社会を変えるっていうと、ルールや制度、システムを変えることとイコールになってしまっているんですが、たぶん別の方向性もあるのだと思います。
たとえば選挙に行ったけど全然変わらないという人がいますが、そんなに変わるわけがない。それは政治というものを選挙や政治家の世界だけに矮小化しすぎたものの見方です。たとえばここでこういう話をしていることが、すでにポリティカルな行為であるとも言える。我々の行為の中にこそ政治があり、私たちがここでどう他者と関わるかが福祉の問題であって、格差の問題でもある。大きな期待を誰かに託すのではなく、身の回りの他者へと視線を向けながら、周囲を少しずつ心地よくしていくことが政治であり、実際にそうした実践は各所で行われています。それは革命的には見えないかもしれません。しかし、そのようにして社会は再構築されていくのだと、思います。こういう言い方、だいぶグレーバーに感化されていますが(笑)
別の現実を生きることもできる可能性
HZ 最後に4月に出た松村さんの編著『文化人類学の思考法』についても少しお伺いしたいと思います。僕も読ませていただきましたが、平易に書かれていながらも文化人類学の最先端の知見が詰まった素晴らしい一冊でした。そもそも、この本はどのいった経緯で作られることになったんですか?

『文化人類学の思考法』(編・松村圭一郎・中川理・石井美保/世界思想社)
松村 はじめは大学の授業で使う文化人類学の教科書をつくる予定でした。でも、執筆者と編者が対話を重ねて、内容や書き方を工夫していくうちに、これは学生に読ませるだけではもったいない、より広く一般の方に読んでもらえる本にしたい、と思うようになりました。『うしろめたさの人類学』が、学問とは縁のなかった読者に予想を超えて受け入れられた経験にも背中を押されました。文化人類学のものの見方や考え方を世の中で必要とする人がそれなりにいるんじゃないかという感触があって、思い切って、基礎知識がなくても読み通せて、しかも日本で暮らしている現実とのつながりを意識しやすいような書き方に時間をかけてブラッシュアップしていきました。ここまで編者が執筆者に何度も改稿をお願いする本って、あんまりないと思います。でも、そうやって本を出したら、今度は、大学の授業の教科書として使いたい、いまの学生にぜひ読ませたい、という声もたくさんあがってきています。ありがたいことです。
HZ 序論にも書かれていましたが、この本には「別の現実を生きることもできる可能性」がさまざまに紹介されていますね。これは今日のお話にも通じますが、どうにも現代においては「この道しかない」「この現実のほかに現実はない」という考え方が優勢的です。それが資本主義リアリズムというものなのかもしれませんが、そうした状況において人類学が積極的にオルタナティブを提示し続けてくれているというのは、頼もしい限りです。
松村 人類学がすごく現実的なオルタナティブを示せるか、と言われると、そうでもないんですけどね、と言いたくなります(笑)。世の中をがらっと変える力があるわけではない。せいぜい自分の関わっている半径50メートル圏内の景色が少し変わって見えるかも、というくらいでしょうか。でも、ご指摘のような「リアリズム」を振りかざす人って、とても視野が狭いことが多い。それは、世界の多様な人びとの営みを目にしてきた人類学者にしてみれば、唯一可能なリアリティでもなんでもない。まあ、誰もがつい狭い視野に陥ってしまうものですが、その見方をちょっとずらしたり、みんながあたりまえだと思っている前提をとっぱらって考えてみると、気持ちが楽になったり、もやもやを解消できたりするかもしれません。
私自身、いろんな報道とかをみても、いつも無力感に打ちひしがれますし、どうしようもない世の中だな、と悲観的になります。でも、この現実を別様に生きている人びとの姿に、つねにそこで立ち止まったり、耳を塞いだりせず、考えつづけろ、と問われるんですね。エチオピアだって、いろんな問題が山積していて、まったくユートピアではないし、みんないろんなことに折り合いをつけながら生きている。そういう生き方に触れさせてもらって、世の中を考えるヒントをたくさんもらってきた。「私が考えた」と思っていることは、そもそも「私だけのもの」で
✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎
松村圭一郎 まつむら・けいいちろう/1975年、熊本生まれ。京都大学総合人間学部卒。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。岡山大学大学院社会文化科学研究科/文学部准教授。専門は文化人類学。エチオピアの農村や中東の都市でフィールドワークを続け、富の所有と分配、貧困や開発援助、海外出稼ぎなどについて研究している。
✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎
Interview & Text by Yosuke Tsuji
〈MULTIVERSE〉
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美





















