1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント── Back To The 80’s 東亜|中村保夫
1984年、歌舞伎町で中高生による自発的で爆発的なディスコブームが発生した。その舞台は東亜会館。東京の中高生の間で一世を風靡した大ムーブメントなのだが、実はこれまでほとんど語られていない。あらためて、あの熱かった時代を振り返る。(Collaborate with 東京キララ社)

歌舞伎町のビルの密室にて
1984年、歌舞伎町で中高生による自発的で爆発的なディスコブームが発生した。その舞台は東亜会館(現在の第二東亜会館)。週末になると、全身パステルカラーの服に身を包んだ中高生男女が東亜会館に大挙押し寄せ、踊って叫んで酒飲んでタバコ吸ってナンパしてとやりたい放題。しかもオープンは昼の12時で、非常階段には開店待ちの長蛇の列ができていた。それから数年間に及び、東京の中高生の間で一世を風靡した大ムーブメントなのだが、実はこれまでほとんど語られていない。そこらへんの事情も含めて、この大きな社会現象を紹介していきたい。
東亜会館とはコマ劇場の向かい、噴水の脇にそびえ立つ8階建てのビルで、そのうち4フロアをディスコが占めていた。7階が比較的大衆的な「GBラビッツ」で、6階がDJ KOOがいたサーファーディスコ「B&B」、4階がとんねるずの「嵐のマッチョマン」の歌詞に出てくるギリシャ館で通称「グリース」、そして3階が僕も通っていた「BIBA」だった。
そのブームの震源地となっていたのは「BIBA」で「グリース」がそのライバルだ。その2つのディスコの共通点は、両方とも客全員が中高生だということで、社会人はおろか大学生さえ一人もいない。もし一般客が間違って入って来たとしても、あまりにも場違いな状況に耐えきれずに30分と持たずに店を出ることになる。
フロアには数百人の中高生男女がぎゅうぎゅう詰め。ちなみに女の子のほうが早熟で下は中2くらいから来ていた。会員証を提示して1000円から1500円ほどの入場料を払うと、あとはフリーフード、フリードリンクで一日中遊べる。食べ放題のフードはバイキング形式で、ヤキソバやポテトフライ、ミートボール、フルーツにゼリーなどが並び、人気メニューはピラフのシチューがけ。ドリンクはかき氷のシロップを薄めたようなジュースだけでなく、水割りやカクテルも無料だった。ただし、カルアミルクだけは原価が高いということもあって女の子しか頼めない。それを利用した「ごめん、カルアミルク頼んでくれない?」というナンパの手口も流行った。

東亜会館「BIBA」(提供:小畑仁/「BACK TO THE 80’s東亜」事務局)
曲はディスコに行かないと聞くことのできない最先端の電子音楽・ハイエナジー、ベストヒットUSAでお馴染みのロックやポップス、いわゆるダンクラと呼ばれるソウルミュージック、そして最新の歌謡曲までオールジャンルでかかる。そしてその一曲一曲に振りや掛け声が決まっていた。掛け声は基本、下ネタ。思春期の男女がフロアでテレビやラジオなら放送禁止となるような言葉を大合唱する。グループで踊りを合わせる激しいステップダンス、ソウルダンスから独自に発展したアクロバティックなバンプ、ツーステップ(芋掘り)などといった踊りが大流行していた。特にバンプは1984年の年末に「バンプコンテスト」が開かれたほど大流行。男同士でペアになって、2人が片足を合わせ半身で向き合い激しく踊り合うバトルのようなダンス、それがバンプだ。

1984年12月に東亜会館で行われた「バンプコンテスト」(提供:小畑仁/「BACK TO THE 80’s東亜」事務局)
フロアでは日頃の練習の成果を披露し合った。上手いペアには拍手が沸き起こり、歓声が飛び交う。文化祭や体育祭のノリに近いが、一番の違いは、東亜会館には親や教師など、うるさい大人がいないことだ。学校や家に居場所のない子供たちに、これ以上ないほどの自由が与えられたのが東亜会館のディスコだった。
規模的には「竹の子族」なんて目じゃないほどのブームだった。竹の子族の知り合いは一人もいないが、東亜会館の常連は至る学校にいて、休み時間にグループでステップやバンプの練習をする風景は日常の一部だった。行われていた場所がオープンな代々木公園ではなく新宿歌舞伎町のビルの密室だったという違いが、時代を象徴する社会現象として残ったか、当事者の記憶にしか残らなかったかを分けたのだ。
また記録メディアの問題もある。もちろん携帯電話なんてないし、家庭用のビデオカメラもまだ市販されていない。カメラだって使い捨てカメラ「写ルンです」が発売されたのが1986年だから、それまでは写真が撮りたければお父さんのカメラを持ち出さなければならない。本来、中高生が行ってはいけない場所だし、酒飲んだりタバコ吸ったりと年齢的に後ろめたいこともあるから、あえて家のカメラを持ち出して証拠を残すなんてことはしない。だから拙著『新宿ディスコナイト 東亜会館グラフィティ』を出す際に、もっとも苦労したのが当時の写真集めだった。現存する写真のほとんどは、ディスコで誕生日パーティーをした時に、お店のサービスで撮ってもらった写真だ。皆、当たり前のようにタバコを咥えピースをしている。時代柄、ポップでファンシーな出で立ちだが、新宿のディスコというのはいつの時代も不良のオアシスだった。1970年代は特攻服を着た暴走族、1980年代後期はチーマーが集った東亜会館。しかし80年代半ば、僕たちが通い詰めていた頃はそういった殺伐とした雰囲気の一切ない、ある意味で健全なディスコブームが巻き起こっていた。その背景にあったものとは何か。

東亜会館「BIBA」(提供:小畑仁/「BACK TO THE 80’s東亜」事務局)
1980年代に入ると、日本はバブル絶頂へと急速に登り詰めていく。「ネアカ」「ひょうきん」が是とされ、日本中が明るくエネルギーに満ち溢れていた。毎日が刺激的で夜だからといって寝てなんていられなかった。それは大人だけではなく、中高生たちもまた歌舞伎町に溢れかえっていた。そんな喧騒のなか、歌舞伎町である事件が発生し、その余波で中高生のディスコブームがピークを迎えることになる。通称「新宿歌舞伎町ディスコナンパ殺傷事件」だ。
法改正が生んだデイタイムの狂乱
事件は1982年6月6日に起こった。新宿のディスコ「ワンプラスワン」(東宝会館6階)などで夜通し遊んだ後の中学3年生の女子2人が、男に「ドライブへ行こう」とナンパされ、1人が千葉市街のサイクリングロードで首を切られ殺害された事件である。この事件は未解決のまま時効を迎えている。
ちなみに僕が初めて行ったディスコもこの「ワンプラスワン」で、事件の数ヶ月後にも関わらず、被害者と同じ中学3年生の僕たちでも簡単に入店できた。バブル前夜の歌舞伎町は日本で唯一の不夜城で、マイアミをはじめとする喫茶店、ディスコ、ゲーセン、ボーリング場、バッティングセンター、映画館などが密集し、家出した中高生が潜伏するのに最適の場所だった。中学生がディスコや居酒屋で遊んでいても咎められるようなことはないゆるい時代でもあった。時代背景からすると、起こるべくして起きた事件なのかもしれない。
この事件の被害者と僕たちは同学年ということもあり、大きな衝撃を受けた。事件当時、高校2年生だった尾崎豊は、この事件をモチーフにした曲「ダンスホール」を書き、事件から4ヶ月後に行われたCBSソニーのオーディションで披露すると、そのままトントン拍子にメジャーデビューを果たす。そして“十代の代弁者”として、東亜会館の常連の間でも絶大な人気を誇った。
そしてこの事件の影響は、ディスコ自体のあり方を大きく変える法改正にまで及んだ。1984年8月14日に風営法が改正され、1985年2月13日に施行されたことにより、ディスコの営業時間は深夜12時までとなったのだ。これにより新宿のディスコは大打撃を受けたと言われている。ある日、BIBAでいつものように遊んでいたら、いつもならこれからもうひと盛り上がりがあるという12時前に曲が止まり、フロアに煌々と明かりが灯った。大人たちに居場所を取り上げられた気がして、白けた気持ちで家に帰ったことを覚えている。
このままではせっかく盛り上がってきたシーンも廃れてしまう。そんな時に東亜会館は奇跡の一手を打つ。週末の営業時間を繰り上げたのだ。最初は午後2時オープンとなり、間もなく昼の12時からとなる。この斬新なアイディアが中高生ディスコブームに拍車をかけた。週末になると、開店前から東亜会館のフロントへと続く非常階段に中高生男女の長蛇の列ができ、入店するまで最低でも1時間は覚悟しなくてはならないほどであった。

東亜会館「BIBA」(著者撮影:1984年7月)
東亜会館の常連は一目見て、そのファッションですぐわかる。パステルカラーの服に身を包み、ピンクのコンバースを履いた一団が、ディスコビルへと集まってくる様は圧巻だった。
長い行列から解放され、白昼堂々と営業する歌舞伎町のディスコに入店すると、そこは夜も昼も関係ないミラーボール輝くいつものディスコのフロアだ。店内一体となって、曲ごとに大声で掛け声を合わせ、日頃のダンスの練習の成果を発揮する。チークタイムもフロアは即席のカップルでパンパンだ。ドラッグこそ出回っていなかったが、酒もタバコも咎める大人は一人もいない。東亜会館では剥き出しの青春が爆発していた。ふと我に返る瞬間はトイレに行った時だ。トイレの脇の通路はガラス張りで、白昼の歌舞伎町が見下ろせた。「なんだよ、まだ3時じゃん」と眼下に広がる現実的な世界と、自分の置かれた環境のギャップに思わず笑ってしまった。
昼間の歌舞伎町に中高生がいること自体は何も珍しくない。映画にボーリングなど健全な遊びもいくらでもある街だから。だからこそ、中高生の間でディスコが爆発的ブームになった。親もまさか真っ昼間からディスコが営業しているなんて思わないし、「友達と新宿で映画観てくる」とでも言って出かけ、晩飯時までに家に戻って来ていれば疑われもしない。子供たちが大手を振ってディスコに行けるようになったことで、東亜会館には新規の中高生客が雪崩れ込んできた。
当時、晩飯を家族と食わずに外で遊ぶことができるのは、よほどの不良か家庭が崩壊しているような子供だ。少し前の時代のディスコは暴走族が特攻服を着て来るような場所で、シンナーやクスリも蔓延していた。ところがバブル前夜に浮かれる80年代の半ばは、暴走族がダサいとされていた。暴走族の連中も来ていたが、僕らと同じファッションだから見分けはつかないし、それほど多くはいなかったと思う。どちらかと言えば、普通の子とまでは言わないが、少しクラスで目立つ程度の子が週末に押し寄せて来るようになったのだ。平日も毎日のように東亜会館に通うレベルの常連からすると「にわか」として疎まれた面もあるが、ブームというものは「にわか」がどれだけ集まるかということでもある。このムーブメントのピークは84年から85年にかけてだが、それからも数年間このブームは継続する。
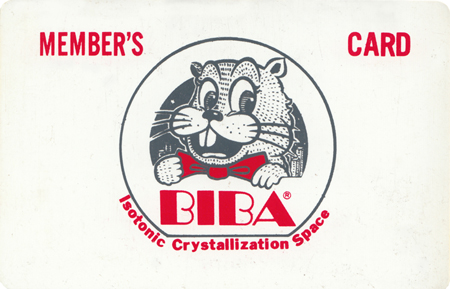
東亜会館「BIBA」会員証

東亜会館「BIBA」会員証(裏)
しかし、麻布十番「マハラジャ」がオープンしたことにより、ディスコのメッカは六本木・麻布へと移っていく。六本木のディスコは新宿とは違って入店時に身分証明が必要だ。それまでは中高生の分際でディスコで遊んでいることに楽しみを感じていたが、時はバブル絶頂となり、煌びやかな大人の世界に憧れ始めた。BIBAの常連の間でも、高校3年生になると東亜会館の卒業宣言をして、次々と新宿のディスコから卒業していった。そして80年代の終わり頃にクラブが誕生する。これも風営法改正の影響だ。ダンスのフロアは新宿の大箱から六本木・麻布の小箱へ。
風営法の改正で生まれた爆発的な東亜会館ブームだが、それもろうそくが消える前の一瞬の煌めきのようなもので、新宿のディスコにあらためて終止符を打ったのも、風営法の改正なのであった。1989年にブームの象徴であった「BIBA」が「ZEBRA」と名前を変えたことで、僕ら旧常連のなかですべてが過去のことになってしまった。以来、その喪失感を感じながら生きてきた人がどれだけ多かったか。最後に、時代の証言者たちの声に耳を傾けてみたい。
忘られぬ東亜会館の記憶
昨年、日本記念日協会が7月22日を「ディスコの日」に制定した。1978年7月22日にジョン・トラボルタ主演の映画『サタデー・ナイト・フィーバー』が日本で公開されてから40周年に当たる日だった。余談だが、7月22日は僕の誕生日であり、7月21日に開催される東亜会館の同窓会的イベントで先行発売するために『新宿ディスコナイト 東亜会館グラフィティ』を執筆している真っ只中に記念日制定の朗報を耳にした。
7月21日に歌舞伎町のFACEで開催された「Back To The 80’s東亜」のイベントには、東亜会館の元常連650人が集まった。「あの日に帰ろう」をスローガンにしたこのイベントは2001年に始まり、昨年で19回目を迎えた。最高で850人もの東亜会館卒業生が集まったという。主催の小畑仁さんは当時、東亜会館の主のような存在で、1984年12月に「BIBA」で開催された「バンプコンテスト」の優勝者である。このイベントを始めたきっかけを仁さんに聞いた。
「1990年頃にはもう、あの日の東亜会館に戻りたいと思っていました。もっと言えば、東亜でバンプが禁止になった時点で、禁止じゃなかった頃に戻りたいと(笑)」
東亜会館のブームの大きな原動力となり、コンテストまで行われた「バンプ」だが、1986年あたりから「バンプ」を踊ってもよい時間帯が設けられるようになり、やがて「バンプ」自体が禁止となる。それは「ステップ」も一緒で、東亜会館のブームを牽引した東亜独自の激しいダンスが禁止されたのだ。残された踊りは手の振りと掛け声くらいで、それが発展して後の「パラパラ」へと繋がる。
そしてバンプなど東亜のダンスの禁止が、大きな暴動へと発展する。それまでの東亜会館ではスタッフによる客への暴行が横行していた。他のフロアの系列店から移動してきたスタッフがいたとする。すると、まずそのスタッフは常連を捕まえてボコボコにするのだ。理由は特にない。ただ単に「舐められないように」ということだけ。「文句があるなら出禁にするぞ」と言われたら、僕らはもう逆らえない。家にも学校にも居場所がなく、東亜会館に集まって来ている中高生にとって、東亜のディスコというオアシスを失うことは何よりも恐れていたからだ。そして事件は起きた。
「それまでは店員に殴られても、出禁を恐れて耐えてきました。だけどバンプとステップが禁止になるならもういいかと。ある日、溜まっていた鬱憤が一気に爆発して、常連対店員の大乱闘になってしまった。店員も常連もDJもみんな殴り合いでボコボコ。パトカーと救急車が来るほどの大乱闘でした。それまでブレーキになっていた出禁が、最後には乱闘の引き金になってしまったんです」と仁さんは語る。

東亜会館「BIBA」(提供:小畑仁/「BACK TO THE 80’s東亜」事務局)
こうして一つの時代が幕を閉じた。気がつくと昔の仲間は一人、また一人と姿を消していった。東亜会館の灯火は次の世代の中高生へとバトンタッチされ、高校を卒業した常連たちは東亜会館を卒業し、大人への階段を歩んでいった。みんな働き盛りのサラリーマンや主婦になり、東亜会館は遠い過去の思い出となり、いつしか記憶が薄れていくかと思っていた。ところが、東亜会館での出来事はあまりにも強烈だった。
『新宿ディスコナイト 東亜会館グラフィティ』を刊行してから、多くの反響をいただいた。本を読んで当時の記憶が蘇ったのか、読者の方々がSNSなどで自分の東亜会館物語を書き始めたり、熱い思いのこもった当時のエピソードが綴られた手紙が送られてきたりした。なかには刑務所からの手紙もあって、「東亜会館で受けた衝撃が凄すぎて、あの時代は本当にあったのかと半信半疑になる時があって、幻だったのかなって。でも、こうして本を読んで本当だったんだって。あの時代に東亜に通っていたことを誇らしく思います」と長文が綴られていた。
これまで誰にもこのシーンが語られてこなかったからこそ、東亜会館の思い出はそれぞれの記憶のなかにしかなかった。しかし、こうして書籍が刊行され、東亜会館の同窓会的なイベントも毎年開催されることで、子供時代の恥ずかしい思い出だった人もパンドラの箱を開け始めている。
今年の「Back To The 80’s東亜」は8月31日に新宿「FACE」で開催される。歌舞伎町の伝説的なディスコ「ニューヨークニューヨーク」が入っていたビルだ。僕も当時と同じルートでイベントに参加する予定だ。新宿駅東口の改札を出て、アルタの横を通り、かつてシンナー売りや立ちんぼがいた場所を確認しながらあのビルへ。バブル絶頂へと向かう昭和と平成の狭間のエアポケットに現れたあの幻のような出来事は何だったのか。自由で無秩序で、多幸感とエネルギーに溢れ、煌びやかで刹那的なあの場所が、あの時代に確実に存在したことを、僕はこれからも伝えていきたい。

現在の第二東亜会館
Text by Yasuo Nakamura
Collaborate with 東京キララ社
✴︎✴︎✴︎
中村保夫 なかむら・やすお/1967年、神田神保町の製本屋に長男として生まれる。千代田区立錦華小学校、早稲田実業中学、同高校卒業。2001年に東京キララ社を立ち上げ、「マーケティングなんか糞食らえ!」をスローガンに、誰も踏み込めなかったカルチャーを書籍化し続ける。書籍編集者以外にもDJ、映像作家として幅広く活動。永田一直主催「和ラダイスガラージ」で5年半レギュラーDJを務め、現在は両国RRRで定期開催されるDJイベント「DISCOパラダイス」を主催。数々のMIX CDをリリースしている。著書には『新宿ディスコナイト 東亜会館グラフィティ』(東京キララ社)、映像作品には『CHICANO GANGSTA』(監督)『ジゴロvs.パワースポット』(監督・編集)などがある。
✴︎✴︎✴︎
特報:「沖縄のハジチ、台湾原住民族のタトゥー 歴史と今」展が、10月に那覇の沖縄県立博物館・美術館で開催。現在、クラウドファンディング募集中。
〈MULTIVERSE〉
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「REVOLUCION OF DANCE」DJ MARBOインタビュー| Spectator 2001 winter issue
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「旧共産遺産は“僕たちの想像力がいかに制限されているか”ということを僕たちに思い知らせてくれる 」── 対談|星野藍 × 中村保夫






















