「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
文化人類学の“静かなる革命”がもたらした「多自然主義」という視座は、現代において最も馴染み深い「多文化主義」の諸問題を炙りだした。僕たちはなぜ「多文化主義」から「多自然主義」へと向かうべきなのか。人類学者・奥野克巳に訊いた。
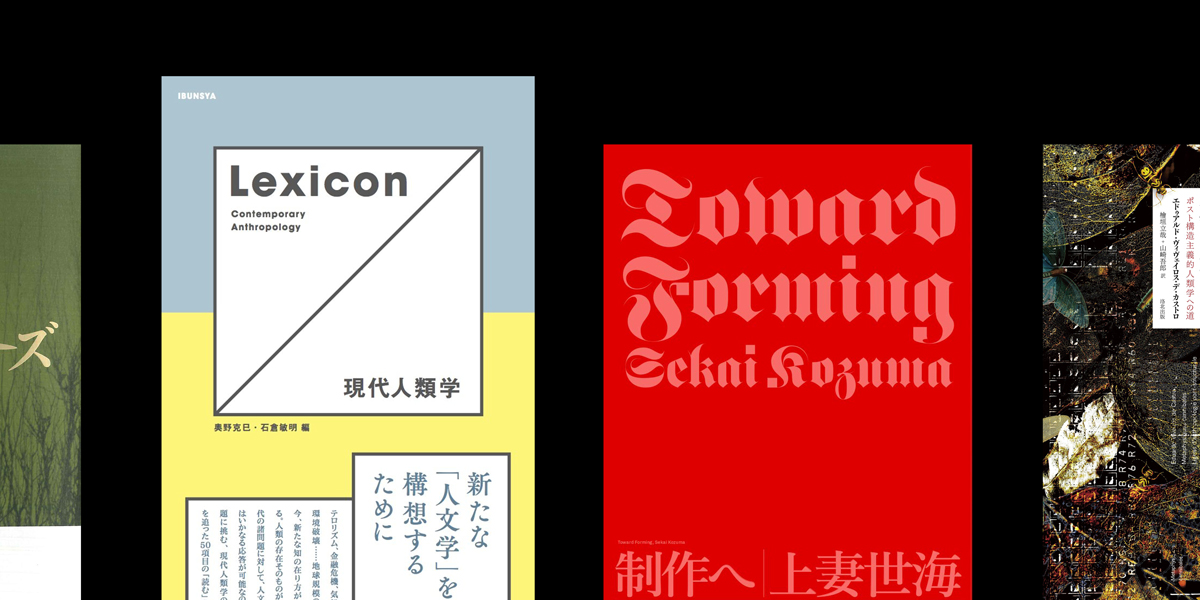
いかにして「存在論的転回」は起こったか
HZ 近年、文化人類学において注目を集めている「存在論的転回」、あるいは“人類学の静かなる革命”については、僕もまた門外漢ながら関心を抱いてきました。とりわけ、ヴィヴェイロス・デ・カストロが「多文化主義」に対置する形で提出した「多自然主義」というアイディアには、それが人類学という学術領域を越えてもちうる可能性という点からも強く惹かれています。
この存在論的転回に関して、奥野さんはレーン・ウィラースレフの『ソウル・ハンターズ』、エドゥアルド・コーンの『森は考える』を始め、重要な研究書の翻訳を多く手がけられています。さらに昨年に奥野さんが編集なされた小論文集『Lexicon』は、この静かなる革命の全貌を把握する上で、この上なく有用な一冊でした。僕も読みましたが、いずれの論文も刺激的でとにかく面白い。人類学への関心の有無を問わず、現代的な「多文化主義」の行き詰まりについてを考える上で必読の一冊と言ってよいのではないかと感じています。
そこで、このインタビューではあらためて、人類学の存在論的転回が一体何を転回させたのか、そして、その転回が広く僕らの日々の生においてどのような意味を持つのか、ということについて聞いていきたいと思っています。また同時に、僕が個人的に存在論的転回を巡って考えていることなどについても、せっかくの機会ですから奥野さんにぶつけてみようと思っています。
さて、まずは前提部分からお聞きしていきましょう。そもそも、この存在論的転回、静かなる革命は、従来の人類学に対するどのような問題意識から起こったものなんでしょうか。
奥野 ふむ、どこから話しましょう。少し遠回りをさせてもらえば、まず人類学の歴史を大雑把に捉えるとすると、1980年代から2000年代前半の約四半世紀の間、人類学は「反省の時代」でした。あるいはポストモダン、ポストコロニアルの時代とも呼ばれていますが、ようするに、それ以前の人類学において制度化されていた作法、「フィールドワークを行なって民族誌を書く」という方法論が、この時代、徹底的に懐疑されることになったんです。
きっかけの一つとなったのはエドワード・サイードの「オリエンタリズム」です。オリエンタリズムとはつまり、西洋から東洋を異なるものとして捉え、東洋をあくまでも客体的な研究や嗜好の対象とみなすこと、あるいは東洋を知的に支配する西洋的な思考様式のことなんですが、こうしたオリエンタリズムに対するサイードの批判から、それまでの人類学の行ってきた記述にもまた同じような構造が潜んでいたのではないか、という反省が起こったんです。このような人類学のポストモダンは、やがて、研究する側と研究される側に潜む植民地的な権力構造の問題検討につながっていきました。こうした人類学の学問の方法論自体を問う人類学を総称して「再帰人類学」とも呼ぶのですが、この時代がとても長く続きました。
そもそも、再帰人類学によって批判された民族誌記述の基本を作ったのは、ブロニスラフ・マリノフスキーというポーランド生まれのイギリスの人類学者なんです。彼の方法というのが、ある場所に長く滞在し、現地の言葉を学び、現地の人たちの視点からその文化を観察してみる、というやりかたでした。その際のスローガンは「現地人の視点から」ということです。
これは文化を相対的に存在するものとして捉え、異文化を深く知ることで私たちの生き方そのものを捉え直すという相対化を含んだ文化相対主義の見方につながっていきます。局所的なフィールドワークとそれに基づいて民族誌を書くことは非常に長く行われてきたわけですが、先ほど申し上げた通り、そこには見逃せないオリエンタリズムの構造が潜んでいるのではないか、あるいは、こうした記述が実は客観的なものではなく、調査者の感覚に基づいたフィクションに過ぎないのではないか、という批判が起こったのです。
フィクションをめぐる問題意識は、やがて民族誌の中にフィクションの断片があるだけでも糾弾されることへとつながり、「実際そうなっている」という素朴な現実感覚は否定され、民族誌の中にはフィクションは許されないとする考え方を生みました。そして、ついに現実それ自体を放棄せざるを得ないという虚無主義に辿り着いたのです。そうした思想は、やがてその重みに耐えきれず、崩れ去っていきましたが。
しかしこうした再帰人類学の問いは必ずしも無産的だったわけではありません。研究倫理を確立したり、再帰人類学の時代を経て、複雑化する文化状況の中で、同時代の課題を引き受けたりして、災害復興やサイバースペースなどの領域へと研究を拡張させたということもあります。他方で、こうした再帰人類学影に隠れてじっくりと熟成していったのが、今、存在論的転回と呼ばれている潮流なんです。
HZ なるほど。背景にはマリノフスキー以来の人類学的な方法論への反省があった、と。しかし、存在論的転回はそうした再帰人類学を引き受けつつも、それとは異なるベクトルを持った潮流ですよね。
奥野 人類学にはマリノフスキーの系譜とは別に、もう一つの重要な流れとしてクロード・レヴィ=ストロースの系譜というのがあるのですが、存在論的転回は概してこのレヴィ=ストロースの系譜に属していると言えるように思います。マリノフスキーがある一地点を集中的に調査し、その土地の文化を記述し考察することに力点を置いたのに対し、レヴィ=ストロースは複数の文化の間を比較検討し、ある一つの文化で見られる現象が、他の文化で変形した形で見られるということを取り上げました。
これが、いわゆる構造主義ですが、同時にレヴィ=ストロースは構造主義を深める過程で「自然/人間」という西洋の二元論思考の別の可能性にも注目していたんです。ようするに、そもそも自然である人間が自然とどう関わっているのか、いかに人間が自然と交感しているのか、その関わり方や交感のあり方や二項の差異やインターフェイスに関心をおいていた。これは人間や人間が生み出す社会現象の観察を主軸としていたマリノフスキーにはなかった視点で、また再帰人類学においてもずっと忘れられていた視点です。
こうしたレヴィ=ストロース的な問いを引き継いで発展させたのが、レヴィ=ストロースの弟子であるフィリップ・デスコラや同じく弟子筋であるエドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロです。そして、その彼らがいわゆる人類学の存在論的転回の旗手となった。
では、彼らが一体何を問題としたのかというと、彼らは人類学の研究者が調査地で現地調査する際に投入してきた認識的次元を問題にしたんです。マリノフスキー流の人類学が肥大化した裏で、おざなりにされてきた「自然/人間」というレヴィ=ストロース的二元論の問題検討を軸に、あらためて調査における認識的次元を問い直そうと試みたんです。
HZ つまり、自然と人間との関係性を自分たち西洋人がどう認識しているのかを明らかにし、その認識的次元が調査そのものにどう影響を与えているのかを問題化した、と。
奥野 はい。たとえば、ヴィヴェイロス・デ・カストロは「アメリカ大陸先住民のパースペクティヴィズムと多自然主義」という論文でレヴィ=ストロースが『構造人類学Ⅱ』で取り上げたエピソードを再解釈しています。そのエピソードとは、大航海時代に大アンティル諸島に上陸したスペインの調査団の白人たちが、先住民たちによって「人間か精霊かどうかを確認するため」に溺死させられ、さらに死体が腐敗するかどうか観察された、という話です。

ヴィヴェイロス・デ・カストロの論文「アメリカ大陸先住民のパースペクティヴィズムと多自然主義」は『現代思想』2016年3月臨時増刊号(青土社)に収録。
このエピソードはどう理解すべきでしょうか。19世紀に主流だった進化主義的な人類学であれば、先住民は未開だからそのような蛮行をしたのだ、と考えられるでしょう。あるいは20世紀後半に広がった文化相対主義的な解釈であれば、彼らは我々とは文化が異なるため、彼らには彼らなりの合理的な理屈があってそうした残虐行為をしたのだ、となる。それに対して、ヴィヴェイロス・デ・カストロは、彼らがそのように振る舞うのは「自然と人間」の間の関係性が西洋人と先住民の間ではズレているからだ、と説明するんです。そうした先住民たちにおける「自然と人間」の関係性のあり方を「多自然主義」とヴィヴェイロス・デ・カストロは呼んだわけですね。
HZ 多自然主義とはつまり「文化というものは一つしか存在しないが、自然というものは多数存在する」という視座のことですね。
奥野 そうです。ヴィヴェイロス・デ・カストロによれば、大アンティル諸島の先住民たちはすべての存在者に同じように精神や魂が備わっていると考えていて、それなのに、それぞれで異なっているのは、物質的側面すなわち身体が違うからだと考えているんです。この精神や魂というのが、すなわち文化のことですね。一方、それぞれに異なる身体があるというのが多数の自然を意味する。文化は人間、動物、精霊などの存在者の間で一つだけで、多数あるのは、身体すなわち自然のほうなのです。
だから、先住民たちにとっては、白人も自分たちと同じ精神を持つことには疑いを差し挟んでいなかった。彼らは白人も死ぬとふつうに死体となって腐敗するただの人間の身体を持つのか、それとも邪悪な精霊に変身してしまうのかどうかを見極めようとした。ようするに白人たちも自分たちと同じ精神や魂を持っているのは自明だったので、自分たちと同じ身体を持っているのかどうかを確認する必要があったんです。
こうした多自然主義の対極にある考えが多文化主義です。多文化主義では、人間の身体そのものはどこででも一緒だけど、精神や魂が異なっている。物質面では同じだが、精神の成熟度において異なっている。それは、身体や自然自体は一つしかないけど、それをどのように解釈するかは文化によってそれぞれだ、という考えでもあり、我々にとってとても馴染み深い考え方です。実際、多文化主義は西洋思考の深くにまで浸透していて、これが認識論的な次元で、先住民たちの行動を人類学者が観察する際のバイアスとなっているということをヴィヴェイロス・デ・カストロは指摘したんです。
多文化主義から多自然主義へ
奥野 多自然主義と多文化主義の違いについてもう少しだけ解説しておきましょう。多文化主義においては自然というものは揺るがない「一」として存在しているんです。零度を下回れば水が氷になる、とか、川は上流から下流に向かって流れる、とか、そうしたものが「一なる自然」として捉えられ、その確信の土台のもとに自然科学が発展してきたわけです。他方、こうした考えに対置されるかたちで文化はそれぞれが相対的に、多数存在する。一なる自然に人間がそれぞれの環境で適応する中で、言葉や文化といったものが作られたわけですが、それらは地域によってそれぞれ異なっている。自然現象は地球上で普遍的に起きるけれど、たとえばヨーロッパとアフリカでは文化は異なっている。自然との関わり方や解釈は地球上に様々あって、その数に応じて文化がある、とするのが、多文化主義です。それは、ほぼ文化相対主義の考え方に等しい。
一方で多自然主義においては、人間も動物も植物も精霊も神々も、同じ精神、同じ文化を持っていて、一つの宇宙論的な共同体を形作っている、とされる。「一なる文化」。諸存在者にとって、文化自体はこのように一つなんですが、身体がそれぞれに異なるため、身体に根ざしたパースペクティヴにも差異が生じる。ヴィヴェイロス・デ・カストロを引き合いに出すなら、アメリカ大陸の先住民にとっての血を、ジャガーは「マニオク酒」とみなす。人間とジャガーでは身体が異なり、パースペクティヴが異なっているため、当の物体は「多様体」として現れるわけです。
このように多文化主義に対して多自然主義を提起することにより、「人間/自然」という西洋二元論思考の根底的な見直しを行うという潮流があります。それは、周囲の存在者や存在物がどのように組成されているのかということに関わっており、現在、人類学の存在論的転回の重要な課題となっています。
HZ 多文化主義においては「自然」にアプローチできる唯一の客観的な尺度は自然科学であり、それ以外は主観に基づく多様な解釈として扱われてきたわけですが、これが多自然主義においては、一なる「自然」、客観的な純粋自然など、そもそも存在しないとされるわけですね。これは最近だとマルクス・ガブリエルの「世界は存在しないが、それ以外は全て存在する」といったような実在論系の話にもどこか通じているように思います。
あるいは存在論的転回においては「アニミズム」にも注目が寄せられていますね。たとえばフィリップ・デスコラは、アニミズムを「類似する内面性と異なる身体性を持つ様態」と説明した上であらためて強調しています。存在論的転回においてアニミズムが重視されているというのはなぜなんでしょう。
奥野 アニミズムとはようするに、地球や宇宙における存在者のうち、人間だけが必ずしも主人なのではない、という考え方のことです。文化というものは人間だけが持っているものでは必ずしもないんだ、というのがアニミズムだと言い換えてもいいかもしれません。そもそも、地球上の諸存在者は、相互に複雑に絡み合った一つの形で生を交換しています。たとえば、田んぼなどをやっているとゲンゴロウだとかマムシだとか、そういった他生が人間の生活空間にちょろちょろ現れるような暮らしをしていることに気づきます。その時、共同体そのものが人間だけから成るのではまったくなく、「ハイブリッド・コミュニティ」、つまり、人間、動物、植物、あるいは神々が混ざり合った共生の空間になっているんです。
こうしたことが多文化主義ではわりと簡単に忘れられてしまうんだと思うんですね。人間と動植物は実は絡まりあって存在していて、そこにはつねにアニミズムが潜在的にある。諸存在者は、内面的につまり精神的次元で互いにつながり合っている。そうであるにも関わらず、多文化主義的な捉え方をすると、人間だけが人間同士で文化的な共同体を形作っているとされてしまい、自然が外部化され、切断されてしまう。つまり多文化主義では人間中心主義、あるいは人間例外主義が生まれてしまう。多自然主義という考えには、こうした多文化主義が有する人間中心主義への批判およびその乗り越えへの意志が含まれているんです。
なぜ「多文化主義」ではいけないのか
HZ 他生を含む自然を外部化するのではなく、より連続的な存在として捉えることが、多自然主義という視座に立つことによって可能になるということですね。つまり、文化圏というものは本来は一つであり、その中で相互が相互の影響を受けながら、かつ相互依存的に暮らしている。それなのに、それぞれの行動に差異が生まれるのは、身体=自然がそれぞれで異なるからだ、と。
ところで、この多自然主義という視座に立ったとき「人間/自然」という二元論の見直しばかりではなく、「人間/人間」という関係性もまた見直しを迫られるのではないか、とも思うのですがいかがでしょうか。つまり、人間と自然の関係を非対称な二元論としてではなく一つの対称性のもとに眺めたときに、人間を含む自然が連続性のある差異の相として捉え直されることになります。生物種というソリッドな境界線をいったん棚上げにし、「似ている/似ていない」の緩やかなグラデーションの中で自然と対峙した場合、同じヒトであったとしても、身体や身体装飾がそれぞれに「似てはいるけど異なる」ということがあらためて意識される。あるいは、そうした差異に応じた無数のパースペクティヴがあるということが意識されることになるのではないかとも思うんです。
つまり、人と人との関係についてを、人とゲンゴロウとの関係についてを考えるように捉え直していくこと。これは現在、完全に行き詰まっているかのように見える多文化共生を、根本から見直す手がかりになるのではないか、と僕は思っているんです。
奥野 なるほど。つまりこういうことでしょうか。現在、多文化共生が叫ばれており、あるいは文化同士の衝突を避けることによって平和というものが構築されるべきだという考えがあるわけですが、これは文化相対主義の旗印のもとで20世紀をつうじてずっと取り組まれてきたにも関わらず、うまくいっているのかと言えば、必ずしもそうではなくて、すでに破綻しているのではないか、と。たとえば、移民問題。日本人と日本にやって来る移民がどう共生すべきか。寛容でありましょう、と言ってみても、実際にはなかなかうまくいかない。さらには、そのことの反動として、端的な排外主義も蔓延している。結局、その往復運動が永続化しているだけではないか。
こうした状況について、存在論的転回や多自然主義を用いてどのようなことが言えるのか。おそらく、そうした反動的な排外主義の前提にあるのは「自己同一性」というものは揺るぎないものなのだ、とする信念ではないでしょうか。あるいは国家の(想像上の)同一性、民族の同一性といってもいいかもしれません。通時的にも共時的にも安定した自己同一性のようなものが想定されていて、さらにそれらが自律したものとして存在していると考えられている。多文化主義の本質にはそうした考え方があるように思います。
一方、多自然主義においては、この自己同一性が揺らぎの中に置かれる。たとえばウィラースレフが『ソウル・ハンターズ』で書いているように、狩猟民であるユカギールたちはエルクを狩猟する際に、まず彼らとの「模倣的共感」の関係を儀礼的に形成するわけです。ハンターがエルクになりきり、夢の中で情を交わすことで、エルクへの接近が可能になると考えられている。実際に狩りの日にはユカギールはギリギリまでエルクそのものになりきって接近し、最後の最後で人間に戻り、エルクを撃ち殺すわけです。

『ソウル・ハンターズ』(著・レーン・ウィラースレフ/亜紀書房)
ようするに、多自然主義的な視座においては、自己が初めからあるわけではない。自己同一性が安定したものではなく、流動的なものとして考えられているということです。上掲書では、エルクを模倣してエルクになる何かとして初めは立ち上がって、もちろん、最後には人間に帰ってこなければならず、エルクになりきってしまうと最終的には死に至る、とも書かれています。ただ、一時的にでもエルクになることができるためには、エルクにも人と同じ人格があるという前提が必要なんです。この他生にも同じ人格があり、身体的な模倣を通じて交感しうるというのが、まさに多自然主義的な感性なんですね。そこでは、ユカギールの人格自体、自明なものではなく、それはエルクとの関わりの中で見出されるものに過ぎません。そもそも精神や魂は一つ、つまりあらゆる存在者が持つものであるわけですから、エルクに人格がなければ、ユカギールにも人格がないという話になってしまうんです。ウィラースレフが言うには、逆では、決してないのです。
つまり、多自然主義的な視座に立つと、自己同一性とは他者や対象との関わりの中で定まっていくものであり、決して初めから自律的に境界づけられたものではないということが分かるんですね。そして、そのことを手がかりとして「人間/人間」の関係性を見直すというのであれば、分かります。
HZ たしかに多文化主義の背景には、安定的で自立した自己同一性という信念があるのかもしれません。また自己同一性というものが本来、他者や対象との関わりの中で定まっていくという点も完全に同意します。
ただ一方で、文化相対主義それ自体が、そうした自己同一性をどこまでも相対化してきたという側面もあるように思います。なぜなら、その視座に立つ限りにおいて、文化の同一性とは相対的なものでしかなく、所詮は解釈に過ぎないもの、となるからです。奥野さんの指摘とは別に、僕は自己同一性や文化というものが、相対化によって“数ある解釈のうちの一つ”に過ぎないものとされてしまうこともまた、多文化主義の問題なのではないかと思っています。いわば、例に出された極端な排外主義も、相対化され現実感を失った自己が、現実感を取り戻すために起こしている反発なのではないか、と思えるんです。
その点、多自然主義的視座に立った場合、自己同一性や文化はもはや解釈のような軽いものではなくなります。相互依存的に絡まり合い、同じ一つの文化を共有しながらも、しかし、異なる身体であるという確固たる現実によって日常的にはパースペクティヴが切断されている。身体による差異は解釈による差異とは違い、それぞれに絶対的なものです。あなたと私では身体が違う、だから違って当然。ここでは安易な相互理解などはあらかじめ拒絶されます。だからこそ、ユカギールがエルクと交感するためには、模倣という特別な儀式が必要だったのではないでしょうか。ヴィヴェイロス・デ・カストロもまたシャーマニズムに触れた文章において、パースペクティヴの邂逅や交感は危険な行為であり、通常の人間においては困難である、とも書いています。
あるいは、『Lexicon』において近藤宏さんが解説されていたエリザベス・ポヴィネリは、「根源的他性」という言葉を用いて「他者との共約可能性の創出には暴力性が伴う」ということを指摘していますよね。相手を理解可能なものと見なすとき、一方の世界に合わせて他方の世界を矯正する必要がある、と。多文化共生における「他者を理解しよう」であったり「互いに寛容であろう」というメッセージは、こうした暴力性にあまりに無自覚である気がします。その点、多自然主義においては、そもそも身体、あるいは身体装飾が異なるのだから、相互に共約不可能であることが最初から前提とされている。理解しあおうと言って殴り合っている現状を鑑みれば、こちらの方がだいぶ優しい気がします。
何が言いたいのかと言いますと、僕は存在論的転回や多自然主義についてを、それぞれが密接に依存しあいながらも同時にバラバラであるということに力点を置いて考えてみたとき、他生と人、人と人を含んだ、新しい共生、共在のあり方が見えてくるのではないかと思っているんです。
奥野 なるほど、多文化主義の行き過ぎである極端な排外主義の横行が、多文化主義の中で徹底的に相対化され現実感を失った自己による反動だということ見方ですね。だからこそ、多自然主義において絶対的に切断されている「他性」を踏まえて考えていく必要があるのではないか。そして、共約不可能なまでの他性に軸を置いて考えることで、人間同士、人間と他生との関係を同時に見ていく視座を切り拓いていく可能性があるのではないか、というご指摘でしょうか。確かに、その立場は、人類学者によって示されていることを敷衍した、一つの有効な見通しなのかもしれませんね。
それ、つまり、絡まりあいながら互いにバラバラであるという他性を手がかりにする見方に対して、ここでは、コーンを手がかりとして、別の可能性についてお話ししたいと思います。
「多種」のうちに人間を含めて諸存在が記号のやり取りの中を生きていると考えるコーンの立場です。C.S.パースの「記号過程」を援用しながら、コーンが描き出す「諸自己の生態学」では、「自己」だけしかいません。他者が見当たらないのです。イコン性とインデックス性に関しては、人間も他生もともに記号の中継点であって、記号を受け取り、他の誰かに記号を伝える存在者です。そこには、他者がいない。いることはいるのだけれども、その用語を用いないことで、コーンは、人間同士だけでなく、人間と動物や精霊の間になだらかなつながりを強調しているように見えます。「記号は精神に由来しない。むしろ逆である。私たちが精神あるいは自己と呼んでいるものは、記号過程から生じる」と述べて、コーンは、記号過程の中で立ち上がってくる自己を記号論的自己と呼んでいます。

『森は考える』(著・エドゥアルド・コーン/亜紀書房)
その諸々の自己だけから成り立つ世界の議論を補うための方略として、コーンは、ブーバーの<我―なんじ>の議論を持ち出します。自己と自己の関係を〈我―なんじ〉と〈我―それ〉に分けています。〈我―なんじ〉とは、自己と別の自己との親密な関係性のことです。他方、〈我―それ〉の〈それ〉とは、他の〈それ〉と境を接する対象のことで、〈我―それ〉は、別の自己を含む対象を自己のために利用することです。詳細は省きますが、そのようにしてコーンは、自己がその都度その都度立ち上がってくる中で、諸々の自己だけから成り立つ世界を、立体的に描き出しています。ようするに、存在論を突き詰めていくならば、他者が存在しない、記号のやり取りをする自己たちから成る記号論ネットワークのような世界に、人間だけでなくあらゆる存在者が住まっているというような見方が出てきているということです。
その考え方は、私は、上妻世海さんが最近出版した本『制作へ』の中で提示しているアイデアに通じるように思います。個人的には、それを「制作論的転回」と名づけていますが。
HZ たいへん興味深いです。僕も上妻さんの『制作へ』は読ませていただきました。これは余談になってしまうかもしれませんが、今の奥野さんのお話、そして上妻さんの制作論に、僕は、レオ・ベルサーニが『親密性』という本において、ゲイカルチャーにおけるベアバッキング(コンドームを使用しないアナルセックスのこと。この行為においては意図的にHIVヘの感染が行われる場合もある)の例を通じて説明していた「非人称性ナルシシズム」という概念を連想しました。
ベルサーニの『親密性』においては、愛とはどこまでもナルシスティックなものとされています。これは、愛とはつねに他者ではなく自己へと向かうものだということ。つまり、ベルサーニもまた他者の存在しないナルシシズムだけの世界を想定していたんです。そうした世界における非暴力的なつながりの可能性として、ベルサーニはナルシシズムをむしろ極限化する形で「非人称性ナルシシズム」という異なるナルシシズムのあり方を提案しているわけなんですが、ここではナルシシズムが非人称的であるために「愛するもの/愛されるもの」、つまりは〈我―なんじ〉の区別自体が無化されているんですね。
たとえばベルサーニは「愛する者の愛する自己は愛される者の自己でもあり、愛される者は愛する者の自己として愛される自己を愛する」と書いていて、これは今のコーンの話にも非常に近しい気がします。ただし、ベルサーニのベアバッキングの例においては、交換されていくものが記号ではなく、より具体的にHIVウィルスとなるわけですけど(笑)

『親密性』(著・レオ・ベルサーニ、アダム・フィリップス/洛北出版)
多自然主義をいかにして実践するか
HZ ところで、人類学の内部では存在論的転回を今後の調査の方法論にまで発展させていこうというような動きは出てきているのでしょうか?
奥野 難しい質問ですね。私自身は2007年ごろより「自然と社会」研究会というのを立ち上げるのに加わって、その流れの中で、人類学の存在論的転回に魅力を感じ、その吸収に取り組んできました。しかし、日本の人類学界全体は、そうした新しい流れに長らく、冷ややかだったんです。今更、南米の先住民のパースペクティヴィズムやアニミズムなどを取り上げてどうするんだ、と。実を言うと、いまだにそうした反応が多いのも事実です。なので、存在論的転回がもたらした知見を今後の人類学の中で実践的にどう活かしていくのか、ということについては、まだあまり熱心に語られていないというのが現状でしょう。
逆にこうした一連の動きに関心を寄せているのは日本では人類学者よりも、清水高志さんのような哲学者や、上妻世海さんのようなアートキューレーター、あるいは芸術分野や建築学の方々など人類学の外部の人たちです。実践ということに関しても同様で、たとえば上妻さんは「制作」という言葉を使って、多自然主義的な実践をしようとされている。ユカギールが狩猟の前に獲物との模倣的共感を儀礼的に行うということについてはすでに触れましたが、それを制作的空間に置き換えたらどうなるのか。そうした問いのもと、対象のパースペクティヴと自らのパースペクティヴの絶えざる往還運動をつうじて作品を制作する過程を描き出そうとしています。

『制作へ』(著・上妻世海/オーバーキャスト)
制作論が面白いことの一つは、作品の制作に加えて、我々人間の生だけでもなく、あらゆる「生」の領域にも深く斬り込んでいこうとしている点です。私はそれをすでに述べたように、制作論的転回と呼んでいますが、むしろこうした実践が人類学の新しい可能性を開いていくのではないかと思っているんです。そうした流れは、人類学にふたたび還流し、石倉敏明さんのようなアートと人類学の交差点でなされている仕事にもつながっていると思っています。
つまり、実践を通じて私たちの身体を変容させていくということ。さっき言ったような、自己同一性をとことん揺るがせるような形で制作が行われ、またそこで制作されたものが最終形態ではなく、相手との関係で次々に別のものに変容していくという絶えざる動態。こうしたものが見えてくるならば、それはとても面白いのではないか、と思っています。海外では、早くから日本の建築学やアート業界に注目されているティム・インゴルドも、同じようなことを言っています。
HZ ヴィヴェイロス・デ・カストロのいうところのカニバリズムもまた、そうした変容の動態へと向かっていましたね。他者を排除したり、あるいは単に自分の栄養源として利用するというのではなく、他者を食すことで、その他性を帯び、自らが不断に変容していく、という。
奥野 私がフィールドワークを行なったボルネオ島の狩猟民であるプナンもそうでした。彼らは動物を単に殺して食べているだけではない。そもそも、人間と動物の距離が近いんです。プナンと話していると、人間の話をしているのか動物の話をしているのか分からないことが多いんですね。食の次元だけでなくて、動物について語り、動物を考えることを通じてもまた、絶えず自己の変容が促されていく。
しかし、プナンだけが特別だというのではない。本質的には私たちも同じなんです。私たちは人間だけで共同体を作っているわけではなく、ネコやイヌや様々な小動物や微生物とともに、すでにハイブリッド・コミュニティーズの中にいるんですから。
HZ 多文化共生ならぬ多自然共生、自分自身もまたその上においてどのような実践が可能か、模索していきたいと思います。実は個人的に、現代におけるタトゥーや身体改造の実践もまた多自然主義の一つの実践と言いうるのではないかと密かに考えているんですが、長くなりますのでこの話はまた別の機会に(笑)。今日はどうもありがとうございました。
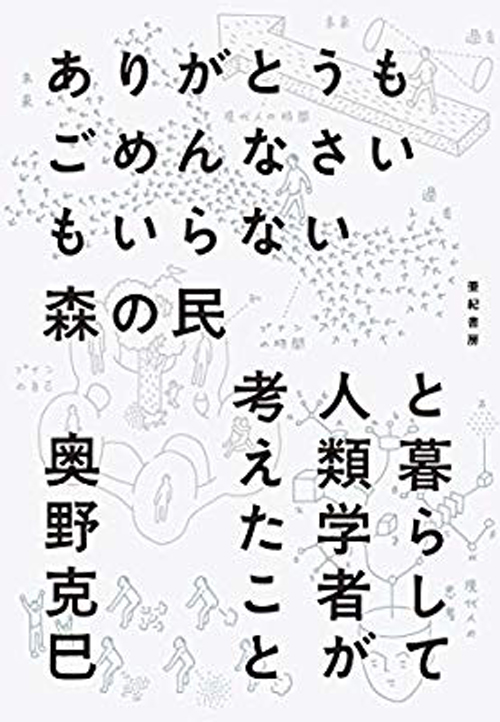
『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』(著・奥野克巳/亜紀書房)
『Lexicon』(編・奥野克巳・石倉敏明/以文社)
✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎
奥野克巳 おくの・かつみ/1962年、滋賀県生まれ。立教大学異文化コミュニケーション学部教授。大学在学中にメキシコ先住民を単独訪問し、東南・南アジアを旅し、バングラデシュで仏僧になり、トルコ・クルディスタンを旅し、大卒後、商社勤務を経てインドネシアを一年間放浪後に文化人類学を専攻。一橋大学社会学研究科博士後期課程修了。主な著書として、単著に、『「精霊の仕業」と「人の仕業」:ボルネオ島カリスにおける災い解釈と対処法』『帝国医療と人類学』『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』、共編著に『文化人類学のレッスン:フィールドからの出発』『セックスの人類学』『人と動物の人類学』『改定新版 文化人類学』『Lexicon 現代人類学』などがある。共訳書にエドゥアルド・コーン『森は考える:人間的なるものを超えた人類学』、レーン・ウィラースレフ 『ソウル・ハンターズ:シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学』など。
✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎
Interview & Text by Yosuke Tsuji
〈MULTIVERSE〉
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美





















