太田光海 × 清水高志|巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる|映画『カナルタ 螺旋状の夢』公開記念対談
南米エクアドルのアマゾンに暮らす先住民族シュアール族と起居を共にし、奥深い熱帯の森での暮らしの断片を撮影した映画『カナルタ 螺旋状の夢』を巡って、監督の太田光海と哲学者の清水高志が語り合う。

南米エクアドルのアマゾンに暮らす先住民族シュアール族と起居を共にし、奥深い熱帯の森での暮らしの断片を撮影した太田光海監督の映画『カナルタ 螺旋状の夢』が、現在公開されている。
現時点(2021年10月11日)で公開からまだ10日足らず、加えて現状では渋谷イメージフォーラムと岡山の円◎結の二館のみの上映にも関わらず、本作にはすでに各方面から数多くの賞賛が寄せられている。
実際、観たものがそれについてを語り出さずにはいられなくなるような、不思議な魅力を持った作品なのだ。それはちょうど、奇妙で不可解な、だけれどなんらかの啓示のようでもある夢を見てしまった翌朝、おぼろげな記憶を手繰り寄せるようにその夢についてを誰かに語り出さずにはいられない、あの心情にも似ている。あるいは映画に繰り返し登場する、唾液に棲まう微生物によって発酵した口噛み酒〈チチャ〉の映像が、観るものに予期的な酩酊をもたらし、鑑賞後の余韻に独特の深みを与えているのかもしれない。
筆者がアマゾニアに暮らす人々の世界観を記録した映像を観たのはこれが初めてではない。しかし、『カナルタ』はそれまでに観た先行作品群とはどこか――おそらくはストーリーテリングの作法やパースペクティブの置き場において――趣を異にしていた。ありていに言えば、『カナルタ』はアマゾニアに息づく近代とは異なる世界観――たとえば我々がアニミズムと呼ぶような存在論の形式――を生きる人々についての映画ではなかった。『カナルタ』においては、『カナルタ』という作品それ自体が、ひとつの世界観を、ひとつの存在論をなしていた。
筆者は『カナルタ』を鑑賞後、かつて泥棒作家ジャン・ジュネに対してサルトルが言っていたことを想起していた。サルトルいわく、ジュネはサドやラスネールなど名だたる悪徳の作家たちとは異なり、悪についての小説を書いたのではなく、悪として小説を書いたのだった。太田もまたそうだったのではないだろうか。つまり、太田は『カナルタ』において、アニミズムについての映像を撮ったのではなく、アニミストとして映像を撮った。その意味において、『カナルタ』とは、ひとつの“存在論的映画”である。
おそらく、その背景には監督である太田光海のキャリアが関係している。神戸大学を卒業後、フランスとイギリスで文化人類学を学んだ太田は、人類学における民族誌のあり方に対して抱いた違和感からそれとは別の記述のありかたを模索する中で、映像人類学といういまだ発展途上の分野へと辿り着いた。本作『カナルタ』は、太田がマンチェスター大学グラナダ映像人類学センターに在籍中、博士号取得のために撮影された映像を元に制作されたものだ。
さて、ここには本作の公開前、9月の中旬に行なった太田光海監督と哲学者の清水高志による対談記事を掲載する。
清水といえば、21世紀の哲学の新動向である思弁的実在論やオブジェクト指向論、さらには文化人類学における存在論的転回などを大胆に援用しながら、来たるべき21世紀の世界像を鮮烈に描出してみせた著書『実在の殺到』などで知られる現代哲学の泰斗だ。なんでも現在、清水は文化人類学者・奥野克巳との共著によって、『実在の殺到』での論考を発展させ、さらに仏教思想とアニミズムへの接続を試みた『今日のアニミズム』という本を準備中だという。
それぞれに異なる方法を用いながら、古くて新しい存在論を今日に伝うる語り部ふたりの、初顔合わせ。三時間以上にも及んだその対話は、さしずめ森の深淵に見るアヤワスカのヴィジョンのように錯綜を極めた。
取材・文/辻陽介
客観的な真のない森
清水高志(以下、清水) 『カナルタ』観させていただきました。なにか客観的な真のない森に踏み入っていくような感じがあり、引き込まれました。映像も美しくて、とても心地良かった。
太田光海(以下、太田) ありがとうございます。
清水 映画の中で太田さんはシュアール族の人たちに「ナンキ」って名前で呼ばれてましたよね。あれはなんなんですか?
太田 村の人がつけてくれた名前ですね。映画の主要人物でもあるセバスティアンがある時「こいつに名前をつけてやらなきゃいけない」って言い出して。それでみんなでつけてくれた感じです。
清水 なるほど。最初の方、映画を見ていて人の名前が少し分かりづらいなと思ったんですよ。セバスティアンがセバスティアンという名前だということもなかなか分からなかった。だから僕は彼がローリング・ストーンズのチャーリー・ワッツに顔が似ていることから勝手にワッツ氏と呼んでいました(笑)。映画が進むうちに段々と彼がセバスティアンという名前らしいってことが分かってくるんだけど、でも最後の方になると今度はセバスティアン自身が自分のことをツァマラインという違う名前で呼んでたりもする。あれ、どうなってるんだ、と。
太田 ツァマラインというのは、元々はセバスティアンのお父さんの名前だったものですね。シュアール族にとって名前はすごい流動的なものなんですよ。彼は現在、一応、セバスティアンというファーストネームでツァマラインが苗字ということになってはいますが、元はと言えばシュアールには苗字の文化がなかったんです。
セバスティアンの父にはアレハンドロという名前もあって、それは1960年代ごろにエクアドル政府にID登録を押し付けられた際につけられたものですね。つまり、役所の人間に言われる形で、ツァマラインという本来名前だったものを苗字ってことにして、アレハンドロという名前を自分につけた。それも「じゃあアレハンドロでいいか?」みたいに役所の人間に言われたからそうしたくらいな感じ。そもそも、名前というものにあまりこだわりがないんです。
基本的にはファーストネームも自由に変えることができます。だから、セバスティアンも常々名前を変えたいと言ってました。どうやらセバスティアンって名前はスペイン系の名前らしいから違うものをつけたいんだ、と。それくらい入れ替え可能なものなんです。僕は光海(あきみ)という名前ですけど、お前を受け入れるにあたり別の名前を与えようみたいになんとなくなって、それで彼らは僕のことをナンキと呼んでいたんです。
清水 名前を取られてしまうというのは『千と千尋の神隠し』に出てくる湯婆婆みたいですよね(笑)
太田 そうですね(笑)。でも重要なものだから与えたり奪ったりするというより、彼らの場合はこだわりがないという方が近いかもしれないです。
清水 本当の名前がどれか分からない。それと近いかもしれないけど、映画自体、全てが噂話みたいな感じになってますよね。あいつがあれを見てこう言っていたらしい、みたいな断片的な噂話をそれぞれが話していて、そこからしか世界が伝わってこない。ひたすらチチャ(酒)を回しながら仕事をしている感じとかも、小説でいうとフォークナーや中上健次の描いた世界観と似ている。客観的世界がこうであるということが示されることなくズルズルとシュアール族の世界を辿っているような感じがあって、それが僕には心地良く感じられたんですよ。

チチャを運ぶシュアールの人々(映画『カナルタ』より)
太田 そこは割と意図的に編集に落とし込んだポイントですね。彼らの生活がそもそも断片性で成り立っていたので、「これはこういうことなんです」とスッキリさせる編集では撮影対象である彼らとその世界観に肉迫できないと思いました。
清水 シュアール族の暮らしを見ていると、森であらゆるものが腐敗し、発酵し、熟成していくというプロセスと、その中で人間が何かを食べ、消化していくというプロセスの境界があまりないんですよね。連想したのは人類学者の石倉敏明が言っていた「外臓」という言葉です。身体が内も外もなく大きな腐敗過程の中に放り込まれているようなイメージ。おそらく、様々な実践を通じてネグエントロピーを増やそうとしているんだけど、その階層が何層も共存的に存在している。実際、彼ら森の木とかもバカバカ切ったりはするんですよね。山の隙間に種をまいて植物を育てるようなこともやってる。原始的な農業。そういう森との関わり方も面白くて、ミシェル・セールが言ってた「林間の空き地 Clairière」という言葉も思い出しました。われわれの知はその連続性が全体として見えているわけではない。そう思えるのは錯覚で、海の中の孤島のように点々としてある、それを「林間の空き地」に喩えたんです。
太田 なるほど、点々としてある、と。
清水 そう、森の奥へと分け入っていくようなイメージですね。暫定的に切り開くというような。セールはフラットネスをとても嫌った人なんだけど、シュアール族もフラットネスに抵抗しているように僕には見えたんです。どんどん奥へと入っていこうという感じがあった。平らなところでゆっくり牧畜をしているのなんて嫌だ、みたいな。多分、日本の縄文人とかもそういう感じだったんじゃないかと思うけど。
太田 フラットネスへの抵抗、というのはとても的を射ていると思います。それがいわゆる西欧主義的なレジスタンスなのか、というとまた少し複雑だとも思うんですけど。例えば、彼らは農作物を均等に植えたり、きれいに配列することを嫌う。バラバラの種を、こちらには規則性がわからないような形で植えるんです。「どうしてそうするのか?」と聞いたら、「この方がキレイだから」とか「うーん、わからない。そういうもんだから」とか言われるんですが、とにかく彼らはフラットネス、またフラットな空間の使い方をエステティックな問題として身体感覚レベルで不快に思い、避ける傾向があります。岡本太郎も言っているように、縄文時代の土器などからは、今のメインストリームにおける日本的美学とは別種のカオティックな魅力がありますが、縄文土器はアマゾン先住民たちの作る土器とその荒々しさにおいて非常に似てるとも思いますね。
清水 あと映画にはドラッグが2種類くらい出てきましたね。実際のところ、どうでした?
太田 いや、トリップしますよ(笑)。ただ、彼らがそれをしたらこうなると証言していたことと僕が体験したことの間にはややズレもありましたね。彼らはよく、ある人が現れて自分自身にいろんな景色を見せてくれた、自分はそこでこういう光景を見たから今後こうなっていくんだ、というようなことを語るわけです。そういう話を聞いてると、それを摂取することで何か目の前に預言者みたいな存在が現れて、進むべき未来を明示してくれるかのようなイメージを持ってしまうんだけど、実際に僕が体験したのはそんなに単純なものではなかった。なんというか、もっとハチャメチャなヴィジョンでした。
清水 もっと幾何学的なイメージ?
太田 最初は幾何学的なイメージから始まるんです。わかりやすいところではディズニーランドにスペースマウンテンという乗り物があるじゃないですか。あれを超音速で乗っているような感じ。もしくはドラえもんのタイムマシーンが通り抜ける4次元空間も近いかもしれない。全部がレインボーで、よくヴィジョナリーアートなんかで描かれているようなカラフルなイメージ、多くの場合、あの感じから始まるんです。
清水 アヤワスカをすると吐くらしいですね。
太田 吐きますね。
清水 あともう一つ出てきたドラッグはなんでしたっけ?
太田 マイキュアですね。あれは吐かないです。ただ、どちらにしても言えることは、さっきイメージの話をしましたけど、視覚的な部分だけではなく体験全体が変わるんですよね。まず耳から変わる。めちゃくちゃ遠くで飛んでる蚊の羽音が急に耳元で聞こえてくるようになるんです。
清水 それは幻聴として?
太田 いや、感覚が鋭くなってるんですよ。そこから徐々に脳の思考や認知を司ってる部分のリミッターが外れていき、自分が思っていない自分の言葉が脳内でグルグルと回り始める。声が聞こえてくるんです。

森の奥深くでヴィジョンを授かる(映画『カナルタ』より)
清水 ジュリアン・ジェインズの『神々の沈黙』みたいな感じですね。古代の人にはいわゆる自分の意思のようなものがなくて、幻聴の声に従って生きていたのではないか、ということが書かれた本なんですが。

『神々の沈黙』ジュリアン・ジェインズ著
太田 そうそう。ずっと声が聞こえてくるんです。自分の中から問いかけのようなものがどんどん出てくる。その問いは普段の僕が考えたこともなかったような問いで、それに僕自身が応答していくんです。
たとえば最初に僕が観たヴィジョンでは、「お前は将来キリスト教徒になる」って言われたんです。多分、それをした時、僕がちょうどアマゾンに入ったキリスト教の宣教師たちが土着文化を否定してきた歴史に直面していた時期でもあったので、心で感じていた歯がゆさのようなものが関係していたのかもしれません。ただ、いずれにしても、僕はその自分の声を否定せざるをえないわけですよ。キリスト教徒になるわけないじゃないか、と。でも一方では次の瞬間、脳内で「よし、俺はキリスト教徒になるぞ」と言い出している自分もいるんです。「いや、なんでだよ、なりたいわけないだろう」って叫ぶんだけど「いや、俺はなる、俺はなる」みたいな声が止むことはなく、むしろ増幅されていく。そんな感じで意識がグルグルと回転していくような感じなんですよね。
清水 なんかすごいですね(笑)
太田 すごいんですよ(笑)。預言者がお告げをくれるみたいなシンプルな体験では決してないんです。
清水 僕はそういうものをやったことはないんですけど、人格の境界というものが皮膚の境界のようなものではないだろうということは分かります。
太田 そうですね。人格の境界は明らかにおかしくなっていました。
単自然論的な世界観の崩壊
太田 ところで清水さんは『今日のアニミズム』という本の出版を準備されているんですよね?

『実在への殺到』清水高志著
清水 人類学者の奥野克巳さんとの共著ですね。ここ数年、色々と考えたことをようやく出せるかなという感じです。11月には発売になるんじゃないかな。
太田 楽しみですね。ここ数年は主にどういうことを考えられてきたんです?
清水 バイナリーロジックをどう調停するかという問題を西洋哲学から仏教思想まで色々と渉猟しながらあれこれと考えている感じですね。
太田 なるほど。
清水 ざっくり説明すると、二項対立に対して、ヨーロッパの人は弁証法だったり脱構築だったりと、ある一つの二項対立の中でそれをどう処理するかということをまず考えるわけですよね。それで、その際に見つけた解決法を他の二項対立に敷衍していくわけです。ただ、僕はそれだと問題は解決しないと思っていて、むしろ最初から二項性を増やしてそれらを組み合わせていくことによって問題を調停するという方向を考えてるんです。
これは現代の人類学、たとえばフィリップ・デスコラやブリュノ・ラトゥールが考えていることとも繋がっています。あるいは僕が研究してきたミシェル・セールなどもそういうことを考えていた人です。僕自身としては三種類くらいの二項対立を組み合わせてみるということを考えています。一と多、主体と対象、包摂と被包摂という三つの二項対立。その上で道元や岩田慶治などを精読したりしてきてたんですが、最近はかなり自分の中でロジックが明快になってきましたね。
太田 さらにそれがアニミズムに繋がっていくわけですよね?
清水 そう。東西哲学を融和するっていうこと自体、まずとてもハードルが高いんだけど、今回はそこからさらにアニミズムに飛ぼうというわけで、三段跳びみたいになっているんですよ(笑)。その上で重要な視点としては、特殊なのはアニミズムの方ではなく近代西洋の方であるということなんです。西洋ロジックはさっきも言ったようにある一つの二項対立を解決してから、その次、その次へと敷衍していく。これがやっぱりダメなんですよね。どうしても還元主義的になる。つまり、一方の極が他方の極に還元されてしまう。実はそうした近代西洋的な考え方を崩したところにある文明は大体が同じ考え方で世界を見ているんですよね。シュアール族もそうだと思います。『カナルタ』でいうと、セバスティアンが森に生えてる草を口に含んでみて、これは毒ではないから薬だ、みたいに話しているシーンがあるじゃないですか。あれなんかとても面白いなと思ったんですよね。
太田 そうですね。ただ、彼らにとってはそれさえもまた向き合い方の一つなんですよ。セバスティアンがこれは毒ではなく薬だとある草について言った時に、そこで一つの言説が生まれるわけですよね。じゃあシュアール族はその後も、その草を薬と判断し続けるのかというと、そうでもない。それは薬草に対する一つのパターンの向き合い方でしかない。

セバスティアンは集落においてメディスンマンとしての役割を担っている(映画『カナルタ』より)
清水 古代ギリシャもそうですよね。毒と薬は表裏一体のものとして考えられてる。
太田 彼らは一方で毒と薬というようにバイナリーロジックで考えているわけだけど、もう一方では薬も飲み過ぎれば毒になるし、毒もまた量や場面を限定すれば薬になるという風に考えるわけです。
清水 そう、その二項が反転しうるということがミソなんですよ。ちょっとそのあたりを説明すると、ヨーロッパの議論はそれこそ中世にドゥンス・スコトゥスが排反関係にあるいくつかの二項対立(無限と有限、一と多など)を「離接的様態」と呼んでいた頃から方向性が決まっていて、そこでは二項のうちの一とか無限とかが「優勢的様態」とされ、それらがいずれも「神の述語」であると考えられていたわけですよ。神に近い側が決まっている。そういう思考の伝統が近代になっても、さらに強固になって残っているんですね。主体は統合するもの、統合されたものとしてあり、一方で多様なものとしての現象界があり、その多様性は最後には人間理性の限界を考慮して一応留保するということで、「もの自体」というような形で取っておくみたいな話になってる。そういう形ではなく、複数の二項対立の組み合わせ自体を変えてしまおうという話に今はなっているわけです。対象となるもの一つに対してエージェントとしての人間的要素が複数ある状態、その循環を考える。ラトゥールのアクターネットワーク理論がまさにそういうものですよね。

『社会的なものを組み直す アクターネットワーク理論入門』ブリュノ・ラトゥール著
ここで大事なのが反転なんです。一と多という二項対立があるとすると、それと組み合わされるたとえば主体と対象のような別の二項対立がある。その片端がもつ性質が一でもあるし、ひっくり返れば多でもあるということ。またその状態が共存しうるということ。本来だったら矛盾律によって共存しえないはずのものが共存しうるということなんです。
太田 僕は人類学をやっていることもあってもうちょっと具体的な状況を想像したいんですが、たとえば一が多に反転する場面というのはどういう状況なんでしょう?
清水 たとえば…そうですね、ちょっと迂回すると、今は客観性という言葉の意味が大分変わってきていると思うんですよね。これまで客観というのは間主観的なものであって、いろんな主体があってそれらで調和をとったものが客観的だみたいな話がドイツ観念論的にあり、長らくそう思われてきたわけです。ただ、この場合、一応「客観」って言ってはいるけど、全てが人間の話なんですよ。オブジェクティビティと言ってみても本当のオブジェクトがそこにはないんです。
脱構築主義まではずっとそうだったわけです。たとえば人間と自然という二元論があったとして、自然に他者性を見出してそこをエンパワーしていけば二元論がやがて緩和されると考えられてた。これは一と多で考えてもよくて、一に対して多をエンパワーしてどんどん多様性を増進させていけばいいと考えられていた。ただ、無限にはそんな作業をやってられないから「もの自体」みたいな概念が必要だったわけですよね。
でも、人間が自然を、一が多を統合するという役割自体を変えない限り、実は主体である人間の側、一の側に燃料を投下していただけだということがわかってきた。そこで今は、あるものに対して複数のエージェンシー、複数の人間が関与しているという状況をまず前提とするようになったわけです。そして、そのように人間が複数になったことによって起こる競合によって媒介としてのものがより分かるようになるというところも見えてきた。
たとえばセールはラグビーボールとラグビー選手の関係でその構造について書いていたけど、ラグビーボールは媒介でありつつ、プレイヤーである選手が増えることによって逆にボールの方が能動的に振る舞うようになる。それによってボールのもつはっきりした意味あいが分かるということがあるというわけです。プレイヤー各人にとってのフォーメーションの意味も違うし、それらはたがいに包摂しあっている。同じボールを見ているようでも、各人が見ているものはまったく違う。ここでは一と多、主体と客体、包摂と被包摂がすでに相互に反転するものとして現れてくるんですよ。
つまり、統合的なものとしての人間がだんだん成立しなくなってきたのと同時に、人間によって統合されるべくある一つの世界という単自然論的な世界観も崩壊してきたんです。これは人類学のトレンドとしてもある流れで、そういう多自然論や多世界論というのは、すでに人文科学の中ではデフォルトになりつつあるわけですよね。
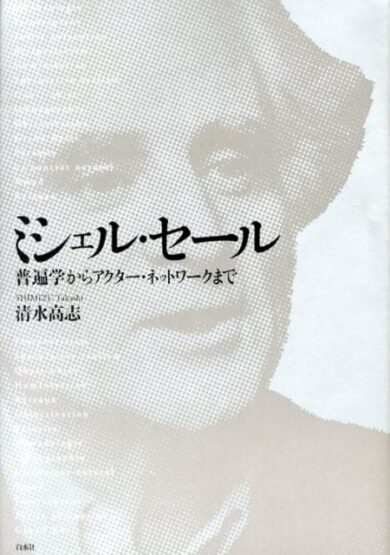
『ミシェル・セール 普遍学からアクター・ネットワークまで』清水高志著
太田 なるほど、「多なる世界」については、僕もアマゾンに行く前からずっと考えています。そして、アマゾンに行ったあと、自分がぼんやりと描いていたマルチユニヴァースというものが、想像よりもはるかに複雑で、しかも逆説的に体感では「シンプル」とすら感じる状況に直面して、いまだに戸惑っていますね。少なくとも僕が思うのは、脱構築主義以降の多自然主義的な思考は、まだ人文・社会科学の限界の中でもがいているということです。じゃあそこにバイオロジーとかニューロサイエンスが介入してきたときに、より多世界論として豊かになっているかというと、そうでもないしむしろ逆に硬直化を招いているようにも見える。ただ、統合されるべくある一つの世界、という世界観に対して、深く抉るように概念を刷新する動きが方々から出てきているのは間違いないですね。
清水 さらにいうと、仏教もまたそうなんですよね。仏教というのはずっと一つの客観的な外在的世界というものは存在しないという議論を延々と展開してきたわけです。唯識仏教なんかまさにそうでしょう。ヨーロッパ人は唯識仏教をドイツ観念論的に理解して、唯一の識があるみたいな理解をしがちなんだけど、ぜんぜん違う。実は唯識仏教における唯識も三項構造になってるんです。相分、見分、自証分としての識というように、見ている自分、相として現れている世界があり、この二者を識が包んでいる。さらに主体の見分にも、眼識、耳識、鼻識、舌識、身識という五感があり、それらが全て相分と関与して循環するようにリアクションを得ながら、世界を捉えているとされたわけです。
重要なのは、そこで捉えられた世界が三項構造に包摂された識の世界に過ぎないということです。また識の世界で見ているその人も、他の誰かの識の世界に今度は相分として入っていく。つまりパースペクティヴが違うんですね。こうした相互入れ子構造が仏教思想にはベースにあるんです。こうした相互入れ子の構造から、一即多、多即一の華厳の世界観がさらに発展して開顕されていくわけです。
これは完全に多世界論そのものなんですよね。マルクス・ガブリエルのベストセラーになった『なぜ世界は存在しないのか』もそういうことを言っている本でした。客観的で唯一の包摂者としての世界は存在しない、ということがあそこには書かれていて、世界同士が相互包摂しているという話なんです。意味の場同士がそれぞれ相互包摂しているのであって、最大の《世界》があるわけではない、と。
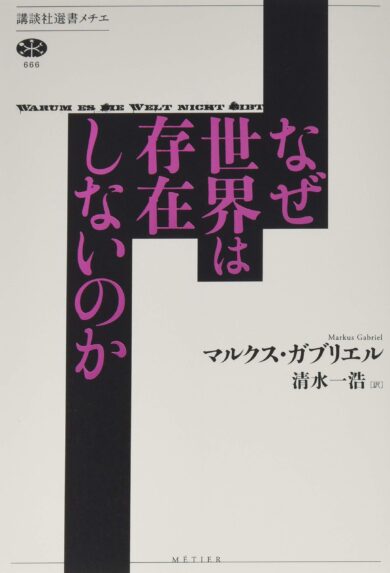
『なぜ世界は存在しないのか』マルクス・ガブリエル著
『カナルタ』を観ていてシュアール族もそういう風に世界を捉えているように感じましたね。ああだこうだとみんなで言い合っていて、客観的な次元がない世界、あるいは全部が相互に包摂しあって存在しているような世界。シュアール族だけではなく、僕は今少しずつ世界中のリアリティがそっちの方へと移っていってるように感じているんです。
メテクシス──個別が一般を含むか、一般が個別を含むか
太田 なるほど……。ただ、唯一の客観的事実は存在しないということは、それこそ古代ギリシャ時代から言われていることだとも思うんですよね。そことマルクス・ガブリエルが「世界は存在しない」と言うのとでは何が違うんでしょう。僕自身はガブリエルをまだ読んでいないんですが。
清水 唯一の客観的世界が存在しないということを素朴懐疑論として言うんであれば、それはただの懐疑論なんですよ。実際、マルクス・ガブリエルを素朴懐疑論として読んでしまってる人は割と多い。でもその読み方は文字通り素朴すぎるんです。
というのは、相互包摂の世界というのは、始まりも終わりもない無始無終の世界のことであって、別に懐疑の世界ではないんですよ。それはそういうものに過ぎないだけであって、相互包摂の世界としてちゃんと存在しているんです。ライプニッツだとそれをモナドたちが相互表出しあっていると表現しますね。そこから合理的な世界の理解が演繹されるような、絶対的な始点があるわけではない、そのなかで、深い森のなかに分け入っていくように思考し、生きるということが重要なんじゃないか。
それこそ、そういう「含む」という問題に関して面白いことが書かれているのはプラトンの『パルメニデス』ですね。あの本ではイデアの根本をソクラテスが説いていて、それに対してパルメニデスが批判していくという形になってます。
論理の前提として、たとえば「これは白いものである」みたいに一般概念に個別のものが落とし込まれてしまうと、もうそれについて「これは黒いものである」とは言えなくなるわけです。つまり、「~である」というロジックの中では矛盾律が必ず成立する、と。ところが、逆に個別のものが違う一般的性質を含んでいても、矛盾律には必ずしも抵触しないんです。たとえば、ここにあるビールの缶は分子よりも大きいが僕よりは小さい、ということは矛盾なく言えるわけです。
つまり、含まれる、属するというのには2種類あるんです。個別が一般を含むか、一般が個別を含むか。後者の場合は矛盾律が成立してしまうけど、前者の場合は一般概念への個物の分類ではないので矛盾律があてはまらない。だからあえて「大きさそのもの」「小ささそのもの」という一般概念(イデア)を立てて、個物がそれを分有すると考えたらどうか? そうすればあるものが「大きくかつ小さい」ということも成りたつ。「大は小である」とか、「小は大である」のような矛盾したことをいっているわけではないので。こういう話を20歳くらいの設定のソクラテスがまずしていて、それに対して65歳くらいの設定のパルメニデスが反論するんです。古代ギリシャの哲学界最強のラスボスであるパルメニデスがどう反論するかというと、それはメテクシス μέθεξις、つまりあるイデアを分有するというのだから、その部分を分有しているのに過ぎないだろう、とそう言うわけです。そして、それとは別にその部分としてのイデアを含んだ本物の一般概念そのものがあるはずだろうと反論するんです。パルメニデスにとって、一番包摂的で大きな一般概念で存在者と言えるものは一だけなんです。「はい、論破!」みたいな感じでコテンパンにやられる。(笑)
このメテクシスの問題が面白いんですよね。メテクシスは「あずかる」とか「分有する」という意味なんだけど、ラテン語だとparticipatioになるんです。英語でいうparticipationですよね。こちらには「持つ」という意味と「参加する」という意味がある。つまり、何かを含み持つことと、何かのグループに参加し、含まれることとは表裏一体なんですよ。おそらくソクラテスもこんな言い方をするんですからもやもやと予感してはいるんですが、まずはこの表裏一体性をはっきり抽出・分離して、それからそれをまた個物の性質として返してやるかたちで二元論を克服しておかないといけなかった。そうでないとせっかくさまざまなイデアを分離して個物がそれをメテクシスすることにして二元性を乗り越えようとしても、ソクラテスのようにパルメニデスによって無残に葬り去られてしまうことになる。含むものと含まれるものの関係が一方向的だ、という前提にイデア論は引きずられてしまったんですね。
その点、インド人はここをあらかじめ分けていたんですよね。メテクシスの二重性を早めに分離していた。一番の問題は「AがBにおいてある」か「BがAにおいてある」かという問題です。「おいてある」ということを考えると先ほどの包摂関係を循環関係で考えられるようになる。AがBを、BがAを条件として成立する、一方がなければ他方もないという関係が、縁起の思想ではあらゆる角度から考察されるわけです。しかしこれは、主体と対象とか一と多とか、さっきの話も同じですよね。対象が一であって多でもあるとか。第三項を別の二項対立の一極から借りてくれば、包摂関係が順繰りにどのようにでも辿られる。二項対立がどちらの極に還元されるわけでもないということをもっともシンプルなかたちで抽出し、そこからさらに現実の世界を捉えなおすということを、すでにインド仏教は考えていたんです。
太田 インド仏教がそこに到達していたということを西洋側の知識人はどこまで理解しているんですかね? 僕の知る限りでは多分そういう風に仏教思想を理解している西洋人は少ない気がします。
清水 全く分かってないと思いますよ。仏教は近代以降、日本人も理解していないし、それこそナーガールジュナが分かるという人はチベット人でもほとんどいないでしょう。『中論』を読んでみれば分かるけど、一見、全く意味がわからないことを言ってますから。僕はそれを論理化しようとしているわけですよ。ただ、文脈は違うとはいえ、今日の人類学はそこらへんの話をかなり展開していますよね。デスコラしかりヴィヴェイロス・デ・カストロしかり。
「アニミズム」という言葉はなんのためにあるのか
太田 そうですね。ただ、最近の人類学の成果に関しては、僕個人としては思うところもあるんですよね。人類学の世界把握の方法、テキストであがってくる上澄みの部分と、実際の人類学者がそれをどのように積み上げていくのかという部分にはかなり差がありますから。あるいは、人類学が他のディシプリンにどういう風に関わっていくかということについても、日本と西洋ではかなり差があるように思います。日本には日本特有の歴史性があるんですよね。それこそ山口昌男とかそういう人たち以降の人類学が日本社会で受容されていく流れは、僕が9年学んでいたヨーロッパにおけるそれとはだいぶ違う。
だから僕はどうしても、たとえばデスコラがある抽象的な理論を打ち立てましたという時に、デスコラがどうやってそこに辿り着いたんだろうと想像してしまうんです。あいだにかなりのギャップがあるんですよね。ヴィヴェイロス・デ・カストロもそうですけど、僕は実際に彼とも会ったことがあって、彼のもとでマスターをとったブラジル人の友達とかもいるわけですけど、彼がどうやってパースペクティヴィズムとか、マルチナチュラリズムに辿り着いのか、そこには色んな政治性とかも関わっているということを知っているわけです。だから、彼がアマゾンの人はこうなんだ、マルチナチュラリズムなんだと言ってきた時に、はい、そうですかと受け取るだけではいられないんですよ。むしろその抽象化の過程そのものが気になってしまうんです。
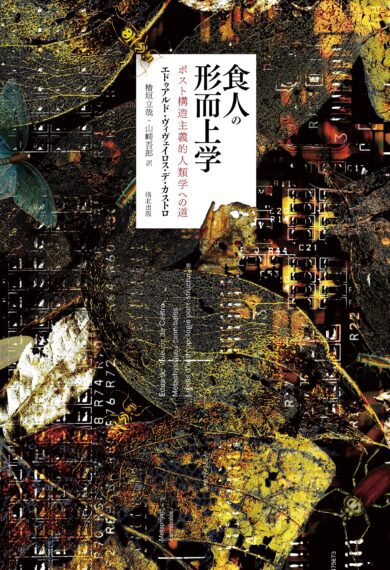
『食人の形而上学 ポスト構造主義的人類学への道』エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロ著
清水 なるほど。ただ僕からすると、ヨーロッパ的な単世界論の方が、特異な世界観なんですよね。何段階かのステップを踏まないと認証しえない。その特異性をはっきりさせる上で、人類学者の言っていることもヒントになるというところなんですよね。セールも、唯識仏教も、その意味では僕にとって全部断片なんです。
自分も日本という非西洋の文化圏で生きて育ってきて、仏教などにもうんと古くから関心を持ち続けてきたんですが、本当にその文明の核を掴もうと思ったときに、こちらはこちらで内圧をかけてぎゅっとそれを抽象化しないといけない部分がある。デスコラがすごいのは、レヴィ=ストロースがさまざまな二項対立を読み解きながら非西洋の文化を考察したように、典型的な西洋近代の世界観も意外と扱えるのではないか、その思考も組み合わせのヴァリエーションのなかの一つに過ぎないのではないかということを、西欧側からの文化相対論ではないかたちで突きつけたところにむしろあると思いますね。彼は西洋近代の思考をナチュラリズムと呼んでざっくり定義していますよね。
弁証法的であったりカント的であったり、そういう世界観というのは、むしろ相当な加工を経てつくった世界観なんですよね。それは民族誌をそこまで大量に読み込まなくても分かる。ただ、あらゆる事象の説明の仕方にヨーロッパ的な世界観が今日では強く反映されているんですよね。日本もまた、そこにかなり順化されていて、物の見方の深いところにヨーロッパ的なものが浸透している。
ただ、そうは言ってみても、歴史的に見ればみんなそんな風にものを考えてきてはいないわけで、お前の自我はそんな統合されたものなのかといえば、実際そんなこともないわけですよ。様々な境界が曖昧だし、主客だって未分だし、そういう体感があるのにも関わらず設定だけがそうではなくなってる。いまだに近代西洋的な設定が強いんです。
この設定が今崩れ始めていて、その先により普遍的な世界が見えてきてるわけですよね。違う知のあり方が。僕はその知のあり方を仏教の中観思想や唯識仏教を経由してアニミズムに戻っていくような形で辿っているところなんですよ。

『自然と文化を越えて』フィリップ・デスコラ著
太田 おっしゃることはわかります。ただ、僕にはその際のアプローチの仕方を問題にしたいところがあるんですよね。たとえば、僕はアニミズムって言葉そのものにも疑問があるんですよ。というのも、僕自身がその言葉がなんであるのかということをアマゾンにいた時に考えざるを得なかったからなんです。アマゾンの人たちと話していても、当然、ヴィヴェイロス・デ・カストロ的な言葉遣いでは彼らは話さないわけですよね。「君たちのアニミズムってなに?」って聞いても「そんな言葉知らねえよ」ってなるわけで、「逆になんだよそれ?」って聞かれるわけです。そこで、「あなたにとってのマニオク酒はジャガーにとっての血なんでしょう? 」と聞いてみれば「なんだよそれ」って笑われるわけです。そうなるとアニミズムって言葉自体が一体なんのためにあるのか、よく分からなくなってくるんですよ。
清水 まあ、アニミズムはタイラーがつくった言葉だけど、タイラーは西洋人が宗教がないと思っているような人たちにも宗教が存在することを示したくてアニミズムという言葉でそれを示したわけですよね。
太田 もちろん。タイラーの功績を否定したいわけではないんです。これは僕がなぜ映像という手段をアプローチとして取り入れたかというところに関わる話なんですよ。今話したように「アニミズムなんて知らねえよ」と彼らに言われてしまった時に、僕は選択を迫られるわけです。タイラーによるのか、つまり彼らを理解するために彼らの行為を定義して分析する側に回るのか、あるいは彼らが語る概念から彼らとともに出発すべきだとするのか。後者の場合、アニミズムという言葉には有効性がないことになる。その二者択一を前にして、どっちにも振れずに表現することが可能だったのが映像だったんです。映像であれば、そのどちらの立場にもYESともNOとも言わなくていい。
清水 そうですね、僕からすると、定義しておくべきはナチュラリズムの方なんですよ。こちらの方が特殊なんだから。その上でアニミズムという言葉やデスコラ的な分類には意味があると思うんですよね。実際、日本の学生と哲学の話をしていると必ずデカルトが考えていたようなことがいまだに出てくる。ものすごく強烈にナチュラリズム的な思考が浸透していて、それ以外の世界像を想像してみろと言っても難しくなってるわけですよ。パースペクティヴィズムだったりアニミズムだったりは人類学の中から出てきたキーワードだけど、そうした断片的なキーワードさえなしにナチュラリズムとは違う世界像を立ち上げるというのはなかなか大変なんですよね。だからこそ、すごく単純明快化された要素というのは大事なんです。西洋人が普通の日本人に、仏教の核心はなんだと訊いても、まず答えられるわけがない。鈴木大拙くらいを連れてくるしかない。しかし仏教的なるものは一般の人にもやはり浸透している。ヨーロッパ人だけが抽象的にものを考えていて、他の文化にはオントロジーや論理的構造がないのかと言ったらそんなことはまったくない。あるわけです。それを示すためには、それこそナーガールジュナの『中論』のようなものをデスコラが単純化したみたいな形で濃縮して再考する必要があるんですよ。
太田 単純化した方がいい、と。
清水 もちろん。一旦きちんと単純化して、普遍的な形で示した方がいいんです。
西洋人類学への違和感
太田 そこで言うと、僕は今のヨーロッパ的知性が、まだこれまでの近代主義的世界理解が傲慢な誤りだったという段階には達してない気がしますね。さっきヴィヴェイロス・デ・カストロについて言いたかったのも実はそこで、そもそも彼らが本当に表現したいことを表現しているかというとそうでもなく、マテリアルな世界から隔絶された言説空間の中で誰が天下を取るかという争い、つまり単にポジションゲームのようになってるところもあるわけです。「言説を通して世界を自分が俯瞰できる」という感覚それ自体が、僕にとってはデカルト主義的に見える。その辺に矛盾を感じながらヨーロッパにずっといて、そこから抜け出すための回路として映像人類学があったんですよね。
清水 文学とかアートにいくしかないわけですよね。
太田 そう。だからデスコラとかについても『自然と文化を越えて』よりも初期の著作や論文の方が好きなんです。そっちの方が具体的なエピソードが並べられていて面白い。ある程度、具体的なことをやり尽くして、壮大で抽象的な理論を提示して一抜けみたいな感じなんですよ。政治性が強いんです。で、その本だけが日本では翻訳されていて読まれてる。本当はその前の仕事の方が面白いのに。
あるいは、そもそもフィールドで行われる参与観察のあり方が、僕が考えてる参与観察とヨーロッパ人のそれとではかなり違うんです。たとえば僕は彼らの家に彼らと共に住み、彼らと同じ作業をして、自分を彼らに一体化させていくという形でフィールドワークを行ったんですけど、ヨーロッパのPhDの人たちは別にそれをやる必要がないんですよ。
清水 へえ、それをやらないで、ただボーッと周囲で見てるんです?
太田 そうです。あるいは一番知識がありそうな現地人にとにかく話を聞き、メモを取る。わざわざ彼らと一緒に草刈りなんてする必要がない。そういう考え方なんです。ただ、僕はヨーロッパに行ってから初めてそういう考え方に出会ったんですよ。日本で人類学の手ほどきをちょっとでも受けてたらそうは考えない。まず第一に対象と同じことをとにかく全てやれ、と教わるわけです。その上で感じたことをノートに取れ、と。日本で人類学が発展してきた固有の歴史の中で、そもそも主客の問題がヨーロッパとは違う形で受け止められてるんですよね。日本の人類学では元から主客を曖昧にさせることを重要視しているので。
今回、清水さんの『今日のアニミズム』の原稿を部分的に読ませてもらって、まだまだ内容としては未消化なんですが、岩田慶治のコスモスと曼荼羅の対比、あそこはとても面白かったです。コスモスは外から眺めた世界の形象であり、一方の曼荼羅は動的な行為者が中にいて世界をつくっていくものなのだ、と。これはまさに今の話ですよね。

チチャを作る(映画『カナルタ』より)
清水 そうですね。もっと言うと、さっきの僕の話とも近いんです。コスモスとして世界を見て、いかにそこの多様性を語っても、見ている主体に素材や燃料をあたえてエンパワーするだけなんです。フンボルトとか昔の博物学者がやっていたのもそういうことだった。だから岩田は参与観察という形で自分自身が中に入っていかなきゃダメでしょって思ったわけですよね。
太田 ただ、それは現在のヨーロッパにおいてはまだきちんと浸透していないんですよね。
清水 ヨーロッパでは客観化しないといけないからあえて一緒にならないみたいな考えがいまだにあるんですかね。
太田 そう。私たちは客観側なので、彼らと同じことをする必要はないし、なんならしちゃいけない場合もあると彼らは考えてる。
清水 一方でマリリン・ストラザーンなんかは割とそういう考えを批判してますよね。文化と自らを繋ぎつつ、切り離されているのがフィールドワーカーである、というのはポストモダンの考えなんだって。
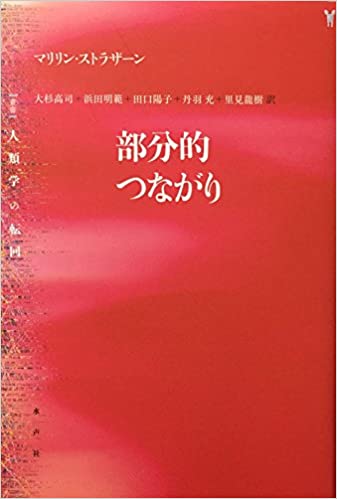
『部分的つながり』マリリン・ストラザーン著
太田 ティム・インゴルドもそういう批判はしていて、ただ逆にいうと、それがヨーロッパではラディカルに聞こえるほど、それをしてない人が多いということなんですよ。インゴルドが「内側から知らなければならないんだ」とあんなに頑張って訴える切実さは、多分、日本の人類学者には分からないと思う。「ああ、そうだよね、私もそう思う」くらいの感じじゃないかな。そもそも、そういう風にやってきてるわけですから。ただ、向こうではインゴルドのそういう姿勢をバカにする人もまだまだいるんです。

『メイキング 人類学・考古学・芸術・建築』ティム・インゴルド著
清水 そこまで言うのか、みたいな?
太田 お前は自分の思いを話しているだけで理論化もできていないじゃないか、と。インゴルドなんかはどちらかと言うと真面目な論文投稿をするタイプではなく、ポピュラーライティングをする人みたいな形で受け止められてもいて、でも彼がそっちにいかないといけなかったという切実性がそこにはあるんですよね。レーン・ウィラースレフとかにしてもそうで、面白いんだけれども日本的にはすでにあった視点だとも思う。ただ日本人は謙虚だから、大したことを言っていなくても一応は拝聴するわけです。その点、向こうは一切拝聴なんてしないですからね。日本人は一度はきちんと読むし、共感しうることが書かれてれば「確かに」となる。「新しくないものよこしやがって」と怒ることはないわけですよ。

『ソウル・ハンターズ シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学』レーン・ウィラースレフ著
清水 でもウィラースレフ以前にそれを書いた人がいたのか、というところもあるわけですよね。
太田 それはそうですけど、すでに存在していた視点だったわけですよね。それこそ清水さんの話だとインド仏教にもあったわけで。デスコラだってそうです。デスコラは一応、タイラー以来のアニミズムの理論を組み替えたということが功績になってるわけですけど、最も大きいポイントはアニミズムでは動物と人間が内面性において同一線上にある、ということを書いたことですよね。僕の友人のフランスの人類学者もそこが画期的だったんだみたいに言っているわけです。でも僕からすると、その感覚自体は目新しくもない。日本でも異なる文脈では同じようなことが書かれたことはあるわけです。そういう別の語りが捨象されたまま今まできていて、それをデスコラが言った途端に「わ、天才だ」となってる。そこにある権力構造や、言説というものがどう巡っていくのかというメカニズムについてはもうちょっと考えた方がいい気がするんですよね。
清水 デスコラってダンディな感じですよね。白と青しか着ないみたいな。確かにアマゾンに行って先住民と同じ作業するタイプにはあまり見えない(笑)
太田 少なくとも日本で指導されるようなほどには、同じ作業をしていないと思いますね。ただデスコラ個人の問題ではなくて、もっと遡ってマリノフスキーやエヴァンス=プリチャードとかの時代から彼らはコロニアリストとして現地に入ってるわけですよ。彼がアフリカに行った時の立場は上からなんてものじゃない。当時、エヴァンス=プリチャードは当局とかに守られながら堂々とフィールドに入っていったわけです。僕みたいに、一歩コミュニケーション間違えたら槍で殺されるかもというような、地べたからの経験はしてない。結構、そのアティチュードが白人には強くあって、それは先生から弟子へと受け継がれ続けているし、なんならフィールドの人たちの対応にも染み付いてる。僕がアフリカに入るのと、白人がアフリカに入るのとでは、現地の人たちの対応も違うわけですよ。僕の非西洋的な身体というものが現地の人との関係性の構築の上では要素の一つになっていて、経験のレベルでかなり違うんです。だから彼らがあっさりと理論化して語ったりする際にそういった経験の質について勘ぐってしまうんですよね。
清水 なるほどね。でも実際、日本人も日本の文化について西洋人に定義してもらうと喜ぶわけだよね。ちょっと日本に来ただけのロラン・バルトに天皇制を一言で定義されて、それをありがたがってずっと引用し続けてるんだから。だから、そこはもうちょっと認めてもいいのかもしれない(笑)。それにデスコラは知らないけど、セールとかはもうちょっと土臭い感じがするんですよね。もうちょっとこっちに近い感じがする。セバスティアンとかと近いというかね。ヨーロッパ内においても違う要素というのがあると思うんですよ。
太田 それもちろんありますね。
清水 それでいうとスペインはどうなんです? スペインの人類学。あそこは言うほど白人ではないですよね。
太田 スペインはヨーロッパのアカデミズムの中では完全に傍流ですよね。真面目に受け止められてない。それは多分、土着的だから。それこそ地を這いながら出てくるものだから。
清水 一方でヴィヴェイロス・デ・カストロなんかは受け止められてるわけですよね。
太田 ヴィヴェイロス・デ・カストロはすごく特殊なやり方で地位を確立したんですよ。彼は強烈にレヴィ=ストロース主義者であると自分で謳っているし、ドゥルーズの理論に接近しながらケンブリッジ大学で客員やってたんです。その時に論文とか本を書いてた。ブラジル人なんだけどレヴィ=ストロースとケンブリッジに接近することでそっち側に自分を転換させたんです。スペイン人でもそれをやればできるんです。カルロ・セヴェーリという『記憶の人類学』という本を書いている人も元々イタリア系ですし、そういうイタリア系、スペイン系の人もフランスの思想史に接続することで中心に入っていくことが一応はできるんです。
無限のイメージの泉
清水 前にエリー・デューリングと話したんだけど、その時にデューリングがヴィヴェイロス・デ・カストロと会ったけどいい男だったって話していたのを覚えてます。
太田 いい男ですよ、ユーモアにあふれてましたね。デューリングは芸術論の人ですよね。
清水 そう、彼のアート論もまた世界の相互包摂の話になってるんですよね。最終的にここにある世界とかの話ではなく、全体で含みあっている。含みあっているから何も言えないのかというと、相互に照応し合うものとして世界はある。
太田 清水さんとしては西洋におけるそうした潮流の元にいるのがライプニッツだということですよね。
清水 ライプニッツは観念がものの中に体現されるという考えをしていたんですよ。セールがライプニッツに言及しながら古代ギリシャの哲学者であるタレスの話をしていたことがあったんですが、有名な話ですがタレスはピラミッドの高さを測る時に杖を持ってきて、杖の影の長さでそれを測ろうとしたんですよね。影と杖の長さが同じときにピラミッドの影を測ればいい。その際には比例という観念が杖というものに体現されているわけです。そういうふうな形でライプニッツは観念というものはものや何らかのモジュール、記号の中において体現されるんだと考えていた。マテリアルの中から形相性が切り取られてくるという考えを認めるんです。十七歳の頃に恩師のトマジウスに宛てた手紙のなかでもすでにはっきりそう書いていますね。これがデカルトとかだと逆なんですよね。普遍的な概念である形相の中に個別のものが入っていって定義されていく形になる。それも認めるんですが、有限の質料のうちに形相性が含まれるということもありで、ピラミッドと杖のように違うマテリアルが互いに間接的に照応しあうというのが彼の基本的な発想です。
つまり、ライプニッツは形相と質料、入れるものと入れられるもの、一と多、そうした二元論を足していって包摂と被包摂を超える構造をすでにつくっていたんです。そうすることで閉鎖系になることなく全体の世界を説明しようとした。それがモナドロジーなんです。モナドロジーは部分によってだんだんと全体が構成されるという話ではなく、全体としての一なるもの、つまりモナドが多数あり、それらが相互に照応しあっているという話なんです。
それを理論的に引き継いで20世紀に現代の諸科学も相互照応と相互翻訳によってできているということを言っていたのがセールで、またいろんなものを動員して、主体が関与することで主軸になる科学的対象を作っていくというケーススタディを具体的に研究していたのがラトゥールです。ラトゥールの話に出てくる対象というのは、循環の中でできているんだけど、だからこそ却って独自のエージェンシーを持っている。そしてこうした対象もまた他のアクターとともに動員されて別の結節点を作っていく。ラトゥールの議論をセールの側から見ると、そういう風にしてしか科学は考えられないということになる。
太田 面白いですね。アマゾンではまさにそれがナチュラルに生活の中で行われているんですよね。それこそライプニッツの形相の話で思い出したことがあります。シュアール族の人たちって家を自分たちで建てるんですよね。誰も建築を学んだことがないし、数学も知らないんだけど、こう建てたら家はだいたい倒れないということが、あの家によって体現されているわけですよ。定規もメジャーもないので、測定も正確にはできないし、実際、棒みたいなやつでだいたいの長さとかを測って微調整してるんです。ただ、そのプロセスの中にエジプト人がピラミッドを使って考えたような数学的理解がすでにあるんですよね。
清水 あれはすごいですよね。我々にとっては家を建てるなんて大変なことなのに、夢で見たからとかそういう理由で家を建て始めちゃう。さらに酒を回されたらみんな喜んで集まってきて一緒に作り出してて。
太田 あれが可能になるためには多元的なエネルギーの流れがあるんですよ。すごい低いレベルでは早寝早起きしてるから体が元気なんですよね。森を毎日歩いてるから体幹がしっかりしていたり。あるいは前の晩に見た夢に従うということについてもそう。彼らには急に「夢で見たから」と言って家を作り出すのと同様に、たとえば「明日ここ撮影したいから一緒にここ行こう」と僕が提案して約束していたことが、翌朝になるとやっぱりやめたということもよくあるんです。理由も朝起きたら目の前をハチドリが横切ったから、だったりする。これはシュアール族ではよくない兆候だとされていて、だから俺は行かない、と。もしくは前日の夢で綺麗な女の人と遊ぶ夢を見た、とか。これは森で蛇に噛まれることを暗示しているんです。そうした色々な兆候が彼らにはあって、だから予定とかを立てられないんですよね。瞬間的に現実の定義が変わりうる。そういう多元的な流れみたいなのがナチュラルにあそこにはあるんですよね。
清水 映画の中で浄水設備を政府と交渉している女性のリーダーが出てきたけど、ああいうのですらひとつの夢の解釈なんですよね。あるいはセバスティアンの息子が医療資格を取るみたいなこともそう。近代文明もまた彼らの夢とともにある。
太田 そう、そこがパキッと分かれてないんです。たとえばセバスティアンは伝統医療に回帰すると解釈できるような行動をするわけだけど、息子が医療資格を得ることについては一方ですごく喜んでいるわけです。僕からするとそこをなんで突き破れるんだろうって悩んでしまう。「自分は近代医療に反対なんだ」という観念がもし彼らの中にあったら、本来、息子が近代医療の制度内で資格を得ていることを喜ぶことはできないはずではないか、と。ただ彼らにはそうした観念自体が希薄なんです。だから近代医療に反対だったならこれは受け入れられないだろうということや、こういう振る舞いをするだろうというようなステップを、彼らは水みたいに変形して躱していってしまうんです。
最初に話したようにアヤワスカで僕が見たヴィジョンはとても複雑で一言では言い切れないものなんですよね。でも、彼らにとってはそのヴィジョンが指針なんです。つまり、そもそもの指針の部分にめちゃくちゃ複雑でわけのわからないものがある。すると、全てがそこを基盤に融通無碍に移り変わっていくんです。たとえば、彼らはあるタイミングにおいて兆候として現れているものを夢の記憶から取り出してきて、今のこの瞬間にはこれはそうなんだというリアリティを一旦決めるんです。そして、それが本当になった場合、夢でこれがあったから今これが起きてるんだと語る。その時の彼らは100パーセントそのリアリティに生きてるんです。だけど、仮に次の日に全然違うことが起きた場合、今度は、あ、そういえばあの夢の中でもう一つ思ったことがあった、それがこれになったんだ、と解釈する。別の世界線が次から次にどんどん出てくるんですよ。さらにその世界線同士がロジカルに矛盾を起こすこともない。なんせ次々に兆候を引き出してくることができる無限のイメージの泉があるわけですから。

森もまた夢を見るのか(映画『カナルタ』より)
清水 面白いですよね。イメージのヴィジョン、これ僕にもあるんですよ。よく眠りながら思いついたことを起きたばかりの震える手で書いたりしてます。起きていて明晰だった時間は一日考えても分からなかったことが、眠ってる最中に「あ、分かった」となる。ただ、そのヴィジョンの方が論理的なんです。そういうことが何度もある。むしろ理数系の人のほうにそういうことが多いらしいですね。
太田 そうですね。僕の父は科学者なんですけど、風呂に入っている時にパッと何かの構造が思いついたりするって言ってましたね。
清水 ただシュアール族は夢のヴィジョンを書き留めることはないわけですよね。
太田 書き留めなくても完全に頭の中から消えるわけじゃないですからね。それはどこかで動いていて、ある瞬間にちょっと姿を変えて別の文脈で出てくることもあるかもしれない。そういうものとしてあるんです。
清水 そもそもシュアール族は文字についてはどうなんですか?
太田 基本的には無文字文化ですね。人類学的な解釈では完全なオーラルカルチャー。今はスペイン語の影響もあって、シュアール語を文字に起こすことはできるようになってるし、彼ら自身、識字もある程度はできるようになってきてますが。
清水 なるほど。やっぱり文字の文化に抵抗するというのが結構大きいんでしょうね。そうすることで人間が生きた文字になる。生きたメッセンジャーになる。
太田 そうですね。でも、そう思ってるのになぜ清水さんは抽象的に文字でゴリゴリやってるんですか?(笑)
清水 僕がこの時代の日本で生きたメッセンジャーになっても仕方がないじゃないですか(笑)。逆に禅とかがあまりに文字にしたがらない、ロジックにしたがらない感じの意味が僕には分からないんですよ。『臨済録』とかを読んでみると、中国人はその場の機知で表現することをすごく大事にしてる。その一方で知的であることを隠そうとする。佯狂の文化なんですよね。ただ、そのせいで禅思想はロジックではなくレトリケーになってるんです。その結果、もう向こうの人にも禅がよく分からないものになってる。だから、僕は一旦レトリケーになってしまったものをもう一度ロジックにしたいんですよ。
今日、コロナ禍で統計というものがすごく力を持っていますが、あれもまたレトリケーなんですよね。実際、ほとんど当たらないわけです。情報というのは情念を増幅する装置であって、ハメルーンの笛吹き男の笛に過ぎないものなのに、それをみんなが持とうとしている。言ってしまえば真実ではないものを真実にするために統計の体を取っているだけ。だから統計はレトリケーでありプレサイエンスなんです。石が落ちるという現象を前にして石そのものが落ちる原因を持っていると考えるガリレオ以前の考え方に近い。本来、他の様々なファクターを考えて数値化しないとサイエンスではないんです。そういう時代状況を見ても、一度、レトリケーとなったものをロジックに戻していく必要を僕は感じているんです。
ただ、そうとはいえ、映像には映像の面白さがやはりありますよね。『カナルタ』はまさに巨大な夢が森の中で繁茂していくような感じで、非常に心地良かったですから。我々が生きている世界というものも、その森の中から見ると小さな夢に過ぎないんだということを直感させてくれる。都市のフラットな社会から出てくるものよりもはるかに鮮烈なものがあの森にはありました。
太田 ありがとうございます(笑)。僕もまた今日はとても刺激を受けました。何より、ものすごく厳密な意味での論理的展開を重視しながらも、文化の境界やテキストが出てきた文脈も飛躍して、勇気を持って異なるものを接続していく清水さんのスケールの大きさに。書くことによる世界生成ですよね。それは僕が『カナルタ』を撮ろうと思ったきっかけにも近い気がします。全く別のアプローチですけど、世界をよりクリエイティブにしていく、根底から深く抉っていくということをお互い目指しているんじゃないかという気がしました。『今日のアニミズム』、楽しみにしています。

取材・文/辻陽介
✴︎✴︎✴︎
太田光海 おおた・あきみ/1989年東京都生まれ。映像作家・文化人類学者。神戸大学国際文化学部を卒業後、フランス・パリに渡り、社会科学高等研究院(EHESS)で人類学の修士号を取得。同時期に共同通信パリ支局でカメラマン兼記者として活動した。英国マンチェスター大学グラナダ映像人類学センターに在籍中、アマゾン熱帯雨林の村に約1年間にわたり滞在し、成果を映像作品にまとめ博士号を取得。その初監督作『カナルタ 螺旋状の夢』が2021年10月2日より日本で劇場公開。
清水高志 しみず・たかし/1967年生まれ。哲学者。東洋大学総合情報学科教授。主な著作に『セール、創造のモナド──ライプニッツから西田まで』(2004)、『来るべき思想史 情報/モナド/人文知』(2004)、『ミシェル・セール──普遍学からアクター・ネットワークまで』(2013)、『実在への殺到』(2017)、『脱近代宣言』(2018/落合陽一、上妻世海との共著)など。
✴︎✴︎✴︎
【INFORMATION】
太田光海監督作『カナルタ 螺旋状の夢』、シアター・イメージフォーラムほか全国順次公開。

【作品データ】 監督・撮影・編集・録音=太田光海。上映時間=121分。配給=トケスタジオ。
現在、シアター・イメージフォーラム(東京)で公開中、なお以下の日程で全国順次公開予定。
10月8日(金)〜円◎結(岡山) 、10月29日(金)〜伏見ミリオン座(愛知)、フォーラム仙台(宮城)、11月6日(土)〜横浜シネマリン(神奈川)、11月19日(金)〜出町座(京都)、 11月20日(土)〜シネ・ヌーヴォ(大阪)、元町映画館(兵庫)、11月20日(土)・23日(火祝)ガーデンズシネマ(鹿児島)、11月26日(金)〜フォーラム山形(山形)、11月28日(日)〜シネマアミーゴ(神奈川)、12月3日(金)〜長野相生座・ロキシー
〈MULTIVERSE〉
「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話
「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー
フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介
「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄
「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生
「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美
「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介
「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く
「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎
「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰
「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義





















