「聴こえざるを聴き、見えざるを見る」|清水高志×松岡正剛|『続・今日のアニミズム』|TALK❷|後編
人類学者・奥野克巳と哲学者・清水高志による共著『今日のアニミズム』の出版を記念する対談篇。第二弾となる今回は、清水高志が編集者で文人の松岡正剛と語り合う。
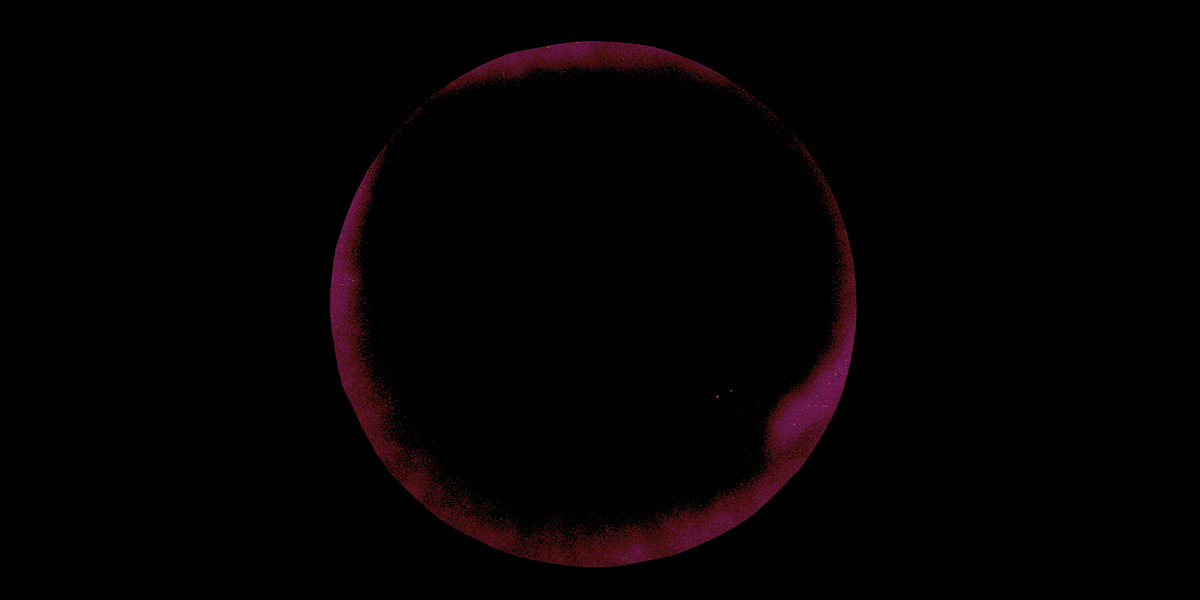
このままからそのままへ
松岡 清水さんは(鈴木)大拙はどうなの?
清水 大拙は好きですよ。ちょっと議論を超論理にしてしまうところがあって、そこはあれなんですが、絶対に偉いのは間違いないですね。
松岡 大拙はね、雑談状態では華厳そのものなんですよ。本当は全部華厳なのに、それをちゃんと書かなかった。秋月龍珉さんは大拙のお弟子さんで、10年ほど色々伺いましたけど、やっぱり大拙は華厳禅だという。だけど、いくら大拙の全集を見てもなかなかその部分は出てこないんです。気になりますね、大拙は。
清水 大拙の『禅百題』を見ていると、「蝦(えび)踊れども斗(ます)を出でず」みたいな語句が出てくる。ああいうのも有限のなかに無限があるという話なんですよね。あるいは「肘外に曲がらず」(*肘は外に曲がることはないが、内に曲がるだけですでに自由自在だ)なんかもそう。全部同じことを言ってる。
松岡 そうね、「分けて分けない」とかね。
清水 盤珪(ばんけい)の歌にも面白いものがあって、「古桶の底抜け果てて、三界に一円相の輪があればこそ」。こういうのもまたスリー・ディメンションだし、岩田の柿の画の話と同じでタコ眼鏡ですよね。
松岡 そうそうそう、盤珪知っているんだ。「そのまま禅」。
清水 盤珪は読んでましたね。
松岡 僕も盤珪はわりと若い時期に気になりましたね。僕の言葉で言うと「このままからそのままへ」というものが盤珪にはある。このhereでthisなものを、そのままbeing thereなものにする。ティク・ナット・ハンなんかをあとから読んで、これ盤珪じゃんというところを時々感じました。
清水 セールがモーパッサンの『ル・オルラ(Le Horla)』に触発されて「オルラ的存在」というような言葉を使っていたことがありますね。オルラは怪奇小説に出てくる謎の存在なんですが、Hors(そっち)とlà(こっち)を混ぜたモーパッサンの造語です。セールは『ヘルメス』の二巻でも「ここ-よそ」的なあり方、ということを語ってますね。
松岡 ふーむ、すごいねセールも。哲学仙人だね。あの人、あまり誰とも話さないで、一人でそういうことを考えていたの?
清水 ルネ・ジラールあたりとは対話していましたね。あとラジオ番組も持っていたので、一応対話はしているんです。ただ、ラトゥールによるセールのインタビュー(*『解明-M.セールの世界』)が出たときには、読んでみてラトゥール分かってないなと。自分の方が分かっていると思いましたが。
松岡 それは、そう思っていいと思うけれど(笑)
清水 ラトゥールはセールをすごく分かりやすくして、科学技術社会論(STS)などの分野ではもはや支配的な理論になっているようです。ラトゥールばっかりですが、スタイル的にあまり好きではなくて。セールはこちらからあちらへと話題を転がしていくに当たってよく語源学、エティモロジーを参照しますよね。松岡さんもそういうことをされている。アングロサクソン系の学者には、そういうのは語呂合わせや洒落を言うんじゃないと批判されるし、ラトゥールもそのアングロサクソンの流儀に合わせてしまっている。でもたとえば授業で駄洒落をいう教授がいて、それがおじさん臭いとどこかで顰蹙をかったとして、じゃあそれでラトゥールがどうなったかというと、「一人ノリツッコミ」みたいな余計しんどいノリになってしまった。《笑》
松岡 (笑)まぁラトゥールより、そこはセールの方が断然好々爺でしょう。維摩居士(ゆいまこじ)みたいなところがある。
清水 フランスではセールは、「大いなる誘惑者」と言われていたみたいですね。
松岡 官能的ですよ。素晴らしい。それだけでボルヘスだというところがあります。
清水 ボルヘスも僕は好きでしたね。ボルヘスとセールは、二十歳のときに一番熱中していました。ここ(*松岡が代表をつとめる、ISIS編集学校事務所)も「バベルの図書館」のようなものを想像しながら来たんですけど……。ボルヘスもまた森とか迷宮とか、有限なマテリアルなものの中に無限を見ていた人ですよね。
松岡 そうですね。さっき言われたショートサーキットのちょっとしたところに大きな矛盾と同居、根本偶然を隠し込める技がボルヘスにはありますよね。
『原人論』と「対の思考」
松岡 結局、思想の半分は僕は枝なんです。テクノロジー、レトリック、メトード(méthode、方法)は枝になってから見えてくる。幹ではわかりません。だから枝がないとダメで、セールはそれがあるけどラトゥールにはないような気がする。西田ももうちょっと官能的に、セクシャルにやってくれてもいいなとずっと思っていましたけどね。西田は幹に寄りすぎている。
清水 そういうのを、今では韜晦とか誤魔化しのように捉える人も多いですよね。
松岡 むしろそっちが強いですね。僕なんかもきっとそう思われてるだろうし、たとえばウンベルト・エーコみたいなのもそう思われていると思いますけどね。でもデヴィッド・ボウイとかを見ているとボウイ自体が韜晦していくというか、そこにないものから降りてきたものを今自分が演っている、というような歌い方をする。「地球に落ちてきた男」みたいなあり方をするというのはね、僕は哲学だと思うんです。ボウイだけじゃないですよ、沢山いますけれどロック・ミュージシャンには。あれを哲学者側がやれているかというと、セールにはそれがあるけど、たとえばレヴィナスにはない、デリダにはない……。
清水 ボウイの『ピンナップス』というカバーアルバムがあって、僕はそれを最初に聴いたんですね、親父が持っていて。それを見るとライナーノーツにアンドレ・ブルトンの言葉が引かれている――「美は痙攣的なものになるか、もしくは存在しなくなるだろう」と。マニエリスムをロックに持ち込んだのがボウイなんだと述べられていて。ある意味マニエリスム的な変奏ですよね、そういうことを哲学もやっていかなければならないんでしょうね。
松岡 マニエリスムや変奏ということだと、僕は三島を読んだり、『ナグ・ハマディ写本』のような聖書の異本を読んだりしていますね。
清水 思想を次々変奏していく、場所を変え語る人を変えて絢爛とそれを展開していくということだと、華厳もまさにそうですよね。僕は一方では、あのほとんどエンドレスに続いていく膨大で冗長な『華厳経』から、法蔵がその思想の核として華厳教学を取り出してきた。そういうことを、セールのややとりとめのない饒舌を相手にやってみたい、という気持ちもあるんです。
松岡 できるんじゃないかな、清水さんなら。もうしてると思うけど。グレアム・ハーマンとかクァンタン・メイヤスー、マルクス・ガブリエルとか、あんまり頭がよくない。ちょっと読んでいて耐えられない。ユヴァル・ノア・ハラリとかも超頭悪いね。なんでこんなにみんな頭悪くなったのかな。
清水 まあ、スタイル的には未熟ですよね。メイヤスーももうちょっと頑張ってくれるといいんだけど、1、2冊しか出ないし。ハーマンも図式がかなり単純だし。今は海外からのインパクトから何かを作るということがやりにくくなってきたので、ブリコラージュ的に作っていくしかない。そうやって出来たのが今回の本、『今日のアニミズム』なんです。ヨーロッパの学知そのものが、みずからの伝統を自家薬籠中のものにして、さまざまな創造的変奏を産みだすような技芸をさっぱり見せてないですね。
松岡 その理由はよく分からないけれどね。観念の連合だとか連鎖だとか、コンティンジェントな矛盾を孕ませながら別様の可能性に向かっていけるようなセンスが見当たらない。彼らはライプニッツとかやってないんじゃないかな。スピノザなんかもとっくの昔に置き忘れているんじゃないか。あなたがさっき話した排中律の話の前後が彼らにあるとは思えないな。オッカムの剃刀はあるんだけど、使いすぎですね。
清水 その一方で仏教は、繁茂しすぎてもはや原型が分からなくなってしまったと思うんですよ。
松岡 それも問題だよね。
清水 議論を絞って刷新したのは、ナーガールジュナだけなんじゃないか。
松岡 その意味ではとっくに仏教の方がヨーロッパを批判するにあたらないぐらいひどい歴史を進めてますからね。ただ法然や道元からはおもしろい。
清水 『中論』を読むと、最初に帰敬序(ききょうじょ)があって、八不が出てくる。そのあと四句分別をしていくけれど、全部否定していくんですね。第十八章の第八偈、あれだけが肯定していて。僕はあれには意味があって、オッカムの剃刀だと思うんですね。東洋的な剃刀。四句分別の第四レンマは、そこにむやみやたらと何かの主語を代入して語ってはいけないもので、それによって否定される構造そのものを表わすごく限られた二項対立だけがそれを語るにふさわしいのだ、という。だけど仏教がその後発展した状況から見ると、八不でチョイスした四種の二項対立、不生不滅とか不来不去とかですが、それで良かったのかとも思うんです。法華一乗や華厳の展開を考えれば「一と多」とか、そういう二項対立の方が本質的だったのではないか。また西洋哲学ともより接続しやすいのではないかと思って、今度の本ではその「絞り直し」をしたというところがある。
松岡 空海が、読んだんだろうけど一切記述していないものがあります。華厳から密教へ変化していくときに、不空とか一行とかが登場し、宗密の『原人論(げんにんろん)』なんていうのが出てきて、華厳の大きな体系が崩れていくんですよ。華厳が密教に吸収され、行為や即身というものが重視されて、金胎両部(*金剛界と胎蔵界)の二つのシステムを一対で動かし、しかも華厳の事事無礙や理事無礙法界の「理」や「事」のように融和するのではなく、二つに分けてしまう。そこで空海がヒントにしたであろう何かが気になっているんですよね。特に『原人論』というのが僕には、分かるようで分からないですね。阿頼耶識の問題を解くにあたって、金剛界、胎蔵界という言葉は使っていないけれど、一対のシステムのなかで同時にプロセッシングするという操作をしている。密教というのはプロセッサー(*ITなどで、一定の手順でデータを変換、演算、加工する機能を持ったシステムやソフトウェア、装置のこと)を作るんだね。
それとはまったく違うんだけど、三浦梅園までくると、紙の表と裏に同時に複数の円の図を描いて、「物/気」とか「天/地」というように概念を一対で配して、それらの関係を順々に切り替えていくということをやっている。
清水 仏教を中国化して導入しようとした時期には、道教の斉一論、つまり太初の一なるものから両義(*りょうぎ、二極性)が分かれ、世界が分化発展していくその原初の一に戻るという思想と、二項対立を超えていこうとする仏教の思想が混同されたところがあったと思うんですが、宗密の『原人論』は道教と仏教を対決させたものなので、かえって二元性を意図的に重視しているところがありますよね。太初の一(太極)からの働きなどというものは唯識でいう「見分」と「相分」のただ「見分」の側であるに過ぎなくて、両者のフィードバック・ループよりも事後的なんだということが分かっていないという批判をしています。身体的な人間も、環界もこのフィードバック・ループから生まれてくるし、その背景にあるのは業としての阿頼耶識です。しかし阿頼耶識も世界も始めから端的にあるわけではないし、その両極の関係も固定されたループではなく次第に置き換わっていく。「内の四大と外の四大は同じからず」と宗密も言っているように、多世界的にさまざまなパースペクティヴが重なり合っている……。そこに両極を切り替えていく、「対の思考」の原型があり、金剛界と胎蔵界という対もそこから出てきている。この両極の「切り替え」は、六道輪廻かも知れないけれどもっと俯瞰して見ると業が散っていくというか、相対化される、非主語化されるということでもある。――おっしゃる通り三浦梅園も、まったく違ってるとは言えこの「切り替え」を引き継いでいる。やはりバイナリーが大事で、僕も今度の本を書いていくなかで、梅園っぽいことをやっているな、と思っていました。
松岡 そんな感じだね。セールも紙の裏と表に絵を描いていったら梅園ぽくなるかもしれない。
清水 今回はやや図式的に絞ってそういうことをしたので、松岡さんからするともっとスタイル的に多様にやれよと、思われるんじゃないかと思ったんですが。
松岡 そうそう、やれると思うし、通常の本作りから切り替えていってもいいんじゃないかな。さっきの絵とかじゃないけども。岩田慶治もそういう感覚が非常にあった人です。ただ文章にするとああいう形になる。僕は喋ってる時の岩田の方がずっと面白いと思っていたんだよね。
はじめて彼が東南アジアの飛行機で、アニミズムを探索するのに上から行ったときに、下に見えている地表から、上空の自分がいるところのあいだを思考のブラウザに――ブラウザという言い方はしていなかったけれど――思考の塊にしているという話とか。
あるところへ岩田さんをお呼びしたことがあるんですが、「今、京都から新幹線に乗ってここにいるんだけれど、新幹線のなかではずっと僕は「そこ」にいたにもかかわらず、京都から東京まで繋がってきて「今」「ここ」にいる。「今」「ここ」で僕が喋っているのは、京都から東京までのさっきの新幹線的な変化とともに「ここ」にいるんだ」と岩田さんは冒頭から語り始めて、その範囲で自分の話を聴いてくれ、と言うんです。「ウナギのように長くなったものが、くっついているんだ」と語る、そんな独特のセンスがあったんです。
清水 それはさっきの「このままからそのままへ」だし、ライプニッツの連続体合成の問題とも一緒ですよね。ボトムアップで考えずに全体から考える。モナドロジーというのはアトミズムをひっくり返したもので、それは部分に先立つ単一の全体ということ。実際には、モナドは確実に相互入れ子状になっているのに、ライプニッツはそれは複合体ではないと言い張るので、皆それで分からなくなってしまう。大事なのは部分や項ではなく、構造なんです。京都から東京まで分割できないというのも、分割することから生まれるゼノンのパラドクスへの応答ですよね。
松岡 おそらく大森荘蔵とか、みんなそこはちらっと分かっていたんだけど、なかなかうまく語れてないんですよね。
大阪の町人学者
清水 松岡さんは仏教学者の宇井伯寿についてはどう思われますか?
松岡 初期は木村泰賢とともに、やはり読みました。ただ宇井伯寿の『インド哲学史』には、パーリ語が入っていないし、東南アジアの話も入っていないので、その後はあまり詰めなかった。あの時代に、浄土宗から清沢満之のような大脅威となる存在が立ち上がってくるなかで、宇井さんは東京大学にイン哲を作って最初に普遍的な仏教学をやろうとした人だった。ただ僕は、木村泰賢とか舟橋水哉の『倶舎論』とかに個人的に惹かれていて、最初からインド六派哲学のほうへ偏っていたんですね。それでサーンキヤとかヴァイシェーシカとかに拠るようになった。僕自身の若いときの経歴はそうなりましたね。今は、宇井伯寿とか読む人は少ないんじゃないですか。
清水 あまりいないかもしれないんですが、大乗非仏論(*大乗仏教は釈迦が説いた仏教とはもはや違うものである、という考え)というものがありますよね。個人の思想の研究でも仏教史のようなものでも、文献研究が進むとすぐに時系列でぶつぶつに切って、進歩や変遷を跡づけた、というような自己満足に陥っていく。偉大な精神や思想には最初から一貫性があるということが分かっていない。それをなんとかしないといけないと思って。
松岡 大乗非仏論はやらないとね。それと天台本覚論。
清水 宇井伯寿はそれなりに初期仏教から大乗仏教まで、一貫したものを見いだそうとしていて、「相依性」という概念もそのために注目したんですが、ただ理論的にはまだ単純だったかなと。
松岡 単純ですよね。ヨーロッパの仏教学とか宗教学をそのまま援用してますから。でも大乗非仏論、あと天台本覚論、もう一つは井筒さんもおやりになった『大乗起信論』、この三つはどうしてもやらないとダメです。
清水 僕はなんとか十二支縁起と離二辺の中道だけをもとに、後の大乗仏教が全部生まれてくると言うことを確証したいんですよね。
松岡 期待します。
清水 もちろん全部までは行けていないですが、今回の本でも頑張って書いてみたんですよ。そこで納得できるものが出せないと、仏教がフィクションで出来上がったようになってしまうと思うんです。
松岡 多少フィクショナルなものが入ってもいいんじゃないの?
清水 フィクションというか、要するに仏教が断絶しているということになって、虚構だと言うことになってしまう。初期仏教を方便だった、という風に済ませてしまうのは嫌なんです。
松岡 なるほどね。富永仲基とかはどうなの?
清水 あんまり詳しくないですが、彼は大阪の町人学者の一人ですよね。
松岡 彼は『翁の文』や『出定後語』という書物を著して、大乗非仏論だけではなく加上論というのを唱えている。要するに大乗仏教はもとの仏教に次から次へと加えられていったものだから、上積み分は元のブッダとは関係ないよという説です。
清水 僕は親父があっちのほう、大阪の船場なんですよ。懐徳堂(*かいとくどう、江戸期の大阪を代表する学問所)の町人学者、中井家とも繋がってるんです。六代前が大高元恭っていう蘭学者で、その妹の土沙(とさ)っていうのが、中井履軒(*兄中井竹山とともに、懐徳堂の全盛時代を支えた)の息子、柚園の嫁になってるんです。
松岡 あ、そうなの?(驚)
清水 それで、幕末になると鴻池家(*江戸期日本最大の豪商。全国百十藩に大名貸しを行い、懐徳堂のパトロンでもあった)の別家になっているんですよね。宮本又次さんの『大阪の研究』にも高祖父の名前が出てくるんです。だからすごく大阪ディープ。
松岡 船場か。(笑)あまり感じなかったね。育ったわけではないんだよね。
清水 (笑)育ったのは名古屋ですね。親父まではずっと大阪です。
松岡 中井履軒か。(笑)船場はね、あの大阪弁っていうのは一回やらないと。近松ですからね。近松がああいう歌のような、言葉のようなものを作ったっていうのは、『歌うネアンデルタール』クラスの大問題ですよ。
清水 近松、面白いですよね。心中する前に小屋から浮世を覗いていたりとか。
松岡 近松はとんでもないね。一番まだ分からない日本のクリエイターですよ。しかも人形浄瑠璃というちょっと特異な、それこそ皮膚も何もかもを換骨奪胎したものを作ってしまったわけだ。その換骨奪胎に、大夫と三味線と人形遣いをつけて、さらにその人形遣いも三人に分けてしまう。それは近松のあとですが、そういう可能性を作ったことがすごい。世阿弥の言語力もすごいけど近松の方言的身体言語はもっとすごいね。ダンテの『俗語論』を持ち出したいくらいです。でも、おそらくダンテよりすごい。大半の概念や言いまわしが裏腹で、両義的。すべてがバイナリー。これはなかなか真似できない。
清水 浄瑠璃に関しては、鴻池家は大の浄瑠璃好きで、最後の鴻池幸武さんは浄瑠璃研究家として知られていて、第二次大戦中にフィリピンで戦死しなければ早稲田の国文の教授になっていただろうといいますね。柳原伯も浄瑠璃が大好きで、意気投合して奥さんを柳原家からもらったとか。鴻池家は生活スタイルは結構西洋風だったのに、音楽だけは浄瑠璃だったらしいです。
松岡 ここ(本楼)でときどき三味線を呼んで、上に太鼓とかをずっと並べて、人形浄瑠璃もやったことがあるんですよ。今、人形論も一回全部やりなおしたほうがいいですよね。傀儡(くぐつ)とかホムンクルス、もちろんそれはロボットとかアンドロイドの起源ですけれども、要するにそれらは御神体と同じなので、一体あれがなんだろうということをちゃんとやった方がいい。いずれも何かになる(being)んだけれど、まずなるためのモデルを作るわけですよね。今は歴史からモデルを選ぶけれど、そのまま同時にやれるっていうのが近松でした。
清水 昔『夜想』という雑誌があって、ときどき松岡さんも寄稿されていて読んでいたんですが、そういう特集をよく組んでいましたね。稲垣足穂の人形論『人間人形時代』も面白いです。
松岡 足穂も船場ですね。
文体のエロス、思考のエロス
清水 なぜか分からないんですが、今回の本に対してアイヌの友人に言わせると「エロい」って言われるんですよね。口を揃えて言われますね。(笑)
松岡 へぇ。でも性的なことは全然書いてないよね。
清水 そうなんです。なのに「くっそエロい」と。(DOZiNE編集の)辻くんも「ネトラレンマ」とかなんとか言ってるし。だんだん華厳から密教に寄せていくと、真言立川流みたいなものがおのずと現れてくるのかな、と(笑)
―確かにすごく、エロチックな情念の話として読めましたよ。(辻)
松岡 清水さんの文体や文章は、大変彫琢されてるから、エロいかもしれないね。官能力があるよね。すごくよく彫琢してある。
清水 結構出るまでに時間がかかったので……。
松岡 いや、翻訳も。最初のセールについての本もそうだったし。よくここまで際どい言葉を選んで一行一行つくってるな、と。あんまりいないよね。もっとみんな横着ですよ。だからタフだなと思って見てました。
清水 なんだかデリダくらいから「文章、汚くていいや」みたいになっちゃったですね。
松岡 日本ではね。
清水 そう日本で。ドゥルーズもそんなに美しいとは僕は思わなかったし。サルトルくらいまでは、学生だった大江健三郎がちょろっとそれを読んで似たような小説を書いたり、「アランを読まずしてアランと同じことを語る」とか言われた人がいたのに、何でこうなってしまったのか。
松岡 本当にね。日本的ポストモダンの悪しき波及でしょうね。まぁそれと翻訳文体の問題もあるかもしれないね。デリダとは宇野邦一君と一緒に対談したけど、そんな感じじゃなかったですよ。ホワンホワンしていて。ただ言いまわしの言語にこだわっているというのはよく分かった。
清水 セールとデリダは両方フランス語で読んでましたけど、やっぱりデリダのフランス語の方が相当単純ですよ。
松岡 ターミノロジーの基礎がない。タブローとテーブルとタブレットが同根だということを忘れています。日本の場合、バルトくらいで止まってた方が良かったんじゃないのかな。
清水 そうですね。僕は審美的に、デリダやドゥルーズを文体で避けたというのもあったんです。セールの方が美しい。
松岡 それは、あなたの文章にちゃんと出てます。しかも露伴とかを日本語のために読んだっていうのがいい。江戸の読み本、黄表紙なんかをちらっとご覧になるともっといいですよ。澁澤龍彦は最後そっちに行って、もう翻訳をやめて自分で書き始めちゃったけど。やっぱりね、露伴の奥にいるのは西鶴ですよ。淡島寒月から紹介されて。その奥は本当に読本や黄表紙で、馬琴のようなものとかに行く。露伴はそこに明治語を駆使して両方やりました。さらに奥はというと近松にまで行っちゃいます。あれは浮世絵のように表層に出てくるものとその奥にあるものとが綯い交ぜです。アウエルバッハの言うミメーシスです。
地の文と会話の部分とを綯い交ぜにしていって、ディエゲーネス(*叙述、ギリシャ悲劇では地の描写の部分のこと)とミメーシス(*ギリシャ悲劇では会話の部分のこと)をそうやって混ぜてるんですよ。これは真似できない。石川淳がやったというけど、全然できていない。『狂風記』なんか中身は面白かったけど、できてはいない。やれる人いないんじゃないかな。田中優子さんも江戸は研究しているけど、江戸流に書くのは無理だと言ってる。ひょっとしたら清水さんはできるかもしれない。
清水 うーん、なにか聞くところによると、高祖父が山田美妙と一緒に本を出してるんです。
松岡 あの頃に?
清水 明治の初めに。曾じいさんも変な文人だったんです。
松岡 おかしいね。中井履軒がいて山田美妙がいるなんて……いや大阪は変だなぁ。
清水 変なんですよ。曾じいさんは明治21年に和英辞書を出してるんですよ。本草学の影響があって、要するに百科事典的なものを作りたかったみたいです。そのあとはピクトリアリズムに傾倒して生態的視覚論みたいなことをやっていた。シャドウ(影)とシェイド(蔭)とライト(光)は全部違う、みたいな変な理論を出してるんですよ(笑)。シェイドとシャドウは動いた時に違ってくるみたいな。
松岡 マッハじゃん。(笑)いや大阪はね、あの当時の大阪はもう世界一の出版文化ですからね。すごいと思う。懐徳堂とかだけじゃなくて、様々な本草とかですね、漢語とか、あと略図ですよね。世界中の略図を大阪で発行してましたから。大正昭和ではプラトン社です。
清水 ああ、それもやってました。青木嵩山堂……。
松岡 そうそう。
清水 あれ曽祖父の兄弟なんです。青木嵩山堂をやっていた青木常三郎。『五重塔』とか、露伴のものもよく出してました。
松岡 えっ! なるほど……。じゃあ血を受けてるね。完全に受けてる。そういう本を一冊あいだに挟んだら? 清水高志、何者かっていうのを。
清水 おこがましいですよ。(笑)
折口の声、ボルヘスの眼――聴こえざるを聴き、見えざるを見る
清水 今日もう一つ松岡さんに伺いたかったのが折口信夫の話なんです。松岡さんはよく折口について語られていますよね、ネットワーカーの話だとか。
松岡 マレビトですね。
清水 マレビトとか、さっきのタコ眼鏡のようなものとも縁が深い、「うつる」(移る、映る、写る)ということが、それに絡めて語られている。あの辺がすごく面白くて、ずっと注目しているんです。
松岡 まだ本格的には書いてないこともありましてね。あまりお話ししていないんですが。
昔、僕の従姉妹が、ガス自殺をしたんです。それで植物人間になって、京都の助役の娘だったので、お金があったから京都中のすごい医師に診てもらったけど治らなかった。そしたらのちに彼女が、お母さんの信仰力で復活したんですね。目が動いたり、指がちょっと曲がりだして。やれ嬉しやと言うんで、お母さんがつきっきりで看病した。そしたら治ったあとに、色々喋っているんだけど、どうやらこの子は本当の記憶で喋ってないということにお母さんが気がついた。「伊勢神宮に行ったとき、暑かったね」なんて言えば「うんうん、そやね」と言ってるから、てっきり全部治ってるのかと思ったら、全部過去の記憶の大きい部分がストンと抜けてて。
清水 エピソディック・メモリーが落ちている?
松岡 コミュニケーション能力は回復していて、だから適当に合わせることはできる。それで叔母に「セイゴォちゃん、この子の記憶があらへんのや。セイゴォちゃんやったらなんとかできるかもしれんさかいに、見てあげて」と言われて、まだ僕が大学生のときです。そのとき会ってみてびっくりして、これって何だろうというところから僕の思想のスタートは切られたんです。脳って何なのか、記憶は何なのか、コミュニケーションは何なのか。いったい脳が冒されてもなぜ社会生活ができるんだろうか。それがすべてなんです。
その後、『遊』っていう雑誌を作るまえに、僕にも脳圧亢進というものが起こった。クモ膜の中にちゃぷちゃぷ水が溜まっているんですが、その水位が1ミリでも上がると吐き気がして何もできなくなるんです。そのときに折口を読んだんですね。ものすごく屈強な看護婦たちに抑えつけられて脳脊髄液を抜くと、スーッと落ちるんですね。ああ、この瞬間は絶対もう二度とないなぁと思って、このときに何か読もうっていうときに読んだのが折口で、まぁアイヌとか古代人になれたわけじゃないんだけれども、折口の『死者の書』みたいな、あの状態のままのブラウザでさっと読もうと思ったのが折口全集でした。折口を読むということは、折口学もさることながら、僕にとっては従姉妹の体験だとか、自分にも脳圧亢進が起こったこととかを経て、意識がすっからかんになりながら、ワーッと見えてくるというものとは何かを問うことだったんです。――まるでネアンデルタールが途絶えて、次から次にホモズが変わっていく瞬間のように思えたので、折口じゃなくても良かったかもしれないけど折口にした、というのが大きいんですね。
だからいまだに折口の文章からは、当時の僕のオラル(*口頭風)で身体的な読み方が蘇ってくる。だからついつい使っちゃうんですね。多分、清水さんがセールを使うと楽になるような何かが、僕にとっての折口にはある。
清水 松岡さんの『日本文化の核心』を拝読したときに、なんで日本には文字が入ってくるのがこんなに遅いのか改めて疑問に思ったんです。かなり国内が統一されてもあえて文字を使っていなくて、明らかに抵抗している。その代わりにメッセンジャーがそれを補って、各地に伝言ゲームみたいに擬(もど)いて伝えていくわけですよね。源流にいる天皇もまたミコトモチ、メッセンジャーで、過去からもそうやって伝わってきたのだという設定になっている。だから、文字がない時点での日本のありかたはどうだろうと考えた時点で、折口はああならざるを得なかったんじゃないか。どこかの文献にどう書いてあるというのではなく、文字を取っ払ったらこうなる、ということを考えているという。
松岡 おそらくね、クスリをやりながら書いていると思います。ハイミナールか何か分かりませんが、そんなにひどいものではないとは思います。それとやっぱり男色であることも大きい。しかもプラトニックな男色です。最後の弟子である歌人の岡野弘彦さんなどに聞いてもそのあたりはあまり分かりませんでしたが、感覚の磨きが格別だったはずです。
それから国学ですよね。国学というものをどうしたらいいのか、折口は昭和10年代くらいに、現人神・昭和天皇がいるなかで、絶対こういうものじゃないと思っていたはずなので、国学を国文学から変更したかったんだろうと思う。漢字研究の白川静さんにもちょっとそんなところがありますが、古代の王をばしゃんとストレージし、そのままそれをエンジンとして使って、ちょっとクスリも飲んだり、万葉をいつも詠唱したりして模索していったんでしょう。
岡野さんに折口がどういう風に歌謡を詠まれていたか覚えてらっしゃいますか?と聞いたら、ああ、もちろんよく覚えている、と言うので、万葉の詠みかたを再現してもらったら、全然違うんですよ。僕らが百人一首とかを詠むのとは。音が違う、古代音なんです。「か」が「くゎ」っていう風になるのは当然なんだけども、色々濁点とか切り口とか、アーティキュレーションが違っていて、それはもうラップを超えてました。カンツォーネでもないしゴスペルでもない、日本という感じ。そういうものを聴いて、折口はこんな風に詠んでいたんだな、と思いましたね。岡野さんによれば、折口は細くて小さくて、声が澄んでいて、『死者の書』のなかの「こう こう こう」という、死者の眠りの声のようなものを持ってらしたと聞きました。会いたかったですね。
清水 なるほど、だいぶ眼前彷彿しましたね。
松岡 時々いますよね。どうしても会っておかないと分からないなっていう人が。僕は埴谷雄高に会って初めて分かったことがあったんだけど、折口には会えなかったんですよね。ボルヘスは良かったよ。
清水 ああ、お会いしたんですね。
松岡 行ってみたいと言うんで、明治神宮を案内したりしました。目がもう見えなくなっていたので、手を引かれながら、砂利の感じとかで、鳥居から神宮の屋代が遠くにあるのに、その大体の距離と、道幅と、樹の高さを当ててましたね。
清水 ああ、僕の父も亡くなる少し前はほとんど目が見えなくなっていたんですが、見えなくてもあたかも見えるかのように動きますよね。
松岡 そうみたいだね。折口もそれを古代のレベルで持っていたんだと思う。僕らは今のような時代にはあまり現在の問題には触れないで、こっち側に向かった方がいいですよ、そんな気がしますね。今日は清水さんもそういう視野とか聴覚とか、最初にそういう話をされましたよね。『声字実相義』とか。五智五大(*五智は、唯識の前五識と意識、末那識、阿頼耶識を仏の智恵に変えた四智に、法界の本性を明らかにする智恵である「法界体性智」を加えたもの。五大は地大・水大、風大、火大、空大の五種類を指す)をどうやって使うかですね。
清水 折口とも縁が深い、ほかひびと(乞食者)や跛行者(はこうしゃ)の話を、松岡さんは日本の文脈で語られますけど、セールも語っているんですよね、物語のなかの人物が、井戸のようなところに「落ちる」というのはどういう意味なんだろうとか。『ヘルメス』でもオイディプスの話に触れたり、ゾラの『居酒屋』のジェルヴェーズが転落して跛行者になることや、ローマ神話の火と鍛冶の神で、同じく跛行者でもあるウォルカヌスについて言及したり、色々ほのめかしてますね。
松岡 キュピドが見えるか見えないかとかね。
清水 どうやらそこに、すごく普遍的な構造があるんだろうと。
松岡 僕らはそうした存在をフリークと思うような時代で育って、それがいいと思っていたけれど、そうではないですね。今はそれが全部封印されて差別用語として使えない状態になっている。でもあれを差別じゃなく受け取れる高速意識の社会というか、相互コミュニケーションができる場面があるんですよ。ヤマダノソホド(*かかし)のように歩けないとか、跛行者だとか、禹歩(*うほ、反閇。陰陽師が邪気を払うために呪いを唱えながら大地を踏みしめ、独特の歩き方をすること) だとか、向こうからそういう人たちが歩いてくるだけで異なる時空間をもらえるというような、そんな強烈なイマジネーションを交わせる社会がありえたんですね。それは今日こそ、少しでもいいからないとまずいでしょう。
清水 「音連れ」(*訪れ)というものについても、松岡さんは書かれてましたね。ああいうことも、セールは書くんですよね。異なる時空間というか、多世界が重なり合う、そのコンティンジェントな合流点にいる何か、その予兆や、その面影、ノイズ的でもあるその存在というもの。
松岡 その点、セールは知覚が研ぎ澄まされているし、歴史の文献からそういうものを引くのが天才的にうまいですよね。世界軸の設定が彼は本当にしっかりしている。
清水 実はセールの存在を僕に最初に教えてくれたのは、文芸評論家の丸山静さんだったんです。
松岡 あ、そうなの。(驚)
清水 丸山静さんが、最後にやっていたのがセールだったんです。その志なかばで亡くなってしまって。あの人も西郷信綱さんと「抒情」を創刊して活動したり、現象学を日本に導入したり、何度も何度も自分の学問を更新していった人でしたが、セールだけがどうしても分からないといって亡くなった。
松岡 へぇー、でも習ったわけじゃないでしょう?
清水 習ったんです。高校を中退してから数年後に。『熊野考』とか『無限に伸びる糸』とか、非常に面白かったですね。文章もスタイルが良くて。丸山静は1968年にはもう、デリダとかフーコーの話を対談でしていましたね。完全なリアルタイムで。在野の時代が長かったんですが、古今東西の文学や民俗学、哲学に通じていたカリスマでした。僕は学問の世界にいて、変わった研究をしていたし何度も首の皮一枚まで追い詰められたんですが、その都度助けてくれたのは丸山静の弟子たちなんです。ライプニッツ研究の米山優さんに師事したのはその後ですね。
松岡 じゃあ、最初からこの本に向かう傾向はあったんだね。
清水 そう、だんだんもとに還っていってる感じですね。(笑)
松岡 やっぱり清水さんは一度、今日話してくれたプラトン、ライプニッツ、西田、途中の空海、セールまで、そのトータルなものを一度つなげて軽く書かれるといいんじゃないかな。
清水 どういう企画になるんでしょう、トータルというと。
松岡 斜めにどんどんと走っていく線が見えるようなね。対角線が次から次へと折り重なっていく、そういうのを書ける人がいない。で、ちょっとこう折り目があって、ところどころ皺を伸ばさないといけない。さっき『ティマイオス』で伸ばしたり、『声字実相義』で折り畳んだりしたように。――そうした部分を限定しておいて、プラトンを全部書くとか、ライプニッツを全部書くとか、西田を書くとかじゃなくて、畳まれてしまっているものを一回清水さんが伸ばしてみせて、ここにはこういう線がついていて、この線はプラトンが伸ばした線とこの部分だけが近いとか、ライプニッツのこの線はどうも西田には来てないとか、そういうことが次々と見えるようにする。そういうことが分かる人なので。どういう文体がいいか、構成がいいのかとかは分かりませんけどね。今日喋られたようなことは、かなりそれに近いと思う。
清水 (笑)うーむ、なるほど。そうですね。
松岡 どうしても書きにくければ、一回対話篇のお相手をしてもいいけどね(笑)
清水 我々はもうすでに、対話篇の中にいるようですよ(笑)
構成/辻陽介・清水高志
「死と刺青と悟りの人類学──なぜアニミズムは遠ざけられるのか」|奥野克巳 × 大島托|『続・今日のアニミズム』TALK❶を読む>>
✴︎✴︎✴︎
清水高志 しみず・たかし/1967年生まれ。哲学者。東洋大学総合情報学科教授。主な著作に『セール、創造のモナド──ライプニッツから西田まで』(2004)、『来るべき思想史 情報/モナド/人文知』(2004)、『ミシェル・セール──普遍学からアクター・ネットワークまで』(2013)、『実在への殺到』(2017)、『脱近代宣言』(2018/落合陽一、上妻世海との共著)、『今日のアニミズム』(2021/奥野克巳との共著)など。
松岡正剛 まつおか・せいごう/1944年、京都生まれ。編集工学研究所所長、イシス編集学校校長、角川武蔵野ミュージアム館長。70年代にオブジェマガジン「遊」を創刊。80年代に「編集工学」を提唱し、編集工学研究所を創立。その後、日本文化、生命科学、システム工学など多方面におよぶ研究を情報文化技術に応用し、メディアやイベントを多数プロデュース。2000年「千夜千冊」の連載を開始。同年、「イシス編集学校」をネット上に開講し、編集術とともに世界読書術を広く伝授している。
✴︎✴︎✴︎
〈MULTIVERSE〉
「あるキタキツネの晴れやかなる死」──映画『チロンヌㇷ゚カムイ イオマンテ』が記録した幻の神送り|北村皆雄×豊川容子×コムアイ
「パンク」とは何か? ──反権威、自主管理、直接行動によって、自分の居場所を作る革命|『Punk! The Revolution of Everyday Life』展主宰・川上幸之介インタビュー
「現代魔女たちは灰色の大地で踊る」──「思想」ではなく「まじない」のアクティビズム|磐樹炙弦 × 円香
「生死観」としての有機農業 ──エチオピアで学んだ生の豊穣|松下明弘
「病とは治療するものにあらず」 ──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践
「俺たちはグレーな壁を生き返らせているんだ」──1人の日本人がまなざしたブラジルのストリート|阿部航太×松下徹
「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝
「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話
「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー
フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介
「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄
「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生
「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美
「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介
「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く
「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎
「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰
「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義
「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志
「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾
「死と刺青と悟りの人類学──なぜアニミズムは遠ざけられるのか」|奥野克巳 × 大島托





















