レオ・ベルサーニをめぐって ──クィアが「ダーク」であること──|檜垣立哉
2022年2月にこの世を去った思想家レオ・ベルサーニ。「ダーク」なクィア・スタディーズとでも言うべきベルサーニの思想の「過激さ」を、哲学者の檜垣立哉が考察する。
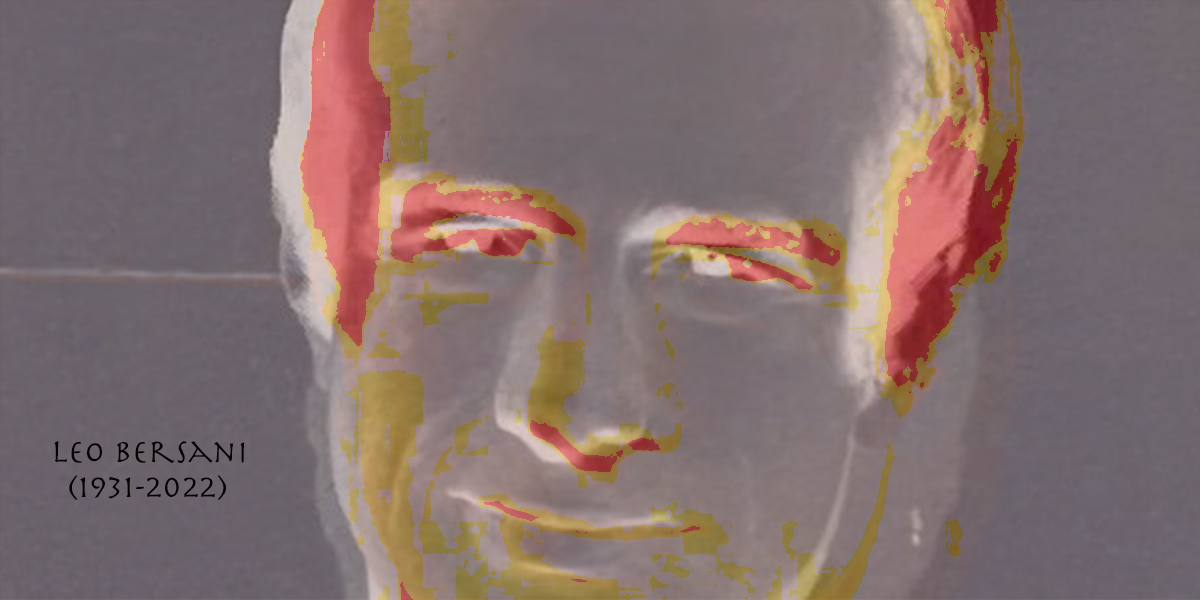
レオ・ベルサーニの「過激さ」
はじめに断っておかなければならないが、私はクィア・スタディーズやジェンダー論の専門家ではない。クィア・スタディーズは、現在、アングロサクソン圏を中心に非常に幅広く、思想的な世界も社会的な運動もまきこみながら、またここでとりあげるレオ・ベルサーニもそうであるように、精神分析の理論などをもちいつつ展開されている。私はそれらの仔細をきちんと追っているわけではない。それなのにこの原稿を書いているのは、もう十年も前のことになるが、洛北出版さんから、『親密性』という、ベルサーニとアダム・フィリップスとの共著を、当時の院生と翻訳したからにほかならない。そして、ほとんど日本でニュースになることはなかったとおもうが、ベルサーニ自身は今年二月九〇歳でこの世を去ったということがある。
ベルサーニ自身はカルフォルニア大学バークレー校のフランス文学科の教授であり、コレージュ・ド・フランスでミシェル・フーコーに招へいされ、講義をおこなってもいる(邦訳『フロイト的身体』法政大学出版局には、その講義が収められている)。プルーストやボードレールの研究をおこなっていたが、ゲイ・スタディーズの代表的著述ともいえる「直腸は墓場か?」という有名な論考を1987年にものにしている(『AIDS ――文化的考察/文化的運動』所収、邦訳は酒井隆史訳が『批評空間』二期(8)太田出版に所収)。『親密性』では、そこでの議論を拡大するかのように、ベアバッキングという、コンドームを使用しない(つまり敢えてHIVウイルスに身をさらす)ゲイの行動が肯定的に分析されている。それだけをとらえると、クィア・スタディーズの過激派にもみえるだろう。
とはいえベルサーニの思想は、上記のHIVをめぐるアメリカの情況や、その理論の中心をなす精神分析についての理解がなければ、何をのべているのかがわからない側面がある。代表作であるといえる『ホモズ』は、日本版では『ホモセクシュアルとは』(法政大学出版局)と訳出されているが、基本的にここでの「ホモ」にはまさに「同一性」という意味がもたされており、精神分析的なナルシシズム概念と連関させずに単純な理解をなすことはできない。『フロイト的身体』が代表作のひとつであることからもわかるように、ベルサーニはジクムント・フロイトの精神分析、とりわけそこでのマゾヒズムと幼児性との連関や、ナルシシズムの「非人称化」について、ときにフランスにおける精神分析の権威であるジャック・ラカンの言説を引用しつつ論を展開する。そのため、その描こうするところを丹念に追うには、それなりの労苦を必要とする部分がある。
また、これもたまたまであるが、今年二月にちくま学芸文庫から、若くして亡くなったクィア・スタディーズ研究者である村山敏勝の『(見えない)欲望へ向けて クィア批評との対話』が再刊され、その最終章には「孤独なマゾヒズム ──レオ・ベルサーニへの斜線」が所収されている(この書物は村山が博士論文として書いたものをもとにしている)。そこではベルサーニの議論がもつ「過激さ」が、まさにリベラルなクィアの運動そのものに違和をもたらし、別の方向を導入するものとして明確に描かれている。
村山は、『ホモズ』で構想されている議論を「同性愛を「関係性それ自体からの暫定的な引きこもりとみえかねないほどにラディカルに、社会性を定義し直す」(Bersani1995[以下Homos]:7) ものとして捉えることであり、同性愛の「同一性(ホモネス)」はここでは、「真に破壊的な力――政治的に受け入れがたく、同時に政治的に欠かせない、アウトローとして存在するという選択を命じる」(Homos 76)ものである」(村山前掲書、260−261頁)と記述していく。そして「[同性愛者の作家であった]ジイドやジュネに見出されるのは、間主観的な共同体の意識などではなく、むしろ一般的な意味での他者との関係性自体を否定するような強度の無為」であるとつづける(同上、261頁)。また、ベルサーニや、その共著者であるユリッセ・デュトワは「クィア批評の世界の孤独な高峰」というべきものであり、クィア・スタディーズという「業界」の代表者であるイヴ・セジヴィックやジュディス・バトラーに対する、「内部からの批判者」「強力な異分子」であるととらえている(同上、262頁)。おそらくこの村山のみたてほど、ベルサーニが著したものの位相を明示するものはないだろう。ベルサーニの主張は「既存社会に同化してまっとうな市民になっていこうとするゲイ」と「ゲイ・セクシュアリティの反規範的生き方として高らかに理想化するゲイ」の双方に「冷水」を浴びせかけるものだというのである(同上)。
ベルサーニの議論からみてとるべきことは、クィアという存在が、自らが現状社会のなかで承認されること(まっとうなゲイになること)でも、その反規範性を理想化することでもなく、徹底したアウトローとしてあるその立ち位置であり、そこから可能になる思考を探ることだろう。『親密性』などで展開される、「非人称的なナルシシズム」の議論は、こうした背景を念頭に読み解かれるべきものである。
LGBTQ運動の展開
少し視点を変えてみよう。現在のLGBTQをめぐる運動や、あるいは身体/精神障害者をめぐるマイノリティ運動は、従来はまさに社会の影に隠され、自らもひきこもりがちであった当事者たちを、前面にだし、彼ら/彼女らの声を世間に届け、その社会的存在を肯定し、差別をなくすことに意義をみいだしてきた。もちろん日本も含む、旧弊依然とした古典的家父長的価値観が意識の底に蔓延る社会や、イスラム圏などまったく異なった文化圏同士での価値観の衝突があることは確かである。とはいえ、広くいえば西洋のリベラル社会は、世界的な流れとして地歩をえてしまっている。戦争とマチスモを合体させたかのようなロシアのプーチン政権がLGBTQに対してきわめて不寛容な施策をとるのは、もちろんアメリカ中心のリベラル社会ヘの反発はあるだろうが、同時にLGBTQの存在が公認されることへの「恐れ」の現れともいえる。それは裏返せば、LGBTQ運動の勝利の証左でもある。
確かに、これまで社会のなかで行き場もなく、カミングアウトも難しかったLGBTQのひとが声を上げること、ひいてはそれがわれわれ全員の性(誰もが幾分かはLGBTQ的であることは否めない)について反省を促し、彼ら/彼女らの存在を、法的なレヴェルも含めてうけいれることは重要な社会的成果であるだろう。実際、クィアの運動もそうした方向性へと進んできている。そして、人権宣言に端を発するリベラル社会の歴史的展開をみれば、最初は白人男性を人権の主体としていたことから、女性をそこに包括し、ついで西欧社会で差別されていた有色人種をまきこみ、さらに障害者運動の成果を経て、LGBTQの運動へといたることは、時代的な必然であるとおもわれる。もちろんこうした運動が抵抗なくおこなわれたわけではなく、そこには数々の闘争があった。先にあげたジュディス・バトラーが、まさに「業界」のトップとして、そうした運動に果敢に身を投じていることも、その苦労もよくわかる。
だが一面、こうしたリベラルな社会をつくりあげる運動がもつ危うさが指摘されてきてもいる。よく語られることでもあるが、ネオリベラルな社会経済活動と、LGBTQの運動とは相性が悪いわけではない。人権のための運動であったものが、ただちに流行のファッションとそれをベースとしたネオリベラリズムの「金儲け」に加担してしまうことは、そこここにみてとれることである。またこれは「差別」問題に対する原理的で解きえない問いであるのだが、「差別」をマジョリティ社会が「包摂」することは、「差別されるもの」に対して、寛容で充分な振る舞いをなすという名目のもとで、マイノリティがマジョリティに対してもっていた「棘」を抜くことでもある。まさに「包摂=インクルージョン」といえるこうした動きは、マジョリティ側に巧く包摂されるものと、そこからすら「こぼれ落ちる」者を分断しもするだろう。障害者問題についてよく語られることであるが、ユニバールデザインやパラリンピックは、確かにそれ自身としてマイノリティの存在を救ってはいるだろう。だがそうしたものが、マジョリティの側の「善意」の「包摂」によってなされているかぎり、そこからはみでる者、はみでる事態は必ず現れる。これは構造的な問題である。クィアにひき戻せば、クィアがマジョリティ社会に承認され包摂されることは、そこで「ノーマル」とされる者に対して突き刺していた「棘」が抜かれることでもあるのである。
ダークなものの価値
近年「ダーク」な、という表現が現代思想の分野でよく使われる。一時期、ドゥルーズというフランス現代思想の代表的哲学者に対し、このラインから、「ダーク・ドゥルーズ」という主張がなされたこともある。そのひとつの機縁は、「加速主義」というキーワードで有名になったイギリスの哲学者ニック・ランドが標榜する、「暗黒啓蒙」という新反動主義にある。それは、リベラル平等社会に対するたんなる保守反動として現出することもあるが、その現出の理由はわからないでもない。ドゥルーズやフーコーの思想は、現代の資本主義社会に対する強烈な、まさに「ダーク」なアンチテーゼであったはずなのに、いつのまにかネオ・リベラル社会はむしろフーコーやドゥルーズのポスト・モダンを「包摂」し、そこでもちいられるさまざまなタームを自らのものとしている。リゾーム的なネットワーク状の接続、潜在性の領域の力の称揚、自己への配慮、自己の統治。これらはネオ・リベラリズムの世界がいとも簡単に自らの領域にとりこみ、アカデミズムがそれをバックアップしてしまう。「ダーク」な、という標語は、こうした事態に対し、本来ドゥルーズやフーコーの思想がそなえていた反―社会的な力を再度ひきたてるべきだという主張であり、それはマイノリティの本来の力能を、破壊的な力においてみいだしなおそうとするのである。ニック・ランドは、ただの反平等・反啓蒙というにとどまらず、むしろ二〇世紀後半の共同体論におおきな影響をあたえたバタイユにかんする著作(『絶滅への渇望』河出書房新社が、最近翻訳された)を著してもいる。それらを考えれば、こうした思考の流れは、孤独のなかでの親密性という極限の他者関係を指向するベルサーニとかさなるものもある。さらにいえば、数年前に、もとはきわめてロジカルな思考実験としてはじまった「反出生主義」=産まれてきたこと自身を否定する議論が思想界のテーマになったこともかさなりあう。
これが、ただの現状のリベラル社会への反動というだけであれば意に介することもないのかもしれない。しかしリベラル社会が、ありとあらゆるマイノリティをも、まさに資本主義の剥きだしの運動のなかに包摂し、利用し尽くしていることも確かである。そのかぎり、こうした「ダーク」な、という側面の強調は無下に否定しえない。
ベルサーニに戻ろう。ベルサーニの一連のクィアの議論は、単純に「ダーク」であることを目指すものではないだろう。村山が書いているように、確かにそれは、クイアの権利要求的な運動に対してアウトサイダーの位置をとるのだが、しかし他方ではゲイ至上主義のような立場も否定するからだ。ベルサーニの議論は、過激なベアバッキングの肯定という、反社会的にみえるといえる行為に対する称揚であるとともに、そうした事態にキエティスム=静寂主義という宗教における聖的な一面をみいだしてもいる。
ただ、ジェンダー・クィア論が、まさに世間の「真ん中」におかれ、正常(ノーマル)な社会に平穏に回収されるあり方をベルサーニは快くおもわないことも確かだろう。社会に対する異質な存在としての「棘」であることの価値を示すことがやはり彼の真骨頂である。それゆえ、彼の立場はどこまでいっても「孤独」である。またニック・ランドのバタイユ論をとりあげるまでもなく、バタイユ的な議論は、ジャン・リュック・ナンシー(『無為の共同体』)にも、モーリス・ブランショ(『明かしえぬ共同体』)など、八〇年代の共同体論に影響を与えている。その時代に、リベラルで正義の民主主義へと回収されることとは異なった生を思考する議論は多く現れた(もちろんそれは、六八年の学生闘争以降の、コミューン的な共同性を語ることの困難さの帰結でもある)。ベルサーニの、過激なゲイの行為における、まさに死を招くのみの共同性を描く戦術も、広くみればこうした一連の流れのなかに含まれるだろう。ネオリベラル社会が世界を綺麗に平等化し、LGBTQの「社会的理解」や「社会的包摂」がますます進み、それを資本の流れ自身が巧妙に回収する現状において、ベルサーニは「ダーク」である一面を、彼独自の仕方でもちえてもいる。
ベルサーニの非人称的ナルシシズム
もう少しことをベルサーニにそくしてとらえてみよう。『親密性』において重要なのは、すでにのべた「非人称的ナルシシズム」にかんする議論であるだろう。それは、『ホモズ』で重視されていた、マゾヒズムの根源性とその孤独という主題の変容でもある。「ナルシシズム」とは普通は「自己愛」であり、あくまで「人称的」なものだ。それを覆すような「非人称的ナルシシズム」という発想について、ベルサーニは『親密性』において、『フロイト的身体』での自らの記述を顧みながら、共著者のアダム・フィリップスとの対話をするように、以下のような記述をなしていく。
「……なぜわたしたちは人称的なものから自分たちを解放したがるのだろうか。自己性とは――そして自己性を強固にすると想定される人称的な種類のナルシシズムとは――、フィリップスが暗示するように、力と関連づけられている……わたしたちは力の魅力と危険の双方をともに明示する必要があったのだ」(『親密性』洛北出版195頁)。
ついでフロイトの言葉がとりあげられる。「フロイトが強調したように、自己とは、自身の利益や生存にさえ敵対するとおもえる世界を自己化しようとするのである。人称的なナルシシズムは、自己化的な所有の極限形態である。それは自我の思弁的なイメージに還元された世界である」(同上)。
だがこうしたナルシシズムはけっして達成されることはない。それは、世界全体を自己のものとしようとする暴力につながるが、世界は必ず自己に抵抗し、こうした我有化するナルシシズムは危機にさらされる。
そのための解決としてベルサーニがひきたてるのが、『フロイト的身体』での、「進化のなかで獲得された」マゾヒズムの議論であるという。
「幼児は、マゾヒズムによって、自己崩壊的な刺激の時期と、抵抗し防御する自我とのあいだにあるギャップを克服することが可能になる。自己が崩壊することを愛するのは、自己保存の戦略なのである」(同上、196頁)。
一見すると奇妙なこの解決は、人称的なナルシシズムを推し進めることで、世界と衝突し、極限的な事態に陥ることを防ぐ狡知ともいえる。だが同時にそこには罠もある。それはその衝突において自我のさらなる誇大と、それにともなう崩壊を招きうるからである(その場面はまさに戦争などの例で示される)。それに対し、ベルサーニが提示するものが、まさに「非人称」なナルシシズムなのである。
このことを示す重要なひとつの事例は、この書物の冒頭でとりあげられる、『親密すぎる打ち明け話』という映画の分析である。
その映画では、夫との間の個人的な問題を精神科のカウンセリングによって解決するために訪れた女性と税務コンサルタントとの奇妙な関係が描かれる。女性ははじめ、精神療法士のクリニックと勘違いして、税務コンサルタントのオフィスを訪れる。個人的なはなしなのでと切りだす女性(税務コンサルタントも、大抵はあつかうものは個人的なはなしである)に対して、税理士は途中で彼女の誤解に気がつくが、女性は一方的に自分のはなしをまくしたて、次回の予約をとり帰ってしまう。次回に女性が訪れたとき、税務コンサルタントは、自分は医者ではないと告げるのだが、精神療法のカウンセラーが医者ではないことは知っていると女性はのべ、夫とのあいだの性的不能にかんするはなしをさらにつづける。三度目に会うときに、女性はようやく間違いに気がつき、税理士に対して怒り、騙されたと非難するが、このすれ違ったカウンセリングの関係は女性の方からの要望でつづけられることになる。
問題なのはこのカウンセリングは、税理士の方の人生にも介入してくることにある。女性は、あなたは本当に税理士になりたかったのかと問う。それは税理士自身の欲望を解放し、それを自ら疑問にさらすことを喚起する。それ自身が税理士にとってある人生の転機ともなる。
ベルサーニは上記のありかたを、「精神分析は、セックスをしないと決めた二人が、たがいに何をはなすことこが可能なのかを問うものである」というアダム・フィリップスの言明(同上、13頁)が当てはまる事例そのものととらえる。しかもこのカウンセリングでは、結局どちらがどちらを治療しているのかもわからなくなる。ベルサーニはそこで、「いままさに、性的な切望や不安から脱した非人称的な親密性をともないながら、おそらく彼らは「自由に考え、感じ、はなす」ことが可能になるだろう。彼らが再開したものは、相互的な擬似的精神分析などではなく、特殊な会話なのであり、さらにいえば、会話を進めるという条件によってしか拘束されない会話なのである」とのべていく(同上、58頁)。
アダム・フィリップスはこれを「潜在性のなかで宙づりにされている」会話であるととらえ、そこにナルシシズムの非人称化の鍵をみいだしていく。何れが何れを治療しているのかもわからない会話。それは精神分析が「ただの可能性でしかない可能性」をうけいれることによってなされるものであり、「無意識を存在の規定された深部」としてではなく、「脱―現実化された存在として」、「可能的な存在」としてあつかうことから示されるのである(同上、58頁)。ついでラカンによる「すべての愛は二つの無意識的な知のあいだでの、ある種の関係性に基づいている」という『セミネール』第二〇巻の言葉がとりあげられ、こうした愛自身が「宙づりにされた」「仮定的な主体性」においてこそ生じるとされる(同上、59頁)。
こうしたベルサーニの記述は、ベアバッキングの実践という過激なゲイの行動と一見すると対比されるようにみえながらも、ベルサーニはその両者に共通するものを探りだす。ベアバッキングはまさにHIVへの罹患を恐れない行為であるのだが、ベルサーニはそこに「公的に断罪された」「自己義性的な愛」(同上、93頁)と同じものをみるのである。それはまさしくキエティスム=静寂主義につながるものであり、自己の愛が、所有や我有化という方向性をとることなく、非人称性へと通じる道を示すという。ベルサーニはこのように対極的にみえかねない事例をとりあげながら、「非人称の愛」をとりだし、「非人称的なナルシシズム」の可能性を賭けるのである。
ベルサーニからえられるもの
こうしたベルサーニの思考をどうとらえればよいのか。すでにのべたように、ベルサーニの思考は、クィア・スタディーズの諸思考のなかでも、異端的でアウトロー的なものである。その言葉をクィアの運動にただちにぶつけたとしても、まさにそれは斜交いにしか届かないだろう。とはいえ、「戦略的なマゾヒズム」という人間の成長段階を強調しつつ「非人称的ナルシシズム」を追い求め、そこでの「人称性」なき「関係性」を「親密性」として重視する思考は、一面では過激にみえながらも、「ナルシシズム」のもつ「我有化」の暴力と、その社会的な暴発をさける道を模索するひとつの例であるといえる。現状の「リベラル社会」やそこに「包摂」される運動が、結局は「人称的ナルシシズム」の誇大化を招くものであるかぎり、「人称的ナルシシズム」の非人称化や、そこでのある種の「宙づり」性の強調は、それとは違う別の生と関係のあり方を「ダーク」に示すものでもありうる。
ベルサーニの理論は、すでにのべたように、ミシェル・フーコーとの関連のなかにあった。コレージュ・ド・フランスでの講演をおこなっただけではなく、『親密性』でのいくつかの箇所でベルサーニはフーコーをー参照している。フーコー後期の思考とは、まさにギリシア・ラテン世界での「自己」という、現状への自己とは「別の生き方」を探る試みであった。まさにHIVで亡くなったフーコーの思考と、ベルサーニのそれとのさらなる接合は不可欠になるだろう。そしてそれは、誰もが「ダーク」なクィアの側面を抱えている以上、案外、誰にとっても「身近な」問題でありうるのである。
✴︎✴︎✴︎
檜垣立哉 ひがき・たつや/ 1964年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。大阪大学大学院人間科学研究科教授。主著に『瞬間と永遠――ドゥルーズの時間論』(岩波書店、2010年)、『西田幾多郎の生命哲学』(講談社学術文庫、2011年)、『ヴィータ・テクニカ 生命と技術の哲学』(青土社、2012年)、『バロックの哲学 反—理性の星座たち』(岩波書店、2022年)など。
✴︎✴︎✴︎
〈MULTIVERSE〉
「死と刺青と悟りの人類学──なぜアニミズムは遠ざけられるのか」|奥野克巳 × 大島托
「あるキタキツネの晴れやかなる死」──映画『チロンヌㇷ゚カムイ イオマンテ』が記録した幻の神送り|北村皆雄×豊川容子×コムアイ
「パンク」とは何か? ──反権威、自主管理、直接行動によって、自分の居場所を作る革命|『Punk! The Revolution of Everyday Life』展主宰・川上幸之介インタビュー
「現代魔女たちは灰色の大地で踊る」──「思想」ではなく「まじない」のアクティビズム|磐樹炙弦 × 円香
「生死観」としての有機農業 ──エチオピアで学んだ生の豊穣|松下明弘
「病とは治療するものにあらず」 ──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践
「俺たちはグレーな壁を生き返らせているんだ」──1人の日本人がまなざしたブラジルのストリート|阿部航太×松下徹
「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝
「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話
「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー
フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介
「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄
「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生
「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美
「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介
「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く
「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎
「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰
「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義
「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志
「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾





















