太田光海 『ナンキ ──まどろみの森で』 EPISODE 05「あの日、世界は砕け散った」
映画『カナルタ 螺旋状の夢』の監督・太田光海が綴るもう一つの“カナルタ”。アマゾン・シュアールの森で青年は「ナンキ」と呼ばれていた。
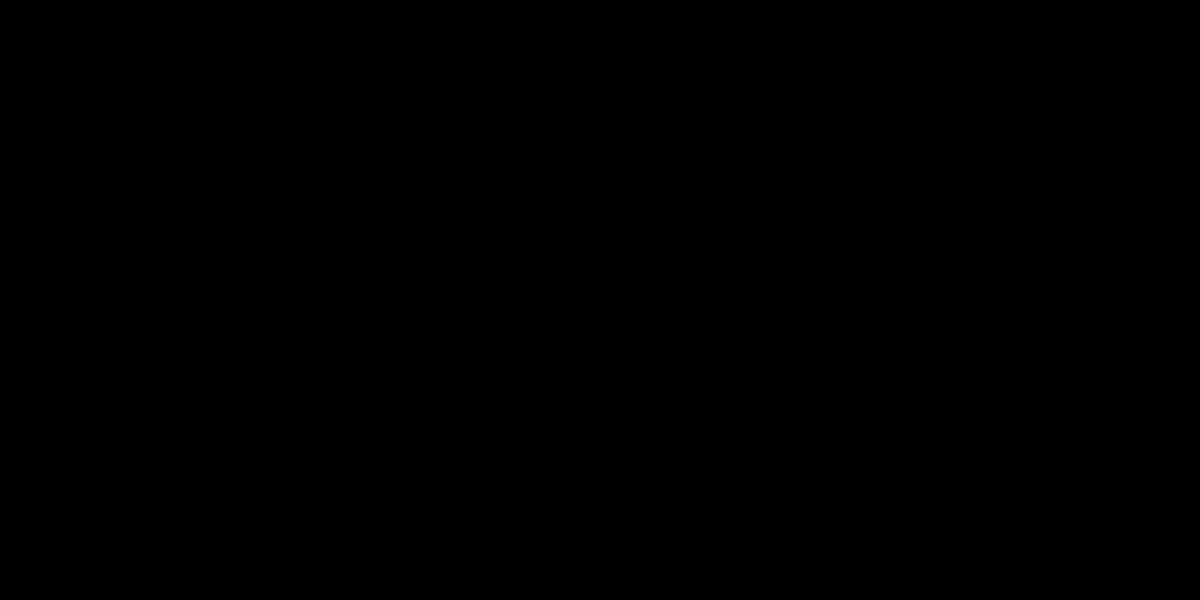
「あの日、世界は砕け散った」
僕がパリに交換留学していたのは、2010年夏から2011年夏にかけての1年間だった。この間に起きたことの中で、どうしても触れておかないといけないことがある。2011年3月11日だ。
あの日、僕は学生寮で少し遅めに目を覚ました。起きて顔を洗い、朝食を取るか取らないか迷っている間に、とりあえず携帯を一瞥した。「スマホ以前」の当時、僕はショップで一番安かったNOKIA製の小型携帯を使っていた。そこには、普段にしては珍しく5件くらいのメッセージが届いていた。「なんだ、変だな?」と思いつつメッセージを読むと、仲の良かったフランス人の友達から「おはよう!日本で地震があったらしいけど、大丈夫か?」と書いてあった。正直、そのときは笑ってしまった。「なんだよ、そんなことか。心配してくれるなんて、こいついいやつだな」と思った。
とりあえず返信せずに次のメッセージに移ると、僕が当時恋をしていて、のちにお付き合いすることになる女の子からだった。「アキミ、元気?日本で地震があったみたいだけど、あなたの友達や家族は大丈夫?」と書いてあった。まただ。最初のメッセージをくれた友達にはまだ返事をしていなかったが、その女の子に僕はすぐ返事を返した。「エミリー(仮名)、おはよう!日本では地震なんてよくあることだよ、心配しなくて大丈夫!」と返した。すぐに返事が返ってきて、「でもかなり大きいらしいよ」とあった。それでも僕は全然心配していなかった。当時、震度6弱くらいの地震は日本でそれほど珍しくなく、もちろんその度に被災した方々がいることも、ときには数名の死者が出てしまっていたことも知っていたけれど、自分の直接の友達や家族がそれに巻き込まれることは想像しがたかった。それがそのときの僕の嘘偽りない正直な反応だった。
2011年は、今ほどWi-Fi環境が整っていなかった。僕の寮にはWi-Fiそのものがなかったし、用意されていたLANケーブルもとにかく遅かったので、僕は情報を確かめることをせずに寮を出て大学に向かった。スマホもなかったので、携帯で調べることも当然できなかった。大学に着いて社会学の講義を受けたあと、校舎の横にあった行きつけのパン屋でバゲットを買いに行こうかと思いながら敷地内を歩いていたときだった。誰かに腕をガッと掴まれた。驚いて振り返ると、その日の朝最初にメッセージをくれていた友達だった。「日本がマジでヤバイことになってるぞ」と言ってきた。顔つきも、かなり心配そうではあった。「そんなに?」と僕が答えると、「うん。とにかく、パソコン室に行って一緒にニュースを見よう」と言う。パソコン室に着き、ルモンド紙だかフィガロ紙だか忘れたけれどフランス語のニュースサイトに飛んだ(大学のパソコンでは日本語が打てない)。すると、目を疑うような光景がそこにあった。
僕と3.11の「ファーストコンタクト」は気仙沼の大火災だった。まさに地獄絵図そのものとも言える、真っ暗な中で煌々と燃え盛る街を写した空撮写真だった。真昼間のパリにいた僕らは、震災当日、ほとんど全ての国家機能が停止し、被害の情報すらもまだほぼ出ていない夜の日本の姿をネット上で確認した。ニュースを読むと、マグニチュード9という、今まで一度も目にしたことのない数字があった。神戸大学に在籍していた僕は、現地に今も深い傷跡を残している阪神淡路大震災のときのマグニチュードが7台だったことはハッキリと覚えていた。その数字だけで、死者の数などの情報が出ていなくても、今回の地震の規模が想像できた。
さらに記事を読み進めると、東北地方を巨大な津波が襲ったとある。「津波」がそのまま “tsunami” で通じるほど、津波は国際的な通念として日本と強く結び付けられている。しかし、僕は人生の中でまだはっきりと「日本を津波が襲った」という状態を経験したことがなかった。正直、津波が実際に来た場合にどうなるのか、ピンと来ない。ピンと来ないけれど、「巨大な津波が襲った」という文字情報だけは目にした。画像もまだ目にしていない。ゾッとするような感覚が体を襲い、ニュースを読んでいられなくなった僕は、とりあえず友達と一緒にパソコン室を出た。しかし、出たあとも、これは感覚的な問題でしかないのだけれど、すでにフランスも含めた世界そのものが以前のものではなくなっているような気がした。
それから数日間、いや数週間、パリに住んでいたにも関わらず、僕は「日本で起きた地震」についての情報から逃れることはできなかった。場所は忘れたけれど、通りがかりのカフェか何かでテレビを見かけたときのことだ。フランスのニュース番組で、なぜか “nucléaire” = 「原子力の」というテロップとともに、 “Fukushima” という文字が並んでいる。「福島」をローマ字表記で読んだのは、その時点の僕の人生で何回目だっただろうか。外国人が “Fukushima” と発音している様子も、それまで聞いたことがなかった。そして、キャスターの顔の横では、何かが爆発するような動画がループしていた。福島第一原発が爆発する様子だった。僕は目の前が真っ暗になるような感覚を覚えた。
チェルノブイリでの原発事故がいかに現地のみならずヨーロッパ全体に甚大な影響を与えたのか、うっすらとは知っていた。それに、原爆を投下された広島や長崎で、被曝者の方々が放射能による後遺症で苦しんだことも、原子力発電所には膨大な数の核爆弾を作れるだけのウランやプルトニウムが仕込まれていることもその時点で知っていた。それだけで、今目にしている動画の意味を察することはできた。そのとき、フランス中のありとあらゆるメディアが、地震と津波と福島第一原発のことを話題にしていたのだ。震災による被害という事実から受けるショックとともに、自分の出身国で起きている話がはるか遠くの一国の全てのメディアの話題を独占しているという状態に、妙にシュールで屈折した感情を覚えた。
僕は寮に帰り、一通り家族や親戚に安否確認をした。全員無事だった。東北に住んでいる身内はいなかったが、高校の友達で東北の大学に進学した人は何人かいた。すぐに連絡がついたか覚えていないが、人づてか何かで無事を確認したはずだ。夕方か夜だかに、同時期にヨーロッパの別の国に留学していた神戸大学の同級生とスカイプで話した。するとその友達が、恐ろしい動画を見つけてしまい、怖いのにそれから目を離せない、と言う。送られてきたのはYouTubeのリンクだった。それを見ると、まさに巨大津波が東北を襲い、逃げようとするミニチュアのように小さく映る車が津波に飲み込まれていく映像だった。
これを目にしたときの当時の感覚は、今でも言葉で表現しにくいものがある。誤解を恐れず言えば、それは神話の世界のようでもあったし、僕にとっての「現実」や「世界」というものの感覚的リアリティを変えるような経験でもあった。日本でその日起きたばかりの天地がひっくり返るような出来事を、僕は物理的には平穏そのもののフランスから眺めながら、気が狂いそうになっていた。これほどの大規模な被害がはるか遠くの自分の出身国で起きているという情報を、これほどのスピード感と圧倒的な生々しさで摂取した人類は、おそらく当時の海外在住日本人が初めてだったのではないだろうか。自分の脳に対してそのときかかっていた負担は、「酷使」という言葉では言い表せない。むしろ、「破壊と再生」だった。脳が一度破壊された上で、すでに変わってしまった現実に対して、必死に自らをアップデートしながら再生しようとしている感覚だった。
少し視点を変えて考えてみると、2011年当時は「報道」という実践のあり方や僕らが情報を摂取する手段が、旧来の新聞やテレビ中心、ネットで見るにしても大手新聞社のオンラインサイトがメインだったのものから、現在のSNSや動画中心のものに変わろうとする過渡期だった。「YouTubeで最新情報を得る」という習慣を当時持っていなかった僕にとって、メディアによるフィルターや補正のかかっていないその動画はあまりにも生々しく、見るに堪えないものだった。
昨年8月、タリバンが首都を制圧したアフガニスタンで、去り行く米軍の飛行機にしがみつこうとした人たちが空から落下する動画が世界中を駆け巡ったが、このように「現場にたまたまいた人」や「非プロカメラマン」が撮影した動画がそのままニュース映像として流れるようになったのは、それほど昔のことではない。震災当時の僕にとって、まだそれは今ほど普通のことではなかった記憶がある。それだけに、3.11に端を発する一連の僕の「メディア経験」は、僕が現実を理解するときの脳内プロセスを無慈悲にねじまげ、屈折させ、粉々に砕け散らせ、二度と以前の状態に戻れなくさせた。
もう一つ、別の視点から考えてみたい。僕にとって、21歳という震災当時の年齢と人生におけるステージは意外と重要な意味を持つように思える。大学3年生の21歳という立場は、非常に曖昧で宙ぶらりんだ。「モラトリアム」と揶揄されがちな年齢でありながら、大学卒業後の進路を考えざるを得ない時期にあたる。すでに就職活動をしていてもおかしくないが、まだ内定は決まっていない。すでに成人はしていて、バイトなどを通して少しは社会経験もあり、知的な面でも大学(もちろん大学進学とは別のルートを選ぶ人も多くいるという前提で)で多少ものごとを抽象的に考える訓練を受けているかもしれないが、まだまだ人格形成の途上である。つまり、3、4歳しか違わなくとも、当時高校生だった人や、25歳だった人とは、大小の比較ではないが、経験の質や受け止め方がかなり変わってくるのではないだろうか。
例えば、当時すでに僕の周りで利用者が多かったFacebookやTwitterでは、年齢が僕より上の多くの人が「辛いけれど、とにかく自分は今できることを変わらずやり続けるしかない」という趣旨の投稿や発言をしていた。その人たちは、すでに就職していたり、自分の生業があったり、少なくとも自分がこれと決めた道を持っていた。僕はそういう投稿を読んで「今、俺ができること?やるべきこと?そんなもの、わかるわけない」と思った。進路のことなど何も決まっていない、しかしやりたいことはぼんやりとある、だからと言ってそれをやると心に決めたわけでもない。そんな状態だった21歳の僕にとって、東日本大震災は全てをリセットし、「生きること」や「この世界での存在のしかた」を根本的に見直す必要に迫られる出来事だった。
〈MULTIVERSE〉
「あるキタキツネの晴れやかなる死」──映画『チロンヌプカムイ イオマンテ』が記録した幻の神送り|北村皆雄×豊川容子×コムアイ
「現代魔女たちは灰色の大地で踊る」──「思想」ではなく「まじない」のアクティビズム|磐樹炙弦 × 円香
「生死観」としての有機農業 ──エチオピアで学んだ生の豊穣|松下明弘
「病とは治療するものにあらず」 ──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践
「俺たちはグレーな壁を生き返らせているんだ」──1人の日本人がまなざしたブラジルのストリート|阿部航太×松下徹
「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝
「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話
「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー
フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介
「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄
「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生
「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美
「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介
「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く
「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎
「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰
「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義
「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志
「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾






















