《perspectives》──沖縄の旧赤線街のギャラリーPIN-UPに集う人々 |第1回「デジタルポップホームレス──ヨシカワサトルの経歴書──」
沖縄県宜野湾市真栄原。かつて〈新町〉と呼ばれた元赤線地帯でギャラリー、PIN-UPは始まった。この連載は、ギャラリーを起点に集い/語らい/表現する人々の視点からローカルの景色を描き出し、共有することを目的としている。

沖縄県宜野湾市真栄原。かつて〈新町〉と呼ばれた元赤線地帯だ。この場所でギャラリー、PIN-UP(ピンナップ)は始まった。。
この連載は、ギャラリーを起点に集い/語らい/表現する人々の視点からローカルの景色を描き出し、共有することを目的としている。我々の暮らす「どこの馬の骨かわからない風景」をあなたのもとへお届けすることが関係者たちの使命だ。
今回の聞き手はPIN-UPオーナーの許田盛哉、葬式(文藝団体 煉瓦)、大城翼(写真家)。執筆は津波典泰(ギャラリー常連客)。
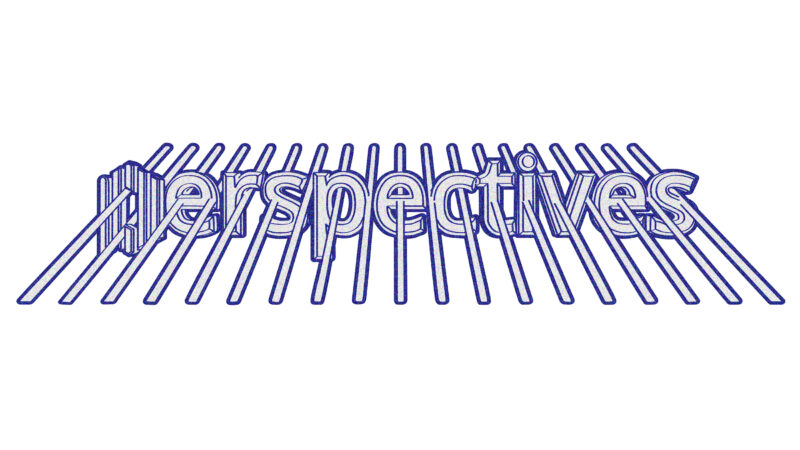
第1回 デジタルポップホームレス ──ヨシカワサトルの経歴書──

ヨシカワサトル(筆者撮影の写真を本人が編集)

2021年の作品(本人提供)

『ここからここに』feat. O葉ちゃん(本人提供)
「女子よりもカワイイおじさんがいる(笑)」
PIN-UPのオーナー、許田盛哉が嬉々とした様子で話したのは2019年の5月。ギャラリーのオープン2周年を記念したグループ展でのことだった。
 ヨシカワサトルの作品『CITY POP』(2019年)。20代から撮り溜めてきた写真、イラスト、人形など私物を組み合わせ自らの中にあるシティポップを表現した(本人提供)
ヨシカワサトルの作品『CITY POP』(2019年)。20代から撮り溜めてきた写真、イラスト、人形など私物を組み合わせ自らの中にあるシティポップを表現した(本人提供)
そのヨシカワサトルなる人物が展示していたのは、自身に提供された壁面の展示スペースを最大限利用したデコレーション。コラージュやインスタレーションではない。あれはデコレーションだ。写真やイラスト、スプレーペイントなどが層を形成し壁を埋めていた。
見た途端に2000年代のローティーンたちが持っていた「プリクラ手帳」を思い出したのを覚えている。
そしてこれをやらかしたのが中年男性だという事実。大丈夫なのかこのおじさん…!、とつっこみつつ笑いが込み上げていた。
その後、グループ展の会場で初めて会ったヨシカワ本人は、痩身のおかっぱ頭で物腰のいい人物だった。その時は酔っていて少ししか話さなかったが、自己紹介として「写真家」という肩書きを簡易的に使っていたのを覚えている。「最近まで写真スタジオに勤めていたんだけど、辞めて自由になった」みたいな話も聞いた。
そこから数年経った現在。ノリが良く、トークの守備範囲の広いヨシカワのことをすっかり遊び仲間の一人だと思うまでに至っている。筆者と歳は20くらい違うはずだが、飲んでいる居酒屋に呼び出し、民度の低いことがバレる写真を撮ったり撮らせたりして…(いや、毎度すみません 笑)。
「ヨシカワさん初対面の時、公文式のショルダーバッグ持っていたので、うちらの間ではしばらく『公文さん』って呼んでましたよ」
そう回想するのは、今回インタビューに立ち合った葬式(作家名)。自身が所属する文藝団体「煉瓦」のグループ展をヨシカワが訪れ、初対面を果たしたときのこと。
公文式のバッグを身につけフレンドリーに話しかけてくるヨシカワの態度は、最初のうち20歳前後の出展者たちを警戒させたという。しかし、スナップ撮影に協力させられたりと、ヨシカワのペースに乗せられ、共に遊んでいるうちに楽しくなり、いつの間にかフランクな間柄になっていたそうだ。
ポップカルチャーを愛し、フットワークが軽く、年長者であるということを問題にしないこの男は、こうやって各所で名物おじさんとなっていく。

取材時のヨシカワのコーデ。テーマは「デニム抜刀斎」。服は全て友人の開催したフリマにて数百円で購入(筆者撮影の写真を本人が編集)
表現遍歴
せっかくなのでカワイイおじさんのこれまでをざっと紹介しよう。
那覇市出身のヨシカワ。初めて大勢の目に触れる作品を世に出したのは中学校2年生の時だった。もともとイラストや似顔絵が得意で、日常的にクラスメイトや先生の絵を描いていたので、その延長で『週刊朝日』の似顔絵コーナーに投稿をしてみたのだ。この時の主な動機は掲載時の謝礼金、5000円。現在もそうなのだが、ヨシカワは意外と現金なところもある。とはいえ、自身の絵の腕試しがしたい、という気持ちも少なからずあったようだ。
結果、投稿を始めてから時を置かずに、当時の横綱・北の湖を描いた作品が見事掲載を果たす。しかし、ヨシカワ少年の心境は複雑だった。
「(似顔絵の投稿は)ダサいじゃない。中学1、2年生ではかっこいいことではない」
クラスでのカーストは中の中。どんなグループとも等しく仲が良かったというヨシカワだが、当時の男子中学生には、絵描きという嗜みにどこか引け目があったらしい。似顔絵と投稿が「モテない」趣味だという自覚もあった。自身の作品が雑誌の紙面に載ったことは素直に嬉しかった。しかし、友人らにはそのことを伏せ、自慢するようなこともなかったそうだ。また、投稿を初めてすぐに似顔絵が掲載されてしまったことで「ちょろいな~」と拍子抜けもしてしまった、と話した。
そんなわけで、ヨシカワはその後しばらく創作活動から離れることとなる。

中学生時代のヨシカワが投稿し似顔絵が掲載された『週刊朝日』の紙面(本人提供)
表現活動が再開するのは20歳をすぎた頃。カメラとの出会いがきっかけだった。
当時よく遊んでいた友人がミノルタの一眼レフ、α8700iを購入。それを一緒に使いスナップを撮ってみたのだそうだ。最初のフィルムを現像したところ、それなりの物が撮れていたことで、「安易にも」写真の道へとのめり込んで行ってしまったらしい。
時代は90年代初頭。写真は今ほどおしゃれな趣味ではなく、ヨシカワの表現欲はまたしてもモテない方向へと進んだことになる。当時、多くの写真家志望の若者がそうだったように荒木経惟、森山大道らから影響を受けた。そして自身の仕事が広告や雑誌を飾ることを理想とした。
この時の写真への熱はかなりのものだったのだろう。20代中盤には県内の写真スタジオに就職。以後、20年以上そこに務めることとなる。家族の事情などがあり、東京など写真表現の中心地に進出する、という選択はしなかった。
いち地方の写真スタジオ、というところから想像できると思うが、就職先の仕事はかなり「泥臭い」ものだったようだ。地元企業の記念撮影、記録写真などを中心に幅広い撮影を請け負う会社だったらしい。カワイイとは無縁の時間の方が圧倒的に多かったことだろう。この時代は格好も雰囲気も今よりもずいぶん地味だった、と本人も振り返る。
もちろん、20年以上にわたり自己欺瞞を抱えて働いていたわけではない。この期間に身に着けた撮影技術や物事への柔軟な姿勢が、現在もヨシカワの表現を支える屋台骨になっているのは確かだ。
勤めの仕事をしながらも、自身の表現を模索し制作を続けていたヨシカワ。しかし、1995年には写真家という枠だけで活動することには明確に区切りを付けている。その原因は、佐内正史のキャノン写真新世紀賞受賞だ。佐内の表現は自身と同じ方向性でありながら、数倍優れていると感じたそうだ。
「勝てないな~と思ったね」
ヨシカワはあっけらかんと思い返した。現在の作品が、写真表現だけでなく、それ以外の要素も吸収している理由の一つはここにあるようだ。

今回の取材は、PIN-UP前の路上で行われたため、ヨシカワとメインのインタビュアーである許田との「公開対談」のような形となった。椅子に座り白いTシャツを着けているのが許田
デジタル時代の幕開けとカニクエブラザーズ
一方、2000年代前後の写真業界には大きな変革の波が押し寄せていた。カメラのデジタル化とPhotoshopなどを使ったデスクトップでの画像編集技術の導入だ。
技術革新に際し、沖縄県内においてもフィルム時代からの古参の職業カメラマンたちが岐路に立たされる、という状況が少なからずあったようだ。しかし勤め先にMacやデジタル一眼レフが導入され、一連の最新技術に触れた時、ヨシカワの胸は高鳴っていた。インターネットの利用も一般家庭に広がっていたことを見据え、これからは誰もが写真や作品を発信できる時代が来る、と直感的に悟っていたのだ。
「Adobe様様だと思ったね」
当時感じた、楽しい予感をそう思い返すヨシカワ。
マスメディアが発信力を独占する時代は終わり、情報過多とカオスが訪れる。SNSが主流となる現代をヨシカワがどこまで見通していたかは分からないが、活動場所や作品の発表方法を不問にするような時代の到来を彼は心のどこかで待ち望んでいたのではないだろうか。
ただし、デジタル技術の進歩によってヨシカワがすぐに今のような表現を獲得したわけではない。さすがに、もっとカワイイことがしたい! と華麗なる転身ができる程身軽でなかった。前述の写真スタジオでもまだまだ働かなければいけなかった。
変化の兆しが見え始めたのは2012年ごろ。自主制作でCDを発表したときだ。
誰が聞いても唐突なタイミングでの音楽活動。本人も「ブラックな会社で家族もいたし、頭おかしい感じ」と振り返る。
CD制作の背景はこうだ。
ヨシカワはもともと多趣味で、様々なカルチャーにアンテナを立てている。そんなわけで自宅録音にも手を出し細々と嗜んでいたらしい。これもまたあまりモテない趣味だ。だが「レコーディングエンジニアもやりたい職業の一つだった」と語るほど、音楽制作にも関心が高かったのは事実である。
4チャンネルのMTR(マルチ・トラック・レコーダー)などを駆使し、自宅で細々と作曲を行っていた頃。彼の精神は生命誕生以前の地球のように不安定だが、一方で大きな変化の予兆を迎えていたと推測される。家庭や職場環境からの負荷、技術革新からのヒント、自己実現欲求、もしかすると何らかの天啓すらも加わったかもしれない。そういった複合的な要因を背景にソロユニット「カニクエブラザーズ」が爆誕した。
仕事と家庭生活の合間を縫って制作したファーストEPは6曲入り。カラオケ好きの友人、貝柱ひとみがボーカルを務めている。制作費用は所有していた写真集のコレクションをほとんど売り払って捻出した。

貝柱ひとみとカニクエブラザーズ『SF Radio 第Q興商』(2012年)。これ以後、新譜は発表していないが、カニクエブラザーズは現在も活動中である
貝柱ひとみとカニクエブラザーズ – 覚醒直列
PVに出てくるぬいぐるみもヨシカワが自作したものである
残念ながら、記事執筆時点ではEP手に入れ、全ての音源を確認するにいたっていない。カニクエブラザーズ本人によると中身は「コンセプチュアルアート」であり、「ヤバいから聴かない方がいい」らしい。
しかしこのリリースこそ、ヨシカワのライフスタイルや表現の方向を、現在の形へと発展させるターニングポイントとなっている。…いや、ターニングポイントではなく修復不能なバグかもしれないけれども。
ヨシカワは、制作でも生き方においても、一つのジャンルや型を極めることに重きを置かない。そのため、あまり彼のことを知らない人からすると、世間一般のロールモデルから逸脱する行動を繰り返しているように映るだろう。先に「バグ」という言葉を使ったのはそのためだ。
一方で、彼の一貫性の無さや「未完の美学」とも言える不完全さ、側から見ていてそわそわするような漸進性(チャレンジ精神?)を楽しむ余裕があるならばどうだろうか。彼の日常は豊かなのだという気がしてくるだろう。

筆者撮影の写真を本人が編集

(撮影:大城 翼)
ジョニー宜野湾にはなれない
「ヨシカワさん、そういう感じの活動してたら、同い年くらいの人とは話が合わないでしょ?」
ここまで話を聞いていて、気になったことを面白半分で尋ねてみた。現役高校生の友だちはいるらしい。しかし、例えば同窓会のような場所で彼が大人しく座り、仕事の愚痴や財産相続の話をするだろうか、と気になったのだ。
「いつまでたっても『ブレードランナー』がすごいって話題は無理なんだよ」
返ってきたのはそんな答え。なるほど、同窓会に行ったとしても話すのはオタクネタか。
年相応のライフステージについて報告し合うこと、かつて興じた趣味やカルチャーを振り返ることー。いずれにせよ現在のヨシカワにはあまり魅力的な行為ではない。そういった場・集団とはやはり疎遠になっているという。
とはいえ、ヨシカワも現在のライフスタイルにたどり着くまでの過程で、加齢に伴うセルフイメージをどうするか、については考えている。彼と同年代かつ、地方に在住する男性、と考えた時に想定できるロールモデルはそう多くない。しかし自身のやりたい表現の方向性を考えたとき、分かりやすい中年男性の型に納まることにメリットが無いことも明らかだった。
そして達したのだ。
「ジョニー宜野湾にはなれないなぁ」
という結論に。
ジョニー宜野湾とは県内を中心に活躍するミュージシャン/タレント。年齢は一回りほどヨシカワより上である。コミカルで楽しく、庶民的。お茶の間でも安心して観れる、分かりやすい「沖縄のお父さん像」の代表としてヨシカワは彼を想定したようだ。コミカルさとか親しみやすさの点ではヨシカワも同じなのだが、ポップさやカワイイが中心となるか、「お父さん」というソフトながらも確固とした男性イメージが中心にあるのか、という違いは大きい。
ジョニー宜野湾『うりひゃあでぇじなとん』
動画の楽曲はキャッチ―なナンバーだが、ハスキーな歌声でブルース調のゆったりとした楽曲も得意とするシンガーだ
CDの自主制作以降、がぜん流行やテクノロジーを追い求めることに力を注ぎ始めたヨシカワ。表現の方向性も時代に合わせ、生産のスピードが早く、複製可能、大量消費的なものへと突き進んでいく。自らが好み、表現したい「ポップ」や「カワイイ」が高度な情報社会を基盤に成り立つことを確信したのだろう。かつて、芸術分野における「アウラ」の喪失を嘆いたベンヤミンがこれを見たら、大泣きするか激昂しそうだが。

2019年11月、PIN-UPで開催された『ヨシカワサトルPOP UPショー ラブ・ユー・ライフ 2019』
「若い頃から現在にいたるまでの作品の展示であり、ヨシカワさんの集大成という感じを受けたので、ポップアップショーというより、僕の中では個展という印象でした」とギャラリーオーナーの許田は振り返る(提供:許田盛哉)


上述の展示『ラブ・ユー・ライフ』と並行して行われたプロジェクト、『PIN-UP highschool』
ギャラリーオーナーの許田を学級委員長に見立て、来場者たちと即興の設定を構築。撮影した。許田は自身を中心に起こった一連の撮影を以下のように総括する。
「ピン高/ピンハイ/ピンナップハイスクール/3年P組/3Pなどといったキーワードを言いたいだけがために作ってしまったイラストや写真も含めた作品シリーズ。80’sポップを感じるようなとてもキュートなイラストと、写真でハイスクールをテーマにしています。ピンナップのお客さんと作家さんをどんどん巻き混んで仕上げていくスタイルです。恐らく本人も何のためにやってるか分からないであろう、ヨシカワサトルワールドが僕は好きです」(提供:許田盛哉)
〈家〉は持たない
以上に書いてきたことで、ヨシカワサトルの生き方が特定のジャンルや表現方法に縛られないものだということは理解してもらえただろうか。
ここで、冒頭で紹介した「デコレーション」の作品を再度読み解くと、あれは「ポップ」「カワイイ」などのキーワードを媒介とした知識と経験の総体である、と捉えることが可能だ。その構造は中心を持たず流動的である。
……今の解釈は全く持って蛇足だ。実際のところは、彼の作品を観るにあたり、そんな堅苦しい解釈や予備知識は必要ない。個々人が好きに楽しめば本人もそれでよろこぶと思う。しかし、やはり強調しておきたいのだ、その境地にいたることの奇特さを。
数十年にわたり、ポップやカワイイを体現し、その熱量を維持し続けるのは人並みならぬ行為だ。
ソフトでキラキラした作品や雰囲気は、その瞬間瞬間からすれば、万人受けし、イージーに消費できるものだ。しかし人生を賭してそれを作り続けるとなればどうだろうか。決別しなければいけない物事や、自らで道を切り開く必要のあることが圧倒的に多いはずだ。表立って特定の主義やジャンルと軋轢を生んだり、世の中の趨勢と対立する思想を掲げることはないものの、カワイイおじさん(ここでは便宜的にそう言わせてもらうが)という生き方も、意外と精神力を必要とするのである。
まあ、ヨシカワの精神力はとうの昔に枯渇し、現在の彼はネジの飛んだ状態である可能性もあるのだが(笑)。
人々が共感するポップさやかわいさは、どんどん更新されていく。なのでヨシカワの表現も次々に新しいものを追い求めなければいけない。この性質上、彼の表現は死ぬまで、いや死んでも完成しない。「集大成」のような作品はできるかもしれないが、人類の文明が持続する限り、探究の余地は永遠に作られ続ける。彼が完成形を知ることはない。芸術としての型やジャンルを確立する気も無いので、後裔がその意志を次ぐこともない。
本人もそれらのことを自覚しているのであきらめの境地である。なんてこった。
インタビューの後半、自身の写真について尋ねられたヨシカワは、自分のスタンスを強調するために、自身たっぷりににこう答えていた。
「写真家とか書道家とか〈家〉を持ったらだめね。オレ、ホームレスだから(笑)」
(※本当に住まいが無いというわけではない、と一応補足しておく)
〈ジャンルレス〉や〈オルタナティブ〉などではない。「ホームレス」だ。ポップやカワイイの探究だけがやりたい、というのが伝わるだろうか。そして、同時に発覚するのだが、彼の活動は、既存の権威を脱構築するような方向も持ち合わせていたようだ。
2、30年後。後期高齢者となったヨシカワがまだ健康で街を出歩けるのであれば、今と比べものにならないくらい友人は増えているだろうし、彼自身のエキセントリックさはさらにパワーアップしているだろう。
巷の有名人となったカワイイじいさんは、聖人、狂人、変質者のいずれの評価も受けていそうだ。しかし彼が表現活動を続けていれば、前人未踏の何かに達している可能性がある。
そう含みを持たせて、ヨシカワサトルと彼をめぐる視点の紹介はひとまず締めくくりたい。
内容も視点も、かなり散らかったものとなってしまったが、連載初回となる今回は、ローカルアートシーンに出没する楽しい表現者、ヨシカワサトルの遍歴と思想について紹介した。
インタビュー終盤で本人が語ったのだが、「ヨシカワさん」と呼ばれるよりも、「サトルさん」とこれからは呼ばれたいらしい。下の名前で呼ばれることで、さらに親近感を高めたいようだ。筆者もインタビュー以後はそれに習っている。
沖縄県外在住のアーティストや表現者の方々で、沖縄での活動・制作を考えており、その足がかりを探しているとき、サトルさんを頼ってみるのは一つの手かもしれない。彼の経験・人脈はおもしろい化学反応を起こす場合がある(質と内容は保障しない)。ヨシカワサトルのSNSアカウントは以下。また、彼のグッズはPIN-UPのオフィシャルストアから購入可能である。
これに飽きず、どうか次回も私たちの視点にお付き合い願いたい。
文/津波典泰
 (筆者撮影の写真を本人が編集)
(筆者撮影の写真を本人が編集)
〈info〉
ヨシカワサトル
Instagram: @yoshikawasatoru
ヨシカワのグッズは、PIN-UPオフィシャルWEBサイトから購入可能。
https://www.pinupgalleryspace.com/
✴︎✴︎✴︎
許田盛哉 Moriya Kyoda/PIN-UPギャラリー、オーナー。 宜野湾市出身。2021年7月5日、豊見城市にPIN-UP POP UP SPACE[iias]を期間限定でオープンする。
現在の夢は昨年9月に全焼してしまったPIN-UPの移転再建。
津波典泰 Noriyasu Tsuha/火災前のPIN-UPで一番酒を飲んだ男。
✴︎✴︎✴︎
〈MULTIVERSE〉
「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話
「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー
フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介
「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄
「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生
「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美
「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介
「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く
「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎
「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰
「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義





















