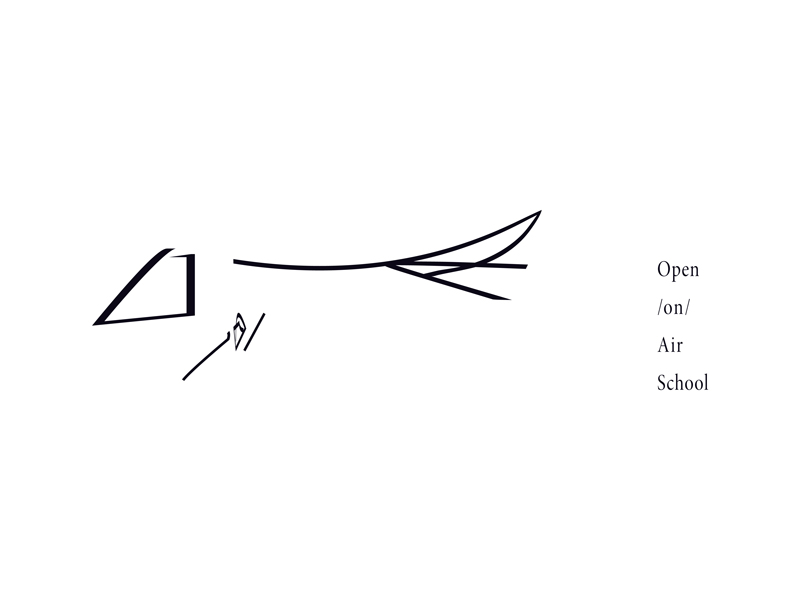21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう(後編) ──七世代先の子孫と一世代前の先祖|山川冬樹 × 村山悟郎
コミュニケーションのオンライン化と先端の顔認証技術は我々の「顔貌」にいかなる影響を与えるのか。後編では、近代的な理性と前近代的な村人性、バランスを具体化する薬学的視点と、断面のアウラをめぐって。

<< 21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう(前編)を読む
<< 21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう(中編)を読む
「バランスが大事」のその先へ
村山 今回のシリーズのテーマである「マルチスピシーズ」という捉え方、あるいは他種との関係性についてもあらためて考えみると、僕の場合は、顔を媒介にした機械学習が対象だったわけです。では、今日において、相手がコロナだったらどうなのかということを考えざるを得ないわけですよね。コロナという他者を考えた時、現状は直面している感染拡大にどう対処するか、短期的な問題解決のフェーズにいるから、その中でマルチスピーシーズ的な観点をどこまで有効化できるのかが、僕はあまりよく分からないんです。だから、対談ではコロナによって変容を被ったコミュニケーションの次元に言及することにしてみたんですよね。
シリーズ「COVID-19〈と〉考える」(HAGAZINE) https://hagamag.com/category/series/s0065
山川 コミュニケーションの次元においてコロナを考える時、視点を等身大の縮尺からミクロなレベルに変えてみると、逆に広い視点で見えてくるものがあると思います。ウイルスというのはゲノム情報を持った非常に遺伝子に近い存在なわけですよね。生物学的にも人間に対する遺伝的な影響が認められていて、遺伝情報の水平伝播みたいことを起こすメディウムとしての役割も果たしている。ウイルスを人間の等身大レベルで捉えると、自分を殺しかねない「敵」ということになるけれど、種というマクロなレベルで考えると進化に寄与する存在でもあるわけです。もしかしたら、新型コロナウイルスが感染拡大していくことによって、ヒトの一部になんらかのアップデートが起こるかもしれない。それくらい大きな視点で考えないと、コロナとのコミュニケーションということは考えられないと思う。
村山 実際にコロナに罹って多くの死者が出ている状況にどう対処すべきかというレベルの話と、人類を超えたマルチスピーシーズの共生関係として考えるというレベルの話がある。その異なるスケールのパースペークティブをどう調停するのかについては、どれくらい議論されているんでしょうかね。アドホックに解決を考えるだけではなく、中長期的な生態環境の調整にいかに人間が関わり得るか。
HZ ものすごくシンプルに考えると、多種との共生を考えるというのはネイティブアメリカンの「7世代先の子孫を思って生きよ」みたいな話だと思うんです。一方で今日のご飯のことを考えながら生きている僕たちがいる。その二つの僕をどう調停するかということだけど、ただ、これは決して相互に矛盾するとは限らないとも思っていて、今日僕が飢えてしまっては困るんだけど、とはいえ今日の贅沢が7世代先を犠牲にするものでもあってはよくない、みたいなある種の程度論だとも思うんですね。目の前の一つの命と、多種を含んだ生態系を考えるということは決して矛盾するものではなく、それは少しだけ時間軸を引き延ばして30年後の一つの命を考えるくらいの視野拡張でも語りうるんじゃないかなと感じてます。ウイルスについて言えば、今、ウイルスに対してなんらかの対策を取ろうとすることと、今後、同じような事態を起こさないような対策を考えることは同時に行うべきだし、行わない方が奇妙ですよね。その今後の対策ということであれば、マルチスピーシーズ的な視点が具体的に意味を持つこともあるんじゃないかと思ってます。
村山 それはわかるんだけど、もうちょっと理論的に、たとえば7世代先のことを数理的にシミュレーションできるんじゃないかなとか思っちゃうんですよ。
山川 外科医(笑)
村山 (笑)。「バランスだよね」みたいな話は当然なんだけど、たとえば今回のコロナの時に「接触を8割減らせ」という話がありましたよね。そのためにはこういう行動制限を、という話もありました。やっぱり、それぞれ個々のバランス感覚でやってくれみたいな話ではなく、具体的に望ましいバランスの目標値の設定が必要なんじゃないかなと思うんです。社会的変数調整に市民が寄与する、という行為をとおして、社会のバランスに何が寄与しているのか市民自身が気づいてゆくようなプロセス。
HZ それこそ専門家会議がやっているような具体的なデータをもとにした議論というのは基準として必要だろうなと思うんですけど、一つの機関がある調査データをもとに一律で具体的な行動指針みたいなものを出していき皆がそれに従うとなると、それは完全に統計学的な管理になっていくわけですよね。統計学が必ずしも悪いわけではないし、間違いとも言い切れないんだけど、統計学には棄却域があるし、零れ落ちるものもたくさんある。あるいは統計というアプローチだと歴史的なコンテクストのようなものを考慮することができないですよね。だから、そうしたデータをもとにした基準のようなものを今日のパニックを機に普遍化しすぎるようなことには警戒心があります。すると、最低限の基準だけ設け、あとはそれぞれがそれぞれの場の特異性に応じて、知恵を働かせていくということが肝要になってくる。ただ、悟郎さんのいう通り、これはなんの具体的な方針にもなってないんですけど(笑)、強いて言えば、そこで生じるだろう多彩な戦略をケーススタディとして記録していくことくらいしかないのかなって気もします。
村山 だんだんと雑談になってきちゃいますけど、昨日、『美術手帖 2020年6月号』のエコロジー特集に掲載されていたブリュノ・ラトゥールのテキストを読んだんですよ。すっごい平たく言うと、近代都市的なライフスタイルの問題について。自分が生きている土地で富を生産せず、食料はどこか遠くの土地で育て、そこから輸送するという生き方。都市生活者は情報を処理して、その情報やサービスを食料と交換したりして生きている。ラトゥールはそういう近代都市の生き方のモデルを批判的に指摘して、問題提起をしている。言いたいことはよく分かるんです。実際、今日のコロナの問題は今の都市のモデルとも明らかに関係があるわけですから。ただ、じゃあ一体、感染症のリスクや生活の豊かさを考えた時、都市においてどのくらいの人口密度が適しているのか、具体的な数字を考えていかないと、結局何も変わらない気がするんですよね。ウィルスは遺伝子を水平に伝播させるからいいんだ、みたいな話になっちゃうと、いや、もうちょい具体的な状況も含めて理論的に考えようよと思っちゃう(笑)。バランスって、結局、政治的闘争になっていくと思うんです。だから、バランスは大事だとして、その言葉の先の明示的な答えが気になる。
山川 さっき僕はなんでも毒にも薬にもなるという話をしたけど、それも一種のバランス感覚と言えますよね。ただそれは相反するものを天秤にかけて中立的なバランスを保とうということとも少し違う。あらゆるものは、ある時には毒に、ある時には薬になるということを理解した上で、それを症状に応じて処方していく薬学的な感覚です。相反する二つのものがコンフリクトする狭間で、単にどちらかに偏向するのでもなく、単にバランスをとって中立でいるのでもなく、薬学的視点を持つことは重要だと思います。
村山 薬学でいうところの致死量ですよね。水でもある一定量を一気に飲むと死ぬみたいなことがある。それは一つの知識として成立してるわけです。
山川 それをはっきりさせようぜ、と。
村山 それをはっきりさせるような議論までなぜ向かわないんだ、と(笑)
山川 そこはすごいよくわかる。日本社会は特にそうですね。
村山 ヒューマニズムや人類学的な知恵もそれぞれ大事だということは分かるんだけど、アプローチがそれだけでは足りない気がするんです。すごい卓越した技術と知で、自らの生を律している人は現代社会にもいて、それは学ばせてもらいたいところなんだけど、みんながみんな「バランス」という概念だけでそうした生を実践できるのかというとちょっと難しいと思う。
HZ それは難しいですよね。ある種の結論を出していかねければならない部分は必要だと思う。それこそ、そういう結論がグローバルな取り決めになっていくんじゃないかと思っていて、ただ、そこで「バランス」という言葉を再び蒸し返せば、じゃあそうした結論をどの領域においてまで出していくのかというバランスが今度は問われてくると思うんです。確かに「バランス」はある種のマジックワードになってしまうんで、それを言ったら身も蓋もないよというところではあるんだけど、一方であらゆることに結論を出してしまうと、すごく画一的な、レギュレーションの多い世界が出来上がってしまうわけですよね。水の例でもそうで、細かく言えば、たとえば、居住環境、食文化、体質などによっても致死量は変わってくるはずです。そういう結論って実は個別性を省略せずには出し得ない。そういう省略の多い世界が果たしていい世界なのかっていうとどうなのか。画一化した文明は必ず滅びるという話もあります。もちろん、全くバラバラに、バラバラの掟で、それぞれのさじ加減に任せ切っちゃっていいのかというと、そこで生じてくる様々な問題があって、そこに適宜に介入していくためにも、法なり国際条約なりがあるわけですけど、とはいえ、法を絶対化し過ぎてしまうと、各土地、各コミュニティ、各文化の特異性みたいなものは、抑圧されざるをえないと思うんです。
村山 分かりますよ。単に都市に人口集中しすぎだろ!って話だし、もう自分が移住しちゃえばいいんだけどね。でも都市というモデルを見直す必要は出てくると思いますよ。「三密」にしても、人間だけ「三密」を回避してもしょうがなくて、家畜も「三密」回避すべきなんじゃないかとか。あるいは、都市で行う大きな文化的な催しが動員を前提にしている以上、モデル自体を更新しなければならない。そのためには、ある程度、バランスを理論立てて考える必要があるでしょう。
HZ 完全に雑談ということで司会という役割を捨てて喋っていきますが(笑)、それこそ対談において、山川さんが問題視された感染者への投石事件のようなものがあるじゃないですか。あるいは県外ナンバー狩りみたいなのが起こっている。やっぱり問題なわけです。山川さんが懸念されている通り、コロナをきっかけとした排除や差別がすでに生まれている。ただ、それをグッて抑え込もうとすると、端的に言えば、グローバリゼーションに短絡していく。だから、時間が必要だと僕は思ったりもするんです。この前の対談でも「村人性」のようなものが、問題視されていたじゃないですか。排他的で同調圧力の強い「村人性」があり、これは問題だ、と。ただ、それを理由にここで「村」を嫌ってしまったら「都市」しか残らないわけです。それだともう「前門の虎、後門の狼」ですよ。
ここで第三の道があるとしたら、村人性をどうアップデートしていけるか、ということだと思うんです。その排他性や同調圧力をいかに穏健なものにしていけるか。たとえばさっき悟郎さんが名前を出したラトゥールなんかは土地と人との関わりを強調するわけですよね。現在、すでに土地は万人から剥奪されているとラトゥールはいう。土地を剥奪された村人というのは、エラのない魚みたいなものです。土地による共同性を穴埋めするように、同調圧力や排他性ばかりが強まってしまう。そこで、まずは土地との関わりを取り戻すことが肝要だと、ラトゥールは言うわけです。『地球に降り立つ』という本でラトゥールは、自然を守ろうというメッセージについて批判し、この自然を「テリトリー」と呼び直そうと奨励してる。テリトリーならば人は守れる、と。僕はこのテリトリー、つまり土地を守るという点において、普遍的なつながりの可能性を見出しているように読みました。それはナルシシズムによる見えない連帯と言ってもいいのかもしれません。今は誰もが自分を愛せない。愛すべきテリトリーを喪失している。それゆえに短絡的な排除のゲームが加速してしまっている。だから、まずはテリトリーを確保する必要があるんだ、と。そういうことを考えると、一時的な縄張り争いにあまり過敏に反応し過ぎない方がいいんじゃないかなとも思います。
近代的な理性と前近代的な村人性のハイブリッド
山川 アップデートの問題はこのコロナ禍ですごく考えさせられました。感染者への投石や県外ナンバー狩りのようなことが起きたとき、ハンセン病回復者やハンセン病問題に関わる人たちの多くが、無らい県運動が繰り返されていると警鐘を発しました。今、僕が問いたいのは「7世代先の子孫を思って」生きる以前に、なぜ僕らは「1世代前の先祖を思って」すら生きられないのか?ということなんです。村山さんが言われた、7世代先まで数理化してシュミレーションすることは難しいかも知れない。でも1、2世代前に実際に起きたことを教訓として現在に活かすことはできるはずですよね。歴史もまたサイエンスとして考えて医学や薬学になぞらえて語るなら、社会が病んでいる時に、臨床試験で得た過去のデータを元にもっと実証主義的に社会を治していくことが何故できないんだろうかと。西洋と日本を比べてどうこう語るのは野暮だとは思いつつ、例えば西洋の社会がどれだけホロコーストが生み出されたメカニズムを分析し、そこから得た学びを反省的に生かしながら、より良い社会を構築するための足がかりを築いてきたかを考えると、日本人は歴史的にあれだけの過ちを犯しながら、そこから教訓を得ず、社会が発展するための足がかりも築けていない。この流砂の上に生かされるかのような不毛な循環はなんなんだろうと。なぜ学ばないのか、学べないのか。
HZ 対談シリーズの第四回で甲田烈さんが山本七平の「裏返し呪縛」のお話を紹介してくれたんですが、これは甲田さん曰く「忘れた」ということを忘れてしまうということ、それによって最初に「忘れた」ことが呪縛として働いてしまうということのようなんです。つまり、日本人は二度、忘却をしている。明治に江戸以前を野蛮な時代だったと忘却し、戦後に戦前を軍部の暴走によるものとして忘却した。それによって戦後がズブズブになってしまっている、と。これはハンセン病の歴史についても同じことが言えるのかもしれません。
『COVID-19〈と〉考える』TALK 04|清水高志 × 甲田烈|我々は対象世界を《御すること》はできない── 既知と未知の「あいだ」の政治を読む
山川 そうそう。前の話で僕が一番伝えたかったことは、らい予防法が間違っていたということそのものではないんです。それは司法で決着がついたことで、すでにリベラル、保守を問わず共通認識となっている。問題は市民自らがそこに加担したことを忘れてしまっていることなんです。ハンセン病を発症した人たちを不当に閉じ込めながら、そのままそこへ閉じ込めたことも、その人たちの存在をも忘れ、さらに自分がそれを忘れたことすら忘れてしまっている。本来なら過去の過ちからは学びを得て、その学びを現在にフィードバックしながら、自分の手で社会をアップデートしていかなければならないのに、あらかじめすべてを忘れてしまっているから、そういう回路自体が成立しない。時には忘却しなければ前に進めないこともあると思いますが、程度論という意味では、日本人はあまりに記憶を喪失し過ぎなのではないかと。近代以前には当時の包摂のシステムが存在し、それなりに機能してきたわけで、近代のシステムの方が優れているとは言い切れないし、「村人性」のすべての部分が悪いわけではありません。
近代的な理性と前近代的な村人性のバランスで言うならば、ハンセン病の強制隔離というのは、両者の持つ悪い部分が絶妙なバランスでハイブリッド化して完成したものなんですよね。それは当時の国際政治力学や、天皇制が複雑に絡み合いながら、半ば無意識的にでき上がったものでもありつつも、やはり市民の村人性を為政者が巧みに援用してきた部分は大きいし、特に戦後は市民も積極的に迫害に参加した。近代的理性にせよ村的メンタリティにせよ、それ自体は毒にも薬にもなるわけで、重要なのは、それらの処方の仕方によってどういう効果が現れるかだと思います。ハンセン病の強制隔離が近代的な理性と前近代的な村人性の悪い部分のハイブリッドであったなら、両者の良い部分のハイブリッドを創ることだってできるはずです。それにはさっき村山さんが言われたように、社会のバランスに何が寄与しているのか、市民自身が気づいてゆくようなプロセスが重要だと思うんです。
村山 今回の対談シリーズにハンセン病の話を出したことについて「関係ないじゃん」と思った人もいるかもしれないけど、僕はとてもクリティカルだと思っているんです。コロナとハンセン病では病状や感染形態が異なるから違うものとして捉えるべきかもしれないけど、政府や民間がとっている対応はすごく似ていると思うんですよね。今回もまた無癩県運動と同じように、感染症対策は地方自治体が率先してやる形になった。全体の対策方針は専門家会議や医師が前に出てきて、細かい部分は地方に任されたわけです。実際、地方自治体の長たちがこの機に乗じてリーダーシップをアピールしようと競い合ってたところもある。僕はもともと地方分権派なんだけど、今回のことに関していうと、県民を動員した競争がはっきりと前面化しているのを感じて、それは問題だなと思いました。
シリーズ『COVID-19〈と〉考える』TALK 06|山川冬樹 × 村山悟郎|隔離され、画像化された二つの顔、その「あいだ」で── ハンセン病絶対隔離政策とオンラインの顔貌から考えるを読む
しかしながら、さっき辻さんが言っていたように、統一的な基準を明確にして、地方ごとの自治を抑圧してしまうとグローバル化に短絡してしまう。その指摘はその通りだとは思います。ただ、地方に投げ過ぎも良くない。たとえば鶏を飼育するのに面積に対して何羽とか、人口密度は平米に対して何人とか、環境権のレベルでは、もうちょっと合理的に考えても良いのではないか。海洋資源の漁獲量とか年間で変動させながら制限しているでしょう、都市の生態系もあれと同じような考え方が適用できると思うけど。もちろんグローバリズムのなかに強者の論理が蔓延ることには抵抗しつつ。
山川 確かにその意味での合理性は欠落していますよね。合理性に欠けているから為政者や専門家も国民をナメてかかってきているところがある。つべこべ言わずおとなしく騙されてくれみたいな。コロナに限らず日本の政治家が説明責任を果たさないことについては、かねてより問題視されてきましたが、他の国と比較しても国民が見くびられてるなというのは感じています。
例えばある島で、島民に抗体検査とPCR検査をしてみたところ、16%もの人がらい菌に対する抗体を持っていたというデータがあります。でもその島からはハンセン病患者は後にも先にも一人も出ていない。つまりハンセン病に限らず多くの感染症は発症しないだけで、かなりの頻度で不顕性感染があるし、病原体もその辺にふつうに存在しているわけですね。でもらい菌が比較的ありふれた菌であるという事実は、今も緩やかに隠されているところがある。なぜなら、それを知ったら恐れを抱く人がいるからです。でもハンセン病は栄養状態や衛生状態の悪い条件下で、らい菌に対する感受性の強い特定の体質の人しか発症しません。これは昔から知られていたことですが、かつては政治的なバイアスもあって多くの医師たちがその説明を怠った。ましてや今の生活環境であれば感受性の強い人でもまず発症しないし、万が一発症したとしても今は治療法が確立されているわけです。市民の恐れの感情が刺激されて差別が助長されるのでは、という懸念も理解できますが、専門家による説明がなければ、市民の間にまっとうな議論も起こらないし、合理的思考も育ちません。そうやってずっと説明が避けられてきた結果、ハンセン病に対する不合理なスティグマが固定化されてしまった。同じような現象は日本社会の至るところに見られると思います。
HZ 差別と偏見の構造というのは、基本的に不合理ですよね。あるいはその事実を知っていたとしても、僕は知っているけど他の人は知らないかもしれないから、みたいな形で差別的な状況が温存されたりする。そこで想定されているイマジナールな関係性は倒錯しているんだけど、「僕は知っている」という自意識のせいで状況が改善されないんです。タトゥーへの偏見なども同じような状況ですね。それこそ僕のタトゥーを見て、「いや僕は全然気にしないんだけどさ、周りがどう思うか分からないからね」みたいなことを言って隠させようとする人は結構います。ただ、そこで「周りの人」と名指されてる人も同じことを言ったりする。彼らの自意識では「自分は偏見がない」ということになってるらしいんですが、いやいや、まさにそれが今もっともありがちな偏見ですよ、と(笑)。そういう想像的な関係性が、差別や偏見を再生産し、固定していくんですよね。
山川 すでに明らかになっている部分で合理化できるところは合理化する必要があると思うし、たとえ一時的に批判が出ても、議論することを恐れず知識を共有する努力をもっとした方がいいと思うんですよね。誰も責任を取りたくないから、それをあえてやってみようとはならないんだろうけど。これこそまさに戦後ずっと続いている「無責任の体系」ですよね。
アウラは断面にこそ生じる
HZ ところで、もう3時間近く話していますね。そろそろ終わりにしましょうか。これ以上は文字起こしが大変そうです(笑)。
山川 一つだけ、話し忘れてたことがあるんですけど、前回の最後、辻さんがコンピューターの充電切れで急に消えちゃったじゃないですか。あれがね、すごい味わい深かったんです。今日、オンラインではなかなかアウラを感得できないという話をしてきたわけだけど、辻さんが消えた瞬間、アウラがものすごい現れてました(笑)。だから、今日も解散する瞬間が楽しみなんです。
村山 面白かったですよね。あの時、辻さんのアウラが確かに立ち上がってました(笑)。通信を切る瞬間というのは、通信の死とも言えると思うんだけど、あの充電切れという切断の仕方がまた妙に「死」を感じさせたんですよね。それこそ山川さんが前回、フェイスライブ上の公開殺人なんかを引き合いにルシファー的なアウラについて話されてたじゃないですか。そういうタイプの緊急性が、辻さんのアウラにはあった。辻さん、充電切れる前から予告してたじゃないですか。あと2%しかバッテリーありません、みたいに。
山川 テロ予告みたいでしたよね(笑)
村山 そうそう。予告はしているんだけど、本当に切れるタイミングはコントロールできない。それはロボットが電池切れで停止するような状況とも似ていて、あれも死のメタファーとして描かれるものですよね。エヴァンゲリオンが、電源切れて動かなくなる、みたいな。その停止した瞬間に感じる有限性みたいなもの、それがオンラインコミュニケーションにおけるアウラの可能性を支えているものかもしれない。デジタルデータって急に消失することがあって、むしろ失われることによってアウラが出現する。
山川 アウラは断面にこそ生じるんですよね。フェイスブックライブで配信される公開殺人のような動画を肯定することは絶対にできないけど、とはいえ、そうした動画には確実に生と死の断面が映し出されている。恐ろしいことですが、それもまた一つの表現であることは事実で、生と死をめぐる一つのスペクタクルとして人々に消費されている。でも単なるバッテリー切れで辻さんがオンライン空間から消えてしまった瞬間にも同じ断面があった。心理的ショックの度合いで言えば、殺人動画の方がはるかに強烈です。でも僕としては辻さんが忽然と消えてしまったことのささやかなショックを、殺人動画よりも鮮烈な瞬間として味わわなければならない、という気持ちがあるんですね。薬というのは飲みすぎると体が慣れてしまってだんだん効かなくなりますよね。そうするとさらに強い薬が必要になって、いつの間にか薬だったものが毒になってくる。情報と感性をめぐって今の僕らにも同じようなことが起きている。でもわざわざ誰かを殺さなくても、生と死をめぐるささやかな断面は実はいたるところに存在していて、感性をブローアップすれば、そこにあるアウラを感得することができる。
そう言えば、ボリス・グロイスがベンヤミンに触れつつ、アウラは現代になってはじめて生まれたんだ、と言っていましたね。村山さんがドゥルーズに触れつつ話された、かつて顔はコミュニケーションにおいてそれほど重要ではなく、メディアの上で描かれるようになってはじめて「顔」として現れたんだ、という話とも通じるな思うんですけど、グロイスは技術によってオリジナルを複製できるようになったその時、つまりコピーによってオリジナルの存在が危機に瀕した時にはじめてアウラが出現したと言っている。つまりアウラが生まれる根拠と消滅する根拠は同じだと。
村山さんが最初に立てた問いは、ZOOMなどのWeb会議アプリを介したコミュニケーションが日常化し、顔が画像化していくことで、僕らはアウラを失っているのではないか?というものでしたが、あの場での辻さんのアウラは、オンラインでつながっていて顔が見えていた時じゃなくて、やはり充電切れで消えてしまった瞬間にこそ現れたんだと思うんです。僕が大島にかつて生きた人たちと作品を介して交流しようとしているのも、彼らが不在であるがゆえに、自分との断面に生じるアウラに取り憑かれているからだと思います。ここは面白いポイントですよね。
村山 電話にはアウラがもっとあった気がしますよね。それこそ恋人と電話で喧嘩していてブチっと切られる時みたいな。特に昔は今のようにかけ放題でもなかったから、電話自体が有限なものとしてあった。断面が生じやすかった。その点、ZOOMとかは四六時中繋ぎっぱなしにする人もいて、有限性をあまり感じない。この前は、たまたま辻さんが充電器を忘れたからああいうことになったけど、否応なしに切れてしまう感じについてはもうちょっと整理して考えたら面白いなと思いますね。
山川 そうですね。一方で断面にアウラが立ち現われるテンションの対極には、こういう風に時間を気にせず話すことから生まれるものもあるな、と今日は感じてます。この前のような時間に制限がある場だと、次々と有用な言葉を差し出し続ける必要があるじゃないですか。でもこういう風に酒を飲み、時間も言葉も蕩尽しながらグダグダと話していると、滞留する時間の中から思いがけなく果実がこぼれ落ちてくるみたいなことが起こるんですよね。この未曾有の緊急事態ではそれもまた重要なのかも知れないなと。「断面」は死者と生者で共有できますが、こういう時間は現世を生きる者同士でしか共有できませんから。特にZOOMの場合は、良くも悪くもプライベート空間同士でつながるじゃないですか。身体的にはディスタンスをとりながら、プライバシー的にはすごい濃厚接触状態にある。誰とでもとはいきませんが、それぞれのプライベートが侵食しあう中で、そのグダグダから生まれるものもある気がする。今日はそんな感じですよね。グダグダしているけど、すごくいい話ができました(笑)
HZ そうですね。後半、対談を仕切るという役割を忘れて僕も好き勝手にグダグダと話していましたけど、この追加収録の場自体がZOOMの可能性の一つだと思います。ただ、とはいえ、あれですね。もうちょい状況が落ち着いたら実際に会って飲みたいですよね。
じゃあ…今夜はどういう感じで回線を切りますか。僕がホストなんでみんなを一斉に切ることもできますけど。
村山 じゃあ、それでいきましょう(笑)
HZ これはカウントダウンとかした方がいいんですかね? アウラ感得のためには。
山川 カウントダウンすると言いつつ、そのまま切るとかね(笑)
HZ ああ、なるほど。じゃあカウントダウンしま…(切る)
(了)
(Text_Yosuke Tsuji)
✴︎✴︎✴︎
山川冬樹 やまかわ・ふゆき/1973年ロンドン生まれ。現代美術家/ホーメイ歌手。横浜市在住。声と身体を媒体とした表現で、音楽、現代美術、舞台芸術の分野で活動。心臓の鼓動の速度や強さを意識的に制御し、それを電子聴診器を用いて光と音に還元するパフォーマンスや、骨伝導マイクで頭蓋骨の振動を増幅したパフォーマンスで、国内外のアート・フェスティバルやノイズ/即興音楽シーンなど、ジャンルを横断しながらこれまでに15カ国でパフォーマンスを行う。2015年横浜文化賞文化・芸術奨励賞受賞。
村山悟郎 むらやま・ごろう/1983年、東京生まれ。アーティスト。博士(美術)。東京芸術大学油画専攻/武蔵野美術大学油絵学科にて非常勤講師。東洋大学国際哲学研究センター客員研究員。自己組織的なプロセスやパターンを、絵画やドローイングをとおして表現している。2010年、チェルシーカレッジ, MA ファインアートコース(交換留学)。2015年、東京芸術大学美術研究科博士後期課程美術専攻油画(壁画)研究領域修了。2015-17年、文化庁新進芸術家海外研修員としてウィーンにて滞在制作(ウィーン大学間文化哲学研究室客員研究員)。http://goromurayama.com/
✴︎✴︎✴︎
〈INFORMATION〉
岡﨑乾二郎&村山悟郎共同企画
アートスクール 「Open /on/ Air School 」トライアルゼミ開講のご案内
2020年11月より、岡﨑乾二郎と村山悟郎が共同で企画するアートスクール「Open /on/ Air School」を開講致します。本スクールは、拠点を持たず、不定期で開催するゼミを継続的に行う、アートスクール・プラットフォームとして構想されました。
「Open /on/ Air School」は、《時間や空間のスケールをみずから制御する方法と技術の獲得を前提に、事物と具体的に関わり、事物を作り生成させる》、一言にすれば《モノをつくることを通して世界を再発明する》、理論と制作、実践を身につけるための学校です。生産、吟味、そしてそれをいかに世界に結びつけるかついて、講師と受講生がともに考え、作品として実装することを目指します。
2020年11月に第1弾として開講するトライアルゼミは、ゲスト講師に豊嶋康子氏、毛利悠子氏、下西風澄氏、土井樹氏を迎え、「①アーティスト・ストーミング・ゼミ」と、「②科学/哲学/芸術のエアスクール・ゼミ」の2本のゼミ(全6回)で構成されます。受講希望者は「ゼミ生コース」と「 聴講生コース」から選択し、対面とオンラインを併用して開催致します。
公式サイト→https://open-on-air-school.org/
〈MULTIVERSE〉
「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー
フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介
「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄
「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生
「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美
「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介
「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎