大島托 『一滴の黒 ―Travelling Tribal Tattoo―』 #24 南島に舞う蝶人たちの羽音──琉球ハジチ考・後編
タトゥー・アーティスト大島托が世界中の「タトゥー」を追い求めた旅の記録。舞台は日本の最南端・沖縄。歴史と今を縫い合わせる「針」の音に耳をすませる。

ハジチは「一つにして無数なり」
那覇に戻る道すがら、繰り返し目につくものがあった。のどかな南国の田舎風景の中にヌッと現れる巨大な米軍基地とその周りに寄り集まるバーや多くの路面店のタトゥーショップ。同じ名前のショップもいくつかあり、チェーン展開しているところもあるようだ。きっと景気が良いのだろう。タイのカオサンエリアやウィークエンドマーケットを彷彿とさせる風景だ。タイの現代タトゥーもベトナム戦争時の休暇アメリカ兵のために始まったというジミー・ウォンの言葉を思い出す。アメリカが世界中に輸出した基地文化だ。アメリカ兵の行くところにはとにかくスパムとタトゥーが付いて回る。
そしておそらくは日本のどこの他の地域よりもスパムが消費され、タトゥーショップが身近にあるのが現在の沖縄だ。
北海道のアイヌのトライバルタトゥーであるシヌエと沖縄のハジチは、手や前腕という施術部位や、それがほとんど女性のみの文化だったこと、明治政府によって禁じられてから現代まで断絶している歴史、など多くの点で良く似ている。さらに最新のDNA研究によれば両者は地球上のその他のいかなる集団よりも互いに近い関係にあることが分かっている。
しかしアイヌがタトゥーファンのみならず世界的に非常によく知られている現状を考えると、ハジチは本当に不思議なほどに認知されていない。タトゥーファンどころか僕の周りのトライバルタトゥーのプロでも見落とす人が出るぐらいのレベルなのだ。実際、僕が最初のハジチ画像をSNSにアップした時に何人かのプロが「Ainu !」なんてコメントしていた。ひょっとして民族の呼称の問題なのかなとも考えた。Ainuに相当するワードがOkinawanなのかRyukyuanなのか、はたまたUchinanchuなのか、がいまいちはっきりしないから印象が3分割されて覚えることが簡単ではなく損をしているとかなのだろうか。
しかしながら世界のコアなトライバルタトゥーファンはもっとハジチに注目するべきなのだ。なぜならハジチは、一つにして無数なり、の最高のサンプルなのだから。
地球上のトライバルタトゥーの多くは一つの地域や部族で一つのデザインだ。両性が入れている場合はそれの男型と女型のパターンが一つずつということだ。それをスポーツチームのユニフォームのように皆で共有している。しかし現地に行って観察してみると実際には個々のデザインには微妙に違いがあることが見て取れるのだ。集落ごとにも何かしらのトレンドがあるようにも見えるのも普通だ。一体これらの差異は何なのか。あるいは類似性は何なのか。地理や政治や距離との関係は。意図なのか自然なのか。さまざまな興味が湧いてくるこのデザイン伝播の現象を、諸島という、付かず離れずの絶好の環境の琉球弧で、他では見たこともないぐらいの精度でひたすら緻密にマッピングしたのが日本のハジチ研究の凄いところなのだ。琉球弧の各島々、各集落、各個人まで地道に丁寧に調べ上げて記録に残している。施術したハジチャー(タトゥーイスト)まで調べた資料もある。これはトライバルタトゥーと一流の民俗学者、記録者が一国内に同時期に共存していたという世界的にも稀有な偶然によるところが大きいと思う。
それによると、まず琉球弧全体で大きな定型があり、その分かりやすい基本的なベースとなっているのは沖縄本島のデザインだということが見て取れる。本島内でも中心の首里から周辺に向かって線のボリュームが増している。その大定型に各島々で独自のアレンジが加わり中定型とも言えるベースを形作る。沖縄本島からの距離と、このアレンジの大きさは比例しているようだ。そしてそれに基づきながら島内の各集落ごとのアレンジで小定型が生まれ個々のデザインが生まれていく。それはまるで手首から指先に向かって神経や血管が広がっていく様を皮膚を透かして見ているような壮大なる精密さだ。ニライカナイの神々が首里に落とした一滴の黒の物語だ。
主だった各島デザインのバリエーションを彫り終えて画像を公開してからは、まずインスタやFBを経由して外国人がハジチを入れに来るようになった。沖縄が好きな旅行者や沖縄にルーツを持つハワイやブラジルの日系人だった。特にハワイでは友人のポリネシアンハンドタップ名人のケオネが周りに宣伝してくれていたようで、彼の関係先からたくさんの問い合わせがあった。ケオネ自身も日系だ。沖縄は貧しさに苦しんだ歴史の連続で、外に活路を求めて移民した人々が多かった地域の一つでもあったのだ。

それに続いて徐々に関東地方在住の沖縄や奄美大島の出身者やその子孫の人たちがホームページ経由で来るようになった。ネットでハジチのことを調べていてうちのキャンペーン告知にたどり着くという流れだった。東京での仕事のことがあり、さすがに手の甲や指には入れられないのでキャンペーン自体には乗れないけれどハジチデザインを身体のどこかに入れたいというお客さんがけっこう来るようになった。

また、別件のデザインで来店しているお客さんと世間話をしていてたまたま沖縄出身だということが分かり、うちではハジチキャンペーンをやっていることを話すとハジチ柄を今回のデザインのどこかに織り込んで欲しいみたいな流れになることもよくあった。そこらへんの決断にはノリの軽さを感じる。これが南国気質というものなのか。そしてどうやら沖縄の若い世代はハジチのことをよく知らないのだということも同時に分かってきた。沖縄の学校では地域史の授業でもそこに触れたりすることはないらしい。そういえば実は僕もタトゥーイストになるまでは沖縄にトライバルタトゥー文化があったなんて思いもよらなかったわけだが。
日系外国人と都内沖縄出身者の両者に通じるのは、人は故郷を離れることによりあらためて自分が何者なのかを強く意識するという構造だ。そして彼らの地元ではタトゥーショップはごくありふれたものなのだという共通項もある。
墨と泡盛の香り
那覇市内でもひときわ賑やかな国際通りの脇道にある月光荘という宿に荷をおろした。大通りからほんのちょい、数十メートルほど脇道に入っただけなのに、それは廃墟じみたボロ宿だった。隣にいたっては完全なるゴミ屋敷だ。界隈全体が築70年ぐらい、つまり第二次大戦の激戦地として荒れ果てていた後に建て直したきりのように見える。ロビー、というか一階の座敷には旅行者たちが集まって飯を食ったり話をしたりしている。ちょっと話に混ざってみると、ここは長期滞在や島外からの移住者たちの玄関先のような場を形成しているようだった。東南アジアのどこかの宿という感じ。庶民の飾り気ない生活感が漂っていて凄く良い空間だ。亜鶴君たちの展示会でのトークの前にここで撮影があるのだ。

昔の旅仲間何人かとも会った。やはりこの宿はその筋ではよく知られているらしい。福島の原発が爆発してメルトダウンした頃を境に沖縄に移住した旅仲間は多い。もともとフットワークの軽い連中だ。放射能汚染を気にするのならば東京にへばりつく理由なんてない。いろいろ聞いてみると現地定着の勝率は5割ってところなのかなと感じた。半分が諦めて帰った感じだ。これは発展途上国で自活するなどよりはもちろん格段に高いけれど、ヨーロッパの大都市と比べるとちょっと低い。日本国内であることを考えに入れると、連中にしてはずいぶんと苦戦しているようだった。とにかく仕事があまりない。これが最大の理由だ。
あとは地元のコミュニティーへの浸透が意外と難しいこと。東京に東京出身者なんていないと言われるほどのごた混ぜ社会ではそれぞれの最小公倍数みたいな薄い空気を読めれば十分なのだが、ここは住人のほとんどが先祖代々のウチナンチューで、その独自の空気が濃密に満ちている世界らしかった。僕が今までに知っているのは薄い空気に順応した、故郷を対象化する目線を持つ沖縄出身者だけだ。国際通り近くのドンキホーテで買い出し中、ウチナーグチ(現地の言葉)の店内アナウンスが何を言っているのかさっぱり理解できず、「濃密な空気」への期待は高まっていった。
翌日の昼前から宿の庭先でハジチのセッションを行った。硯に泡盛を注いで墨をすり、指で直接つまんだ針束で彫る、琉球古来の手法を用いた。モデルはアーティストでありエッジの利いた被写体として沖縄の若い世代に広く知られる吉山森花、カメラは沖縄のストリートを撮って木村伊兵衛賞受賞の石川竜一、記事はStudio Voice誌の編集者で現材はHagazine主宰の辻陽介。誤解のないように言っておくが、いつもこんな大げさなことをやっているわけではない。今回、僕らは京都の丸善に檸檬を置くような気持ちでここに集ったのだ。しかも森花ちゃんと写真集を撮ったこともある現代日本を代表する沖縄の写真家石川真生さんが彼女の付き添いで見物に来るというオマケ付きだった。沖縄のご意見番みたいな超大御所の思わぬ登場で場に緊張が走るが、これで良いんだと深呼吸して墨を丁寧にすり続ける。

ハジチを沖縄でウチナンチューに彫るのは初めてだ。ネオトライバルタトゥーとしてこれまでオープンに展開してきた僕のハジチキャンペーンが、現地ローカルへ、つまりリバイバルタトゥーのサイドにより深く踏み込んだ瞬間なのだ。インド人にカレーを作って出すことになった日本人主婦の気持ち、というものが仮にあるとするならば、今の僕にはそれが痛いほど分かった。
墨と泡盛の混ざり合った強い香りは独特だった。今まで嗅いだことのないものだ。針束が皮膚を弾くたびに生み出される「チャッ、チャッ」という音が静かな昼前の路地にリズミカルにかすかに響く。

森花ちゃんはとても安定していた。うなじに「不滅」という文字が見える。その頃、僕はちょうど、タトゥーをめぐる死と再生=永遠、というようなことを考えている最中だったので、そのことを話しながら針を進めた。特に痛いことで知られる指先の第一関節の上を彫っている時も、彼女は何かに耳を澄ませるかのように落ち着いている。
途中休憩の間、僕は道具を一つずつ取り出して解説し、セットアップの手順も初めから通してやって見せた。彼女は印象的な絵を手がけるペインターでもあるし、きっとタトゥーを彫ることにも興味があるんじゃないかと思ったからだ。今回のセッションは、とにかく沖縄の若い世代にハジチの存在を知ってもらうことを一番の目的としているが、なおかつ、あわよくばその中からハジチャーが出てくることも期待しているのだ。僕が今まで出会ってきた理想的なタトゥーリバイバルの担い手は、その言語、風習を己のものとし、外見に人を惹きつけるインパクトがあり、内面には勇気をなみなみとたたえる人たちだ。とりあえずそれは東京の小太りなオッサンではない。オッサンは本来、トライバルタトゥーからエッセンスを汲み上げて自由に再構成する立場の者であり、リバイバル的な動きは本格派が現れるまでの場のつなぎ役としてやっているに過ぎないのだ。


その後のセッションでは森花ちゃん自身が針を握り、僕は皮膚のストレッチと余分な墨汁のふき取り役に回った。思ったとおり良いハンドコントロールだ。リキみも、ためらいも、ビビリもない。

「島の時間と繋がった」と彼女は言った。
「いろいろと上手いな、大島組は」真生さんからは合格点がいただけたようだった。

新大久保のサトウキビ畑で
あれからはや数年が過ぎた。
翌年にはタトゥー人類学者山本芳美によるハジチと台湾原住民のトライバルタトゥーの展示が沖縄県立博物館・美術館で開催された。公立博物館でタトゥーの展示が行われるのは実に本邦初の画期的な出来事だった。その準備期間中にHagazine上で対談(※)させていただいたのだが、漂えども沈みはしないはずの研究者である氏をあのタイミングで行動させたのは正義感だったと思う。これを機に全国紙の新聞をはじめとする多くのメディアがハジチの記事を出した。そしてそこでの問題提起は、その後のラグビーW杯日本大会で最強軍団ニュージーランド代表がマオリ族のプライドであるタトゥーの露出を自粛して試合に臨んだことの是非をめぐる議論にまでつながっていったように思う。やがて裁判では無罪が確定した。
※「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

ハジチのことを知っている人は格段に増えた。しかも可愛くておしゃれなイメージをともなってだ。ハジチデザインのモチーフを肩や腰などの身体の別の部位にワンポイントなどで入れたいというオーダーは、ウチナンチューに限らず、また国籍も問わず、今やオーガニック好きの女性客たちの選択肢の一つに登って来つつあると言っていい。最近ではうちのキャンペーンに応募してきてくれた人の中からハジチャーを目指す女の子が出てきたし、また他の沖縄のタトゥーイストが手がけた完全な形のハジチの画像をちらほら目にするようにもなった。そろそろ無料キャンペーンでのスタートアップは終了すべき時期がきたのかもしれない。仕込みは上々。パーティータイムの始まりか。
そういえばスパム卵焼きおにぎりも最近は都内のコンビニで見かけるようになってきた。そんな時は「赤いきつね、でか盛、お揚げ2枚入り」と真空パック入りの豚角煮も一緒に買ってラフテーソバにしてイートインコーナーで食べるのだ。すぐ隣の歌舞伎町に行けば美味い沖縄ソバ屋もあるのは知ってるけど別にこれでいい。島のよろず屋は懐かしいが、新大久保の雑踏だって気の持ちようによってはサトウキビ畑みたいなもんだ。
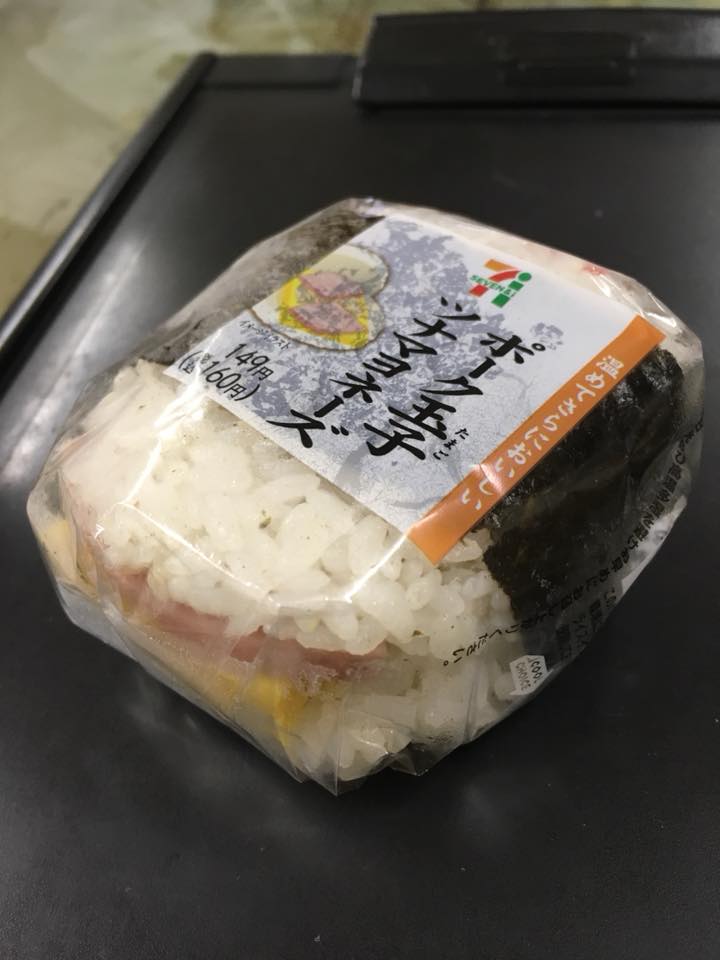
島の時間は僕の中でも流れている。
なんだかトントン拍子でカチャーシーみたいに盛り上がってきたハジチだが、僕には同時期にスタートさせたもう一つのトライバルタトゥーのプロジェクトがある。次回は北海道のアイヌタトゥーについて書いてみようと思う。
〈MULTIVERSE〉
「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話
「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー
フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介
「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄
「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生
「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美
「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介
「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く
「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎
「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰






















