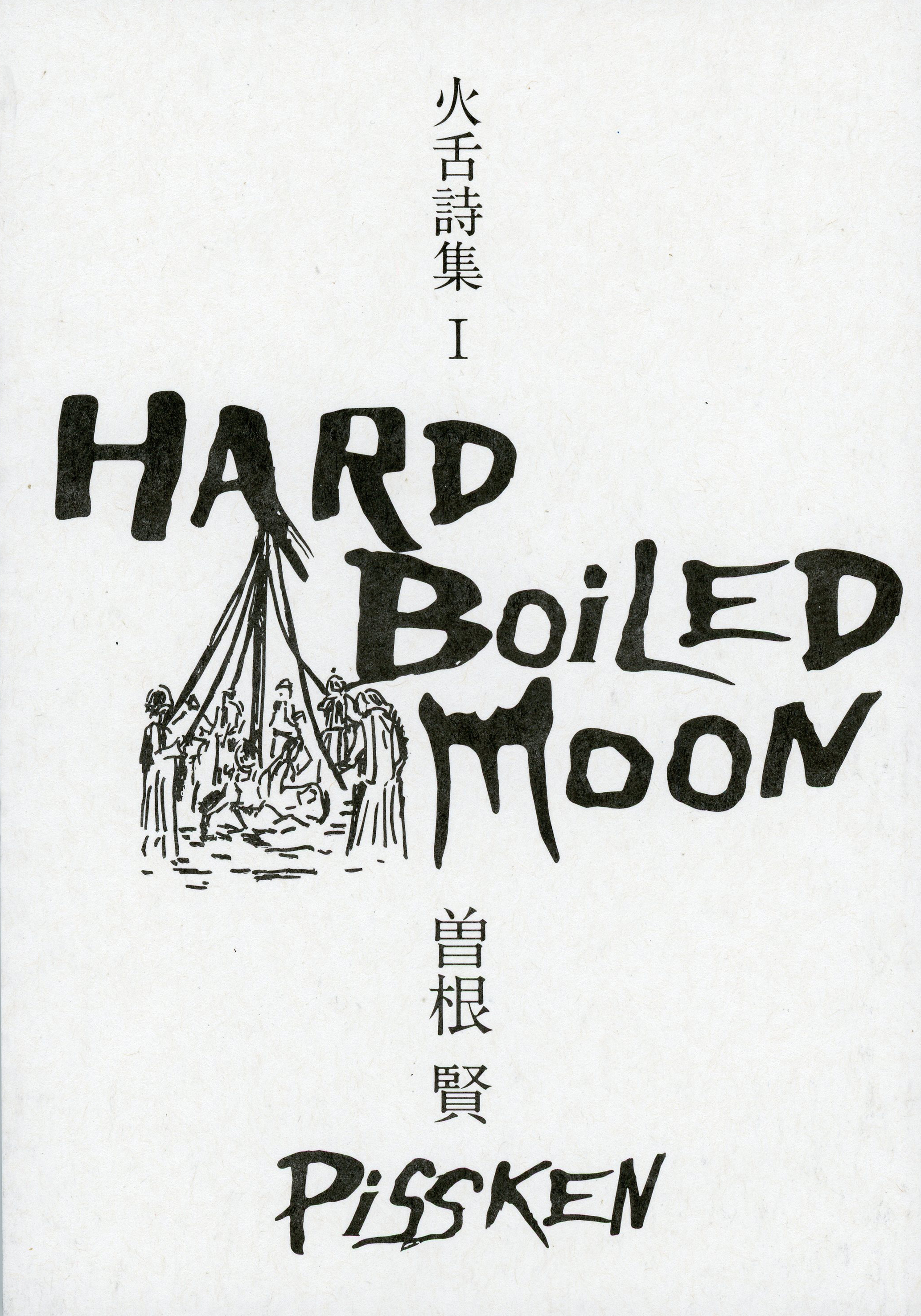「ある詩人の履歴書」(火舌詩集 Ⅰ 『HARD BOILED MOON』より)|曽根賢
『BURST』の創刊編集長だったピスケンこと曽根賢が、給付金を使って発行した処女詩集『火舌詩集1 Hard Boiled Moon』より。

ある詩人の履歴書
厄年。不倫相手と同棲し、二十年暮らした妻と離婚、その年会社を馘首になる。
女のヒモとなり小説を書こうとするが、満足な一行も書けず、お決まりの酒とクスリに逃げ込む。
酒は焼酎をコーヒー割で一日七合。
クスリはたまに眠剤と覚醒剤とアシッドと向精神薬、ガンジャはちょくちょく。
四十五歳から四十六歳にかけて三回もアルコール性重症膵炎で入院する。
最初運ばれたときは致死率四割と死にかけた。
が、大酒はその後もつづく。
「おれはもうとっくに気が狂ってるんだろうか?」
やがて女の実家である酒屋で、女の母親と妹と犬と同居する。
アル中が酒屋へ婿入りとはこれ如何に。
一日に三度の犬の散歩と、夕食をつくる以外の時間は、友人まで引き入れて、店の高価なベルギービールを呑みまくる。
ヒモとしての肝心の仕事、セックスと夢を語ることもせず。一年後、午前中に「どうか出ていってください」と、丁重に女から頭を下げられる。
午前中の丁重な別れの言葉は本気なので、酒屋を出るしか仕様がない。
その後一年間、後輩のデザイン事務所二つと昔の女の家を転々としてから、五十五歳の現在まで、この「七曲り荘」に住んでいる。
雑司が谷鬼子母神「七曲りの路地」のどん詰まりに位置するアパートだ。
六畳一間の風呂なし便所共同家賃三万円。
一階に住む大家さんは御年九十二歳、小林多喜二マニアの往年の文学少女だ。
女のヒモが首からとけたのにおれは働かなかった。
当然、家賃を払えず、毎年半年も滞納。年に二度盆暮れに帰省し、年金暮らしのおふくろの脛をかじり取った。
(ちなみにバスの運転手の親父は、おれが二十八歳のときに脳出血で即死している。享年六〇)
食費と酒と煙草代等は友人たちにたかり、電気が止まるたびに蝋燭の燈りで晩酌し、冬なら友人に電気代を払ってもらい、ついでに金をむしり取る。
郷里出身の餓死自殺をした詩人のごとく、殊勝にも餓死を目指したときもあったが、元来スラム育ちなので、いわゆる泳げるものは入水できないのと同じで、餓死などできようもない。
借金は一切せず、八年間を親兄弟仲間贔屓筋の世話となり、「詩人は民衆のヒモだ」とうそぶいては、贔屓筋からの到来物の肴と酒に舌鼓を打つ。
「おれはもうとっくに気が狂ってるんだろうか?」
部屋の四隅から悲鳴が上がるときもあった。
しかし、慢性膵炎でインスリンが出ないのに、それでも朝酒はつづく。
糖尿病の栄養失調状態がつづき、どんどん痩せ始める。
暦に背を向け、政治に背を向け、あらゆる投票に参加せず、酒を呑み、なにか食べ、眠る。毎日。毎年。いつまで?
細い金主のおふくろも二年前の七月二十四日、芥川の河童忌、谷崎と、おれの五十四歳の誕生日の早朝に死んだ。
死因は胆嚢癌。黄疸が出て入院し、医者が言う通り一ヶ月で死んだ。
そのあいだおれは寝室に寝泊まりし、朝からずっと呑んだくれていた。
通夜の席で、弟二人に、「お前たちはテオになれ!」と暴言を吐き、取っ組み合いとなる。
葬儀を終え、七曲り荘へ帰ってから本格的に連続飲酒状態に突入する。
「おふくろが引っぱっているんだろう」と罰当たりなことを口にしながら。
たちまち身長一七四センチの体重が五十キロを割る。
歩みは老人のごとく、斜度五度ほどの坂に敏感となり、スーパーの帰りは、ストレッチャーで運んでもらいたいと切望する有様。
女もののシャツが似合うようになる。
ある日、無理やり友人に病院へ連れていかれたときには、四十一キロまで痩せていた。
「余命半年」と医者に脅かされ専門病院へ三週間入院。
痩せすぎて体温計が腋にはさめない。
退院翌日、海の見えるアル中病棟へ三ヶ月間叩き込まれる。
しかし一週間目あたりから全身を針で刺すような痛みと、悪寒をともなうしびれに襲われ、寝たきり状態となり、断酒プログラムに一切参加せぬまま退院する。
痛みもしびれも後遺症の神経症で、この先治るかどうかわからないと医者が笑顔で送ってくれた。
無論、七曲り荘に帰ってからも寝たきり状態はつづき、やがて紙おむつをはき、廃人同然となる。
「万事休す。進退窮まった」
言葉がゴミためのような六畳間に響くが、そんな悩みごとも部屋の隅にころがしたまま、雨戸を閉めきり引きこもりは春までつづく。
しかし世はその間に、全世界的に引きこもらざるをえないことになっていた。
おれの寝たきり姿を見かねた友人たちが、おれに内緒で役所に相談し、あれっというまに生活保護受給者となり、本物の「民衆のヒモ」となる。
「おれはもうとっくに気が狂ってるんだろうか?」
男ができることは何もできない。釘を真っ直ぐ打てたためしがない。
地図が読めない。運転がへた。とっくに免許は失効済み。精神病院が怖い。
虫が殺せず、草をむしれない。つるむことができない。
なにより子を生すことができない。
(二十六歳のエロ本編集者&男優時代、本番撮影で副睾丸炎となり不妊症となった)
しかし卑怯なものだけにはなりたくない。
だから裏でこそこそ動き回ることが得意である。
父母も妻子もなく、原稿依頼もなく、根気も謀反気もない五十五歳。
退院後これまで一滴も呑んじゃいないが、それは呑める体調じゃないからであって、この先復調すればわからない。
そりゃ四十年近く呑んできたのだから、止められるほうが不思議だ。
が、アル中病棟へおれを叩き込んだ友人との約束があった。
「この先、酒を取るか文学を取るか?」
その大仰な問いに、おれは殊勝にも「文学」と答えたもんだ。
今日もモルヒネ入り一種を含む四種の痛み止め&しびれ止めを四度飲み、やはり一日四度インスリンを打つ。
万年布団に寝たり起きたりを繰り返し、やましささえ感ずることなく、一日一日をやり過ごす。モルヒネにラリりながら。
「おれはもうとっくに気が狂ってるんだろうか?」
四十を過ぎてから、年に二度ほど天井を見つめながらつぶやいてきた。
そのたびに女の横顔を盗み見し、女に棄てられてからは友人たちの顔を思い浮かべる。
そして脅えた心を踏みつぶし、将棋好きのおれは、「これもまた一局の将棋だ」とうそぶくのだ。
別れた妻も去年再婚したそうだし、おれを棄てた女も、やはり去年、高齢出産で女子を産んだそうだから、彼女たちの、そのときそのときの決断は、間違っていなかったのである。
今月おれは五十六歳となる。体重は五十四キロまで増えた。
どうやらおれは、生き延びたようである。今しばらく。
これからもこの七曲り荘二〇二号室で、おれは生きてゆく。
大家さんが死ぬか、おれが先に死ぬか勝負だ。
おれはここ数年、死を考えるたび、どうせ首をくくるなら太陽で首を吊りたいと願ったものである。
そう、死ぬなら明るく景気よく生きていきたい。
それは考え方しだい、金のかからない生き方だ。
天井に書いた言葉が、バラバラと雨のように降りそそぐとき、あなたのことを考えて、優しい気分になる夜もあるのだから。
✴︎✴︎✴︎
曽根賢 ぴすけん/1964年、宮城県生まれ。1984年、大学入学ともに上京。以後、大学には通わずライブハウスなどでアルバイト。大学中退後、建設現場でアルバイト。1991年、平和出版に入社。雑誌の編集長となる。1995年、白夜書房/コアマガジンに持ち込み企画で雑誌『BURST』を刊行。当初はバイクをメインとした雑誌であったが、先鋭的なサブカルチャー(パンク、タトゥー、ドラッグ、ピアス、死体写真など)路線にコンテンツを拡大、その大胆で斬新なデザインも相まって若者から支持をあつめる。また『BURST』から『TATTOO BURST』『BURST HIGH』など複数の雑誌が派生し編集長をする。2000年、短編小説集『バーストデイズ』(河出書房新社)を上梓。野間文芸新人賞候補作となる。2005年、『BURST』休刊。コアマガジン退社後は小説の創作活動を行う。2006年、雑誌『群像』(講談社)に「桜の膳」を、雑誌『文藝』(河出書房新社)に「ウィトゲンシュタインの結界」を発表。その後も小説の執筆を続け現在に至る。
✴︎✴︎✴︎
〈MULTIVERSE〉
「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話
「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー
フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介
「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄
「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生
「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美
「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介
「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く
「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎