シリーズ『COVID-19〈と〉考える』 TALK 07|辻村伸雄 × 石倉敏明|パラドクシカルな「共生」の技法──歴史と神話の「あいだ」の実践
マルチスピーシーズ人類学研究会の「COVID-19を分野横断的に考える 」シリーズ第七弾。今にわかに語られ始めている新しい「共生」とは、一体なんなのか。その時の「共生」とは一体いかなる形のものであり、あるいは、それは本当に、私たちにとって「可能なこと」なのか。
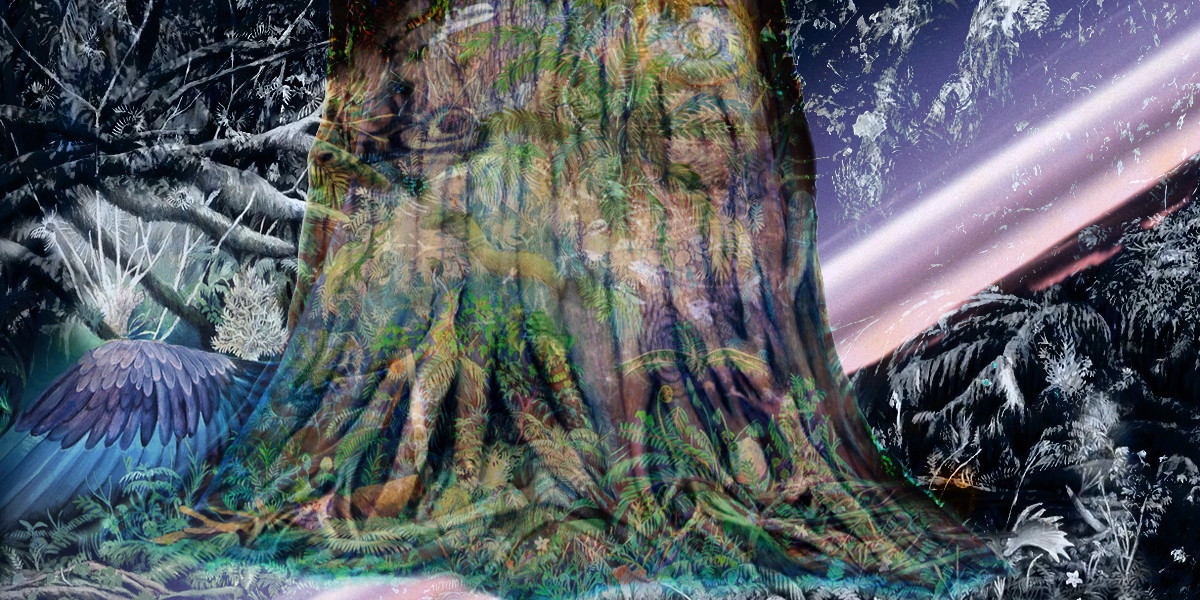
<< TALK 01|奥野克巳 × 近藤祉秋|ウイルスは人と動物の「あいだ」に生成する──マルチスピーシーズ人類学からの応答を読む
<<TALK 02|逆卷しとね × 尾崎日菜子|接触と隔離の「あいだ」を考える──コロナの時代の愛をめぐってを読む
<<TALK 03|吉村萬壱 × 上妻世海|都市を彷徨える狩猟民に〈知恵〉はあるのか──私と国の「あいだ」を/で問い直すを読む
<<TALK 04|清水高志 × 甲田烈|我々は対象世界を《御すること》はできない── 既知と未知の「あいだ」の政治を読む
<<TALK 05|松本卓也 × 東畑開人|ケアが「閉じる」時代の精神医療── 心と身体の「あいだ」を考えるを読む
<<TALK 06|山川冬樹 × 村山悟郎|隔離され、画像化された二つの顔、その「あいだ」で── ハンセン病絶対隔離政策とオンラインの顔貌から考えるを読む
この記事は、マルチスピーシーズ人類学研究会の「 COVID-19を分野横断的に考える 」シリーズの第七弾として5月29日に行われた、ビッグヒストリアンの辻村伸雄と、芸術人類学者・神話学者の石倉敏明によるビデオ対談(司会:辻陽介)の内容を、記録、再構成、加筆したものです。
今日、新型コロナウイルスという人獣共通感染症の世界的な流行に際し、あらためて人類とウイルスとの関係性が問い直されようとしています。その中で、これまでは主に多文化主義の文脈において考えられてきた「共生」という概念が、人間的な他者のみならず「他生」をも視野に入れた多自然主義的な概念として、人々の関心を集めつつあります。
自分たちの生命を脅やかすウイルスのような「他者」を前にしたとき、果たして、どのような「共生」の形がありえるのか。そのパラドクシカルな「共生」の技法をめぐって話し合いました。
Drawing by Maki Ohkojima
Text by Yosuke Tsuji
ウイルスと「共生せよ」というクリシェ
HZ みなさん、こんばんは。このシリーズの司会を務めさせていただいております辻陽介です。この研究会「COVID19を分野横断的に考える」は立教大学の奥野克巳さん、北海道大学の近藤祉秋さんらが主催するマルチスピーシーズ人類学研究会と、僕が編集しておりますウェブメディアHAGAZINEとの共催という形で行なっているもので、COVID-19のパンデミックと、それがもたらしている社会的影響、あるいはその時下における「生」のあり方について、分野横断的、多角的に考えてみようという対談シリーズになります。なお、今回は特別に桜美林大学ビッグヒストリー・ムーブメントにも共催頂いております。新型コロナウイルス感染拡大の状況といたしましては本日(5月29日)時点で感染者数は約580万人、死亡者数は約36万人です。
さて、第7回目となる今回はビッグヒストリアンの辻村伸雄さんと、芸術人類学者・神話学者の石倉敏明さんをお迎えしております。設けさせていただいたテーマは、「パラドクシカルな共生の技法――歴史と神話のあいだの実践」というものになります。
今日、COVID-19のパンデミックによって、あらためて人類とウイルスとの関係性が問い直されている、そういう局面に我々が置かれているということは、これまでの対談においても、幾度か語られてきました。そうした中で、これまでは多文化主義的に、つまり人類という限られた範囲の問題として考えられがちであった「共生」という概念が、生物、無生物を含む種としての他者、あるいは種間関係なども視野に入れた多自然主義的な概念として捉え直されようとしているように思います。
ただ、そうした言説というのは、実はすでに結構ありふれています。それこそ「我々はウイルスと共生しなければならない」というような話は、この3月以降、本対談シリーズをはじめ様々なところで語られていて、言ってしまえば一つのクリシェ(紋切り型)になっているようなところさえあるように思います。
そうとはいえ、ここでいうところの「共生」というものが、一体どういう実践なのか、具体的なイメージはいまだつきづらい。たとえば、新型コロナウイルスというのは現状において人間の身体に毒性があり、場合によっては死に至らしめることもあるというのは厳然たる事実であり、実際にすでに世界では36万人もの方が亡くなっているわけです。あるいは、新型コロナウイルスに限らず、ウイルスや細菌の中には、人間の生命維持にとって明らかに敵性を持っていると言える存在が数多くいるわけで、するとやはり「我々はウイルスや細菌とも平和的に共存できるのだ」と簡単に言い切ることはできないようにも思うんです。
であるならば、つまり、ウイルスとの「平和的な共存」が困難であるならば、今、捉え直されようとしている新しい形の「共生」とは一体どのような「共生」を指すものなのでしょうか。それは一体どういった視座のもとで、どういったレベルにおいてなら、成り立つものなのでしょうか。つまり、今問われなければならないのは、ウイルスと「共生」するかどうかの是非論ではなくて、「共生」という概念そのもののアップデートと、その具体的なイメージを提示することではないかと思うんです。そこが本日の対談における、まず一つの大きな問いとしてあります。
その点に関し、辻村さんは人類とウイルスを必ずしも別個の敵対するものとして捉えるべきではないという認識を踏まえつつ、平和的な「共生」ではない、対立的な「共生」の可能性を考えられていると聞いております。辻村さんはまた、地球が「ガイア」としての自己調節機能を持っているのだとすれば、人間もまたそのコントロールの対象であり、無軌道な拡張を続ける人間社会にとって、ウイルス圏はまさにブレーキとして機能しているのではないか、ということも言われており、今日はそういった視点からのお話をお聞かせいただけるのではないかと思っています。
一方の石倉さんは生命とも非生命ともつかぬウイルスの不確定性に向き合い、そうしたパラドックスを抱えた存在との「共生」を考える上では、ロゴス的な知性では不十分であると指摘されています。その上で石倉さんが問うているのは、生命と非生命の境界線を超え、さらには「人間的世界の終焉と再生」をも視野に入れた歴史と神話の対話の可能性です。石倉さんはまた、東アジア諸国の共存を唱える哲学者・小倉紀蔵の「共異体」概念を拡張し、人間と非人間の関係を更新する必要性についても語られていて、今日はその「共異体」という概念についてなどもお話して頂けるのではないかと思っております。
前置きが長くなりましたが、それでは対談にうつっていきたいと思います。まずは最初に、お二人それぞれに、今この状況に感じていること、この状況の中で考えていることについてをまとめて語っていただき、そこから対談に入っていけたらと思います。
ウイルスは我々を守り、脅かす──ウイルスとの平和的共存と敵対的共存
辻村伸雄(以下、辻村) よろしくお願いします。まずはじめに、皆さん、金曜の夜にお集まりいただきありがとうございます。一週間、お疲れ様でした。私はビッグヒストリーを研究している辻村伸雄と申します。
辻さんのご説明にもあったように、今日はマルチスピーシーズ人類学研究会とHAGAZINEと桜美林ビッグヒストリー・ムーブメントの三団体の共催ということになっております。桜美林大学では2016年に片山博文先生と宮脇亮介先生が日本で初めてのビッグヒストリーの講義を始められていまして、その時に桜美林ビッグヒストリー・ムーブメントが立ち上がり、私もその時から一緒に活動しています。マルチスピーシーズ人類学研究会との関わりというところでは、以前、奥野さんに桜美林大学のビッグヒストリー講座にゲスト講師として来ていただいたというご縁があります。その後、奥野さんがマルチスピーシーズ人類学研究会の方に私を呼んでくださったことなどもあって、石倉さんとはそこで出会いました。またHAGAZINEについては、昨年に「肉食のビッグヒストリー」(※)をめぐって、辻さんにインタビューをして頂いたご縁があります。というわけで、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
※HAGAZINE「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を喰らった──生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー」https://hagamag.com/uncategory/6222
さて、ここではまず、小さなものと大きなものについて、二つの角度から話してみたいと思っています。一つ目の小さなものと大きなもの、それはウイルスとガイアです。そして、二つ目の小さなものと大きなもの、それは言葉と世界です。ここで重要なポイントは、小さなものが大きなものを動かしうるということ、あるいは小さなものが大きなものの支えとなりうるということです。そうしたことについてお話しさせていただきます。
まず一つ目、ウイルスとガイアについてです。
今、新型コロナウイルス感染症が問題になっていますね。一般に感染症の原因となるのは、細菌、ウイルス、菌類、寄生虫だと言われています。ウイルス、それから細菌と寄生虫の中でも単細胞のものにはある特徴があります。それは私たちの目には見えないということです。
生命の歴史は約40億年になります。その中で、人間の目に見えるような生き物が現れたのは、ざっくり6億年くらい前です。つまり、それまでの34億年間、地球には目に見えない生き物しかいませんでした。目に見えない生物を微生物と言います。実は生命の歴史の8割以上が、この微生物の歴史なんです。
ところが、人間がこの微生物の存在を目で見れるようになったのはごく最近のことなんです。1665年、イギリスのロバート・フックという人が『ミクログラフィア』という世界初の微生物の図解を出します。これを可能にしたのは1590年に発明された光学顕微鏡です。フックは微生物を光学顕微鏡で見て描きました。しかし、この光学顕微鏡によっては、まだウイルスを見ることはできませんでした。ウイルスが見えるようになったのは1939年に電子顕微鏡が発明されてからです。つまり、人類の歴史700万年の中でほとんどすべてと言っていい期間、人類は虫より小さな生き物がいることを知らなかったし、また見ることもできなかったんです。
とはいえ地球で最も数の多い生物は微生物で、ウイルスはその微生物の10倍は存在しているだろうと言われています。ウイルスの住む領域、「ウイルス圏」(virosphere)は生物圏全体に広がっていて、1リットルの海水に100億くらい、ウイルスが含まれているんだそうです。ウイルスは一般に生物ではないとされていますが、もしウイルスを生物であるとみなすなら、ウイルスは生物圏全体の中で一番数の多いマジョリティでしょう。
こうしたウイルスについて考える時に、特に今はネガティブなことが中心になってしまいがちですが、実を言うとウイルスはいいこともしているんですね。たとえば海でプランクトンが大量発生して赤潮が発生してしまうことがあります。赤潮が発生すると、魚のエラにプランクトンが詰まって窒息死させてしまったり、海域の酸素濃度を低下させ生き物が住めない状態にしてしまうと言われています。そういう時、大量発生したプランクトンにウイルスが感染して、プランクトンを殺していくんです。それによって赤潮が解消される。さらに、このようにウイルスに破壊されたプランクトンの死骸は深海まで舞い降りていきます。これはマリンスノー、つまり「海の雪」と呼ばれている現象です。詩的ですね。それが深海の生態系を富ます餌になっている。
人間とウイルスとの関係性にしても同様です。一般的には人間とウイルスは対立的なものとして考えられがちですが、人間の体ひとつとっても、実はヒトの細胞というのは人体を構成している細胞のうちの1割だけなんです。あとの9割は微生物やウイルスでできている。たとえば腸内細菌は胃腸の働きを助けてくれてるものですよね。腸内にはウイルスもいて、ウイルスが増えすぎた腸内細菌を殺すことで、それらのバランスを整えてくれています。
さらに遺伝子を見てみると、人間にとってウイルスの存在がいかに大きいかがいっそう分かります。ゲノムの中で、ヒトの体のパーツを作ることに直接的に関係しているのは、たったの1.5%なんです。一方、人がウイルスに感染したことによってゲノムに組み込まれた部分――こうしたものをヒト内在性レトロウイルスというんですが――、これは9%もあると言われています。おおもとは3000万年前から4000万年前くらいに我々の祖先である霊長類の間で感染したウイルスだと言われていますが、ある時、ウイルスが精子か卵子に感染して、ゲノムに組み込まれ、子孫へと伝わっていったということのようです。
そうしたウイルス由来の遺伝子の機能の中には、我々の出産を助ける働きなどもあります。たとえば胎児は、母親だけではなく父親由来の遺伝子を持っていますよね。そうした父親由来の遺伝子は母親の体にとっては異物なんです。だから、母体のリンパ球は、自分を守るために胎児を攻撃し、排除しようとする。では、なぜその排除が起こらないのかというと、胎盤では母親の血管と胎児の血管がつながっていますよね。そこに母親の血管と胎児の血管を隔てる一枚の膜があるんです。その膜は母体から栄養だけを通してリンパ球を通さない仕組みになっていて、その膜があるからこそ、胎児は排除されずに母親の胎内で成長することができるんです。この膜をつくっているのがウイルスの遺伝子なんですね。ウイルスにはエンベロープという膜を持っているものがいるんですが、このエンベロープを作るための遺伝子が哺乳類の胎盤形成を可能にしたと言われています。だから、我々はある意味でウイルスに守られて生まれてきたとも言えるんです。
とはいえ一方で、今、新型コロナウイルスが僕たちの命を脅かしているという現状があります。ですからウイルスには、我々の命を守るものもあれば、我々の命を脅やかすものもある。人間とウイルスとの関係はこのように、今日のタイトルでもある「パラドクシカルな関係」なんです。つまり、矛盾を孕(はら)んでいるんです。
その上でウイルスとの「共存」「共生」をどのように考えるべきか、ということが言われているわけですが、僕は共存とは必ずしも「仲良く平和に一緒に過ごす」というものだけではないと思うんです。敵対的共存、対立的共存というものもある。それに、共存したい・したくないに関わらず、ウイルスとは共存していかなければならないんです。人間の視点から見れば感染症はできたら撲滅したいわけで、これまでもその撲滅が試みられてきたわけですけど、人間がこれまでに撲滅できた感染症は天然痘と牛疫の2つだけです。その他のものは撲滅したいけど撲滅できなかった。結果として今も共存しています。ですから敵対しても、撲滅できない限りはそうなるんです。だからと言って、僕は「共存を目指せ」という風には言いたくありません。そういう言説は経済活動再開の理由として利用されるだけです。なので、あくまでも“結果として”共存せざるを得ないだろうということを考えているんです。(※)
※以上の話を組み立てるにあたり、参考にしたのは主に次の文献である。山内一也『ウイルスの意味論』みすず書房、2018年/Dorothy H. Crawford(永田恭介監訳)『ウイルス』丸善出版、2014年/Nicholas P. Money(花田智訳)『微生物』丸善出版、2016年/アランナ・コリン(矢野真千子訳)『あなたの体は9割が細菌』河出書房新社、2016年。
ガイアと文明──地球史と生命史を統合するオリジン・ストーリー
辻村 さて、小さなもの、ウイルスについて話しましたので、次に大きなものに目を向けたいと思います。ガイアです。1960年代末、人間は初めて宇宙から地球という大きなものを見ました。その時にジェームズ・ラヴロックという人が「地球はひとつ」だと言いました。地球は、大気、海洋、土壌、生物圏を含んだ一つの複合体なんだ、と。そして、それは自己調節機能を持っている、つまり、生きてるんだ、と。これがラヴロックの「ガイア仮説」です。
そのガイア仮説に関連して、『オリジン・ストーリー』という本を紹介したいと思います。これはデイヴィッド・クリスチャンという歴史家の本で、彼はビッグヒストリーの提唱者でもあります。これはクリスチャンの集大成となる一冊であり、この本の第Ⅱ部では地球史と生命史が統合され、地球生命史として一体的に描かれています。そこで重要なのは地球史と生命史を結びつけるポイントです。その2つを結びつけるのは、「地球ではどうやって生命が存在できる温度が保たれてきたのか?」ということなんです。クリスチャンはこの問いに、「それは地球の気温が生命が存続可能な範囲に調節されてきたからだ」と答えます。これはガイア論的です。クリスチャンはガイア仮説を正しいと言っているわけではないんですが、『オリジン・ストーリー』でも前著『時間の地図帳』(未邦訳)でもガイア仮説を取り上げています。つまり、意識的であれ無意識的であれ、ガイア論の影響を受け、その図式に乗っかっているんです。
昨年クリスチャンが日本の高校生向けに『オリジン・ストーリー』の内容を、気候変動という点にしぼって、単純化して説明しました(https://youtu.be/eEkMC2XRzaQ)。これからお話しするのはその時の話を、ラヴロックの最新刊『ノヴァセン』の内容とも呼応させつつ、さらに単純化したものです。ですから今からお話しするのはものすごくおおざっぱな内容です。『オリジン・ストーリー』ではもっと詳しくちゃんと説明されていますので、その点を念頭においてお聞きください。
40億年前、地球の深海で生命が誕生しました。生命が存在するには液体の水が必要ですが、40億年前はまだ、太陽の明るさが今より3割ほど暗く、冷たかったんです。そのままでは水が火星のように凍りついてしまう。では、どうしてそうならずに、生命が誕生できたのか。地球による気温調節が行われたからです。大気中の温室効果ガスが毛布のように地球をくるみ、それが地球を暖めたからなんです。これは非生物による気温調節です。
その後、40億年かけて太陽は3割ほど明るくなっていきます。そのままでは太陽が熱くなるにつれ地球も熱くなっていく。ではなぜ、地球の海は金星のように蒸発しなかったのか。それは生物による気温調節が行われたからです。シアノバクテリアが30億年前に(酸素発生型の)光合成を始め、温室効果ガスの一つである二酸化炭素を取り込み、酸素を排出するようになりました。これにより、大気中に占める温室効果ガスの割合が減り、気温の上昇が抑えられたんです。
さらに3億年前には、樹木が初めて出現しました。地表を森林が覆うようになりました。森林は大量の二酸化炭素を吸収し、酸素を排出します。このことも地球の気温調節を助けています。そうして二酸化炭素を吸収し、分解されず地中に埋まった木々の死骸がやがて石炭になっていく。石油など他の化石燃料もまた動植物の死骸が変化したものです。
この数百年、人間は、そうして数億年かけて貯め込まれた二酸化炭素を、化石燃料を燃やすことで大気中に放出しています。それによって地球の気温調節を狂わせ始めている。今度は人間による気温調節が必要だ、というのがクリスチャンの考えです。ラヴロックもそういうことを言っています(もっともラヴロックの場合、最終的には人間とサイボーグが協力してこの惑星を冷やしていくということを考えているわけですが)。
ところが、現状を見ますと、二酸化炭素の排出を抑えて空気を浄化させているのは人間ではなくコロナじゃないか、と。人間は自分こそがガイアをコントロールするんだと思っていたけれど、その人間がガイアからのコントロールを受けているように“見える”。注意していただきたいのは、私は話の枕としてこういうことを言っているんであって、そういう因果関係がある、またそれを実証できるとは言っていないということです。
むしろ、ここで私が言いたいのは、現代の文明がどれだけ脆弱な基盤の上に立っているかということなんです。漫画『ONE PIECE』のキャラクターに「白ひげJr.」というキャラクターがいます。このキャラクターの造形がまさに現代文明の歪さを表しています。白ひげJr.は上半身ばかり巨大で、脚が棒切れのように細い。見るからにアンバランスです。これはまるで現代文明です。それは日本の姿でもあります。効率最優先でどんどん無駄を削ろうとしていった結果、余裕がなくなり、病床を削る、エッセンシャル・ワーカーを削る、保育士の給料は低いまま。そうして社会を支えるための脚が細くなってしまった。すると、今回のような厄災が起こると、すぐに揺さぶられてグラついてしまう。これはこれまで小さなものに目を向けてこなかったということでもあります。しかし、実は小さなものが大きなものを動かしている。実際、今日ではウイルスという小さなものに大きなものである人間の世界が揺さぶられているわけです。
〈言葉の真摯さ〉を「自分の言葉」で取り戻す
辻村 もう一つ、小さなものと大きなものの話をします。それは言葉と世界です。この点を今日はどうしても話したかった。石倉さんと“だから”語り合えると思ったんです。それは今、日本語から真実性が剥ぎとられていっているという問題です。
たとえばこの春、「自粛」ということが盛んに言われました。自粛とは自分からある言動を慎むことです。つまり、他人からお願いされたり、要請されたりした時点で、それは自粛ではないんですね。それなのに行政は「自粛を要請する」という破綻した言葉を使っています。それは要請する側の責任を見えなくしたいからです。「それは自粛でしょう、自分からそうしたんでしょう、だから補償はしませんよ」という風に言い逃れをする上で、都合の良い言葉として「自粛」という言葉が用いられているんです。
さらに、その言葉をマスコミがそのまま流している、追認してしまっている。これは非常に問題です。「自粛を要請するという言い方は日本語として成り立たないのではないか、卑怯ではないか」というふうに為政者に詰め寄らなかった。言葉の機関としての務めを果たしていない。言葉を使うことを仕事にしているその他の人たち――研究者や作家や詩人など――も「自粛なんて言葉は嘘じゃないか、実際は在宅要請、休業要請じゃないか」ということを積極的には言っていない。言葉の門番としての務めを果たしていない。
「自粛」という言葉に乗っかる人は、政府が責任をうやむやにするのに加担しているのと一緒です。だから「自粛」という言葉に現実が引きずられていく。これは恐ろしいことです。何万というふつうの人たちも「自粛」という言葉を口にしてしまっている。自分で自分の首をしめる言葉を。「自分からそうしたんでしょう」と言われてしまう言葉を。痛ましいですよ。
今大事なのは、政府の言葉、メディアの言葉、宣伝の言葉とは違う、「自分の言葉」をもつことだと思うんです。そのためには、それらが使っている言葉にそのまま乗らないこと、自分にとって〈真なるもの〉を自分の言葉で語ることが大事だと思います。
こないだ桜美林大のある学生が「人生って不要不急の集まりで出来ている」ということを言ったんですね。その通りです。不要不急というのは「社会軸」の発想で、社会から見た時に今すぐ必要でないとされるもののことです。でも、本当は自分にとって必要なものは人によってそれぞれ違う。自分にとって必要なものは「自分軸」なんです。自分を軸にしないとわからない。そして、人生とは自分にとって大切なもの、必要なものを味わうためにあると思うんです。
この春は僕も家にいる時間がいつもより長かったんですが、皆さんの多くもそうだったと思います。そういう時に自分にとって大切なものは何か、何が心地いいのか、自分は本当のところ、何がしたいのか。色々なものを一度止めて、自分の内面にぴたっと手を沿わせて感じ取る時間を持つ――野菜を切る。包丁の鋭さと交わる。野菜の皮の厚みと交わる。それを焼く、煮る。匂いと交わる。そこに自分にとっての手ざわり、リアリティがある。テレビでは放送されていない、他人の手垢に塗れていない真なるものが。そうした個にとっての真なるもの、交わりの尊厳、きらめき――それにぴったりくるような言葉を探し、語り出すことが大事なのではないでしょうか。それが、言葉に対する真摯さです(※)。そうしたものの担保なしには客観的な真は成り立ちえないんじゃないかと思います。
※辻村は今年、NHKに対して「国会の全審議のテレビ中継」
べレンズと石の交感
辻村 奥野さんたちが翻訳され、最近出版されたティム・インゴルドの『人類学とは何か』という本があります。この中にあるエピソードがあります。人類学者のハロウェルがカナダの先住民オジブワ族のもとを訪れた際のエピソードです。彼はオジブワ族とともに暮らしていく中で、あることに気がつきました。それは、オジブワ語では石がまるで生き物であるかのように主語になることがある、ということです。そこで彼はオジブワ族の酋長べレンズに尋ねました。「ここらへんの石はみんな生きてるのかい?」。しばらく考えこんだ末にべレンズが答えます。「そうじゃない!でも生きてる石もあるのじゃ」。べレンズの観察したところによれば、石はみずから動くこともあるし、人が話すように音を立てることがある。石は動く。石は話す。そうベレンズは言うんです。
ふつうなら「何を馬鹿なことを言ってるんだ。科学も知らない連中のたわごとではないか」。そう言われてしまうようなことかもしれません。でも人類学者はそう思わない。少なくともインゴルドはそう思わない。そこにきらめきを認めるんです。そこにある。何か光ってるものが。きらめいている。何かが、と。その上で、これはどういうことなんだろうと真剣に考えるわけです。そうか。考えてみれば、石は自分の重さに耐えかねて斜面を転がり落ちることがある。いや、石は水や氷や波によって運ばれることもある。石はたしかに動く。石は石同士を打ちつけ合ったり他のものに打ちつけたりすると音が鳴る。話すということが耳で感じとれるようにするってことなら、石だって話すことがあるじゃないか、と。
これが〈交感〉です。交わるからこそ観得できる世界の姿、実相がある。僕の言葉で言えば、それは詩的感性がとらえた世界の姿です。交感のきらめきです。世界を感じとる方法は科学だけではないということです。
僕には大好きな瞬間があるんです。それはリラックスしている僕の周りで、友人たちが僕のことを話しながら歓談し、笑い合っている瞬間です。赤ちゃんの時に皆さんもそういう時があったでしょう? 幸いにも、僕の人生にはそういう瞬間が今に至るまで幾度もありました。僕はそれを黙って聴いているのが好きなんです。そういうあたたかな声のさざなみを。
今、さざなみと言いました。それは海のさざなみととても似ているんです。声のさざめきと海のさざめき。人が話しているのと波が鳴っているのとどう違うのか。「何も違わない」――あなたが芸術家ならそう言ってくれるでしょう。少なくともそう言ってくれる人がいるでしょう。そのあなたに向けて今日は話しているんです、もちろん石倉さんにも向けて。これは僕にとっての交感です。真なるものです。
少なくとも、人類学者はべレンズの言葉にきらめきを認めます。これは話をでっちあげているのではない、真摯な言葉なのだと認めて真剣に受け止めようとする。実際、べレンズの言葉には真摯さがあります。彼は口ごもったんです。そのあと考えこんでようやく口を開いた。それは質問されたことに誠実に答えようとしたからです。
一方、「自粛」という言葉には真摯さがありません。そして、言葉に対する真摯さのない者が百万言を費やそうとも、コロナについて何をどう分析しようとも、そこに真なるものは立ち現れない。僕たちが今一度、言葉の真実性を取り戻すためには、世界と一人静かに交わり、それを真摯に言葉にする必要があるのではないでしょうか。べレンズのように。
前提としてそれがないといけないのだと思います。そこだけを見ると、あまりにささやかで無力に見える。けれど、それなしにはどんな巨きな現実も変わりえない基点のようなもの――これはそういうものだと思うんです。小さなウイルスがガイアという大きなものを支えているならば、私たちの小さな言葉が大きな真実を構成し、世界を支える基盤となりうるのではないか。小さなウイルスが大きな世界を揺るがすならば、私たちの小さな言葉にも大きな世界を揺るがす力が宿りうるのではないか。今、私はそのように思っています。まずは以上です。
ウイルスはオブジェクトなのか、サブジェクトなのか?
石倉敏明(以下、石倉) ありがとうございます。辻村さんとお話できるということで、デイヴィッド・クリスチャンの『オリジン・ストーリー』を読ませていただきました。とても面白かったです。21世紀に入ってから、特に「人新世」ということが言われるようになりだした頃から、いわゆるグローバルヒストリーの研究、つまり、地球という全体的な空間を踏まえて、これまでの人間の活動を俯瞰するような大きな物語というものが、いろんなヴァージョンで出てきていますね。地球的な規模で人類の営みを総覧したユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』や『ホモデウス』、人類学と歴史学を架橋するジャレド・ダイヤモンドの『銃・病原菌・鉄』以後の研究などもそうでしょう。巨視的な立場から、人間を中心とする「一つの地球世界」を説明しようとする歴史学が、求められるようになってきました。
なぜそうした問いが浮上しているのかというと、一つは人間がやってきたことがあまりに地球そのものへの影響力を持ってしまったということがあると思います。そして、もう一つとしてグローバリズムの問題があると思うんです。発達した交通網と情報網によって人間が世界中のどこにでも行けるようになり、また瞬時に連絡が取れるようになった。連絡革命です。その背景には新自由主義的な経済のネットワークが存在していて、文字通り地球を覆い尽くしている。たとえばアートの世界などでもグローバルアートということが近年盛んに言われてきましたし、あるいは医療や衛生に関してもグローバルヘルスということが言われるようになっていました。
その上で、この『オリジン・ストーリー』のユニークなところは、「起源」の考察を人間から始めていないところだと思うんです。この本は第Ⅰ部、第Ⅱ部、第Ⅲ部という形に分かれているんですが、第Ⅰ部では宇宙、つまり万物の起源についてビッグバンから始まる話が書かれています。次いで第Ⅱ部では地球、つまりこの星とこの星の生命の起源についての話が書かれている。そして、ようやく第Ⅲ部になって人間と人間性の起源の話が書かれ始めるんです。そこでは、ノンヒューマンの歴史とヒューマンの歴史を調停する大きな時間の流れが描き出されているわけですが、その姿勢は言ってみれば「人間以上の歴史」と呼べるようなものだと思います。この視点は、万物の起源を語る神話とも親和性が高い。僕の専門は神話なんですけど、言ってみればローカル版のオリジン・ストーリーを僕は日頃から聞いたり集めたり、比較研究したり、あるいは自分でもつくってみたりと、実験的に色々やってみたりしてきたわけです。そういう大小様々なオリジン・ストーリーの中で、いま一番大きなヴァージョンというのが、このデヴィッド・クリスチャンの『オリジン・ストーリー』という本なのかなと読んでいて感じました。
実はこの本の中にも、今日のテーマである「共生」がたくさん出てくるんですよね。リン・マーギュリスの細胞共生説やその元夫であるカール・セーガンの話、あるいはラヴロックのガイア仮説も登場していて、いろんなレベルにおける共生の話が出てきている。言ってみれば、人間というものが種として単独ではありえないということがこの本を読めばはっきりとわかると思うんです。
翻って今日、パンデミックということが非常に大きな問題になっているわけですよね。このパンデミックとはそもそも「パン(すべての)・デモス(人々)」であり、これは全ての人が等しく影響を受けるということを意味します。そのことを踏まえると、この本『オリジン・ストーリー』は直接ウイルスについてたくさん書かれているわけではないのですが、ウイルスと人間の関係を振り返る上でも、非常に示唆に富んだ一冊だなと感じます。というのは、人間の歴史に限定した時間軸でウイルスについてを語ってもやはり分からないことが多いんです。ウイルスについてを考える上では、生物との関係、あるいは宇宙、万物との関係の中で考えていかなければ分からないことが多く、そういう前人間的な歴史と照らし合わせていく必要があると思うからです。
ウイルスに関して、僕が気になっている点は、辻村さんも指摘されていた、その矛盾を孕んだ性質です。ウイルスというのは今のところ、生物学上の合意が完全にあるわけでないけど、一般的な意味で「生きている」ということはほぼ共有されている。つまり、なんらかのDNAの情報を持って、複製されていくという点では「生きている」と言える。しかし、それは自律的に増殖するわけではなく、ある有機体に乗り移るようにして、つまり他の生物の細胞をハイジャックすることによって、自らを増やしていくんです。これは生物の条件である「自己複製を行えること」を満たしていない。つまり、ウイルスは「生きているけれども生物ではない」という矛盾を孕んでいる。すると、ウイルスについて考えるためには、やはり生物の歴史だけを見ていっても分からない部分があるんです。
これは存在として、オブジェクト、つまりモノとしてのレベルと、サブジェクト、つまり主体性を持って情報を伝える存在という生命情報学的なレベルとの両方を見ていかなければいけないということです。言い換えれば、ウイルスとはオブジェクトとサブジェクトの境界にある。この曖昧さ、つまり「生きている」けれども、生物として定義可能な有機体ではないという矛盾している部分、あるいはその両義的な性質が、僕たちの不安やモヤモヤを作り出している。一方で、もっと大きな不確定性、これから人間と世界との関係をどれだけ続けられるんだろうかとか、地球温暖化の問題であるとか、人類がこのままの形で経済活動を続けられるんだろうかというような、非常に切迫した問題もある。
ラトゥールのアクターネットワーク理論を引くまでもなく、人間は地球全体に、オブジェクトとサブジェクトの諸次元をつなぐハイブリッドなネットワークを築き上げてきました。さらに、人間自身もまた、動物であると同時に動物圏から超越していて、人智圏、すなわち社会的なコミュニケーションの領域や、人間的な意味の世界というものを作っている。言い換えれば、人間は生物でありながら、同時に生物を超えたものとして地球上の生態系に干渉するハイブリッドな存在です。これは『オリジン・ストーリー』でいうと、第Ⅲ部で語られていることでもあります。そのように考えていくと、今般の危機の原因と目されているSARS-CoV-2というウイルスも、その被害を受けている人間も、ともに両義的で、不確定な存在であると言える。こういうハイブリッドな領域についてをどう捉えていけばいいのかということが今日、考えられるべきことなんじゃないかと思うんです。
人間は基本的に意味の世界で生きているので役に立つものと役に立たないものを分けたがるところがあり、その中でウイルスという存在についても「敵」というメタファーで語られることが多い。「ウイルスとの共生」という表現は、そうした見方に対するカウンターとして生じているものです、辻村さんが指摘していた通り、歴史的に考えたら天然痘と牛痘以外は人間は撲滅できていないわけですし、このシリーズの最初で近藤祉秋さんが言ってましたけど、永久凍土が融けてしまったら、そこから天然痘が復活するかもしれないという話もある。すると、本当に撲滅されているのかどうかも危うい。そういうレベルにおいても共生は理想というよりも事実としてある。じゃあ、人間の意味の世界と、生命や地球そのものが持ってる情報の世界とをどう繋いでいったらいいのか。そこが今の差し迫った課題なんだ思います。
さっき辻村さんが胎児の話をされてましたが、僕もたまたま先日、三木成夫の本(『人間生命の誕生』築地書館、1996年)を読んでいたところ、面白いことが書かれているのを見つけました。三木いわく、我々人間には草を雑草と薬草に分けたり、虫を害虫と益虫に分けたりする傾向がある。しかし、また一方で路傍の石ころ一つにも生命の躍動を感じたり、そこに現れる自然の心に共鳴するという別の側面がある。これは先ほどのインゴルドの話にも近いと思います。つまり、甚だ様子のことなった二面が多少に関わらず、どの人間にも識別されるのだ、と。これはウイルスとの共生を考える上でも、なかなか示唆的な捉え方だなと思うんです。
三木成夫によれば、前者は人間を思考の中心とする「自然征服」の態度ということになります。これを突き詰めていくと、資源開発や品種改良といった技術至上主義の文明が発展し、人物の背景として自然の景観をあしらうという近代の西洋絵画、つまり「油絵」の芸術世界が生まれるのだ、と。これに対して、後者、石ころ一つに命を感じるというようなありかた、これはつねに自然を中心とする態度であり、「人間をも含めた森羅万象のすべてが生命に満ち溢れ、宇宙の全体が大きな生活共同体としてとらえられる」(p.11)。ここでは「自然崇拝」が前景化し、宇宙生命との交流をあらわす方法として、風物の一点景として人間をあしらう墨絵のような芸術世界が生まれます。医療の方面にこの見方を広げれば、いわゆる西洋医学と東洋医学の差異ということになるかもしれません。しかし、ここで重要なことは必ずしも西洋の批判者として東洋を持ち出すことではありません。三木はここで、ルードヴィッヒ・クラーゲスの思想を引き合いに出しながら、自我精神の発生と、宇宙生命との心情による交流という「二つの柱」を抽出し、人体における頭と心、頭脳(体壁系)と心臓(内臓系)という二つのシステムの共存というビジョンを引き出します。つまり、「精神」のロジックと、「心情」のロジックを共存させていこう、とするわけです。
これを人類学の文脈に置き直すと、前者はフィリップ・
このようなナチュラリズムとアニミズムの対比は世界中に見られると思います。しかし、その点においても、ウイルスはかなりパラドクシカルな存在なんです。そもそも、ウイルスは内面性も外面性も判別がつかない。つまり、細胞膜がない。ウイルスという、その細胞に侵入する、タンパク質や脂質に包まれたRNA構造体の振る舞いを、どう捉えたらいいのか。ここを考えていく手がかりとして、アニミズムについてもう少し深く検討してみたいんですが、たとえばアニミズムの存在論についてデスコラは『自然と文化を越えて』の中でこのようなことを書いています。アニミズムとは「生命力・精力・繁殖力が、肉の捕獲・交換・消費によって、様々な有機体間を恒常的に駆け巡っているという」思想である。つまり、それは種の範疇を越えて食物連鎖の中で他の生物と関わり、捕獲し、交換し、食べることによって、その生命力がたえず肉体を超えて駆け巡っているとする生成論である。デスコラはそう言っているんですね(p.191)。
つまり、アニミズムとは常に動いているということを前提とした、運動や生成の論理なんです。それに対して、ナチュラリズムとは「あるか/ないか」を軸とした存在の論理なんです。これを踏まえてウイルスについて考えると、それはある種、ナチュラリズムの極限で現れた、それとは対照的なアニミズムの現実態のようなものとして理解し直すことができるのではないか、と思います。ウイルスとはまさに、身体の親密な接触や交感によって、様々な有機体間を駆け巡っている存在です。とりわけ、今回のパンデミックは、動き、生殖し、食べる存在であるという人間の動物的な側面によってウイルスが増幅され、移動やコミュニケーションに寄生するように拡張されていきました。都市という超有機体的な社会空間の中で増殖し、変異し、民族や文化、種を超えて生き続ける「前生物的」なもの。こうした媒体を、存在論的に捉えるのは非常に難しい。しかし、アニミズムの汎対象、汎生命力な思考法、つまり、魂が様々な有機体間を駆け巡っているという見方において生成論的に考えれば、ウイルスというハイブリッドな生成体をもっとリアルなものとして、適切に捉えることができるのではないか。こうした理解を進めていくためには、おそらく民族誌学において議論されてきた呪術的感染の論理や、「あるか/ないか」を軸とした存在の論理に代わる「成り変わる運動」として、生成論的に感染症の実態を吟味する必要がある。おそらくは今後、こうしたことが考えられていくべきポイントなのかなと考えています。
混沌に向き合う「ブリコラージュ」の知恵
石倉 もうひとつお話ししたいことは、先ほど辻村さんがした言葉の問題と関わる話です。我々は今、ウイルスを前にして戸惑っているわけですよね。ストップしてしまっている。約十年前になりますが、アーティストの高嶺格さんが「Big Stop」、日本語では「大きな休息」とか「大きな停止」という表現で、現代社会を支えているコミュニケーションの構造を宙吊りにする作品を発表していました。今日の我々もまさに、全てを宙吊りにせざるをえないような、大きな足止めを食らっている。そうした混乱した状況下における政治ということを考えた時に、テレビをひねったりラジオをつけたりすると、桜を見る会をめぐる首相答弁として「私は幅広く募っているという認識で、募集はしていない」みたいな言葉が平気で流れてくる。さらには、政府が言葉の社会的な用法にズカズカと介入して、「『そもそも』は『基本的』という意味」「戦ってはいたが戦闘行為ではなかった」「『反社会的勢力』は定義困難」といった日本語学者が頭を抱えるような答弁や閣議決定を連発するようになってきています。意味の世界に住んでいる人間としては、これは非常に困ってしまう。都合よく意味を操作しようとする言説の政治がそこにはあって、一般の国民は政治家が発する曖昧な言葉に注意を払うことを妨げられたまま、現実の追認を求められてしまう。言葉と現実の関係が、非常に不確定的なんです。言ってみれば、僕らは今、生きているんだけど生物ではないウイルスと、募っているんだけど募集していないと言い放つ政府の間で、不確定性の渦に溺れかけているように感じます。

高嶺格[大きな休息]明日のためのガーデニング1095㎡|パンフレット(2008/せんだいメディアテーク)
こうした状況を正気で生き続けるのは、とても難しいことなんですよね。インフォデミックみたいな言い方もありますけど、実際、僕らは確かに無数の情報によって右往左往しています。たとえばWHOにしても、マスクは感染防止対策に効果はないと言ってみたり、やっぱり効果はあるので着用を推奨すると言ってみたり。手指の消毒液として市販されている次亜塩素酸水の有効性も、諸説入り乱れています。つまり国際機関も専門家会議も、その都度、防疫的な判断基準を更新しながら、この未知のウイルスに対応していて、我々もまたその都度情報をアップデートして、不確定性と向き合わなければいけない。ウイルスがその微小さゆえに目に見えないというオブジェクトレベルからもたらされる混乱だけではなく、それをめぐって飛び交っている情報のレベルにおいても我々は混乱してしまっている。実はウイルスとは、剥き出しの生命情報を含む核酸(RNAまたはDNA)をタンパク質の薄い殻で包んだ情報体です。たとえば新型コロナウイルスの場合は、RNAの生命情報が薄い脂質と突起のある殻にエンベロープされていて、人間が動いて他者と接触してそのウイルスを拡散することによって、世界的な混乱が作り出されている。すると、我々は生命情報という物質記号論的なレベルと、人間の行動や言葉を操作するポストトゥルース的な混乱のレベルの間で、行き場を失っていると言えると思うんです。
このような不安を混乱を制御するために、もちろん医療従事者や科学者が奮闘していますが、そこにはPCRのような非人間のアクターも不可欠です。たとえば「PCR検査の範囲を拡張したほうがいいのか、限定すべきか」みたいな話が今ありますよね。検査値によってウイルス感染の有無が明らかになる。3.11の後にも似たような状況がありました。放射性物質のレベル、これも目に見えないものでしたが、それをガイガーカウンターで測って、計測値をめぐって大きな政治的な判断が下されるという、不慣れな状況があった。このガイガーカウンターはガイガー・ミュラーが1928年に発明したガイガーミュラー計数管を基にしていて、それによって目には見えない放射線物質が可視化されたわけです。
一方、PCRが発明されたのは1983年です。科学技術史を辿れば、ガリレオから始まりロバート・フックを経て電子顕微鏡へと至る可視化の歴史があるわけですが、PCRという方法はウイルスを映像化するのではなく、核酸に含まれる情報の一部を増幅するような形で数値化するものです。いずれにしても、今の私たちはこうしたガイガーカウンターやPCRを通じて、肉眼では見えない「大きな結果を生み出す微小なもの」を計測し、それによって安心したり不安になったりしている。ではこうした技術的媒介がなかったら、我々はどうなっていたんだろうかということも想像してしまいます。つまり、ここまで情報と生命の話、オブジェクトレベルとサブジェクトレベルにおける混乱についての話をしましたけど、そのあいだには人間が作り出した道具や機械の歴史が欠かせないものとしてある。ブリュノ・ラトゥールは、こうした技術的媒介が実現されることによって、モノや生命の次元にある情報が、社会的なレベルにある言語へと翻訳され、「柔らかい主張を、固い事実にする」プロセスを論じています(『科学が作られているとき 人類学的考察』産業図書、1999年)。僕たちも今、生命情報のレベルに生起している不確定性に対処するために、いろんな形でそれを可視化したり、制御できるネットワークの中に囲い込もうとしているわけです。
なかなか困難を伴うプロセスですが、人類学者は呪術師の呪いから科学者の実験室に至るまで、混沌や混乱に立ち向かう様々な技術の生成に立ち会ってきました。現在の混乱を乗り越えるために、PCR法の開発について振り返って見るのも良いと思います。人類学者のポール・ラビノウによる科学民族誌『PCRの誕生』を読むと、PCR法を発明したキャリー・マリスが何を成し遂げたのかがよくわかります。マリスは昨年(2019年)亡くなってしまいましたが、自伝やインタビューなどもたくさん出ています。この人はとても不思議な人で、たとえばエイズ否認主義者だったりするんです。つまり、HIVという媒体は、ウイルスの要件を満たしていないという主張をしていたりする。フロンガスによる地球温暖化否定論者でもありました。もちろん、免疫に関するベンチャー企業を率いる開発者でもあったので、かなり新自由主義的なところもあったり、矛盾を孕んだ人物です。
ラビノウはクリフォード・ギアツの門下で人類学を学び、モロッコで調査を行いつつ、ミッシェル・フーコーの系譜学に影響を受けた人物ですが、マリスを中心とするかなりユニークなネットワークの中でなぜPCRが開発できたのかを丹念に追っています。この本を読むと、マリスが投資家の世界や医療技術の世界、研究所や科学者のコミュニティーの中を行き来しながら、ユニークな開発を成し遂げたことがわかります。彼はある時、交際相手のジェニファーさんを助手席に乗せてホンダのシビックで走っている時、運転席でふと数式が頭に浮かび、車を止めてPCRの元になる化学式を書いたそうです。その数式から、彼はPCR(ポメラーゼ連鎖反応)という概念を発明しました。さらに彼は、概念を実験系に変え、実験系を技術に変え、さらにその技術を再び概念にするという連関を作り出しました。その成果によって、彼は1993年にノーベル化学賞を受賞することになります。様々な偶発性を呼び込み、いくつものレベルの異なる不確定性を乗り越えて現実を動かしていくマリスの開発技術を、ラビノウは人類学者レヴィ=ストロースの『野生の思考』から借用して「ブリコラージュ(日曜大工)」の技術と形容しています。つまり、ラビノウによれば、マリスは現代の科学技術の世界に一種の知的な「ブリコラージュ」の作法を持ち込み、大きなイノベーションを起こしたということになります。
人類学者レヴィ=ストロースは、英仏両軍間の連絡将校としてフランス・ドイツ国境の戦地に派遣されていた時、ある日曜日に一茎のタンポポの球体を見つめて、我を忘れたそうです。彼は、一見あり合わせの記号のつぎはぎに見える神話の構造が、タンポポの花の構造のように、進化の精妙な調和を生み出していることを発見します。つまり、人間の精神が生み出すものと、人間が関与しない進化の歴史の中で生み出されたものの間に、見事な同型性が認められるというわけです。この発想は、レヴィ=ストロースにとって決定的な啓示となったようです。よく知られているように、レヴィ=ストロースは『野生の思考』の中で、神話の構造は「ブリコラージュ(日曜大工)」によって作り出されているということを明らかにしました。その見解はもちろんその後の神話学や人類学に大きなインパクトをもたらしますが、それは一見混沌としているように見える記号の渦の中に、「構造」という奇跡的な秩序を発見する方法を彼が見出そうとしたからではないでしょうか。興味深いことに、実は遺伝子レベルの進化の歴史に同じような飛躍があったことを、生物学者のフランソワ・ジャコブが雄弁に指摘しています。ジャコブによれば、生物の進化はある設計図に則ってそれを展開するといった目的論的なプロセスではなく、レヴィ=ストロースが『野生の思考』のなかで説いている日曜大工(ブリコルール)のように、有限の要素を繰り返し用いている。つまり、生物は決して無から有を生み出すのではなく、すでにあるものを組み合わせて進化に飛躍をもたらすということです。
人類学者の中沢新一は、近著の『レンマ学』のなかでこのことを踏まえて、次のように述べています。
「現代生物学が明らかにしているように、「進化は不器用な日曜大工(ブリコルール)であり、手持ちの遺伝子を繰り返し再利用しているだけである」(フランソワ・ジャコブ)ために、ニューロンとシナプスからなる神経組織の中でおこなわれる情報処理の仕組みと、脳を用いて人類のおこなっている思考には、ほとんど同一の様式が反復して用いられている。そのために、タンポポの花の構造と神話のような撹乱されない状態の人類の思考との間にはある種の並行性が発見できるのではないか、という人類学者の直感には、深いレンマ学的根拠が見出されることになる。」(p.121)
ここで「レンマ学的根拠」という表現で言い表されているのは、自然界に存在する要素を操作し、支配し、資源化する根拠にもなっている人間の「正気」、すなわちロゴスとは別の知的作用のことです。中沢はここで、生物進化の構造と人間の思考の構造をつなぐレンマ学的な「並行性」に、混沌とした不確定性の海を渡っていくヒントを求めようとしています。「レンマ的知性」とも呼ばれるこの働きは、物事を分別し、時系列的に整理することによって理解可能な意味のネットワークを作り出す「ロゴス的知性」と共に働きながら、その働きを包摂しつつ、分別を超えて問題の全体性を把握する直観的な洞察の方法として、仏教をはじめとするユーラシアの知恵の伝統において探求が進められてきました。
仏教は人間の精神においても、自然界の秩序においても等しく「ダルマ(法)」という精妙な関係性の論理が働いていることを説いてきましたが、その働きは決して到達不可能な神秘として放置されるのではなく、むしろ時空間の中で構造化され、さまざまなレベルで同時発生的に起こっている「レンマ的知性」として理論化されています。近代ヨーロッパではずっと後になってから、フロイトやユングをはじめとする精神分析学者の探求によって心の無意識的構造を説明する論理が生み出されていきますが、仏教の伝統においては混沌の中で人間が生きていく方法や、煩悩の中で知恵を現実化する方法として、とても古くから実践的な叡智が形成されていきます。こうした点を踏まえて、『レンマ学』では手持ちの要素を繰り返し再利用しつつ、不確定な混沌に飲み込まれそうな現実を渡っていく「野生の思考」の根拠が再発見されている、と言えるのではないでしょうか。
フランソワ・ジャコブが進化について述べている知見や、美しいタンポポの構造を前にしたレヴィ=ストロースの神話的瞑想は、マリスがシビックの運転席で急いで書きつけた数式とは、一見何の関係もないように思えるかもしれません。しかし、マリスの発明したPCR法は、微小なウイルスを検知する方法として実際に多くの社会で活用され、膨大な人間の生命を救うことに役立っているはずです。実は我々は、生命情報のレベルから、道具や機械のレベル、さらには神話的ないしビッグヒストリー的な宇宙や生命の起源の説明に至るまで、非常に様々な不確定性に向き合いながら今まで生きてきている。今日の状況というのは、それが先鋭化して、目の前に突きつけられているということなんじゃないかと思います。我々の正気の範囲を凌駕してしまうような、あまりにも自然的で微小な存在、そしてあまりに人間的で尊大な政治の前で、狂気や混沌ではなく知恵を選択するためには何を考えなければならないのか。あるいは、どのようなブリコラージュの知恵を稼働させるべきなのか。どのような形で言葉を発して行けば良いのか。そうしたことを、世界的な「大きな停止 Big Stop」の時期に考えてみることが必要だと考えています。
「ロゴス的共生」から「レンマ的共生」へ
石倉 さて、ここからが今日の本題でもあるわけですが、今までお話ししたようなことを踏まえて、あらためて「共生」について考えてみたいと思います。共生とは文字通り「共に生きる」ということですから、辻村さんがおっしゃったように言葉を大事にするとしたら、実際に「共に生きる」ことを意味しているはずです。しかし、僕たちは、強力なウイルスのような、自分自身を死に至らしめるものと、本当に「共に生きられる」のだろうか。たとえば、各国の政府は、これまで好んで「ウイルスを撲滅しよう」「ウイルスと闘おう」と主張してきました。フランスのマクロン大統領は「ウイルスとの戦争」という表現を使っています。こうした論理は明らかに、新型コロナ・ウイルスには永遠の死を、人間には生をもたらそうという単純なロジックに基づいています。別の言い方をすれば、ウイルスを撲滅することで、人間の側に勝利をもたらし、これまで通りの都市生活や経済活動と、グローバルな移動のパターンを取り戻そう、という主張になっていくわけです。しかし、問題はcovid-19だけではなくて、今後現れるであろう感染症との関係を含んでいます。ワクチンの開発などでウイルスの制圧が可能なように見えても、実際には変異し続ける新たなウイルスとのいたちごっこを続けなければならない。このことを、今どう考えればよいか。
たとえばある生物が他種を自らの環世界の構成要素として生きていくような「共利共生」の関係は、通常のロゴス的な意味での共生に近いと思います。文字通り、互いを互いの生存に役立てることのできる他者として認識しているわけですから。この場合の他者関係は文字通りの「共生」と言って良いでしょう。ここではこの関係を「ロゴス的共生」と呼んでおきましょう。人間とイヌ、あるいは牛・豚・鶏のような家畜との関係は、動物たちがどう感じているかは不問のまま、人間中心主義の論理によって、少なくとも道義的には「共生種」として地球上に存在していることになっています。ところが、まさにこうした「ロゴス的共生」の領域を拡張し、人間中心主義の論理を拡大することによって、人間は都市圏を拡張し、定住生活の中で密集した生活領域を確保してきました。なぜなら、人間が密集し、相互に簡単にコミュニケーションを取ることができるということは、人間同士が互いに利益を増幅させたり、人間的な価値観を増殖させるためには都合が良いからです。ところが、今回のcovid-19は、まさにグローバルな規模で進行する人間中心的なコミュニケーションのあり方や、そのための他種との共生関係を土台にして爆発的に感染を拡大させてきてしまったわけです。そのように考えてみると、現在のパンデミックは、人間にとって速やかにコミュニケーションを行うことのできる快適な生息空間を、郊外や野生の領域に広げて行くことによって引き起こされた、「ロゴス的共生」の亀裂のような事態だということがわかります。
今、人類が直面しているのは、上記のような限定的な共生の条件がもはや通用しないような、地球規模の変化ということではないでしょうか。これは一つの試金石のような事態であって、今後繰り返し似たような感染症の流行が発生するかもしれない。僕たちがロゴス中心的な論理によって「ウイルスと共生しよう」と言った場合、それは人間を例外的な種として隔離したまま、他の存在をコントロールできる、という単なる「綺麗な言葉」で終わってしまう可能性を常にはらんでいます。つまり、あくまでも共生がメタファーとしての意味しか持たず、実質的には、せいぜい感染拡大に注意して、社会的活動を自粛しながら生きるという受動的な態度のみを表すことにとどまってしまうのではないか。そうではなく、もしより深い場所から共生という概念を掘り返そうとしてたときに、中沢新一の『レンマ学』を踏まえた「レンマ的共生」というもう一つの道筋を検討する必要があるのではないか、と僕は考えています。
たとえば、辻村さんが先ほど出された赤潮の例などを、真剣に考える必要が生まれてくると思うんです。赤潮が起こった時にウイルスがプランクトンに感染し、それらを殺すことで海洋の豊かな生態系が保全されるということを考えるなら、パンデミックによる人間の大量死なども、もしかすると異なる種の共生を可能にする歴史的出来事として考えなければならなくなるかもしれない。ただし、僕は地球環境の保全のために人類の大量死を容認すべきと言いたいのではありません。そうではなくて、人間側に都合よく編集されたロゴスからは「敵」とされてしまうウイルスのような存在と、僕たちはこれからいかに距離を取っていけば良いのか、ということを考えてみたいのです。そのためには、「共生」という概念を再定義する必要が出てくるのではないでしょうか。
互いに役立つ存在同士がある空間に集住することは、複数種の関係においては決して珍しくありません。しかし、何を持って共益的とみなすかは、実はなかなか定義が難しいことですよね。たとえば生物の数を尺度として考えるならば、地球上に夥しいほど存在している人間と、その共生種として存在させられている経済動物、すなわち「生きた道具」としてのさまざまな家畜は、人間を中心とした社会圏の中で見事に繁栄を遂げた成功例とみなすことができます。ところが、同じ人類でも、少数の億万長者に対して数億もの貧困層が存在しているように、家畜たちがおかれている集約的な食肉工場を中心とする牧畜の環境は、それぞれの動物たちの福祉にとっては必ずしも望ましいものではありません。それどころか、人間は自らの正気に従いながら、たくさんの動物に苦痛を与えたり、生態系の豊かさを作り出す深林の植物を伐採したり、土や海や河川を都合よく変形することで自分たちの生きやすい状況を作り出してきました。人間の活動が地球規模の影響を与えることによって、現代の地球は白亜紀の小惑星の衝突に匹敵する「第六の大量絶滅期」を迎えている、と考える科学者のグループも存在します。
では、やはり、人類と他種の共生は不可能なのだろうか。「ロゴス的共生」は限界に達しつつあり、これ以上一方のロゴスを他者に押し付けるのは難しいでしょう。しかし、ロゴスとは異なる論理であればどうでしょうか。「レンマ的共生」とは、ロゴスでは捉えきれない別種の論理による、パラドクシカルな共生のことです。アリストテレス以来のヨーロッパの論理学では捉えきれない、矛盾を孕んだ全体性の把握。それが東洋においてはレンマという論理によって捉えられてきた。先ほど紹介した中沢新一さんの『レンマ学』では、これを「対称性論理」と「非対称性論理」のバイロジック(複論理)構造なのだとも述べられています。我々は常にロゴスの世界で生きていると同時に、レンマの世界でも生きているのだ、と。つまり、先ほどお話した不確定性、人間が動物であると同時に動物ではないロゴス的存在でもあるとか、ウイルスは生きているけど生命ではないとか、人間とウイルスは共生せざるをえないけど共生しえないとか、こういうパラドクシカルな論理のレベルが現実に、刻々と目の前に生成しているわけですよね。これを「ロゴス的共生」を超える「レンマ的共生」の課題として捉えた時に、我々が今後向き合わざるを得ない、あるいは積極的に向き合っていくべき多元主義の方向性が見えてくるはずです。その時にもう一度、世界の複雑性に向き合う言葉の真摯さというものを取り戻したり、あるいは我々の生存のきらめきというものを取り戻すことができるんではないかと思うんです。ひとまずはここで、僕の話を終えたいと思います。
〈目に見えないもの〉にどう迫っていくか
辻村 今、石倉さんが不確定性ということを何度もおっしゃいました。見えないもの、分からないもの、あるいはロゴスで見ると矛盾してしまっている両立できないもの、そうしたものとどう向き合っていくのか。そういう不確定性のさまざまなレイヤーに挟まれて今私たちは困ってしまっていると、そういう話だったと思います。
まず分からないということに関して言うと、実はずっとそういう状況が続いていると思うんですね。ある意味、分からない、見えないのが当たり前というのが人類の歴史だとも言えると思うんです。ビッグヒストリーも神話も、どういう宇宙観、世界観を持つかということのヴァリエーション(様々あるもののうちの一つ)だと思うんですが、たとえば古代ギリシャの哲学や天文学、あるいはその後に発達していった神学などもそうですよね。
たとえば哲学は形而上学とも言いますけど、それは形を超えたものについての学、すなわち目に見える現象の奥にある、目には見えない原理を扱う学として始まったものです。見えないものを、見えないのだけど、見ようとする。それが形而上学です。
あるいは天文学というのは、宇宙そのものが音楽であり、一つのハーモニー(調和)であるという考えから始まっています。その音楽は普通にしていては聴こえないんだけど、それをどうにか聴こうとする。そのための学だった。天体の位置や運行にはどういう法則があるのか、どういう調和があるのか、それを観察することによって知ろうとしたんです。
その後に現れた神学もそうですね。これもさっきのレンマと同じで、矛盾したものについて考える学でした。神はどうしてこのような世界を作ったのか、どうしてこのようなことをされるのか。人間は神になれないから神の考えていることを理解するのは不可能なんだけど、とはいえ、少しでも、わずかでも、そこに近づこうとしていた。いわば思考しえないものを思考する学です。
このように、基本的には不可能なんだけれども、そこに迫りたいという衝動は、人間の中にずっとあったように思います。そして、その中で様々な形で、見えない、分からないものに対する向き合い方というのを作ってきたんだと思うんです。
石倉 そうですね。目に見えないもの、分からないものをどうイメージしていくのか、あるいは物語化していくのかという歴史が我々にはあって、同時にレヴィ=ストロースが「野生の思考」と呼んだような、現存する情報や記号を操作しながら、ブリコラージュ、つまりつぎはぎしながら世界像を作ってきたという歴史があるわけです。実はヨーロッパの知的伝統では、形而上学は、必ず形而下学とセットになっている。一つのフィジックス(形而下学)と複数のメタフィジックス(形而上学)があるということ、言い換えれば、たった一つの「目に見える地球」に対して、複数の「目に見えない世界」があるということ。こうした見方を人類学者のフィリップ・デスコラはナチュラリズムと呼んでいるんですが、僕たちはいまその限界の外にある別の存在論をどう扱って行けば良いか、という問題にも立ち会っていると思います。
つまり、目に見えないものがすなわちメタフィジックスであると考えてしまうと、目に見える世界全てが単一の自然ということになってしまう。こうした見方に対し、実は最近ではコンパラティブ・メタフィジックス(比較形而上学)という考え方が現れてきていて、形而下と形而上の関係性には、たくさんのヴァリエーションがあり得ると指摘されています。形而下の現実と形而上の世界は、実は知的なブリコラージュによって組み換え可能である。そのように見ることで、目に見えるものと目に見えないものの境界は、西洋以外のさまざまな存在論の様態と関連づけられていくわけですね。すると、天文学者が考えた宇宙のハーモニーはより多声的な作曲法になっていくし、ノイズを孕んだ音律も現れてきます。歴史と神話の関係についても同じようなことが言えるのではないか、と思います。
一方で、今回のパンデミックは、世界の多元性というよりは単一性の現実に直面している「同期化」が発生しています。今日では、世界全体が同じウイルスに直面している。つまり、「たった一つの世界」に我々は向き合わざるを得なくなっている。しかしながら、ウイルスは目に見えないものであって、接触感染や飛沫感染によって増殖し続ける多様体であり、変異体でもある。世界全体の人間たちが、同じように感染症のリスクを抱える「たった一つの世界」に暮らしていること。そして、それぞれの社会ごとにその受け止め方や対処法に違いはあるとしても、少なくとも同じようにこの厄介な「目に見えないもの」のリスクに直面しているというのが、現状です。
この対談シリーズでも、早くから「ワンヘルス」という概念が登場してきました。この場合の「ワン」とは、人間と異種の生命を連続した一つのものとして捉え直し、いわば人間以上の健康を再定義しなければいけないということで、現在のWHOの活動にも取り入れられている考え方です。人獣共通感染症を考える上で決定的に重要な概念であり、種を超えたウイルス感染の現実に焦点を据えた学際的でマルチスピーシーズ的な視点でもあります。
同時にこれは地球全体で、人間の健康維持のために異種とのさまざまな関係性を包摂しなければいけない、という強い考え方でもあります。つまり、実はこの「ワンヘルス」という考え方の中にも、人類を頂点とする人間中心主義が潜んでいるんじゃないかという議論があるんです。その前提にあるのは西洋由来のグローブ(地球)であり、単一の自然であり、あるいはその「自然を超える」という考え方ではないか。「一つの地球」には、人間を中心とした存在の序列を生み出してしまう可能性もあるのではないか。では、僕たちが一つのオリジン・ストーリーとして共有してしまっている、あるいは共有を迫られている大きな物語に対して、そこから排除されてしまう多くの歴史をどのように理解していけば良いのか。「ワン」という観点からこぼれてしまう世界の可能性について。その点について、辻村さんに聞いてみたいと思っていました。
ビッグヒストリーは神話や神学のようなものも含めて、
たとえばクリスチャンの『オリジン・ストーリー』
辻村 おっしゃっていただいたように、ビッグヒストリーというのは万物の起源の物語(オリジン・ストーリー)であって、それも一部の地域とか文化だけでなくて、あらゆる人々が共有できるものを作ろうじゃないかと、そういう視点から試みられているものです。その意味では、ナチュラリズム(単一の自然を前提としている)じゃないかと言われればそうかもしれません。
ただ、デイヴィッド・クリスチャンが言っているのは、いろいろなスケールの地図があるんだということなんです。その意味において、ビッグヒストリー、138億年史というのは、中でも一番スケールの大きな地図であるというだけです。たとえばある街に行った時にはある街の地図が、地下鉄に乗る時には地下鉄の地図が必要なように、目的と行動に応じて、必要な地図というのは変わってくる。それはビッグヒストリアンも否定しません。ビッグヒストリーを作ったからといって、それよりスケールの小さな地図を排除するとか、それらよりもビッグヒストリーの方が優れているとか、そういうことを言いたいわけではないというのがまず一つあります。
もう一つは、ビッグヒストリーといっても、デイヴィッド・クリスチャンだけじゃなくていろいろな人が書いているんですよね。そうすると、ビッグバンを始原として共有しつつも、細かいところでいうと、どういうところに着目するかとか、何をその一つの流れとしてみるかというのが著者ごとに違ってくるんです。それはいくら自然科学的なファクトとか歴史学的なファクトに基づいたとしても、その中で何が一番重要と思うか、何を選びとるか、そしてそれらを結びつけてどういうストーリーに編み上げるかというのは、書く人の人間観や生命観、また自然観や宇宙観の影響を受けるんです。ですから、自然とそのストーリーは違うものになってくる。そのように、ビッグヒストリーという枠の中でいろんな形のストーリーというのが描かれればいいと思ってますし、結局、そのうちのどれが残っていくかといえば、多くの人が支持したものが残っていくんだと思うんです。
石倉 歴史という現実への理解が、実は多くの人の支持に委ねられているという点、面白いですよね。どういうヴァージョンが適しているか、どんな地図が必要になってくるか、対立する視点からの批評を乗り越えて、ストーリーがブラッシュアップされていく。まさにいま、生成しつつある歴史だと思います。今まで自然史と文化史は分断されて来たし、博物館の展示も別々だった。しかし、イデオロギーによる統制ではなく、諸科学の成果をブリコラージュすることによって、統合される可能性も出て来ているのかもしれません。
実は神話学の中でも、地球規模の研究成果を統合するような「世界神話学」が生まれています。マイケル・ヴィツェルという人が、世界中の神話を包括的に研究する学を作っているんです。あるいは人類学の中でデスコラがやっていることも、あらゆる地域の民族誌を動員して人類学を再構築しているという意味では「ビッグエスノグラフィー」と言えるかもしれません。このように総体的に人間存在の位置付けを考えていく。そして、スケールの異なる地図や海図を駆使して、不確定性の海を航海する。そういう時代になってきているんだと思います。
先ほど辻村さんが指摘されたように、これからも目に見えないものは目に見えない次元にあり続けるでしょうし、他の生物種の存在も、謎を残すことになるでしょう。そこにどうやって迫っていくかは、我々がそれぞれ引き受けて、解消されない不確定性とともに抱え続けていかなければならない。こうした謎については、おそらく「解消されない」というところが重要で、だからこそ、たとえば、それを比喩によって表現したり、直観的な知性によって把握していかなければならないんだと思います。そこにアートや詩、音楽の価値というものがあるのかもしれません。
人類学におけるパースペクティヴィズムも、それこそ大掛かりな比喩であるわけですよね。人類学者のヴィヴェイロス・デ・カストロがあげている有名な例だと、アメリカ大陸の先住民のコスモロジーでは、人間にとってのマニオク酒がジャガーにとっては血である。人間にとっての蛆虫は、ハゲワシにとっては美味しそうな焼き魚である。こういう他種の視点の交錯関係による世界像を、僕たちはパースペクティヴィズムと呼んでいます。この考え方は、人間以外の種に「他者」の資格を与え、それぞれの身体から捉えられる世界の在り方を理解しようという、人間中心主義に対する根本的な批判を伴っています。
ヴィヴェイロス・デ・カストロの研究は人間性の理解にとって深い洞察を含んでいるのですが、彼自身はそれを、アメリカ大陸の先住民研究の文脈に限定しています。しかし、そこで話を止めてしまうのではなくて、我々自身にとってのパースペクティヴィズムを考えていくことも必要ではないでしょうか。
最近、僕はパースペクティヴィズムのような思想を通して、一種のウイルス関係学のような思考実験ができるのではないか、と空想することがあります。少なくとも現時点において、我々にとってはウイルスというのは気持ち悪いものだったり、怖いものだったりするわけですよね。でもウイルスにとってみたら、人間とはどんな存在なんだろうか。もしもウイルスにパースペクティヴや、それを可能にする身体があるとすれば、彼らにとって人間は格好の「共生種」と言えるんじゃないでしょうか。なんせ人間がいることによって爆発的に増殖することができる。都市を築き、密集して暮らし、頻繁に移動し、さらに社会的なコミュニケーションによって頻繁に身体接触してくれる。こんなにありがたい存在はない、と。
そう考えると、もしかしたらウイルスにとっての人間は、人間にとってのグローブ(地球)そのものなのかなという気もするんです。ミシェル・セールが指摘したように、我々はある意味では地球空間に寄生しているパラジット(寄生者/奇食者)なわけで、するとこの視点を拡張して、地球から見たら人間とはもしかすると疎ましい存在であり、あるいは悩みの種かもしれない、と想像することができます。地球にとっての人間は、もしかすると大規模に自分を改変し、壊滅的に破壊してしまうようなウイルス的存在なのかもしれない。それが人間にとってはウイルスであり、ウイルスから見たら我々の作り出した人間圏が、地球環境に相当するのではないか。そのように敢えて乱暴な空想実験を実行してみると、「共生」に向かっていくらか異なった視点が開けるのではないかと感じています。
ワールドとワールドの境界を超えて──保苅実の実践
辻村 パースペクティヴィズムというのは、違う肉体を持っていたら違う視点があるという考え方ですよね。別の生き物の肉体からは、また別の世界のありようが見えてくるんだ、と。そういう異なるパースペクティヴ(視点)の間を行き来する。奥野さんによれば、パースペクティヴィズムとは「異種間のパースペクティヴの交換/交感」のことであり、それは生き物たちが、自分が捕まえる獲物の視点、あるいは自分を食べようとする捕食者の視点に立って行動し、生き延びてきたことにその原点があります(※)。
(※)奥野克巳「生ある未来に向け、パースペクティヴを往還せよ」野田研一、赤坂憲雄編『文学の環境を探る』玉川大学出版部、2020年。
そういうことでいうと、ビッグヒストリーはもちろん人間史を超えたスケールから歴史を見ていこうとする、脱人間中心主義の志向をもっている。だからそこには人間以外の視点というものが存在する。『オリジン・ストーリー』には、世界を認識し、周囲の情報を集め、分析することはあらゆる生物にとって必要なことであり、現代の科学も、元をたどれば単細胞生物に始まるそうした営為に起源する、と書かれています。
また今日出た話で言えば、産業革命は数億年にわたる化石燃料の形成・蓄積によって準備されたものであり、人間がそれを燃やすことで何十億年にもわたって作られてきた気温調節の仕組みを狂わせ始めているということは、たかだか数十万年の人間史のスケールでは決して理解することができません。それは地球生命史のスケールに立って初めて見えてくる。
けれども、現状のビッグヒストリーは、最終的には、昨年の鼎談(※)の最後で僕が述べたように、まだ人間から見た物語になってしまっていると思います。
※HAGAZINE「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄」https://hagamag.com/uncategory/6850
だから、僕はもっとラディカル(急進的/根本的)な方向、たとえば石から見たビッグヒストリーとはどういうものなのか、花から見たビッグヒストリーとはどういうものなのか、それは文字で表現しうるのか、文字じゃなかったらどうやって表現するのか、というようなことにも興味があったりする。だからこそ、マルチスピーシーズ(複数生物種の)人類学に関心があるんです。
その上で、ウイルスから見た人間とはどういう存在なのかを考えるのは面白いですね。ただ、石倉さんはウイルスにとっての人間は最良の伴侶種じゃないかとおっしゃいましたけど、地球の歴史から考えると、今後、太陽がもっとどんどん熱くなっていくことは分かっているわけです。最終的には海も蒸発してしまって、地球は太陽に飲み込まれるんじゃないかと言われている。その過程において、宇宙にでも脱出しない限り、人間のような目に見える大きな生き物は最初に滅んでいくんです。そして、最後まで生き残っていくであろうものは細菌のような微小な生き物です。ウイルスはそういう微小な生物にも寄生して生き延びますから、やっぱり人類より、ウイルスの方が長生きするんですね。だからウイルスにとっては「昔、人間ってやつがいたな。ああいう家に住んでたなあ。懐かしいな」みたいな、そういう感じになるんじゃないかと想像します。
もうひとつ、人間もウイルスみたいなものじゃないかという話がありましたね。確かに人間が地球に寄生しているんだと思えばそう見えます。自然環境を破壊して好き勝手にやっているわけですから。ただ、そのように人間をヒール(悪役)のように考えることと、人間が地球温暖化を救う、生物圏を救うんだみたいに、ヒーローのように考えることとは、同じコインの裏表だろうとも思うんです。
それに環境破壊ということを言えば、最初の話で光合成ということが出てきましたが、この光合成によって酸素を作るということが始まった時、当時の生き物にとってはその酸素が猛毒だったわけですよね。実際、「酸素ホロコースト」(酸素による大量殺戮)と呼ばれる大量絶滅が起こっている。地球上の大気が猛毒の酸素に汚染された。これは地球史上最大の大気汚染じゃないかとも言われています。
その点、人間はほとんどの生き物が生きられないような大気汚染とか、ほとんどの生き物を殺してしまうくらいのことはまだ起こしていないんですね。それこそ視点をどこに置くかで、環境破壊そのものの見方も変わってきます。実際、酸素ホロコーストにおいては、環境が破壊されることによって新たなバランス(大気組成の変化や新たな気温調節の仕組み)が生まれたんです。私たちが生きているのは、そのおかげでもある。だから考えていくべきは、変わっていく環境の中で、どういう関係を他の存在と結んでいくかだと思うんです。
石倉 石から見たビッグヒストリー、花から見たビッグヒストリーというのはとても魅力的ですね。そういう巨視的な視点からみると人間の道徳的基準も相対化されていくでしょうし、より広いところから個人や社会の責任を確立することにもつながるはずです。たとえば、地球にとって現在の人類の営みがウイルスのようなものだとして、それを悪いものだと決めつけなくてもいいと僕は思うんです。実際、数百万年かけて進化してきた人類の歴史の大部分は、決して地球的な破壊力を持った20世紀以後の人間の活動と同一視できないし、地球全体を救おうとか、世界規模の破壊力を持とうという発想も倒錯しています。地球に対する負担について考えても同じです。
とはいえ、じゃあどういうところで人間が地球温暖化やガイアへの非常に大きな影響を作り出してきたのかというと、その背景には一つの世界という前提があったということ、これは否定できないんじゃないでしょうか。これについてジョン・ローというアクターネットワークセオリー研究で有名な人類学者が、2011年に「What’s wrong with a one-world world?」(https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1600910X.2015.1020066?journalCode=rdis20)という論文を書いていて、そこでローは一つの世界ということをOne-world-reality、つまり「一世界リアリティ」と呼んでいて、そこに「一世界形而上学」が生まれるのだという言い方をしているんです。これに対して彼はMultiple-world-reality、つまり「多元的世界リアリティ」というものを対置している。これが今のポストプルーラルと言われている人類学の議論につながっていきます。
たとえばオーストラリアのアボリジニの人たちが土地を開発されようとした時に、それは人間がフリーハンドで開発していいものじゃないと言って抵抗しています。土地が人々に所属しているんじゃなくて、人々が土地に所属しているんだ、我々は継続的なドリーミングで生きているんだ、と。ここでは先住民の神話やコスモロジーが先鋭的に取り出されていて、地下資源の採掘のような企業の活動に対して、先住民側から、敢えて「ここは私たちの世界なんだ」という言い方がなされているわけです。こういった例は特に先住民の居住地における世界認識の亀裂として立ち現れていて、世界中でコスモロジーの政治、あるいはイザベル・ステンゲルスのいう「コスモスの政治(Cosmopolitics)」を生み出しています。そういうことを踏まえると、現在生み出されているいくつものグローバルヒストリーの世界認識に対して、こうした多元的なリアリティをどういう風に考え、「一世界」と「多元的世界」の関係を調停して行くのか、さらに「決して一枚岩ではない人類」というものをどうやって理解していくのかということが大事になってくると思うんです。
これを歴史学との境界で考えていたのが、保苅実という人だと思います。保苅さんは2004年に夭折された歴史学者で、彼が亡くなった後に『ラディカル・オーラル・ヒストリー』という本が出版されています(2018年に文庫化。『ラディカル・オーラル・ヒストリー オーストラリア先住民アボリジニの歴史実践』岩波現代文庫)。その本で保苅さんがやろうとしたことは、オーストラリアの先住民が世界の始まりについて語ったオリジン・ストーリーを真剣に受け止めるということでした。それまでは歴史学者が神話として退け、神話学者が神話として研究してきたものを、話者が主張しているように一つの歴史的現実として、コミュニケーションのギャップを超えて受け止めようとした。彼らの歴史は我々の歴史とは違う。ただ、そのように同じ歴史を共有できない相手との間にどう新しい歴史を生成させていくのかということを保苅さんは考えていたんです。彼はそれを「Doing History(歴史する)」と表現していました。僕はこの『ラディカル・オーラル・ヒストリー』は優れて先駆的な存在論的人類学の著作だと思っています。
それこそ辻村さんが言われた「言葉の真摯さ」というレベルでも保苅さんはいろんな実践をしていましたね。その一つの辿り着いた形式として、非常にポリフォニック(多声的)な文体で書かれています。彼はアボリジニのジミー爺さんというおじいさんの語りを非常に生き生きと書いてるんですけど、その語りを元にラディカルな歴史相対主義を掘り下げていきました。彼は歴史学と人類学の境界を超え、同時に地方化された歴史と「一つの世界」の境界を超える方法を模索していた、と言えるかもしれません。マルチ・スピーシーズ人類学との接点では、デボラ・バード・ローズの『生命の大地 ーーアボリジニ文化とエコロジー』(平凡社、2003年)を翻訳しています。人間と非人間、生命と非生命の境界を超えた現実に目を向けた歴史学として、保刈さんの研究はポストコロナの時代に我々がもう一度真剣に受け止め直す必要があると思います。辻村さんは保苅さんについてどのように考えてますか?
辻村 そうですね。まず、今のお話で思い出したことから言うと、2017年にニュージーランドの先住民マオリがワンガヌイ川に法的人格があることをニュージーランド政府に対して認めさせたというニュースがありましたね(https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/20/022700131/)。そういうニュースを見た時に、それこそまさに先ほど石倉さんがおっしゃったように世界はひとつながりのシート(布)じゃないということ、多元的なものである、いろいろな世界が入り組んだ襞(ひだ)のようにして存在しているんだ、ということを思わされるんです。ナチュラリズム的な見方からすると、そこに川という物質があり、そこにはさらに川の生態系があるといったように考えられて終わってしまう。ところがマオリの見方では、川は生きているわけです。だからニュージーランド政府も川の地勢的要素と形而上的要素を一つのものとして法人格を認めた。つまり、ワンガヌイ川は物的要素と心的要素が一体不可分となった生きた存在であるということです。こういう〈物心一体〉の小世界が自然の中にいくつも存在している――しかも、心的世界をもっているのは人間だけではないから、それこそいろいろな生き物たちによっていろいろな小世界が同時・多重・異形のかたちで存立している――ということは、ナチュラリズム的な見方からは見えてこないものです。
そういう座標軸自体が異なっているような世界のあり方がありうるんだ。自分たちの見方だけで世界を塗りつぶすことはできないんだ。そのことに気づくためには、自分にとっては当然の物の見方や前提というのものをいったん脇において、自分には知覚できていなかった世界を知覚している人の話に耳を澄ませてみようという態度が必要だと思うんです。これは近年の人類学で「他者を真剣に受け止めること」(taking others seriously)と言われていることですね。
保苅さんはそれを実践した先駆者だったと思うんです。オーストラリアのアボリジニのもとに赴き、歴史学者ながら人類学者ばりのフィールドワークをやっている。そこで保苅さんが試みたのは、たとえばアボリジニのジミーじいさんを歴史家だと見なして、彼が語ることを文字通り真実として受け止めてみたら、そこからどんな歴史が姿を現すだろうということでした。ところが彼によれば、彼らの歴史を知るためにはまず大地の声を聴かねばならない。これはもちろん、通常のアカデミックな歴史学のルールや研究の仕方からは外れています。しかし、保苅さんがやったのは、そういう自明な歴史のあり方からはみ出してしまっているものにどう向き合うのかという実践であって、これは僕がビッグヒストリーに足りないと思っているものにも通じているんです。
僕はかねてよりビッグヒストリーには「三多」、すなわち三つの「多」が必要だと言ってるんです。一つ目は「多文化」です。現状、ビッグヒストリーと名のつく研究や教育を実践している人たちは西洋の人が多いんですね。ですから自然のなりゆきとして、そこでは西洋の文脈や文化的蓄積が暗黙のうちに前提されている。ビッグヒストリーの始祖をアレクサンダー・フォン・フンボルトに求めるのもその表れと言えるでしょう。ところが、人類学者の岩田慶治は、西にフンボルトがあるならば東には三浦梅園ありと書いているんですね。しかも梅園のコスモロジーを体系化した『玄語』(1775年)は、フンボルトの『コスモス』(1845–1862年)が出版される前に書かれている。ここから、もしかすると梅園は日本におけるビッグヒストリーの創始者と言えるような人物なのかもしれないと関心を抱き始めました。もちろん、同じような人は、世界各地にいくらでも見つかるでしょう。そこから、別様のビッグヒストリーを構想することができるのではないかということを考えています。
二つ目は「多自然」です。これは今日話に出たパースペクティヴィズムもそうですが、異なる生物の視点を通して見えてくる世界の実相というものに目を向けようということです。そうすることによって、石倉さんが言われたような、単一でない多元的な世界が目の前に開けてくる。人間を含めて、あらゆる生物の世界認識はヴァーチャル・リアリティです。どの生物も認識能力に限界があり、そうした制約をふりはらって世界そのものを直接認識できる者はいない。しかし、それぞれに観得している世界の姿、実相はある。であるならば、そうした不完全でヴァーチャルな世界像を重ね合わせていく、突き合わせていくことでしか、世界の姿をもっと鮮やかに見ることはできないんじゃないかと思っています。
三つ目は「多形態」です。石倉さんはよくご存知かと思いますが、神話はただ単に文字で書き綴られるものではありません。神話は、歌われるものであり、踊られるものであり、描かれるものでもありました。そういう様々な表現形態で存在してきた。だからこそ、人々の生活に溶けこんでいたし、人々の世界観の基底たりえた。ビッグヒストリーというのは、そうした神話を現代においてもう一度創ってみようという試みです。であるならば、新しい神話であるビッグヒストリーも単にそれを本にして活字にすればいいということではないんじゃないか。むしろそれは、あらゆる表現形態で噴出するものだと思うんです。それにはどういうものがありうるのか。その可能性を探るために、桜美林大学のビッグヒストリー講座では、毎年一人必ず、アーティストやクリエイターの方をお招きしています。(※)
※これまで招聘したクリエイター、アーティストは、初音ミク開発者の佐々木渉、アニメ監督の河森正治、現代アーティストの小松美羽、AKI INOMATAの諸氏(敬称略)である。この他に、各分野の第一線の研究者にもお越しいただいている。
Doing Big History
HZ 残り時間が少なくなってきました。ここで一つ質問をさせてください。石倉さんの問いかけから始まった、グローバルヒストリーとローカルヒストリーをどう調停していくのかということをめぐる一連の流れ、非常に興味深く聞かせていただきました。それはつまり、ロゴス的な知性とレンマ的な知性をどう調停していくのかという問いにも結びついていくことのように感じます。対話の中で保苅実さんの話も上がりましたね。保苅さんのいう「地方化された歴史」をどう受け止めるのか、という問いは今日、非常に重要だと感じます。たとえば思い出したのは人類学者の石井美保さんの議論です(※)。石井さんは、こうした複数の歴史や世界にギャップを超えて向き合う上で「かもしれない」という態度が可能ではないかということを書かれていました。それはある種、中庸的な表現ですが、僕はその「かもしれない」による折り重なりには希望を感じています。特にこうした状況下では安易に「普遍性」が立ち上げられてしまいやすく、そこに対する危惧はこの対談シリーズでもこれまで幾度か語られてきています。そうした「普遍性」が覆い隠してきた「地方化された歴史」に目を向けていくことは、まさに喫緊の課題なのだろうと感じています。
※石井美保「現実と異世界:『かもしれない』領域のフィールドワーク」松村圭一郎、中川理、石井美保編『文化人類学の思考法』世界思想社、2019年。
ただ、一方でポストトゥルースの問題というのが、その時、一つの大きな躓き石になってしまうのではないかという思いもあるんです。普遍的ではない歴史と向き合うといった時に、たとえばリヴィジョニズム(修正主義)などにはどう向き合うべきなのか。ファクトを超えて政治化された歴史にどう対処するのか。それすらも「かもしれない」という形で真剣に受け止めるべきなのか。結局、そうした決していい意味とは言えない歴史的実践が次々に立ち上がってしまうと、やっぱり普遍的な歴史が大事だよね、グローバルな統合が大事だよね、One-Worldでいこうよ、という話になってしまいかねない気がします。ここの難しさについて、お二人がどう考えてるかを聞いてみたいんです。
石倉 ポストトゥルースという問題について考えるなら、神話はある意味では最初から「ポストトゥルース的」な語りの形式を含んでいます。つまり、数多くのヴァリエーションが存在していたり、互いに矛盾したストーリーが並存していたりします。ですから、正しいか正しくないかは本当に「かもしれない」としか言えないんです。しかし、それにもかかわらず、なぜレヴィ=ストロースが研究したような、人間を宇宙や自然の中に位置付ける見事な洞察や共存の哲学が、神話として語り継がれてきたのでしょうか。それは、人間が都合よく改変できるようなご都合主義とはもっとも遠い、非人間を尊重する態度を、世界中の神話が育んできたからだと思います。星々や季節の起原、洪水の後に生き残った先祖の話、火と料理の発明、疫病や戦争の記憶といった神話の要素は、ある集団の「無意識」から生み出されます。つまり、意識的な修正をほどこされた国家神話、あるいは権力者の歴史とは違って、ある集団が世界の中で勝ち取ってきた生存の根拠、そして哲学や倫理学が、神話の語りの中には断片的に含まれているのです。
もちろん、世界中の伝説を見てゆくと、歴史修正主義的な物語もたくさん存在しています。権力者が自分に都合の良い形でヒストリーを書き換えてしまうことも少なくありません。真実性を支える基準も、権力によって簡単に操作されてしまいます。しかし、あるイデオロギーや政治的な目的のために歴史を改変しようとする物語は、石井さんが指摘された「かもしれない」という柔らかな相対性を否定して、現実を頑なに固定しようとします。つまり、他の「かもしれない」を抑圧してガチガチに歴史を固めてしまうところに、むしろ「歴史操作主義」と言ったほうが良いような拙劣さが現れています。
神話の多くは、歴史的な現実を記録しようとするロゴスを相対化し、人間にとって決してコントロールできないカタストロフィーを物語に包摂します。ですから、神話的な現実とはある種の循環や反復の中で、何度も始まりと終わりを繰り返すわけです。このような神話の語りは、実は人間の歴史と、大地や天候の歴史、あるいは諸生物の歴史のギャップの中で生まれてくるものです。たとえばレヴィ=ストロースの方法論を、東アジアの感染症パンデミックの研究に応用しようとした人類学者のフレデリック・ケックは、そうしたギャップに立ち会うことで、歴史と神話の境界を見極めようとしています。ケックは、狂牛病以後の人間と動物の関係を踏まえた上で、まさにウイルスや細菌感染症の運び手となる鶏・豚・牛などといった動物と人間の種の境界を超えて、「パンデミック神話」という新しい神話のヴァリエーションが刻々と生み出されている、という興味深い指摘をしています。
この対談シリーズの第一回目(※)で、奥野克巳さんが非常に明快に、ケックが立脚している研究方法に対して「人間中心主義である」という批判を投げかけていました。その上で、人間以外の諸生物の生態や共生関係を踏まえたマルチ・スピーシーズ人類学の潮流や、人獣共通感染症を踏まえた「ワンヘルス」の人類学的動向が現れてきているというお話をされていましたね。確かに、人間社会の言説や医療体制の差異に着目したケックの研究は、人間の営みを超えてさまざまな生物種の相互関係をつぶさに調べてきた「マルチ・スピーシーズ民族誌」とは、一線を画しています。ただ、僕が思うのはポストトゥルース的な情報の氾濫や現代の人間性について、一貫して真摯に探求してきたのはむしろケックの方法なんじゃないか、ということなんです。
※TALK 01|奥野克巳 × 近藤祉秋|ウイルスは人と動物の「あいだ」に生成する──マルチスピーシーズ人類学からの応答
というのも彼はウイルスを一つの変異体として、つまり常にヴァリエーションを生み出すアクターと見定めた上で、それをグローバルに監視するWHOのような組織体であるとか、あるいは各地域の政府研究機関が、その地域ごとにどう新しい変異のあり方に対応してきたのかを観察し、記述してきたわけです。そして、それはレヴィ=ストロースが『神話論理』の研究でやったことの発展形でもある。つまり、レヴィ=ストロースがアメリカ大陸全体の民族誌を通して行った神話研究を、彼は現代のグローバル化した世界で変異していくウイルスと人の関係の中に見つけようとしているんですね。彼はパンデミックという現実は必ずしも疫学的な問題に還元できるとは言えなくて、そこにはむしろ神話的な無意識の構造が現れるんだということを書いています。ケックの代表作である『流感世界』には、副題として「パンデミックは神話か?」と書かれているんですが、ここが非常に重要なポイントないんじゃないかと僕は考えています。
つまり人間と微生物の世界の間に生じている「グローバル臨床」というフレームの中で、日常生活において発生するある種の集団的恐怖に対して我々がいかに影響されてきたのか、それに対してどのように動員力のある物語を生み出してきたのか、そういうことがケックの関心の焦点なんです。ケックは鳥インフルエンザを世界規模の「全体的な社会的事実」として扱おうとしていますが、これは明らかにマルセル・モース的なフランスの伝統に則った態度で、ある意味では文学的とも言えるような修辞を使うことも厭いません。ケックは『流感世界』の最終章で、プリシラ・ヴァルドの先行研究を踏まえて実は物語というものもまたcontagious、伝染的なものであるということを述べています。これはまさに神話的な認識なんですよね。
実は演劇やアートも同じです。感染する物語、あるいは感染する身体というものを、どういう風に生み出していくのかというアーティストたちの関心が、大きなテーマとしてある。たとえば土方巽の暗黒舞踏とか、アントナン・アルトーの残酷演劇などにおいては、明瞭に「感染」という言葉が使われていたり、ペストやウイルスの比喩が使われていたりします。衛生観念を持った現代人がもっとも気をつけければいけない「感染を避ける」という常識を、彼らはアニミズム的に侵犯していくことでナチュラリズムに染まった世界に激震を走らせました。これは近代社会にとって、最大の禁忌の侵犯です。彼らは身体をもって別の身体に何かを感染させていくことが、芸術実践にとってもっとも重要なことだということを言っているわけです。
なぜ疫学と神話が、公衆衛生と芸術が問題系として繋がるのか。それはまさに「全体的な社会的事実」という多様体の中で感染症という現実が響き合っているからです。ちなみにフレデリック・ケックはフランスの国立科学研究センター(CNRS)に所属しつつ、ケ・ブランリ美術館の研究部門で働いています。同時に、彼もまたWHOなどと連携しながら、「ワンヘルス」との関係で世界的な疾病管理がどのように構築されてきたのか、というプロジェクトにも関わっているようです。ケックによれば、現在の国際社会が、グローバルな感染症研究の領域で自然界の貯蔵庫にある様々な遺伝子の変異を研究するように、グローバルアートの領域では文化的な遺産をどうやって変容させ、新たな作品を生み出していくのか、そういう変異体をめぐるゲームになっている、ということを指摘しています。現代のミュージアムが、まさに無菌状態の管理空間としてウイルスや細菌を駆除しながら、実際には文化的な領域で変異し、増殖する新たな価値の体系を相手にしている、というわけです。
つまり、アートの世界はもともとポストトゥルース的なんです。ピカソがかつて述べたように「芸術とは真実を伝える嘘である」といえばわかりやすいかもしれません。最初から明白な嘘であり、操作された虚構の現実なんだ、という前提がある。ただ、その虚構を通してしか伝えられない真実があって、それは事実への執着を批評的に捉える。つまりアートとはジャーナリズムとは違って、事実をできる限り虚飾なく、生のまま伝えるという情報伝播ゲームではない。むしろ、ウイルスがどんどん変異していく様子を世界的にウォッチするという、「ワンヘルス」のようなWHO的スローガンを反転した場所に、現代アートの場所が用意されている。すなわち、グローバルアートにおいては、医療体制が世界規模の自然界の変異に目を光らせていることとちょうど逆転した形で、個人や集団が担っている新たな文化的な変異体の独創性が競われている。敢えて皮相的な見方をすれば、美術界という村にはそもそも新しいもの好きな連中が集まっていて、どこそこのビエンナーレや芸術祭で、誰が、どういう新しい作品をつくって展示した、ということばかりが話題になっているというわけです(笑)。ケックからすれば、それは新型ウイルスの監視という、グローバルな医療監視のシステムの裏返しのように見える、というわけですね。ちなみに現代の医療が「ワンヘルス」を扱っているように、現代の芸術も、人間とさまざまな非人間の共同作業によって作られる「作品」に、新たな関心を注ごうとしています。
そう考えると、医療界と芸術界がやっていることは、グローバル化した世界で新たな変異体を扱う技術として、対照的な位置を占めることになります。こういったケックの考え方について、必ずしもそれを人間中心主義とは言えないのではないか、というのが僕の個人的な考えです。ケックが一貫して主張しているのは、いわば「One-World」とそれぞれの地域の歴史というものを調停する中に、我々の情報の世界があるということ。つまり、日本列島の住人は日本社会の中で新しい感染症神話を生み出しているし、それは香港・台湾・シンガポール・韓国の神話とも、ヨーロッパやアメリカ合衆国の神話とも異なっている。それは、必ずしも多文化主義的な「一つの自然」に対する態度の違いではありません。一つの社会から別の社会に移動するときに意味を反転させたり、変容させたりしながら現れてくる「構造」の次元にこそ、人間と非人間の間に穿たれたギャップを乗り越えていくさまざまな技術や物語が現れる、というポスト・レヴィ=ストロース的な考えになってくると思います。もっと細かく見ていくならおそらく地域ごとに、さらに稠密な感染症対策や文化的感受性の違いを描くことができるはずです。
辻村 では、私も質問にお答えします。歴史修正主義というか、歴史の改竄ですよね? たとえば南京大虐殺はなかったというような。修正主義というのは学術的に真っ当な手続きがとられた異説について言うのであって、彼らのような主張は修正主義と呼ぶに値しない。そう呼ぶのは彼らを増長させるだけです。また修正主義という中立的な呼称を用いることで、人びとにそれにも一理あるかのような印象を与えてしまう。「言葉の真摯さ」ということに照らせば、それをどう呼ぶかということはとても重要なんです。嘘は嘘と言わなければなりません。
そういう歴史を捏造・否認する人たちは、自分たちの主張こそが史実だと言っている。保苅さんからすれば、彼らはまだ史実性に縛られているということになるでしょう。逆に保苅さんは史実性をいったんカッコに入れて、つまり史実性から解き放たれることによって、初めてアボリジニの話に向き合うことができるようになったんだというようなことを言う。たとえば彼らは、アメリカのケネディ大統領が自分たちの土地に来たんだ、と語るわけですね。そんな歴史的事実はないんですけれども。しかし彼らは歴史を捏造しようとして、そうしたことを語っているのではない。そんなことをたくらんでも彼らの間では誰にも相手をされないんだと保苅さんは書いています。ケネディ大統領が来たというのは、彼らのコミュニティで様々な人たちが分析・吟味した結果、出てきた歴史認識なのです。つまり、そこにはなんでもありとは違う真摯さがあると保苅さんは判断したわけです。逆にそうした検証・吟味の過程において真摯さが感じられないのが、日本の戦争犯罪を否認する人びとです。
くわえて、そうした否認派の人びとは、既に語られた歴史を真実ではないとして、自分たちの認識を普遍化しようとします。たとえば歴史教科書を書き換えさせようとするわけです。ところがアボリジニの人びとがケネディ大統領が来たという時、彼らにはそれ以外の歴史を否認したり、書き換えたりしようという動機はないんです、保苅さんが言うには。そうした自らの主張を普遍化させようという欲望はなく、あくまで地方的な歴史に留まっている。そういう地方的なものがたくさんあるからこそ、そこに多元性が担保されるとも言えるわけです。これはつまり、世界はOne-Worldではなく、多元的な世界、多元的な現実があるんだ、と言った時に、史実性とは別の回路があるということだと思うんです。それはアカデミックな歴史学のアプローチではない、別の回路です。ではそうした世界に触れるための入り口にどうやって立てるのかと言えば、石倉さんが言われた「直観」というのが一つのキーワードだと思います。
たとえば、神話学者のジョーゼフ・キャンベルがこういうことを言ってます。ウパニシャッドにこういうことが書かれている。夕日を見て感嘆する人は神性の中に入っていける。そういう人は自分より大きな存在に開かれていく。キャンベルはそういうことを書いている。これはつまり、経験に対する真摯さの話です。それは夕日をみて「ああ」って感嘆するような、そういう体験のことであり、そういう体験というのは、実は誰にでもできるもので、思春期の頃にはみんなそうだったかもしれない。それを詩に書いたりして、自分の中で「黒歴史」になったりしているかもしれません。でも実は、その瞬間が、世界と感応する戸口に立った瞬間だったとしたら、One-worldじゃない別の世界、別のレイヤー(層)があるんだということに気づきかけた瞬間だったとしたら、そこから多元的世界が開けてくると思うんです。そこから多元的世界での暮らしが始まる。だからこれはやっぱり一人ひとりが探求していけることなんだろうと思います。そういう自分の暮らしの中の手触りを大事にするということが真摯さなんです。
石倉 今の「真摯さ」という言葉、キャンベルの言葉に思い出したことがあります。それは河合隼雄さんが言っていた神話の定義です。河合さんはユングの心理学を研究していらっしゃったわけですけれども、ユングの自伝から繰り返し引用されているエピソードがあるんです。それはユングが東アフリカのエルゴン山中で先住民と対話した時のエピソードです。その先住民たちの間では太陽が非常に大切にされていたので、ユングは彼らに「太陽は神か?」と聞いたそうなんです。すると彼らからは「違う」という答えが返ってくる。ではどういうことかというと、彼らにとって太陽を人格化して神としているのではなく、太陽が昇ってくる時、その瞬間こそが「神」なんだというんです。太陽が昇ってくる瞬間に暖かさを感じたり明るさを感じたりすること、その体験こそが神性なんだ、というんですね。このユングの聞き取ったエピソードが河合さんにとっては非常に重要な気づきだった。ユングの壮大な心理学の体系全体が、こういう出来事に対する驚きや共感から発しているのだ、と河合さんは言うんです。もちろんユングには原型論をはじめ、とてもユニークな無意識についての理論の体系がありますけど、そのベースにある考え方は、こういった世界への直接的な接触であると。ユングは、太陽が昇ってくるという事象に対する気づきこそが物語を生み出すのだ、という言いかたをしている。朝の日の出に「神」を感じたというのは、ユングにとっては非常に小さな、個人的な出来事だったかもしれません。けれど、それはキャンベルがウパニシャッドから学んだことにも通じていると思います。
たしかにビッグヒストリーのような試みはすごい大事だなと思うんですが、一方でその全体性の中で、ちょうどよく太陽の暖かさを表現できるようなサイズ感を探ることも大事なのかな、という気がしています。太陽と地球の距離感は、遠すぎても、近すぎても生命を生み出すことはできなかった。同じように、我々の集合体には、あまりに大きすぎたり、あまりに小さすぎたりすることがないような、One-worldと無数の小さな現実を繋ぐのにちょうど良いサイズのストーリーが必要なのではないでしょうか。このことについては、ジェイムズ・クリフォードやダナ・ハラウェイが説いている「大きすぎない理論」「小さすぎない理論」が必要だという主張に同意します(参考:ダナ・ハラウェイ「人新世、資本新世、植民新世、クトゥルー新世 : 類縁関係をつくる 」高橋さきの訳、現代思想 45(22)、2017年、青土社)。つまり、僕たちが正気を保って生きていくのに必要な、ちょうど良い物語の規模というものがあるんだと思う。それはどの規模かは、どこに住んでいるか、どういう人たち、生物や無生物たちと共生しているかに関わっているんですけど、僕はその時の単位について共同体ではなくて、「共異体」という言い方をしています。というのは、我々はもともと同質性を持っているわけではなくて、むしろ全く異なった特異性を持ち寄っていかなければ、生存し続けることは不可能だからです。
「共異体」のサイズは、一概に規定することはできないけれど、少なくとも共生・共存に適した規模というものがあると思います。そこで今後感染症のリスクとなるウイルスと、どのような距離を取っていくのか、という課題がリアルになってくるのではないでしょうか。現代においては一つの世界というものを我々はどうしようもなく共有せざるを得なくなってる。これは一つのロゴス的な真実だと思います。しかし、それに対して、多世界は死んでしまったのかと言えば、そんなことはないんですよね。インゴルドが2016年のバッハオーフェンレクチャーで「One world Anthropology」ということを言っていました。つまり、一つの世界の人類学です。その中で彼はウィリアム・ジェイムズが言っていた多元世界というものをどうやって人類学の中に取り戻していくのかという議論をしてる。これは先ほどの辻村さんの話ともほとんど符合します。つまり、多文化・多自然・多形態という、変容しつつ多様である現実を、どのようにデザインしていけば良いか。地球全体がシームレスに繋がっているかのように見える現代の情報社会で、実は地域ごとに大きく異なっている「共異体」の諸相をつかむことが、今後僕たちが向き合っていかなければいけないポリティクスになってくるのではないか、と考えています。
では、たとえば人間が他の生物種と共存する時のように、他種の現実を想像し、その視点を取り入れることは、ウイルスに対しても可能でしょうか? このことは、「ウイルスを含む共異体」にとってとても重要な問題です。僕自身は、まだこの問いに答えを持っていないのですが、「lundimatin」というヨーロッパのオンライン・ジャーナルに3月21日に掲載され(※1)、HAPAXという日本語のサイトで3月30日に翻訳掲載されていた「ウイルスの独白」という記事(※2)を読んで、一種の神話的な面白さを感じました。これは夏目漱石の「我輩は猫である」みたいに、ウイルスの一人称で語られているテキストなんですが、そこではウイルスがこう語っています。「親愛なる人類のみなさま。笑止千万な我々への宣戦布告はおやめなさい。復讐心に満ちた目を向けないでください。私たちウイルスはこの世界に細菌が誕生して以来、地球においての正真正銘の生の連続体でありました。私たちがいなかったならば、皆様が陽の目を見ることはなかったでしょうし、菌糸細胞ですら生まれることはなかったでしょう」。こういう言い方をしていて、まさにウイルスのパースペクティヴから語りかけられてるんです。一つの荒唐無稽な寓話ではあるんですが、たとえばウイルスの視点を本気に受け取ってみたら、どういう風に世界が見えるのかということを実験的に書いてみたテキストだと思うんですね。世界的な感染症の拡大について考えた時に、もちろん多民族・多言語・多集団の世界をいかに維持していくのかという政治もあると思うんですが、こういう種を超えたリアリティを扱っていくこと。つまり、生物種を超えて、さらに非生命の境界を超えて、石や大気、あるいは地球そのものの語りをどうやって取り戻していくのかということが問われているように思います。
※1:MONOLOGUE DU VIRUS, lundimatin#234, le 21 mars 2020(https://lundi.am/Monologue-du-virus)
※2:HAPAX 3月 30, 2020 ウィルスの独白 LUNDIMATIN(http://hapaxxxx.blogspot.com/2020/03/blog-post_30.html)
辻村 石倉さんが「ちょうどいいサイズの物語」ということをおっしゃいました。そうなんです。僕はビッグヒストリーを自分が若い時に学びたかったと思っているんですが、たとえば今の若い人は若いうちに学べるわけですよね。その時に、宇宙とか地球とか生命とか他の生き物と自分を結びつけるような物語や世界観というものを、できるなら自分自身で作っていってもらいたいと思ってるんです。大学の講義とかでビッグヒストリーを教えるのはきっかけに過ぎない。ビッグヒストリーというのは、もっとその人自身がどういう人間観を持つか、自然観を持つか、生命観を持つか、その人自身の人生の中でそれらを生成していく、実践的なものだと思うんです。そこについて僕は「観関喜」という言い方をしています。まず、世界観。この世界観が変われば、その他のものたちとのつき合い方が変わっていく。つまり、関係性が変わっていくんです。また関が変われば観も変わっていく。そして生の喜びというもの、生きる喜びは、暮らしの中で、人生の中で、より良い観と関を探っていくことの中にある。その結果生まれるのが歓喜です。ビッグヒストリーを、そこに関わった人がこの宇宙に生まれて良かったと思える、そこに繋がっていくようなものにしたいなと思っています。生まれてきた赤ちゃんを「おめでとう‼︎この世界にはいろいろなことがあるけれど、生きることは素晴らしいよ!これからいろんな喜びに出会えるよ!」と言祝(ことほ)げるものでありたいんです。
そのために、いろんな入り口を持っていて欲しいなと思いますし、その一つが直観なのだと思います。ラヴロックもそういうことを言ってました。論理的な思考――言い換えるとロゴス――だけじゃ足りないんだ、直観的な思考をおろそかにしてはいけないんだ、と。歩いてたら目の前に崖があって思わず止まった。その時、あれがこうでああだからと論理的に考えこんだ末に止まったわけじゃない。体が止まったんだ。直観というのは体が判断しているんだ、と。
そういう直観の世界、さっきのキャンベルの話、夕日を見て「ああ」と感嘆するのもそう、インゴルドの石が話すんだというのもそう。そういう現実の多元性、現実の襞みたいなものは、自分の生や感覚に真摯になることで、初めて開かれていくものだと思うんです。この対談のタイトルは「パラドクシカルな共生の技法」となっています。その技法が何かというと、やっぱりナチュラリズムだけではないと思う。つまり、今の自然科学的な学問をやっている人たちの方法だけではない。もっといろんな技法があるんだということを人類学や神話学は見せてくれているんだと思うんです。そういう世界との接し方が、つき合い方があるんだということを。だから、私たちがビッグヒストリーを勉強するのではなく「ビッグヒストリーする」にはどうすればいいのか、神話を学ぶのではなく「神話する」にはどうしたらよいのか。今日の対談が、それを探る上でのヒントになるんじゃないかと思っています。
HZ まさに「Doing Big History」ですね。そして、その大きな物語を支えているものも、冒頭の辻村さんのお話に引き寄せれば、小さな物語たちなのだと思います。そうしたある種の矛盾を孕んだ歴史的実践によって、我々がもっともらしく感じられる、ちょうどいいサイズ感の物語をそれぞれが探っていく、そこに「技法」が発見されていくんだろうということを思いました。さて、時間が超過しています。ここから質疑応答に移りたいと思います。
質疑応答
Q 奥野克巳です。かなり盛りだくさんのお話でした。まだ十分に整理することができていないんですけど、以下では三つの点についてお話ししたいと思います。
一つ目は、インゴルドに関してです。『人類学とは何か』を取り上げていただきました。その第2章のタイトルは、「類似と差異」です。一方で、類似というのは共通性・普遍性のことで、他方で、差異とは、個別性・独自性のことです。その二項が想定されうるのですが、それらはそれぞれ自然と文化です。自然が普遍であり、文化とは個別性です。これまでは、そういう風に、いわゆる「多文化主義」的に考えられてきました。ただ、そうした考えが多文化主義的だと言っても、その裏返しの「多自然主義」がこれから目指されなければならないというような話では全くありません。
インゴルドは、一でもあり多でもある世界、世界は一つであるとともに多様であることを同時に示すのが重要なんだと言っています。それは、まさにお二人がお話しされていたことに重なってきます。たとえば、言語学者スティーヴン・ピンカーは、我々人間には、自然という普遍の土台としての「言語獲得装置」が与えられていて、つまり、そういったものを本能あるいは自然のレベルで持って生まれてきて、その後それぞれの言語を身に着けて、言語の多様性が現れるのだと言っています。しかしインゴルドは、そうではないと言います。生得的な能力が言語を話す能力を準備するという風に、前者と後者を切り離すことはできないのです。インゴルドは、彼のお父さんが言っていたことを引っ張り出してきます。人間は最初「四つ足」、つまりハイハイをします。その後に「二本足」で歩くようになり、やがて老いて杖をつき「三本足」になります。彼のお父さんは長生きで、百歳まで生きたのですが、最後には、介護されるようになって、歩行器を付けて、「六本足」の昆虫のようになる。生体の成長と文化的条件付けの二つに分かれているのではなく、あくまでもそれは同じ一つのものだというのが、インゴルドの見方です。つまり、生きているということ自体を見ていくと、自然が土台の部分にあって文化的なものが枝分かれしていくというわけでなく、自然と文化は切り分けられない。身体が老いると私たちも老いるということでしかないというわけです。
こうしたインゴルドの議論は、これまでの著作『ラインズ』や『メイキング』で述べられたことと基本的には同じだと思います。インゴルドが年内に出版を予定している新著『コレスポンデンシーズ』、日本語では「交感」/「交歓」くらいになるのかもしれませんが、その本の中で意図されているのが、無始無終の、はじめもなく終わりもないような形で繋がっていく、コレスポンデンシーズです。それに対比しうるのが、「インタラクション」です。インタラクションとは、インタラクトするAやらBやらが、最初から存在するわけですね。そこでは、AとBがインタラクトするというようなイメージです。他方で、コレスポンデンシーズでは、最初から実体性を持った単位そのものがないんです。行為の中で存在が生まれる。生きるとは、そういった繋がりに他ならないとインゴルドは強調するんです。
二つ目は、ビッグヒストリーに関してです。今日のビッグヒストリーのお話を辻村さんから聞いていて、途中で、ビッグヒストリーが、人間を中心として考えているのではないかというようなことをおっしゃったんじゃないかと思います。ビッグヒストリーのもくろみは、マルチスピーシーズ的な関心と同じで、人間を超えている、いや人間を超えているどころじゃなくて、宇宙の果て、有限ではなくて無限を目指して一気に行ってしまう。石倉さんもおっしゃっていましたけれど、『オリジン・ストーリー』は、宇宙の誕生から話を始めていて、人間から話を始めているわけじゃない。これは我々にとって途轍もない大きな問題を提起しているんだと思うんですね。一旦宇宙の起源まで行ってしまうとは一体どういうことなのかを私は考えています。
今日お話にあったアニミズムを探ろうとすると、我々の足元にいる先輩にアニミズムに関して深く掘り下げた岩田慶治がいた。岩田をたどっていくと、道元禅師にたどり着くわけです。道元は『正法眼蔵』95巻を書いていて、その中にビッグヒストリー的な思索がたくさん出てくるように思います。今から800年くらい前に、日本でビッグヒストリーと同じようなことを考えていた人がいたのではないかと思っています。仏教的な思想の流れの中に、宇宙を掴んだんだろうと思っています。
たとえば「山水経」という巻があって、そこで語られているのは、まさにビッグヒストリーなんです。たとえば「青山常運歩(せいざんつねにうんぽす)」といったくだりがある。山は歩いているという、中国の禅師が語った言葉を引いて、道元が山というのは常に歩いているのだと言っています。山が歩いているなどと、なぜそのようなことが言えるのか、それを禅的に捉えるわけです。人間が歩いているのは分かるけれども、山が歩いているなんていうのは、そんなことはおかしいっていうことへの囚われ自体から自由にならねばならない。歩くということを人間や動物が歩いていることに限定して考えていれば、最初から囚われてしまっていて、山が歩くなんておかしなことのように思えてしまう。ロゴスによる知的理解を超えた話は、「無理会話(むりえわ)」と呼ばれます。我々の世界は理屈や論理で成り立っている、つまりロゴスだけでできていると思っているのですが、それだけではなく、そうじゃないロゴス以前の世界に想像力を拡張してみることができないと、宇宙の理解には達しない。
何が言いたいのかと言うと、道元が『正法眼蔵』で言っていることをもう少し実証的に、現代の科学的なデータ、科学的にもたらされた見方をつぎ込みながら、それを補強しているのが、現代の神話としてのビッグヒストリーなのではないかという風に思えるんです。ビッグヒストリーは、先ほど辻村さんが言われたように「三つの多」、「多文化」「多自然」「多形態」を加えることによって、より確かなビッグヒストリーにしていくプロセスにある、つまり「ドゥーイングビッグヒストリー」ですか、自分たち自身でそれを生成して行くべきなんだというようなことをおっしゃっていましたが、他方で、ロゴス=科学のかなたにそれをすでにやっている人がいたんじゃないか、それは仏教思想などではすでに語られてきたことではなかったかということが、雑駁な感想です。
三つ目に、気になった点があったので述べたいと思います。「言葉」の問題です。辻村さんは最初、小さいものと大きなものとの対比で、言葉と世界という話をされました。たとえば「自粛を要請する」というのは言葉としておかしいんじゃないか、と言われた。そういう言葉に対して、文学者や哲学者はちゃんとアクションできなかった。これだけを聞くと、政府に対する批判、反知性主義に対する反対意見、さらに知識人の怠慢への批難という風に聞こえて、わざわざ言う必要もないことなのではないかと思えたのですが、よくよく聞いていると、真意はそんなところにはないように思えました。つまり、言葉というものへの信頼の上に、言葉を通じて世界を理解し、それを表すということをやっていかなきゃいけないんだということの再確認のようなことがおっしゃりたかったことなのではないかと思います。ただ、「自粛が要請される」というヘンテコな言葉遣いがされたから、改めて言葉に対して真摯にならなければならないというわけでもないのではないかと思います。つまり、我々は日ごろから常に、自己というものを見つめる中で、言葉を切り詰めて考えていかなければならない。そうは言うものの、言葉やロゴスだけで世界をすべて捉え切るということはできないんであって、世界をいかに言葉で掬いあげるのかという点に関して真剣に向き合うことが大事なのではないかということがポイントだったのではないかと思ったのですが、いかがだったのでしょうか。
そのことにも関わるのですが、言葉に関して最後に、辻村さんがおっしゃったインゴルドの「石」の話ですが、オジブワの長老が言った石が生きているんだということに対する私の解釈は、ちょっと辻村さんと違っているんです。言葉というものを辻村さんは信じているからこそ、言葉そのものを大切にして、現実に向き合っていかなければならないというお話はよく分かるのですが、インゴルドの話は、言葉だけではなくて、言葉で捉えられないものもあるんだ、つまりロゴスだけで全部が成り立っているのではなくて、経験と想像力、つまり言葉で捉えられるものと言葉にできないものを溶け合わせることによって、目の前の現実に向き合っていることを重視すべきだ、というのが、インゴルドの言っていることだという風に解釈しています。
石倉 ありがとうございます。「目の前の全ての石が生きているのか?」という人類学者ハロウェルの問いに対して、オジブワの長老ウィリアム・べレンズの答えは「いいや、しかし、生きている石もある」というものでしたよね。つまり石という存在のカテゴリーとして、すべての鉱物が例外なく生きているというわけではない。石の中に、局所的な生命があるのでもない。反対に、世界に満ちている生命の中に石が置かれている。だから、ある種の石は生きているし、コレスポンダンス、交感も発生するということ。まさに「レンマ的共生」が、オジブワの世界には成立していたということだと思います。これは、たとえばインゴルドの言う「類似と差異」の問題、つまり同時代に一つの世界を共有しつつ、多様かつ独自な世界観を持つという、二つの論理が共存していることに繋がると思います。
我々はある時はナチュラリズム的な分類法によって石を捉えることもあるし、別の時にはアニミズム的に捉えることもある。我々も実は、ロゴス的な言葉の分類の世界と、レンマ的で濃密な実存の世界を行き来しています。たとえば文化大革命の時に寺院の建築や大切な仏像を破壊された仏教僧が、ある時には泣き崩れたと思えば、次の瞬間にはケロッと笑っている。その奇行に戸惑った小坊主が、「なぜ笑っているのですか?」と僧侶に聴くと、僧侶は「あいつらは自分が土塊(つちくれ)を壊しただけだと知っているのか?」と答えたと言う話が記録として残されています。仏像は、もちろん仏教徒にとっては特別な意味を持った造形物である。でも、信仰を持たない紅衛兵にとっては破壊すべき偶像にしか見えない。そうして、宗教的な虚妄を否定するために破壊された仏像の残骸の前で、僧侶はなぜか笑っている。なぜなら、彼は仏像が聖なる意味の乗り物であると言う信仰的な理解の世界に住んでいるだけではなく、それが単なる材料の寄せ集めであり、「空虚な物質」であるということも、重々承知しているからです。場合によって石が生命体になったり、モノになったりするオジブワの世界観のように、チベット仏教の世界でも、仏像が特別な「聖なるもの」になったり、破壊されても何も傷つけられない「土塊」になったりする。色即是空、空即是色というように、唯物論と聖なる空性の世界を往還するということ。だからこそ、共産主義者による仏像や寺院の破壊行為を通してさえ、僧侶の心にある盤石の法や仏性を傷つけることはできない。そういうことが起こるのではないかと思います。
オジブワの長老や道元禅師、今紹介したチベットの僧侶などは、ある意味ではそういう世界の往還を実現している存在なのではないでしょうか。つまり、ある存在論に固定された「アニミスト」や「トーテミスト」でさえもなく、「ナチュラリスト」でも「アナロジスト」でもない。しかし、同時にそれらの全てでもある。保苅さんが書いているジミー爺さんというのもまさにそういう人でした。荒唐無稽な話をしているようにも思えるんだけど、その語りは道元禅師にも劣らない特異性を持っています。彼はローカル版の歴史と、白人の歴史の違いを知っています。前者ではドリーミングという今も止むことのない創造の只中にいて、先住民は過去・現在・未来を結ぶダイナミックな神話的現実の生き証人です。しかし、
僕の話の中では、ウイルスをオブジェクトとして捉えるだけでなく、ある種のサブジェクトとしてみていく必要があるという話をしました。言い換えればそれはウイルスというものを「生成するもの」と「存在するもの」という、二つの相から捉え返してみることと繋がっています。三木成夫的にいえば、世界中心的な生成の世界と、人間中心的な存在の世界。「死をもたらすものとの共生」というパラドックスを孕んだレンマ的共生と、「共に生きるもの」同士の繁栄を目指す共利共生。対称性論理によって把握された世界と、非対称性論理によって分類された世界。こういった二相の往還は、どちらかを選ぶ二者択一の思想でも、対立的な二元論の思想でもありません。こうしたバイロジックの往還運動によって、目に見えない小さなものの世界と、ビッグ・ヒストリーのように人間どころか生物や地球さえも超えていくような大きなものの世界をつなぐ中間領域を開いていく必要があると思います。「大きすぎるもの」と「小さすぎるもの」の間に「ちょうど良いサイズ」を見つけていくこと。それは、「一つの世界」と「多元的世界」、「健康」と「病」、「生」と「死」という異なる二極の間に、パラドックスに満ちた特異なものの共生と共存を成し遂げていく実践として結実していくのではないか、と考えています。
辻村 最後に、奥野さんが話されたことについて応答したいと思います。僕は今でこそ言葉を大切に思い、その力を信じていますが、少年時代は自分が口下手なのもあって、まったく言葉を当てにしていませんでした。言葉で自分の考えを表現できるなんて嘘だと思っていた。だからこそ、言葉によらない自然との交感の時間を持てたと思っています。
石倉さんの言う多元的世界へ開かれていく、あるいは多元的世界へ参入していくには、まず言葉によらない交感が必要で、べレンズの話も、石とべレンズとの言葉によらない交感――僕の言い方では、詩的感性による交感――がまず先にあって、そこが肝なのですが、言葉というところに話を寄せてしまったがために言葉の話にしか聞こえなかったかもしれません。
そういう多元世界を観得し、その中へ入っていくための扉は万人に開かれていて、実は自分の生活の中のありふれた一瞬の中に隠れている。それに気づくためには自分の暮らしのディテール、手触りを繊細に感じとることが必要で、僕はそのことを「入り口」「交わりの尊厳」「直観」という言葉で言おうとしていました。交感というのは、そうやって自分が世界へ開かれていく契機の一つなのです。その交感の瞬間を、僕は「きらめき」と呼んでいます。
つまり、〈言葉への真摯さ〉の前に〈経験への真摯さ〉が要るんです。真摯な言葉というものは、自分の経験に真摯に向き合い、それにぴったりくる言葉を探る中で初めて会得されるものだと思います。そうした真摯な経験に裏打ちされた言葉は、未だ宣伝文句化されていない、手垢にまみれていない生の現実を露出させる。それは、実はやろうと思えば色々な人ができることじゃないでしょうか。これは東千茅さんや坂口恭平さんを見ていても感じることです。世界観を転覆させるような巨大な揺らぎは、小さな個人が自らの生の手触り、触感を精細に感じとり、言葉にするところから始まるのではないでしょうか。
感じとり、言葉にすると言いました。ここでも経験と言葉の順番になっています。〈言葉の真摯さ〉というのは、そうした〈経験の真摯さ〉を言葉によって捉え、人間に“人間語”で伝える時に問題となるものです。人間の領域を超えて人ならざるものと交感し、人間の領域ではそれを人に人間の言葉で伝えるというのはシャーマンの役割です。
ビッグヒストリーが現代の神話であるなら(デイヴィッド・
だから今日の対談のタイトルに話を戻すならば、人と人ならざるものの間の「パラドクシカルな共生の技法」というのは、ある意味シャーマンの技法であり、僕がビッグヒストリーに足りないと感じているのはシャーマンだということ、それがこの対談をしたことによってはっきりしました。
人と人ならざる他者の間を往還し、交感し、それを言葉にする。その他者にはもちろん他の生き物も、ウイルスも、物も含まれている。結局、他者というのは自分の思い通りにはならないものなんです。そうした思い通りにならない他者たちとどういう関係を築いていくのか。どんな共存、共生の形がありうるのか。今日はそうしたことを考えていくための場になったんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。
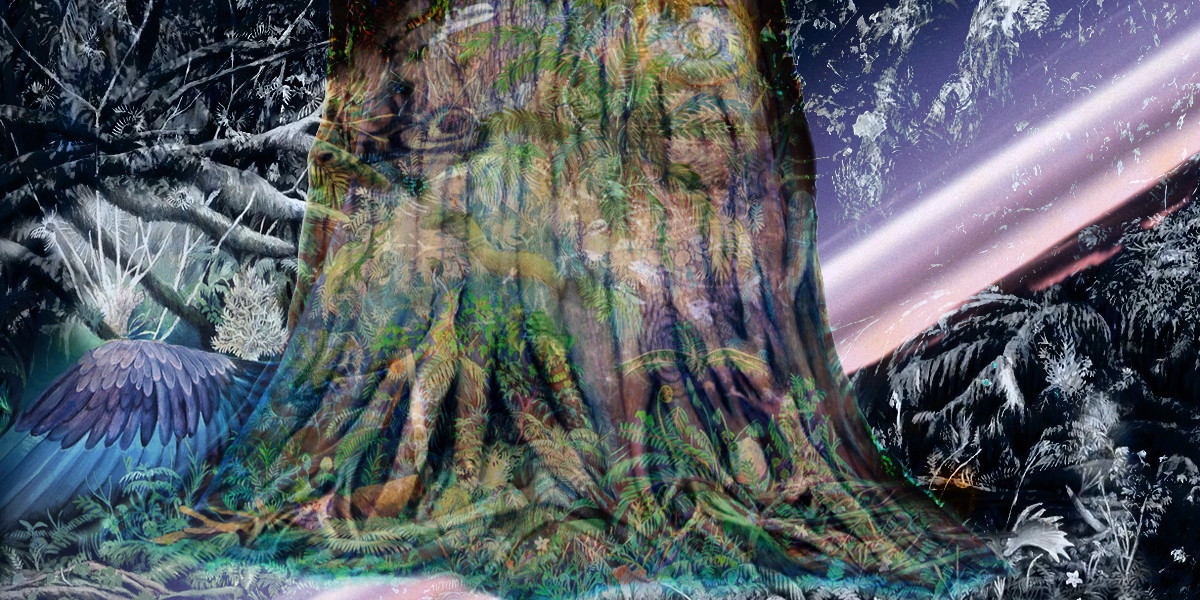
構成|辻陽介
ドローイング|大小島真木
✴︎✴︎✴︎
辻村伸雄 つじむら・のぶお/1982年、長崎生まれ。アジア・ビッグヒストリー学会 会長。国際ビッグヒストリー学会 理事。2016年より桜美林ビッグヒストリー・ムーブメント 相談役・ウェブマスター。2019年に桜美林大学・
石倉敏明 いしくら・としあき/1974年生まれ。芸術人類学者、神話学者。秋田公立美術大学大学院複合芸術研究科准教授。明治大学野生の科学研究所研究員。第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展において、日本館代表作家として、美術家の下道基行、作曲家の安野太郎、
✴︎✴︎✴︎
〈MULTIVERSE〉
「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー
フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介
「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄
「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生
「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美






















