シリーズ『COVID-19〈と〉考える』 |TALK 02|逆卷しとね × 尾崎日菜子|接触と隔離の「あいだ」を考える──コロナの時代の愛をめぐって
マルチスピーシーズ人類学研究会の「 COVID-19を分野横断的に考える 」シリーズ第二弾。COVID-19の感染拡大によって広がっている「接触忌避」、そうした市民感情に併走、便乗する形で進んでいる「命の選別」、そして、その中で顕在化している生の「不安定性」をめぐって。
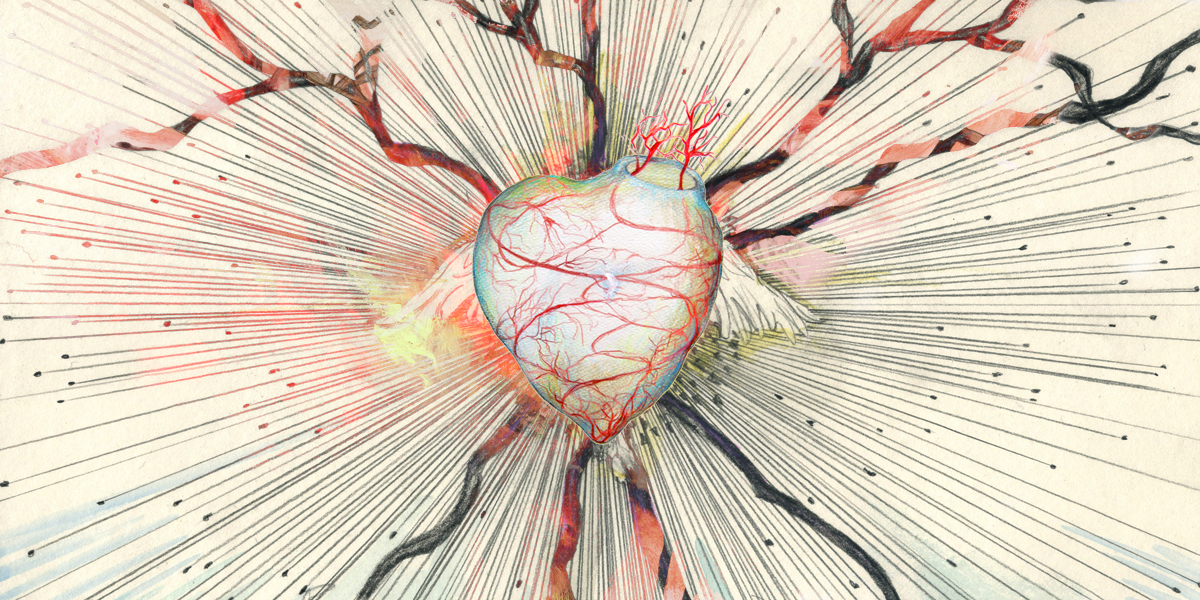
<< TALK 01|奥野克巳 × 近藤祉秋|ウイルスは人と動物の「あいだ」に生成する──マルチスピーシーズ人類学からの応答を読む
この記事は、マルチスピーシーズ人類学研究会の「 COVID-19を分野横断的に考える 」シリーズの第二弾として4月17日に行われた、学術運動家の逆卷しとねと小説家の尾崎日菜子によるビデオ対談(司会:辻陽介)の内容を、記録、再構成、加筆したものです。
今回は、COVID-19の感染拡大によって広がっている「接触忌避」、そうした市民感情に併走、便乗する形で進んでいる「命の選別」、そして、その中で顕在化している生の「不安定性」をめぐって、話し合いました。
Drawing by Maki Ohkojima
Text by Yosuke Tsuji
「接触」とは偶然性に開かれた実践である
HZ みなさん、こんばんは。前回に引き続き、司会を務めさせていただきますHAGAZINEの辻陽介と申します。この研究会「COVID-19を分野横断的に考える」は立教大学の奥野克巳さん、北海道大学の近藤祉秋さんらが主催するマルチスピーシーズ研究会と、僕が編集しておりますウェブメディアHAGAZINEとの共催という形で行なっているもので、COVID-19のパンデミックと、それがもたらしている社会的影響、あるいはその時下における「生」のあり方について、分野横断的、多角的に考えてみようという対談シリーズになります。新型コロナウイルス感染拡大の状況といたしましては本日(4月17日)時点で感染者215万人超、死者14万人超となっております。
今回、第二回目のテーマは「接触と隔離のあいだ」、あるいは、この事態の下で顕在化している生の「プレカリティ(不安定性)」になります。このテーマについて、逆卷しとねさん、尾崎日菜子さんのお二人に語って頂こうというわけですが、まず簡単に、事前の打ち合わせでお二人から聞き取らせていただいた言葉、問題意識をもとに僕がまとめた「趣旨文」を、ここで読ませていただきたいと思います。3分程度で済みます。
今日、COVID-19の感染拡大下において、人々の移動を制限し、行動変容を促す「social distancing (社会的距離化)」という概念が注目を集めています。この言葉で推奨されているのは、人と人とが距離を図ること、すなわち各自による各自の「隔離」です。では、そこで忌避されているものとはなんでしょうか。他でもない、人と人との、街と街との、国と国との、つまり、私とあなたとの「接触」です。
確かに、過去の感染症の悲惨な歴史、たとえばサントドミンゴ島(エスパニョーラ島)の悲劇などを踏まえるなら、人々が他者、他生との過剰で不用意な接触を控えていく、少なくとも接触の仕方を再考していくということは、倫理的にも非常に重要なことです。あるいは、COVID-19のさらなる感染拡大を防ぐ上では、外出自粛、テレワーク、リモートワークの推奨などを含む「ステイホーム」のスローガンには、一定の合理性があるでしょう。
しかし、終息への道のりの長期化が予測されている中で、その日々を現実に生きていかねばならない私たちは、いかに「接触」が忌避され、あるいは自らで「接触」を忌避していようとも、生きていくために、直接的にせよ間接的にせよ、人と「接触」せざるをえません。また、私たちは「接触」による命の危険を感じ、そこに伴うリスクを認識しながらも、同時に、性や食を通じた「接触」を望まずにはいられません。そもそも、私たちが「生きている」ということそれ自体が外界との「接触」に他ならず、すると、ウイルスという「見えないもの」をめぐる不安の蔓延によってにわかに市民権を得たかのように見える「接触忌避」とは、畢竟、「生」そのものの忌避であるとも言えます。
さらに、そうした市民感情と併走、あるいは便乗するかのように、今日では政治レベルで「命の選別」とも言いうる新しい排除も進んでいるように思います。そうした新しい排除は同時に、私たちの「生」のプレカリティ(不安定性)をも浮き彫りにしつつあります。
こうした局面において重要なことは、「接触か隔離か」という二極論にとどまらないこと、「接触」のもつ暴力性を真摯に認識しつつも、「接触と隔離のあいだ」を、差別や排除によってではなく、豊かなケアの実践、愛の実践によって満たしていくこと、そして、その方法を模索すること、ではないでしょうか。
学術運動家として「文芸共和国の会」を主宰し、主にダナ・ハラウェイの研究・翻訳を在野で行っている逆卷しとねさん、トランスジェンダーの当事者であり、ジュディス・バトラーに私淑するフェミニズム活動家であり小説家の尾崎日菜子さん、共に「思索」と「実践」の「あいだ」を生きる二人の対話から、「接触と隔離のあいだ」の倫理、「コロナの時代の愛」の在り様を考えてみたいと思います。
それでは対談に移っていきたいと思います。まず、最初のテーマ「接触と隔離」について、お二人が今考えていること、感じていることをお聞きしたいです。
逆卷しとね(以下、逆卷) はじめまして、逆卷しとねと申します。ご紹介いただいたように文芸共和国の会という、まあ出会い系のような会をやっています(笑)。どんな会かと言いますと、世間のいろんな方々、それこそ研究者でもなんでもない人からガチガチの研究者までを集め、あるテーマに関して三名ですね、三者三様の発表をしていただき、その後、3時間ほど、参加者みんなでああでもないこうでもないと言い合い、いかに我々は分かり合えないか、ということを確認するという、カオスのような会で、僕はその場を作る活動をしています(笑)。その活動の延長線上で、マルチスピーシーズ研究会の奥野(克巳)さんとも出会い、今日の司会の辻さんとも出会い、こうして尾崎さんとも出会い、というように、常に外に外に、出会いが広がっていってる感じです。
今日のテーマは「接触」なんですが、今お話ししたような「出会い」という観点から言っても、「接触」は非常に偶然性が大きい実践であると僕は考えているんですね。たとえば「コンタクト(contact)」という言葉があります。これは「接触」の意ですね。それから昨今、今日の事態を予言していたとして話題の映画『コンテイジョン(Contagion)』のタイトル、これは「接触感染」を意味する言葉です。英語において、接触と接触感染は、コンティンジェント(contingent)という「偶然に」を意味する言葉と、語源が同じなんです。全部、元々は「共にタッチする」(contingere)というラテン語に由来する。[1]そういうところから考えても、「接触」というのはそもそも、自分の知らないものや未知のもの、楽しいことも怖いことも驚きも危機も同時に常に含み持つ、偶然性に開かれた実践であると言えると思うんです。
それにもかかわらず、現在においては、「接触」という行為があたかも急にリスクのあるものになったかのように語られ始めている。実際、「ステイホーム」とか「社会的距離を取れ」とか「8割の接触を減らせ」といったお上からの号令ばかりが目立っていますよね。そればかりか、一般の人たちも、この新型コロナへの恐怖のあまり、緊急事態宣言を政府に自ら要望するような、権力をこちらから大きくするような方向に動いている。お上は、そうした一般における「接触忌避」の空気を吸い上げていくことで強い統制をかけるという循環が出来上がりつつある。そのように感じるわけです。
けれども、専門家会議の「接触を8割減らせ」という要請にも表れているように、実際のところ、暮らしから接触を10割、完全になくすということは不可能なんですね。それに、専門家会議で言われているのは、あくまでも「人との接触を減らせ」ということですけど、我々が生きていく上では普通に空気から酸素を吸入しているわけですし、引きこもっていても物質には触れているわけですし、対象を人間に限らなければ常に接触は起こっているわけです。もちろん、人間のいないところにだってウイルスはいるかもしれない。そういうことを考えていくと、生きているということ自体が、常に偶然性に取り囲まれている、そこから逃げられない状況にあるということが分かるんです。それなのに、今日、初めてその偶然性に気づいたかのごとく、世の中の空気が隔離一辺倒に進んでいき、さらに、政府・行政のような権力に隔離・接触忌避を命令する権限を委ねていくというのは、どうもおかしいんじゃないかと感じるわけです。
つまり、いくら隔離だと騒いだところで、絶対的な隔離は原理上存在せず、相対的な隔離しかありえない。そういうことを踏まえ、より実践的なレベルで今日の状況を考えていくにあたっては、接触か隔離かという二極論で考えるのではなく、誰と、どういうタイミングで、どのような状況で、接触を行うのか、といった形に、接触をグラデーション状のものとして捉え直していった方が、はるかに建設的だろうと僕は考えています。とりあえず、最初の挨拶としてはここらへんでしょうか。尾崎さん、いかがでしょう。
尾崎日菜子(以下、尾崎) じゃあ、私からもご挨拶を。みなさん、はじめまして、尾崎日菜子と申します。私自身のアイデンティティ……というか、いろんな背景を紹介しようとしてしまうと時間があれなんで(笑)、ここでは必要なことだけ語ります。私はトランスジェンダーで、自分のアイデンティティとしてはジェンダークィア、で、元セックスワーカーです。最近の状況としては、母が今年の一月に脳梗塞で倒れまして、今は病院で医療介護を受けています。母は寝たきりで話すことができない状況なので、私は親族として介護者のような形で母と繋がり、病院の医療者や介護者の力を借りつつお見舞い要員として関わっています。
で、私の方から「接触と隔離」の問題について思うことなんですけど、私としては、実践的なところからこの話はしたいなというのがあります。というのも、今お話しした母の状況がですね、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、大きく変わってきてるんです。具体的には、母が誰と会うか、どれくらいの時間会うか、ということが限定されるようになった。元々コロナ騒ぎが起こる以前は、病院の面会時間内の朝から夕方までであれば、誰が来ても何時間いてもよかって、むしろ、面会する人大歓迎という感じだったんです。それがだんだんとコロナが問題化していく中で、最初はまず親族しか面会できないというように限定され、次いで親族は5分までなら面会できるという風になって、最終的に、母は誰とも会えないという状態になってしまって、現在、母は病院外部からは完全にシャットダウンされてしまいました。
そういう状況において、しとねさんが先ほどおっしゃっていたことにようなことを、私も今感じています。つまり、母がいくら病院外部からシャットアウトされても、たとえば看護師さん、介護士さん、医師の方には接触しているわけで、その隔離はどこまでも相対的な隔離でしかないんですよね。そうした人たちとの接触がないと、寝たきり状態で口から栄養を採れない母は、その命自体が存続できない。現在、母はそういう依存状態にあります。母がそのように誰かとは接触しているということ、それ自体は私も、ケアマネージャーさんなんかの他の関係者も問題視はしていないんです。でも、これってなんなんやろうって思うわけです。
たとえば、最初の段階、親族以外は会うなという状況においては、母の友人がリスク要因とされていたわけですよね。で、次の段階では私なんかの親族がリスク要因とされることになった。こうして、だんだんと排除されていく人が増えていく、というような状況が起きました。比喩的に言えば、「死神」とされる人がどんどん増えていってるんです。最初はなんてことのない普通の人間が突然、あの人は実は死神なんじゃないか、あいつも死神や、こいつも死神かもって、次々に人間の「死神性」みたいなものが発見されていっている状況のように感じています。
ただ、もちろん、私としても理屈として、会えばリスクがあるというのは分かるんですよ。母や他の患者さん、医療スタッフの方にウイルスを持っていってしまう、病原体を持っていってしまうというリスクは理解してるし、母をあえて感染症に感染させたいかといえばそうではなかったりするんです。ただ、自分がもし仮に「死神」やと言われたとしても、あるいはほんまに自分が「死神」やったとしても、やっぱり会いたいという気持ちはあるんですよね。っていうのは、ちょっとエゴイスティックな思考実験かもしれませんが、仮に私が母の立場だとして、面会に来てくれる母や友人や恋人が死神やったとして、幽霊やったとして、悪魔やったとして、それでもやっぱり誰かに会いたいと思うと思うんですよね。
そういう意味で、私たちの「生」、生きるということを考える上では、寂しさという感情を切って捨てることはできない。だから私としては、そういう寂しさというものも踏まえて、隔離ということがどういうレベルで不可能であり、そしてそれが不可能なんやとしたら、どういうレベルで繋がりうるのか、ということを今日は考えていきたいなと思ってます。
半径10メートルの「接触」の倫理
逆卷 実はこの前、日菜子さんとは30分くらいお話したんです。その時に今のお母さんのお話は聞いていて、ただ、あの後、病院の面会が再開するみたいなことを日菜子さんがツイートされてるのを見かけたんですけど、それはどうなったんですか?
尾崎 あ、それなんですが。面会が再開するという話になって、つい先日病院に行ってみたんですけど、うーん、私が向かったタイミングにはもうシャットダウンになってですね、母の病棟の4階までは行ってみたものの、看護師さんから「これ以上は入れません」と説明されてしまいました。というわけで、母のベッドサイドまではあと一歩のところでたどり着けなかったんです。今の状況はこんな感じですね。
逆卷 そうだったんですね。お母さんに面会されている時はいつもどんな感じのやりとりをされていたんですか?
尾崎 寝たきりの母は喋ることはできなくて、文字盤を目で追って視線入力によって話したりということも今のところはできないので、私の方から一方的に話すっていうことがほとんどっていうか、いつもですね。まあ、もう母の機能は回復しないだろうというのは医師から告知もされているので、あんまり病気のこととかは話さないというか……。だから、なるべくくだらんことをというか、母の飼ってたロボットのアイボが私の言うことを全く聞いてくれないとか、そういうしょうもないことをなるべく話すようにしている感じですね。
これは他のこととも繋がってくるのかもしれないけど、こういう時こそユーモアって必要で、笑かしにかかっていかなやってられへんような状況ってあると思うんです。あと、もう一つは、これも他のこととも繋がってくるのかもしれないですけど、コミュニケーションを私と母の関係だけに閉じないようにはしてますね。母の友人のAさんが絵手紙くれたよとか、Bさんが来週来たいって言ってるけど面会に来てもらってもいいかなみたいな、なるべく関係を複合的にするというか、その場にいるのは一対一だとしても、関係性を一対一にしてしまわないようにするというのは、心掛けて話していますね。
逆卷 それってとても大事なことだと思いますね。再び社会全体の話に戻りますけど、今の状況って政府なり自治体なりを介しての関係があまりに肥大化してると思うんですよ。なんでみんなが政府とか自治体に「緊急事態宣言をもっと厳しくしろ」みたいなことをいうのかと言ったら、おそらく「自分は大丈夫だ」と、そう思ってるんです。つまり、自分は大丈夫なんだけど他人のことが信用ならん、と。他の人らは飲み屋に行くかもしれない、風俗にも行くかもしれない、いろんなところに好き勝手に行くかもしれないって思いがある。今はやたらと夜系ばかりが標的にされていて、その割に満員電車にはみんな乗ってるじゃんとか色々とおかしいなとも思うんですけど、いずれにしても、そうした不信をベースに権力をお上に委譲をするという流れになんの疑問も抱かずに乗っていく現状は危ない気がします。政府とか自治体とかって抽象的な存在で、顔も浮かばないし、友達でもなんでもない。そういう抽象的なものを介して、他人をコントロールしようとしている。他人は信用できないけど、政府は信頼できるというのはどういう理路なのか。さっき尾崎さんが言っていたミニマルな一対一の関係性に閉じさせないという話もそうだけど、そういう形で自分の半径10メートルくらいのところから接触の倫理を実践的に積み上げていく方が、本来、はるかに建設的だと僕は思うんです。
というのも、大前提として、やはり個々人、状況が全然違うわけですよね。同じ自治体に暮らしててもそう。僕は福岡県に暮らしていますが、福岡県の中でも言ってみれば過疎みたいなところもあるし、博多みたいに人が密集しているところもある。お家におじいちゃんがいるだとか、子供がいるだとか、友人関係でこういう人がいるだとか、ああいう人がいるだとか、状況は本当にバラバラなわけですよ。それを一元的に、具体的な関係性のない自治体を介して無関係の他人までコントロールしようという状況は歪だし、もっと自分の身の回りから自発的に接触の関係、これはケアの関係とも愛の関係とも言えると思うんですが、そういうものをちょっとずつ積み上げていき、この人なら信頼できるという具体的な形で、関係性を構築していくことが大事だと思うんです。もちろん、信頼というものは不確定性を含んでいるからこそ信頼が必要になるもので、信頼できないから信頼が必要であるという再帰的な概念だとは思うんですけど、とはいえ、そういう実践が個人レベルで必要ですよね。
尾崎 そうですね。さっきしとねさんがおっしゃっていた、お上を介した自分と他人みたいな関係じゃない、もうちょっと複合的で豊かな関係を形成する必要があるというのは、母と接していて強く感じるところです。やっぱり病院なんかに入ると、親族というのがすごい特殊な存在だとされているということを痛感するわけです。あとはせいぜい医者とか看護師というお上が特別なポジションとしていて、その他の友達なんかの血縁関係の外側の人たちは、元気な時にどれだけ親密でも全き赤の他人として分類されてしまうんです。でも、私からしても母からしても、もうちょっとそこはグラデーショナルなんです。つまり、信頼関係というのはグラデーションで繋がっていて、この人は全然話が通じひんなっていう他人もいれば、この人は私よりも母のことを知っているな、そういう母の一面を知っているというのは、きっと母もその人のことを信頼していたんやろうなっていう他人も当然いるんです。ある部分では私のほうがよく知っている母の一面もあれば、私がほとんど知らない母の一面を知っている友人もいるって意味では、愛の関係とかケアの関係というものは、最初から家族を超えたネットワークだったんじゃないかと、こうなってみると思うんですよ。
でも、この新型コロナ騒動によって、あたかもその豊かなグラデーションを含んだネットワークがないかのようになってしまってる気がする。というか、突然、線が引かれた感じがするんです。特権的に接触がゆるされて、他の人に母との接触の許可を与えることもできる医療者と、接触可能なギリギリの線上にいる家族と、全ての接触が許されなくなってしまった赤の他人という感じで、もともとグラデーション状になっていた人間関係が分けられてしまった、みたいな感じです。母と誰との関係も変化していないのに、私と母の友人たちが馴染みのあるものと、全く馴染みのないものとに、分けられてしまったのは、どうもしっくりこないんですよね。
逆卷 そうですね。実際、給付金にしても「世帯単位」でという話が上がっているわけですよ。でも世帯って言ったって、その世帯の内情はさっきも言ったように本当にそれぞれです。最近はDVがひどくなったとか、コロナ離婚したとか色々聞きますよね。世帯なんて普遍的に「世帯とはこういうもの」みたいな共通認識が得られるものでは本来ないのに、人間関係が一律に世帯単位に限定されてしまっている。僕もそうだったんですけど、たとえば親よりも外の人により近しさを感じてきたし、実際に生きていく上で重要なことは、部活だったりとか新聞配達だったりとか、そういう外の関係の中で学んできたという自負もある。「社会的接触を断て」というのが、イコール「家庭に閉じこもれ」という話に短絡すると非常に暴力的ですよね。
そこでいうと、日菜子さんの場合は、母親と日菜子さんの関係は親子関係なので、世帯という限定の範囲内からスタートしてきているとは思うんですけど、でも母親が持っている関係はそれだけじゃないし、日菜子さんの関係も当然、母親に限定されるわけじゃないですよね。そこをいかに、信頼なり、ケアなり、愛なりという形で繋ぎ直していくかということが、今問われてるんだと思います。
パンデミック下で露わになる差別構造とプレカリティ
尾崎 私の関心は、ヒトと他の種との関係というよりも、人間と人間との関係についての関心が非常に強いんですけど、あえてしとねさん的な関心、つまり、ヒトと他の種との関係という点から母の話を考えてみると、母は新型コロナの問題が起こる前からすでにいろんなリスクがあると医師から説明されていたんですよ。他の細菌性の肺炎になるかもしれないし、鼻からの経管栄養だから胃腸が弱ってくる可能性もあるし、脳梗塞の再発の可能性も高いから覚悟はするようにだのなんだのと、以前は言われていたんです。ただ、新型コロナが流行って、病院がシャットダウンするかしないかの場面になるや、病院としても「リスクはウイルスや、COVID-19なんや」となって、「とにかく手を洗え」みたいになってきた。
まあそれは正しいっちゃ正しいんですけど、急にリスクがコロナだけに限定されて語られ始めるんです。今まで他のリスクをさんざん説明されてきた私としては、違和感しかないんですよね。他の感染症とか誤嚥性肺炎とか、脳梗塞の再発のリスクはどうなってしまったんや、と。それは家族と家族じゃないもの、馴染みのあるものと馴染みじゃないものっていう風に線引きがなされたのと似ていて、COVID-19とそれ以外みたいな、変な線引きがなされてる気がするんです。たとえば、母の便の中にいて長い時間お尻の皮膚に触れているとトラブルを起こすような細菌とか、母の肺へ入ると危険だと言われていたようなCOVID-19以外のウイルスとかのリスクは今、誰も声高に注意喚起しないんです。急にCOVID-19だけがめちゃくちゃ馴染みのあるものになって、他のものはどうでもいいということになっている感じというのは、認識としてもアンバランスだなと思うんです。
逆卷 いや、本当にそう思います。いまや我々はコロナを中心に生きている。みんなコロナの動向、と言っても見えはしないんだけど、とにかくコロナを避けろ、そのために人を避けろ、といった感じだし、行動変容って言っても、一様に変えることが求められているだけで、そこにはまったく可塑性もなければ遊びの余地もない。本当にそれでいいのかと思います。
確かに、新型コロナは感染力が強い。人間がこれまでに免疫を持っていないウイルスなのでそれは当然なんですけど、ただ、日菜子さんおっしゃったように他の病気、事故とかも今日だって起こっていて、それで死ぬこともあるわけです。[2] あるいはこの状況で、本当に飲食店を畳んで自殺した人もいる。僕の高校時代の友達は宮崎県で畜産業をやっていたんですが、口蹄疫の問題があったときに、やっぱり自殺してしまいました。そういう風に、直接的にはウイルスの影響ではなくても、それが遠因となって、死ぬこともあるし、なんだったらコロナのことを一生懸命気にしていたら階段から転げ落ちて死んでしまったみたいな、そういうことだってありうる。リスクを極力排除しようという時、コロナのリスクだけを気にして生活を組み立てていくということには、どうしても危なっかしさを感じざるを得ない。それこそ一番リスクがあるのは、安倍晋三さんとその周りの人たちなんじゃないかという気もしますし(笑)
尾崎 他にもリスクがあるという点で、元セックスワーカーとして思うことは、一時期、厚労省が必死に喧伝していた梅毒の流行についてです。確かにある時期ある種の梅毒リバイバルが起こっていたみたいで、梅毒患者が増えているらしいというのは業界内部からも聞こえてきていて、実際、現役のセックスワーカー達もすごい気をつけてて、検査に行ったりとかしてたんですけど、そういうリスクがこうした事態下においては急に語られなくなってますよね。それに、梅毒自体も完全な予防法はないんだから、ちゃんと検査にいけ、油断をするなとしきりに言われていたんです。セックスだけじゃなく、柔道やサッカーの接触でもうつるんじゃないか、梅毒の感染力の強さをみくびってはいけないとかなんとかしきりに注意喚起されていたように記憶しています。でも、そこで柔道やサッカーをやめようって話にはならなかったし、恋人間のセックスをやめようって話にもならなかった。あの時もセックスワークだけにリスクが限定されて語られてしまっていたように思います。今回のコロナの流行でも、「夜の街クラスタ」だとか言われて、特定の業種の特定の行為が過剰にフォーカスされているように思うんです。
そうなった時に、今日のもう一つのテーマである「生の不安定性」というのもまた顕在化してくるように思うんです。たとえば、梅毒になったときに検査に行けるか、病院に行けるか、きちんと治療を受けられるのか、というのはワーカーとしてはすごい切実な問題です。感染症についての問題の切実さはどのワーカーでも同じくらいなのだけど、その時に休業補償があるかどうかとか、どれくらい売れっ子でどれくらい預貯金があるか、家賃がどれくらいの家に住んでるかとか、そういう差異が感染をきっかけに露わになる場面があるように思います。生活費が安くて、ケアの人的ネットワークが充実していて、貯蓄がたくさんある人の方が、やっぱり治療しやすいし、梅毒の知識も得やすいし、病院にも行きやすいし、仕事も休みやすいんです。逆を言えば、治療を受けたくても受けられない、仕事を休みたくても休めないという人たちがいる。これは今回のCOVID-19においても起こっていることのような気がするんですよね。
たとえば、学校一斉休校時のシングルマザーへの支給金の話がされるときに、セックスワーカーやナイトワーカー、あとは他の風営法関連の仕事をしている人、そういう人が支給の対象から外されたり[i]するわけじゃないですか。他にもさいたま市の朝鮮学校がマスク配布から排除されていたり[ii]ということもありました。あれは詳しく聞いてみると、さいたま市が直接管轄していない他の国立の小学校も排除対象になっていたようなんですけど、結果的にはそういう風に見えてしまうようになっている。あとは最近で言えばBuzzFeedの記事[iii]で、厚生労働省のクラスター対策班の西浦博さんがインタビューに答えているものがあって、その中に性的に男性同士の接触のある人などでは感染が起こってはいるけど一般の人にはまだ広がっていない、というような表現があったりして、新型コロナ以前からずっとあるような差別構造がさらっと表象されたりしている。男性同性愛者を一般の人ではない存在に特殊化して、彼らについてのリスクだけを語るのは、エイズの時代からずっと存続している差別的な認識の構造だと思うんです。これはそうした差別意識の表象の問題でもあるけど、それと同時に、所得の格差や政治への関与など構造的な不平等の問題でもあって、そうしたことが、もう一回ここで再演されてしまっているように感じます。こうした緊急事態下で露わになる差別構造や生の不安定性という問題は、ウイルスと人間との問題というより、人と人との関係の問題なんじゃないかっていう気がしています。私は社会的な関係にこだわりすぎてるのかもしれませんが。
逆卷 いや、それでいいと思うんですよ。今の話に少し付け足すとすれば、生の不安定性は新型コロナ以前からあったということですよね。そもそも、不安定性(precarity)は人間の条件でもある。ジュディス・バトラーの『アセンブリ』[3]における議論でも、不安定性、プレカリティは、生きていく上で当然みんなが共有しているものとされていて、不安定だからこそ相互依存が必要なんだ、不安定だからこそ人と人とはつながれるんだという両義性を、バトラーは言っているわけです。このように我々の生は根源的には脆弱で不安定なんだから相互依存して支え合っていかなきゃいけないんだけど、ただ一方で、不安定性が現実化したものである可傷性(vulnerability)の配分が不平等だということもバトラーは議論していて、そうしたコロナ以前から存在していた根源的な不安定さとそれが現実化されるときに露わになる不平等の様態が、ようやくコロナという見えないものによって可視化されているというのが今日の状況だと思うんですよ。
ただ、これは単に貧富の差だけに還元できるものでもなさそうな気が僕はしています。それこそ今回のテーマである接触ですよね。今、特に困っていたり差別されたりしているのは、この接触を生業としている人たちなんですよ。実際に最近では、配達員の人に消毒のスプレーを吹きかけるとか、その人たちが持っていたペンを持ちたがらないとか、そういう、そもそもお前注文するなよ、みたいな話が実際に起こってる。そういう風に接触を生業にしてる人たち、あるいは医療関係者もそうかもしれないけど、もともと世間からよく思われていなかったセックスワーカーとか夜の商売をされてる人たちもあわせて、あらたな「接触する階級」みたいなものとして、今日、浮上してきているような気が僕はするんです。
エンドユーザー至上主義がプロセスを見えなくする
尾崎 そうですね。ただ、最初のしとねさんの話にあったように、リスクを伴う接触の中でも語られている接触と語られていない接触があって、私がやはりこだわってしまうのは、そこにおいて語られていない側の、恋人間とか夫婦間とか家族観とかの接触なんです。夫婦間や恋人間のセックスはなぜか語られていなくて、たとえばセクキャバに行ったらやばいとか、風俗に行ったらやばいとか、配達員はやばいとか、スーパーのレジでのやりとりはやばいとか、要するに、血縁関係や家族関係の外側の接触だけが、危険なものとして饒舌に語られている状況があるんだと思います。そういう接触だけがすごい危険なものだと認識される一方で、親密圏の内側の語られていない接触については何もリスクがないかのように扱われている。
これも最初にしとねさんが言っていたことですが、とはいえ、私たちは接触ということをもうすでにしている、語られない、意識されないレベルで、常に接触は起こっているわけです。たとえば、私が使っているこのコンピューターのネジだって、誰かが触った結果、作られ、組み立てられ、運ばれているわけやし。道に散らばった街路樹の桜の花びらはいつのまにか綺麗になってるけど、あれだって掃除のおっさん・おばちゃんが綺麗に掃除してくれてるからやし、私らには勝手にそうなっているかのように見えるかもしれへんけど、それは誰かの接触によってそうなってるんですよね。それにも関わらず、そこがあたかもなかったかのようにになってしまって、分かりやすく目に見える接触、特に、普段からスティグマライズされている人との接触というか、みんなから「えっ!?その人は……」って思われるような、低俗だとか猥雑だとかされいる人との接触だけが、過剰に抜き出されて、悪いものとして語られてしまっているのは、正直、強い違和感を感じているところです。
逆卷 僕はそれをエンドユーザー至上主義と言ってるんです。この隔離政策下において自宅に「ステイホーム」してみたとしても、日菜子さんが言ったようにパソコンのネジは誰かが「ステイホーム」せずに作っているわけです。テレワークと言ってみても、じゃあそのテレワークで使う電子機器はどこで作ってるのと言ったら、それは「ホーム」ではないんです。エンドユーザーという末端においてのみ隔離が成立しているということ、エンドに届くまでの過程では実はいっぱい接触とかが生じていること、そうしたことがすっかり視界の外に置かれてしまっていて、ただただエンドユーザーの隔離生活のしんどさが前景化して語られるというのは、やっぱりちょっとおかしい気がします。
ただ、これは今に始まった話ではないと僕は思ってて、スプレーで除菌とか、脱臭剤で匂いを消したりとか、そういうある種の潔癖症を是とする流れの中で、社会的距離化は始まっていたと感じるんです。つまり、僕たちはパンデミック以前からそういう生き方をしようとしていた。接触の連鎖から距離をとって、エンドユーザーとしての自分にとどまり、エンドユーザーとしての生を支えている相互依存の関係はまったく顧みない。これは新型コロナ以前からずっと起こっていたことで、それが今、分かりやすく噴出しているだけというような気もしますね。
尾崎 エンドユーザーのお話に引きつけて、もう一度、私と母の問題という具体的な話に戻すと、母が入院している病院にいる医師とか看護師で、たまに私と話すことをすごく警戒しはる人がいるんですよ。他にも、病院では何かにつけて同意書を取ろうとしてくる。私はまあ当然、そういう時に同意書を書いたりするんですけど、やっぱりそこで感じるのは相手が私をクレーマーとして恐れているんだなということです。でも、私が望んでいるのは、何かが起こった結果について責任を取って欲しいとか、母の治療に高価で先進的な装置を使って欲しいとか、そういうことじゃなくて、母が今いる状況をよく知った上で、もっと良い状況はないかということを医療者たちと一緒に考えたいって、それだけなんです。そういうことをきちんと伝えると、向こうの態度もちょっと変わったりするんですけど。
結局、同意書をベースとしたような、責任の所在だけを逐一はっきりさせていくというようなコミュニケーションにおいては、過程における納得があまり大切にされてへんと思うんです。たとえば、こちらは母が栄養を取る際にどんな方法があって、どれが一番苦痛がすくないのか協議したくても、母の鼻に管を入れるか入れないかというような、二者択一の話にしかならない。そうした過程を省略して、医療のエンドユーザーにとどまってしまうと、話し合いの過程は充実しませんし、合意できる内容も豊かにならないし、なにより、母を取り巻く様々な関係性がスカスカになっていくように思うんですよね。
逆卷 そして、そのエンドユーザーにおける協働性というものが、世帯とか家族とかに縮減されたものとしてイメージされてしまう。でも、それって戸籍制度のただの反復じゃん、みたいに思うわけです。新型コロナによって再浮上する戸籍制度、家父長制みたいな感じ。だから、エンドユーザーが考えなきゃいけないことは、君はもっと別の協働性を持って生きてきたじゃん、ということ。すでに色々なものと繋がってきたよね、ということ。そういうところをもう一回思い出していくことが、このプレカリティのポジティブな面をベースに、相互依存による協働性や繋がりをつくりなおしていく一つの契機になりうるんじゃないか。もちろん、それはいつどうなるか分からないという不安とも紙一重ではあるんだけど、不安定性を共有していくためには、エンドにとどまらず接触者たちのプロセスを見ていかなきゃいけないんだと思います。
尾崎 やっぱり、誰もがみんな傷つきうる存在ですからね。生産者や運搬者、医療関係者も傷つきうる存在で、もちろん末端にいる自分も傷つきうる存在っていうことを、認識しなおしていく必要があると思うんです。傷つきやすさが不平等に分配されているという問題はあるにせよ、自分にものやサービスを提供してくれている人も傷つくことから自由じゃないんやっていうのは、あらためてゆっくりと考えるべきでしょうね。
あと、さっきのしとねさんの話に別の観点から話を加えると、協働性というものも、今のような接触の形が唯一の形ではないと思うんですよ。たとえばエイズパニックが起きた時、つけるのが面倒だとかなんだとか文句をいいながらも、そそくさとコンドームの装着をみんなが会得したように、パニックを契機にして、人の行動は変わるし、愛の表現も変わる。だから、この家父長的な愛の伝え方が未来永劫続くみたいな形で考えるのは不健全で、これからのような接触が難しい時代にどうやって新しい接触の形、愛の形を作っていくのか、その変化をどう楽しんでいくのかっていう話をしないといけないように思います。
逆卷 そうですね。今は、こうしたら新型コロナに感染する可能性を最小化できる、という形で結論だけ押し付けられてて、僕ら自身で考えて新しい関係性を作っていくというフェイズが全く削ぎ落とされてるんですよね。全てが上から降ってくる感じ。でも、上からの結論にしたって、こうじゃないかっていう仮説に過ぎないわけですよ。あるいは、そうした仮説の中でも色々と工夫の仕方はあるはずなんだけど、ひたすら家にいろみたいな結論ばかりを押し付けられてるような感じがして、そこを突き崩していくような作戦が必要だと僕も思います。
愛の接触には始まりも終わりもない
逆卷 ところで、不安定性の話にもう一度話を戻すと、新型コロナがもたらしたのは、日菜子さんが先ほど言ったように「みんなが傷つきうる」ということ、金持ちだろうが、貧乏人だろうが、どんな職業だろうが、みんな傷つきうる、みんな病気にかかりうる、みんな死にうるということだと思うんです。新型コロナというのは、そうしたある種の平等性を人間社会に持ち込んできたアクターなのかなという気もするんですよね。つまり、人間が生きている原理的な部分、根源としての不安定性に働きかけているアクターではないかとも言えると思うんです。原理的にはみんな死にうる、ということは、新型コロナの問題を考える時には結構大事なことなのかなっていう風に思います。
尾崎 それは私も同意です。ただ、私自身のルサンチマンを含めて、しとねさんがおっしゃった死は平等に訪れるという話をひっくり返すと、そもそもなんでこうした契機がないとみんな不安定性に気づかなかったんだろう、自分自身も死にうるっていうある意味では平等に分配された人間の傷つきやすさになんでこうもみんな鈍感だったんだろうっていう、嫌味を言いたいところもあるんですよね(笑)。これまでだって、みんな失業しえたし、みんな家を失いえたし、みんな貧しくなりえたし、みんな経済的・社会的に追い詰められて死にえたじゃないですか。そういう状況が、2000年代以降の小さな政府化、社会保障費削減などのプロセスの中で、どんどん露わになっていたというのは、誰しも知っていたはずなんです。でも、どこか他人事だった。年越し派遣村みたいに、一時的にメディアで取り上げられて、これはまずいって話題になるんだけど、喉元過ぎればってやつで、しばらくすると何事もなかったかのようにされてしまう。何かきっかけとなる触媒みたいなものが現れると、ブワッとみんなの意識の上に不安定性が広がって、それを認識できるようになるんだけど、逆を言えば、そうした触媒がなければほとんど誰も認識できない。新型コロナもまさに今、そういう触媒になってますよね。
なんでこの話をするかっていうと、この新型コロナの問題がいつか長期化していって、緩く広く蔓延し、人々がCOVID-19と共生するような道を選んでいった時に、今ならビビッドに見えてる不安定性、たとえばスーパーのおばちゃんのパートの賃金はこんなに安くて、休みたくてもなんの補償もない危うさを生きているんやってことが、やっぱり忘れられていくんだとも思ってしまうんですよね。しとねさんがおっしゃったみたいに、原理的には我々の生の根源をなしているはずの不安定性や、全ての人間が晒されているはずの人の可傷性というものが、浮かび上がっては、すぐ消えていってしまう。こういう難しさ、自分も含めた人間の想像力についての難しさというのはなんなんやろうと歯がゆくもなるんです。
逆卷 スパンの長さというのは結構重要な問題だと思います。要は継続性の問題です。ツイッターとかを見ていてもそうだけど、何かが瞬間的にバーっと炎上してバーって消費されて、そしてサーっと消えていく。ツイッターだけじゃなく、そういう短期的な忘却のサイクルが常態化していて、言っちゃえばみんなすぐに忘れてしまうわけです。ちょっとした災害によって、万人の不安定性が顕在化する瞬間というのは定期的にあるんですが、でも、その意識が継続しない。震災の時とかもそうですよね。起きてすぐの時は、みんなすごく注目してて、ボランティアに参加したり、物資提供したりとかするんだけど、時間が経ったらほとんどの人が自分も不安定性の当事者であることを忘れてしまった。なぜそうなるのかと言ったら、やっぱり関係が遠隔的だからだと思うんです。遠隔的であり、かつ抽象的だから。寄付金も団体を通しての関係性だったりして、直接的な関わりが一切ない。そういう、遠隔的な関係、接触のない関係であるがゆえに、根源的な不安定性は忘却され、現実における被傷性の分配の不平等だけが残される。これは非常に問題だと僕は思ってます。
尾崎 消費っていうタームが出ましたけど、実際、不安定性から生じる悲劇とか、ある特定の傷のようなものが、すぐに物語化されて消費されてしまうんですよね。たとえば、ニュース番組とかでは、それが商品となってるのだから、ある程度は仕方がないのかもしれませんが……。とはいえ、しとねさんの寄付金や支援物資の話は私も耳が痛いところで、私もテレビで基地の埋め立て工事が始まるなどの象徴的な出来事があるたびに騒がれる辺野古の基地問題については、そういう関わりにになってしまっているような気がしています。ただ、騒がれた後も出来事は続いているし、遠い場所との接触は続いてしまっているという認識はそれでも重要である気はします。逆説的ではありますが、実際に接触のある場所から問題を考えていくことが重要なのかもって、しとねさんのお話を聞いていて感じました。
身近に引き寄せすぎかもしれませんが、私がよく散歩するコースには、夏になるとハマヒルガオが咲くんですね。そのハマヒルガオはどうやら私の住んでいる場所の砂浜保全運動が部分的に成功した恩恵をうけて咲いているみたいなんですが、そうした細かいヒトと他の種とのつながりや開発に抵抗する力が、関西から遠く離れた沖縄の環境保全にもつながっているかもしれへんなあって、ふと感じました。そういう意味では、確かに事実をマスメディアが報道するのは遠くで起きている問題を知る上では大切だとしても、実際の接触とか愛というものを考えるには、そして、手近なとこから遠くのものへ愛が波及されていく可能性を考えるには、もっと別の回路が必要なんやろうなあとは思います。物語化して消費して、視聴者が一時的なカタルシスを得るだけでは、報道されたその次の瞬間にも接触は続いているこの現実にアクセスできないような気はしますし。
これはいい譬えかは分からないですけど、そういうスパンの短い関わりというものには、男性がセックスしてる時に腰を振りまくって、射精したらそれで全部終わりみたいなノリと近しいものを感じます。インサートしてる一瞬だけが愛で、他の時間はもう知らん、みたいな、つまり、一緒にラブホテルを選んだり、ローションを使うかどうかで喧嘩したり、最悪の場合、前戯もかもしれませんけど、インサート中以外の時間は愛とはカウントしませんみたいな、そういう感じに似てると思うんです。それは男性っていうよりも、ペニス中心主義的なものなんでしょうけど。ただ、本来、愛っていうのはずっと続いてるものだし、人と人との関係もずっと続いてるものですよね。セックスの場面の外側でも、愛の接触はずっとあって、一緒に歩くだったり、一緒に食べる料理の献立を考えるだったりが続いていたわけですよね。でも、そういう微細で豊かな接触の連続は忘れ去られてしまいやすい。そういうところとも似ている気がします。
逆卷 よくセックスを回数で数えるじゃないですか。一回、二回、三回みたいに。でも、それって射精の回数に過ぎなくて、実は女性の側からしたら一回もないよ、みたいな話だったりするわけでしょ。そもそもセックスが数えられるものかどうかも分からない。セックスっていつから始まってるの? みたいなところもあるわけですよね。もしかしたらこの会話もセックスの一部かもしれないし、あるいは会ってない時にその人のことを思い出したりするのもセックスの一部かもしれない。これもプロセスの話になってくるのかもしれないけど、愛とかケアというのは始まりと終わりを恣意的に区切って「はい、ここまで」みたいな感じにするようなものではないと思うんですよ。
尾崎 そう思います。あとセックスってどこか垂直的に捉えられやすいというか、親が子に、子が孫にみたいな生殖の関係で考えられがちだけど、さっきしとねさんがおっしゃったような前後の会話もセックスの一部なのだとすれば、ラブホテルに入る時の受付のおばちゃんと気まずい接触をしていたり、ホテルを出るときに掃除のあんちゃんと遭遇してしまって二人で苦笑いするみたいなことを私たちは当たり前にしていて、そういう水平的な愛の繋がりというのもあると思うんです。ケアにしても、家族というユニットだけでケアを考えると、どうしても親と子の垂直的な関係にしかならないけど、そこの枠組みを破ってしまって、もうちょっと豊かな人間の関わり合いを見ていけば、もっと横に向かってケアの輪が広がっていくんじゃないかとも思うんです。もっと言うと、実際に介護を家族だけに限定するのは現実的にも不可能とちゃうかなって感じもあるんです。だからこそ接触というものを、血縁を超えて横にも広がるような広いものとして考えていきたいっていうのはあります。
逆卷 まさにダナ・ハラウェイは、ネオダーウィニズムの柱である遺伝子の垂直伝播、種の再生産に対して、それはまあ一応あるにしても、それだけじゃないということをずっと言い続けてきた人なんですよね。一昨年に熊本県で開催されたマルチスピーシーズの研究会でも話したことですけど、遺伝子には水平伝播というのがあるんです。垂直伝播というのが生殖関係だとすれば、水平伝播は横のつながり、横に向けられた遺伝子の交換、それも種を超えた交換があるという話で、それはたとえば食や感染からもたらされるものなんです。[4]
人間は今70億人以上いて、地球上でさも唯一のアクターであるかのように振舞っているわけじゃないですか。でも、人間がこれだけ繁栄できているのはウイルスと共生しているからだという説もあるわけですよね。ウイルスによって遺伝的多様性がもたらされたという話もある。そういう風に人はウイルスと共生してきている。新型コロナは人類にとって未知のウイルスで、まだ出会ったことがなかったからこそ、致死性はエボラ出血熱や狂犬病、SARS(重症呼吸器症候群 2002-03)やMERS(中東呼吸器症候群 2012-現在)ほどは高くないけど感染力(伝播力)が強い。感染者の母数が多いから死者も多くなるタイプのウイルスであるように、僕は今のところ感じている。ただ、既存のインフルエンザにはみんなかかったことがある。生きてるうちで一回もインフルエンザにかからない人はいないとも言われてるんですよね。たとえ、その人に感染した記憶がなかったとしても、実は軽い風邪だと思っていたものがインフルエンザの無症状パターンだったりするらしい。そういう風に考えていくと感染って日常的に起こっているわけですよね。今回は初めてのウイルスで伝播力が強く死亡者も多いので問題になってるけど、もともと我々は感染しながら生きてる。それこそ全然知らん通りすがりのおっさんが持ってたウイルスに感染したり、あるいは感染させたりしながら生きてるんです。[5]
僕はケアのクラスタを作ったらいいんじゃないかなと思いますけどね。今クラスタ対策であれこれ言われてますけど、やっぱり愛もケアも水平の関係における不確かな信頼をベースにしたものだと思う。さっき日菜子さんがコンドームの話をしていたけど、同じ濃厚接触をするにしても、いろんな水準が細かくあって、そこを手探りで心地よい形を模索していくしかないんじゃないかな。[6]
尾崎 ケアが水平的というのは実感としてもよく分かります。なんでかというと、さっきも言いましたが、母と娘のように垂直的なケアの関係を作ってしまうと、実務的にもすごい大変なんですよ。それは制度上においてもそうで、たとえば日本の法制度上では母のケアをする責任というのが、私に集約されているみたいなんです。つまり、私が何もしないでいると、虐待だ、ネグレクトだというような話になってしまうんです。こういう責任を分散できない状況は、ほんとにストレスフルなんですよね。たとえて言うと、母から預かった卵を10個以上、一人で素手で抱え込むような感覚です。そういう垂直的なケアしかない状態は、だから、生存戦略としてもあまり現実的じゃない気がするんです。家族がかなり上手くいっていて、親が金持ちで自分も金持ちで、というような預かった卵を一人で全部持てる条件が偶然整っている人なら可能かもしれへんけど、多くの場合、ケアっていうのは横に関係性を開いていかんと、つまり、卵を分けてバスケットにいれとかんともたへんっていう状況がやっぱりある。だけど、今の政府がやってる感染症対策は、「家族で家にいろ」みたいな、すごく単純化された話になってますよね。たしかに今の状況的にはそれしかないのかもしらんけど、家族というのは実際のところ、そんなに安全ですべてのケアの体制を備えたような万能の方舟じゃないんですよね。
逆卷 それこそ親とか家族とか関係なく、手探りで「こいつは信頼できる」「こいつはもうちょっとだ」みたいなのを探りながら、そういう感じで人間は生きていると思うんです。だから、今の状況がすごい不自然な感じがするんですよ。おそらく、家族や肉親との関係にしたって、常に組み直されているものでもあると思う。日菜子さんのお母さんとのケアの関係にしても、おそらく、ケアの実践のなかで母子関係に一般化できないレベルで関係性が組み直されていく経験なんだとも思う。もちろん、親や家族と一緒にいるのがダメだというのでは全然ないんです。家族関係、母子関係としてだけでは記述できない関係性が作られていく可能性の話ですね。
尾崎 その実感は強くありますね。なんでかっていうと、寝たきりの母に喋りかけ続けるという関係が、どこか母娘というより恋人関係のように感じる瞬間もあるんです。これってフロイト的で気持ち悪いんですけど、やっぱりなんか、単なる遺伝子を引き継いだ子供としての目線じゃない目線がそこにはあって、今日は首動くかなとか、私を眼差す今日の目の感じは可愛いなとか、そういうことを色々と思うんですよね。母を性的に欲望するとかは全くないんですけど、いわゆる母が子供をケアする、子供が年老いた母をケアするみたいな物語に収斂されない余剰みたいなものを感じてしまう瞬間が、ケアの実践の中にはやっぱりある。そういう関係の組み直しは実際に起こっているし、非常に面白いなと感じているところです。接触がどういう風に関係性を組み直せるかという大きな問いに答えることは難しいですけど、そういうことを語っていかないと組み直しも起こらないので、積極的に語っていったほうがいいと感じますね。
お仕着せの「行為変容」とは別の方法で
HZ 残り時間も少なくなってきましたので、ちょっとここで、あらためて話を振り返っておきつつ、僕からの感想、質問を述べてみたいと思います。まず最初に、逆卷さんから接触という行為は常に偶然性を孕んだものなのだという指摘がありました。そして、今日においてはおそらく、新型コロナに対する不安が蔓延する中で、接触の中にあるそうした偶然性が避けるべきリスクとしてばかり捉えられてしまっていて、接触のネガティブな部分ばかりに人々の意識が向いてしまっている、という状況についての確認がありました。
その上で尾崎さんから家族主義の強固さについての問題が提示されました。家族関係とそれ以外の人間関係との間にはっきりとした境界線が設けられ、家族がサンクチュアリ化する一方で、その外部がリスク化するという単純化が起こっている、と。本来は、そこはグラデーション状になっているはずなのに、そうしたことがすっかり忘れられてしまっているのではないか、その上で、具体的な人間関係の調整についてを考えることもなく、政府や自治体による一元的な「社会的距離戦略」や「ステイホーム」の奨励に同調し、またより強い政策を期待するような流れは不健全なのではないか、そういう問題提起でした。
ただ、逆卷さんも指摘されていたように、こうした、本来ならグラデーション状に広がっているはずの関係性を無視するような家族主義であったり、エンドユーザー至上主義であったりというのは、兼ねてよりあった傾向でもあって、それがCOVID-19が問題化する中で顕在化しているだけだとも言えます。それこそ2000年代以降、特に支配的になった新自由主義的な市場が、そうした関係性のミニマム化を要請しているという側面もあると僕は思います。少なくとも日本の都市部で定着しているような核家族主義、個人主義というライフスタイルは、マーケットとの関連抜きには語れないように思っています。
そうした中、この緊急事態下において人々が積極的に一元的なコントロールを政府に期待していくというのは、確かに不健全だなと感じますし、そうした一元的な行為変容、社会的距離化には、はっきりと違和感を感じます。ただ一方で、新自由主義をベースとするような、共同体が分断された匿名的な都市における集住を旨とするライフスタイル、そこにおける日常的な振る舞いそのものについては、根本的なところで行為変容を考えるタイミングなのかもしれないとも感じるんです。隣人の存在がリスクでしかない、あるいはリスクとしてしか感じられないような社会では、接触が極めて危険な行為だと感じられても当然と言えば当然だし、そういう意味で、特に都市部に生きる人たちというのは、新型コロナ以前からすでに隔離されていたと言えるのかもしれないとも思います。
ですので、政府や自治体が一元的に奨励するような「行為変容」は批判しつつも、そういったものが望まれてしまう今日の状況をボトムアップに変えていくという意味での「行為変容」というものは積極的に考えられるべきだと感じています。あるいは「社会的距離」についても同様で、いわゆる僕らが暮らしている日常の範囲内における人々との交流という意味での社会的距離と、もう少しマクロなレベルにおけるグローバルな人の行き交いや他生との関わりを意味するよう社会的距離という、二つの社会的距離があるという考え方もでき、その場合、それぞれの社会的距離に対する評価は異なってくるようにも感じます。
また、対談の中でバトラーの相互依存についてもお話に上がりましたが、この相互依存に関しても、二つの軸があるように感じました。というのも、今日、マーケットにおいては未だかつてなかったほどに相互依存が進行しているわけです。もはやネーションの単位で何かを決めることが難しく、ありていに言えば、国境を超えて絡み合うマーケットの方が強くなっている。しかし一方で、そうした相互依存的にグローバル化したマーケットが要請する新自由主義的な経済政策は、暮らしのレベルにおいては逆に、人々の相互依存的な関係性を解体しているという問題もあります。ジェントリフィケーションなどによる商店街の壊滅などは、その分かりやすい例ですよね。もちろん、お二人の議論においては、こうしたことも折り込まれていたわけですが、「相互依存」が素晴らしく「社会的距離」がまずい、というような単純な理解を避けるために、一応、そうした複数の軸があるということをここで確認しておけたらと思います。
その上で僕からお二人への質問なんですが、尾崎さんからは、なぜこれまでプレカリティに人々は気づいていなかったのかという指摘があり、逆卷さんからは今日における人々のある種の健忘症的な継続性のなさについての指摘がありました。そうした健忘症に陥らず、継続的な行為変容、愛やケアの実践をしていく上では、遠隔的な関係に満足することなく、エンドユーザー至上主義批判において語られていたようなプロセスへの想像力を逞しくしていくことが大事になってくるんだとは思いますが、ただ一方で、想像力だけでは、やはり不十分な気もするんです。想像力によって、一時的に不安定性やプロセスに思いを馳せてみても、それこそ目の前の仕事に忙殺されていく日々の中においては、たちまち忘却されてしまうようにも思う。だから、より具体的なレベルで、なんらかのアクション、行為変容を起こさないといけないとも感じているのですが、そうした具体的なレベルにおいてはどういう実践が可能なのか。お二人のお考えをお聞きしたいんです。
尾崎 では、先に私から。このコロナ騒動でセックスワーカーの多くは仕事を失っているわけですけど、仕事がなくて暇な時間を利用してユーチューバーを始めたワーカーを一人私は知っていまして、ものすごく現代的な商売のやり方やなあと感心していたりします。他にも、コロナがきっかけで新たに整備された家賃補助なんかの行政による支援へのアクセスを支援する市民団体の情報がツイッターを通じて拡散されて、困っているナイトワーカーが情報を手にいれたり、ナイトワーカー間で彼女たちの生存に欠かせない情報がやり取りされている光景も目にします。こうした光景というのは、辻さんがおっしゃるようなマーケットレベルで人々が簡単につながれるようになってきた現象の一部でもあり、同時に、ご指摘のようなグローバル資本主義の拡大が人々の生存可能性を脅かすようになってきた現象の一部やと感じています。
というのは、新しくユーチューバーになったセックスワーカーは確かに技術革新の恩恵をうけて簡単に他者にアクセスできるようにはなってはいますが、その裏側では彼女の生存の一部はグーグル社という私企業のさじ加減に支配されていると言えなくはないと思います。また、生活支援の情報が欲しいナイトワーカーたちの生存も、ツイッター社という私企業にがっちり握られてしまっているのは事実でしょうし、COVID-19の出現によってウェブを通じで情報を漁らないといけないというのは、彼女たちの身近な関係が新自由主義的な政策によってボロボロにされて、距離的に近くて実際の接触がある関係ほどいがみ合うようになってしまった結果かもしれません。そういう意味では、辻さんのおっしゃるように地球規模に広がった市場が、人々の生存可能性や、相互に絡み合う生の豊かさを私たちから奪い去っている可能性は大いに考える必要があると思います。
だだ、そういう発達した資本主義の結果、張り巡らされたある種の抑圧の網の目を使って、単に想像の中での甘やかな連帯のような形ではない、この不条理な網の目で実際に生き延びる実践が物理的に起こってしまうということがあるのは、とても重要やと考えています。できてしまった不愉快な構造物を利用して多様な人がスケボーで遊んでトリックを競い合ったりしながら、たまにスケボー同士がぶつかるような、そんな生のゆたかさがあればええなあと勝手に思っています。そうした実際の動きをのんきなまでに肯定的に評価していいのかという議論はもちろんあるとは思いますが、私からはそういう現状をとりあえずはお伝えしたいと思います。
逆卷 質問に回答するにあたって、まず僕が文芸共和国の会を始めた理由を話そうと思います。実は日本って結構コミュニティがいっぱいあるんです。コミュニティはいっぱいあるんだけど、ただ、それらのコミュニティ同士が交わらないなってのがあった。だから、それをガラガラポンして、カオスの場を作ってみようというのがあったんです。そもそも、最近、やたらと使われているクラスタって言葉も、当初はオタクみたいな感じで使われてましたよね。歴史クラスタとかガンダムクラスタみたいな感じです。まあ、それくらい共同体がセグメント化されていたんです。それは消費に応じてかもしれないし、企業のマーケティングによって分断されていたのかもしれないけど、ただコミュニティ自体はいっぱいあり、それらが交わらずに、問題意識を一部分でも共有したりするきっかけがないなと感じていたので、そういう場の一つとして文芸共和国の会を立ち上げたんです。だから僕が作ろうとしたのは共同体ではない。出会いの場を瞬間的に立ち上げて、あとは若い人たちみなさんどうぞみたいな感じ。僕自身はやり手ババアみたいな感じで、そこで信頼関係だったり愛だったり色々生まれたりするかもしれない、そういう可能性を持った場を作ってみたんです。実践レベルにおいては、そういうすでにあるコミュニティを混ぜる場を作るということが非常に重要だと感じているというのがまず一点あります。
あとグローバル化についてですけど、多分、グローバルなものと言ってみても全部が全部、同じように繋がっているわけじゃないと思うんですね。たとえ同じソフトを使っていても、そこで行われているコミュニケーションのあり方は多様で、金融経済と同じように均質に回っているわけじゃないと思うんですよ。たとえば、最近はZOOM飲みとか、テレ飲み会とかが流行ってるみたいですけど、使い方としては割と凡庸というか、始まりと終わりがあって、そんなに面白いものじゃない。ただ一方に、そうではなく、ただ繋ぎっぱなしにして、言語的なコミュニケーションをしないという人が結構いるみたいなんですよ。ZOOMに繋ぐんだけど、することはただ生活するだけ。片方は掃除したりしてて、もう片方はご飯を食べていたりする。それで時々、「元気?」みたいに声をかける程度のそういう繋がり方みたいなのがある。[7] それって情動的な紐帯というか、雰囲気の共有ですよね。今、世の中的には空気の支配みたいなものが徹底されていますけど、これだけ恐怖で満たされている世の中にあっても、それとは別の形で穏やかな雰囲気の共有というのが行われていたりする。ZOOMやスカイプは基本的には通話のためのサービスですが、「別に喋らなくたっていいんじゃない」という、独自の使い方を発見してる人たちはいて、そういうところにヒントがあるんじゃないかなという気がしています。
HZ ありがとうございます。まず尾崎さんが紹介してくださった話は、とても元気が出ますね。たしかに、それはICTへの依存であるとも言えるし、テックジャイアントによる新しい管理支配のようなものも連想してしまわなくもないですが、とはいえ、すごく強かだし、アナキーでもあって、そういうボトムアップの狡知によって、この分断された状況下をサバイブしていこうという、そういう動きには非常に共感を覚えます。そうした動きが複数的に折り重なって広がっていく中で、隔離の時代の新しいつながりが発見されていくんじゃないかという気がします。
逆卷さんのお話も非常に興味深かったです。出会いの場を立ち上げるということの重要性、グローバルな均質化という紋切り型が取りこぼしている差異、ICTを使用した情動的紐帯の可能性、などいずれも重要なポイントだと感じつつ、ただ一方で、趣味のクラスタであったり、寂しさを癒す上での情動的な紐帯であったりというものが、リアルな暮らしにおける相互扶助へとなかなか結びついていかないことに、現状の難しさも感じています。確かに仲間と話したり話さなかったりして群れることで、心のケアというものはできると思うんですが、今日起こっているような「今月の家賃が払えない」というリアルに差し迫った状況においては、少し繋がりが弱いのではないか、という気もしてしまう。今は国がどれくらい補償するかが議論されているところですが、それがイマイチあてにならんぞって時にどうするのか。経済単位としての家族主義、世帯主義をどう組み直していけるのか。そうした暮らしのレベルにおける相互扶助の関係性というものもまた、今後、問われていくことになるのかもしれませんね。
さて、時間がきましたので、ここからは質疑応答に入っていこうと思います。
質疑応答
Q1 人類学者の奥野克巳です。とても興味深いお話をお聞かせいただきありがとうございました。冒頭での逆卷さんのお話ですが、今何が起きているのかというと、科学者の専門家会議が答申をして、政府が「三密」という規範を含めて、措置策を広めていくという役割を担っています。つまり、科学をベースにしながら政治が強い力を持っているということだと思うんですね。ただ、科学のデータは、逆卷さんがおっしゃったように、仮説でしかない。それなのに、政治と科学が一体化することによって、私たちに投じられているものを、私たち自身が内面化するという状況が生まれている。私たちは、無意識のうちにそれに従わざるを得なくなっている。それに従うことがこの「疫病との戦争」に勝利するために有効なのだろうと感じている。そして実は逆に、そうした制度上の通達なり措置を、私たち自身が望んでいるということもあるのだと思います。
さて、本日の対談のテーマは接触することと、隔離すること、つまり忌避することに関するものでした。誰とどのように接触しまた誰をどのように忌避するかは、文化的に形成され、秩序化・構造化されてきた習慣性や文化であり、それは様々な要因によって流動化するのだと思いますが、対談は、新型コロナの状況下で、私たちの身の回りの接触と忌避というその二つの関係性の配分が大きく揺さぶられているというお話だったと整理することもできるのではないかと思いました。
社会人類学者のラドクリフ=ブラウンの構造機能主義に、「冗談関係」と「忌避関係」という概念があります。前者は、彼の言う「未開社会」で、会えば冗談を言い合って触れ合う間柄のことで、後者は、逆に、会わないように互いに遠ざけ合って、忌避し合う間柄のことです。冗談関係にある相手とは、例えば道でオイがオバに会うと、「あんた、いま発情しているんだろう」という冗談などを飛ばして、ふざけ合い触れ合ったりする。むしろそうすることが期待されていたりします。他方で、忌避関係にある間柄では、口を聞いても目を合わせてもいけないし、目下から目上には無礼なことがあってはいけないので、会いそうな状況になったら会わないように出会いを避けるというようなことをします。誰もが誰とでもと冗談ばっかり言い合っているのでは、つまり触れ合いばかりでは息が詰まるので、それとは反対に、別の間柄では、距離を置く関係を作っておくことで、社会がうまく回っている、統合されているのだと、ラドクリフ=ブラウンは言います。
ラドクリフ・ブラウンの考えを援用すれば、人間どうし互いに接触し合う間柄・場と、忌避し合う間柄・場の両方の配置によって成り立っていた社会秩序が、いま外部から襲い来る新型コロナという未知の力によって撹乱され、揺さぶられているというお話として聞くこともできるのではないかと思いました。
はたして、外部からのコロナの衝撃が大きいのか、あるいは社会統合のシステムがそもそも脆いだけなのか分かりませんが、接触と隔離をめぐって、いずれにせよ、私たちが築き上げてきた社会性はいまとても脆弱さをさらけ出しているように思えます。対談では、そのことをプレカリティ(不安定性)と呼んだのだと思います。プレカリティはスタビリティ(安定性)の対極にある。いま、スタビリティが揺さぶられているのだと思います。
もう一つ、傷つきやすさ、ヴァルネラビリティという言葉も出されました。お話を聞いていますと、プレカリティとヴァルネラビリティは一本で繋がっているという印象を持ちました。そのヴァルネラビリティは、私たちが外にある世界に目を向けないこと、言い換えれば、内側の世界にだけに篭りきっていること、つまり、日本社会にどっぷりと身を預けて安住してきたことによって、生み出されているのではないかと感じます。プレカリティは、仮構されたに過ぎないスタビリティの外部に出ることなく、内側のみに留まって、状況変化に傷ついていることを自らさらけ出す私たち自身によって作り出されているのではないかというのが、お二人の対談を聞いた私の雑駁なコメントです。
一つ、これもコメントの延長ですが、尾崎さんのお話を聞いていて思ったことなのですが、私にも昨年から認知症で施設に入っている母がいて、3月に入ってから、新型コロナ感染の措置として、まったく面会できなくなりました。認知症なので、電話はできません。4月に入ると、毎晩のように母が夢に出てくるようになったのです。夢を40年にわたって記録し続けた明恵上人のように書いているわけではないですが、目覚めたときにまざまざと思い出される夢が続いているのです。隔離された愛には、おそらくはそういった回路もまたあるのではないかと思った次第です。
ハラウェイの翻訳や思想に取り組んでおられる逆卷さんには、一つ質問があります。対談中、少しハラウェイの話が出ましたね。ハラウェイは触角や触手、テンタクラー(tentacular)にかなり強い関心を払っています。例えば、この対談シリーズの初回に話題になった「人新世」に関しても、ハラウェイは、その騒ぎを茶化すように、あまり暗い感じになるのではなく、もう少し楽観的に、そんなことを言ってみても仕方がない、というような言い方をしているのではないかと思います。人新世(アントロポセン)に代わるものとして、触手に頼って動く蜘蛛の比喩を用いて、クトゥルーセンという造語を生み出したりしている。その背景には、ハラウェイの接触、触れ合うことへの関心があると思うのですが、いかがでしょうか?
逆卷 ハラウェイはもともと、言説のレベルで研究していた人で、霊長類学者の言説の研究という形で、現場にはいないような言葉優先の人だったんです。それがサイボーグ宣言以降、だんだんと距離の問題を扱うようになって、人類学者の皆さんもご存知のように2000年代以降、犬と人の関係だったり、最近ももっと多種に開かれた関係を考える上で、自分を含むコンタクトゾーンに注目して考えるようになってきたわけです。その中で、ひとまずハラウェイにとって人新世が仮想敵のひとつになっているのは、間違いありません。クトゥルー新世は人新世に取って代わるものというよりは、人新世に内在しているものとしてある。確かに地質年代は長大な営みであり、人間の活動を近視眼的な制約から解放する意味で有効だと思うのですが、生命の営み自体は、地質年代に縛られることなく続いてきたわけですよね。地質年代というのは人間が地質学的に作った括りですし。
単純化すれば、接触の時空間がクトゥルー新世なら、俯瞰する目を特権化するのが人新世です。クトゥルー新世は、奥野さんがおっしゃったようにピモア・クトゥルフというカリフォルニア州に生息するクモの名前に由来し、クモがもつtentacularity、触手をその関係生成の形象(figure)にしている時空間の名称です。もちろんジョーク含みなんですけど、クトゥルー新世は、最近のマルチスピーシーズ人類学でもよく言われるエンタングルメント(entanglement)、つまり異種どうしの絡まり合いが、ほぼ常態としてある時空間なんですね。生は予め分離された個体どうしのあいだで生じるのではなく、絡まりあった触手状の関係から変態的なものとして生じる。これに対し各状況に応じた接触に由来する、独特の関係生成の現場を無視して、ひたすら上を見上げて俯瞰のポジションの確保に努めてきたのが、グローバリズム、資本主義、人間例外主義という普遍化・俯瞰を是とする地質年代である人新世です。状況に応じた接触と変容の持続に加わらず、そことは無縁であるかのように唯我独尊的に振る舞う人間例外主義が人新世では常態化している。ところが、人新世には継続性がない。「俯瞰という隔離」は生命の持続原理(ongoingness)とは無関係なんですね。クトゥルー新世という接触の時空間は、生命が誕生してからずっと続いているし、これからも人新世が邪魔をしなければ、変態的な生成を繰り返しながら続いていく、生命の持続原理を体現した時空間なんですよ。
500年後とかに学術的に通用するくらい、人新世が長期にわたるかはまだわからないですよね。そこでハラウェイの結論はシンプルです。クトゥルー新世の時空間に人間も加わっていけば人新世は短くなるのではないか。人新世は、実質的には全面的な絶滅と生物多様性の奔出が同居するK-Pg境界(ググってください)のような、地質年代どうしのあいだに挟まれた境界的な時空間になり、それとは異なる新たな地質年代を呼ぶ先触れとなるかもしれない。ハラウェイは、全体主義的に俯瞰する人新世を、状況に応じ常にすでに接触している触手状の思考(tentacular thinking)の実践によって内破する可能性を模索しているわけです。たとえば、バクテリアは農耕民(farmer)だとハラウェイは言うわけです。一般的には人間が農耕文明を作り出したというように語られているわけですけど、いやいや現在人間がやっているのは、大地を搾取する農業という産業(agriculture)であり、農耕(farming)ではない、残っている農耕民はバクテリアぐらいでしょう、というようなことをハラウェイはいう。バクテリアがいる、人間を越える触手状の多種が絡まりあう時空間に人間も入れ、という。
あるいは接触に関しては、ハラウェイはあやとりの形象を出してます。あやとりって言語的なコミュニケーションじゃないわけですよね。糸で形を作って、それを受け渡すということの繰り返し。接触しなければできない、しかしこれは、人間以外の生きものすべてが、それぞれの置かれている状況に応じて参加することのできる触手状のコミュニケーションなんですね。人間だけを特権視する、俯瞰する視覚に照準を合わせる人新世の物語り行為に対し、多種の触手どうしの接触、地べたを這うようなあやとりに根ざした物語を作ろうというのがクトゥルー新世ですね。[8]
HZ 今のお話に尾崎さんからは何かありますか?
尾崎 めっちゃ難しくて、正直、ご質問の意味をどれだけ私が理解できているのかわからないんですけど、んー、そうですね。やっぱり多種との絡まり合いということについて、私はリテラシーがなさすぎるなと感じます。私にとっては人間と人間の絡まり方にすごい興味がある。だから、今お話してたバクテリアと人との絡まり合いのような話も私が翻訳すると、バトラーの相互依存、つまり、人間の生がこの社会においては相互に依存してるという話の延長線上の話になってしまうんです。たとえば母の鼻に入っているチューブはきっと途上国の誰かの成果であるだろうとか、母が摂取するどろどろの栄養には豚由来のゼラチンが使われているようですが、その豚を飼育している人の賃金はきっと絶望的に買い叩かれているだろうとか、そういう視点しか私はまだ持てていないというか……。言い換えると、そういう国際的に分業化された労働の産物が、母の体内で彼女の命を支えていたりすることについての認識だけは、私にもあるというか……。実際、私もそれなしには生きていかれへんような相互依存的な関係性がすでにあって、そういうものを多分、他の種への依存性へと拡大した話なんやろうと想像しながら、いい加減に聞いていました(笑)
逆卷 プレカリティというのはそのようにして繋がっていくんじゃないですかね。まあ、バトラーはどうしてもヒューマニズムの人なのでね(笑)。ただなんか最近は、ハラウェイに寄ってきてるところはあって、『アセンブリ』においてはハラウェイにも言及してるし、物質であったり他の生物であったり、そういうものにも申し訳程度に言及はしてる。だから、ハラウェイの議論ともプレカリティなんかの部分では繋がっていく気はしていて、さらに、そのプレカリティの話はアナ・チンなんかの議論にも繋がっていく。アナ・チン『マツタケ』原書のタイトルにあるように、エンド・オブ・ザ・ワールド、突端ですよね。[9] そうした絶滅の淵にあるようなプレカリティにおいて、エンドユーザーたちは種の隔てを越えて協働しつつ考えていく必要があるのかなとは感じます。
Q2 大変興味深い話をありがとうございます。相互依存的な関係性のネットワークの中に持ち込まれる、死のリスクについて、お二人にお伺いしたいです。私は普段アメリカに住んでて、今はこのコロナ騒ぎで鎌倉に帰ってきているのですが、2週間前の3連休の時は、鎌倉の小町通りというところは観光客で溢れかえっていて、まるで竹下通りのようでした。あと私は今も普段、普通に外に出て、活動をしているんですけど、エクセルシオールなどのカフェに行くと、驚くほどご高齢の人たちが集まっていて、マスクもせずに楽しそうにおしゃべりをされてるんです。それを見た私の最初のリアクションとしては、この人たちはなんでこんな時にここに集まってきてるんだ、なんて無防備でなんて情弱な人たちなんだ、というものでした。
でも、よくよくそこで立ち止まって考えてみると、おそらく、死についての捉え方って人によって全然違うんだろうな、と思ったんです。つまり、それは不平等に配分されている可傷性の問題とつなぎあわさっていて、普段、死の近くで生きてる人ほど、また普段のQOLへの期待が低ければ低い人のほど、死の捉え方が、そうではない人と違ってくるんではないかとそう考えたんですね。それと共に、3.11の時のことをちょっと思い出しました。現在は私はパートナーと一緒に住んでいるのですが、当時その彼は原発事故が起きて、すぐ避難する形でアメリカに飛び立ったそうなんです。一方の私がその時どんな心境だったかっていうと、もう日本も滅びるんだから、一緒に滅びればいいやっていう感じでした。それで、3.11のリアクションの違いみたいなものをその後に二人で話しながら確認していくうちに、あ、死に対する捉え方って全く違うんだって思ったんです。
私は現在、大学院でクィア神学を専門に勉強しているんですけど、いろいろなクィアな性的実践を学んでいくうちに、死がすぐそばにあることを享楽する、死が自分の間近にあるからこそ楽しいし嬉しいし気持ちいいという現象があるってことを知り、それについて考えたりしています。たとえば会社員がサイバーセックスで犬のように扱われていたとして、その動画がもし会社に流出したら、社会的に抹殺されてしまうかもしれず、その行為には社会的な死のリスクが伴っているわけです。でも、それでもやめられない、いや、だからこそ楽しいんだというような現象もある。そのように人の死に対する捉え方は様々であるにも関わらず、お上の人が死は絶対に悪で、生きることがいいに決まってて、生きてることが丸儲けで、だからみんな家を出るのをやめましょうというように一刀両断するというような暴力的な健全さについて、私はとてももやもやしたものを感じているんです。こうした点について、お二人はいかがでしょうか。
尾崎 今のご質問は私にとってすごい興味深かったので、この質問もまず私からお答えされてください。一つは死に対して身近な人ほどリスクをどんどんとっていくって現状があることについてですが、それは喜ばしいことであると同時に悲しいことであると私は感じています。というのは、現在の新型コロナウイルスの感染拡大下において、まったくビビらずに外に出て誰とでも触れ合えるっていうのは、冒険的だし、自分や自分と他者との関係の可能性を広げる挑戦であるとは思います。と同時に、そうした冒険ができるのは、その人がそもそも最初から「死んでもいいや」という生を生きてるからこそできることでもあるのかなとも感じる。そこはすごい両義的なことやなと思います。ただ、私としてはどっちかっていうと前者のリアリティが好きなんです、たとえば私の今の状況に絡めて言えば、私が今、無理して母に会えば母を殺すかもしれないんですよね。私が母にウイルスを運んでしまうかもしれない。でも、だとしても、やっぱり会いたいという気持ちもある。それは私が彼女を殺すことでもあるかもしらんし、彼女が私を殺すことでもあるかもしらんけど、母と私との愛とケアの関係の最大の目標をお互いのリスクをゼロにすることだと仮定したうえで互いの接触をなくしてしまった時に、それが私にとって人間らしいことなのかというと、全然違う気もしているんです。だから、リスキーなセックスとかリスキーな接触っていうのを常に悪いものとして考えるのには違和感があるし、そうした冒険だからこそできる触れ合いみたいなものもあるんだろうと思います。
ただ、そうした肯定的な側面と関連されての二つめなのですが、ご質問者さんのパートナーとの関係にあるような、自分は死んでも別にいいけど、相手はどうだか分からないという問題はすごく難しくて、それこそ私の母は今、話すことができへんわけやけど、もし話せてたら、「私にそんなもん持ってこんといて」って言うかもしれないわけです。あるいは、明らかに淋病を持っている誰かに「生でセックスしよう」って私が言われたとして、そのオファーを受け入れられるかっていったら、関係にもよるとは思いますが、私だってその冒険に肯定的なリアクションをとれないかもしれない。関係性や状況に依存しすぎていて、どの程度リスクを引き受けて冒険するかというのは答えがない問題かもしれません。
ただ一つ、三つめとして言えるのは、語り始めがないと語り直しもありえへんということです。「淋病を持ってるけどセックスしよう」というオファーが絶対的に倫理に反するとしてしまうと、セックスの可能性自体がどんどん閉じていくんじゃないか、とは思うんですよね。つまり、死の可能性がある限り接触はすべきではないって言い出したら、どんどんと相互依存的な生の豊かさっていうか、いろんな他なるものとの触れ合いのなかで生かされていることの生の分厚さがなくなってしまうとは思います。死ぬかもしれないという享楽に身を任せて生きろとはよう言えませんが、生きながら死んだり、死にながら生きたりという可能性を簡単に見逃さずに、リスクと接触とのバランスを考え続けることはできるんじゃないかって思いますね。
逆卷 僕の方からの回答としては、今日は割と、プレカリティを逞しく生きようみたいなポジティブ方向の話が多かったのかなって思いますが、基本的に生の背後には必ず死があるんですよね。偶然性というのは、必ずしもポジティブに働くと決まってないからこそ偶然性なわけで、そこにはたとえば接触したがゆえのDVみたいなことも起こるわけじゃないですか。接触というのは自らの行動を撹乱していく一つの契機のようなものなんで、それをどの程度の機会持つのかというのも、それぞれが考えるべきことなんだと思います。ただただ危険な方に触れるのがロックだパンクだって言ってるんだとしたら、それはただの馬鹿なんじゃないかとも思うわけですよね。そういう形じゃなくて、その危険さがどれくらい危険なものなのかというのをちゃんと考えて、共有していくという方向に愛があると思うし、ケアがあると思う。日菜子さんとお母さんの関係のようにリスクの分かち合いに非対称性がある場合は難しいけど、無謀ではなくて、危険さを理解し、その上で行動するというのが大事かな、と。そのエクセルシオールのおじいちゃんたちがどうだったかは僕には分からないですけど(笑)
Q3 素晴らしい対談をありがとうございました。自分は東京工業大学の大学院で人類学を学んでいるものです。この対談前に東工大の北村匡平先生がツイッターで「人との接触を今ほど意識したことはない」というところから始まるツイートをいくつかされていて、レジの支払いだったり商品の受け渡しだったり、ウイルスは私たちの生活における「触れること」に関する意識を変質させている、ということを語られてて、それは結構、自分の問題意識の中にもあることだったので、考えさせられたんです。文化人類学を学んでるものからして、今回のテーマである「接触と隔離のあいだ」に思い出されるのは、アンダマン諸島の北センチネル島に暮らすセンチネル民族、世界で一番凶暴な部族とよく言われる部族のことです。彼らは立ち入ろうとする侵入者たちに対して、弓で矢を撃ったりするとされているわけですけど、そういう外からやってきた人たちを攻撃するということが、今日ではまったく他人事じゃないなという気がするんですね。ただでさえ、現在は「リキッドモダニティ」という言葉もあるように、色々と価値観が多様化している中で人々が孤立しやすい世の中なのに、それがますます酷くなっていくんじゃないか、と。それこそ権威主義的パーソナリティみたいな人たちも増えてきていて、どんどん隔絶化が進行している気もします。その中で、接触と隔離のあいだをどう考えればいいのか、たとえばここに集まっているような頭のいい方々は、この状況がひどくならないようにするためにはどういう働きかけが可能だと考えているのかなと思っていて、あらためてお聞かせいただきたいなと思ってます。
尾崎 じゃあ「頭がいい方」じゃない方から答えますね(笑)。この状況に対する処方箋みたいなものは私には出すことはできなくて、見知らぬものとか、馴染みのないものとかに対する排斥感情や忌避感情みたいなものと自分がどういう風に向き合っているかというレベルでしか答えられないかなって感じたんで、私の手元にある感覚でお答えしたいと思います。レズビアンでもある私にとっては異性愛者の男性とかって完全に見知らない、馴染みのない存在なんです。ただ、そういう見知らない存在としての異性愛者の中にも、たとえば、こういう服装の女性に愛着があるとか、物語に登場する女性のこのジェンダー化された言い回しがたまらんとか、やっぱり部分的に重なるところを見つけることはできると思うんです。セクシュアリティの次元だけでなくて、他にもたとえばエスニックマイノリティの人たちも、私にとっては見知らぬ者やったり異者やったりするんやけど、でもコンビニではよくレジ打ってはるよね、みたいなのはあって。そういう、なんとなく繋がってしまっていることとかがある。
つまり、これは自分に馴染みがあるとか、逆にあれは自分には他者にしか思えないって意識のレベルの外側で、奇妙な類似性が存在していたり、実際の接触が起こっていることはあると思うんです。あるいは逆に、家族を始めとする身近にいて見知っている人たちがいきなり全然見知らぬ顔を見せてくるということもあるわけです。意識のレベルでそれぞれの隔絶化がどれだけ進んでいったとしても、実際の関りはなくならないんじゃないかなって思うんです。でも、実際には他者にすでに触れてしまっている現実はあるにせよ、意識のレベルではそうした経験がなかったことになっていたり、もっと先鋭化した形では、質問者の方もおっしゃっていたような、自分との類似性を秘めた目の前の人を、関わりたくない他者とか遠ざけたい異者と見なして激しく排斥することもあるだろうと思います。だからこそ、これは私の主観的な意識の問題でしかないけど、近さと遠さ、見知ったものと見知らぬもの、はっきりと線引きされた内側の自分と外側の他者みたいな二極を、語ることや物語を書くことを通じて混ぜ返していったり、撹乱していくような実践はやっていきたいかなと思っています。そうすることが結果として、意識の外側の実際の接触の可能性を広げてはくれへんかなあと、根拠の不確かな空想をしたりもしています。
逆卷 僕も、全体とか、社会とか、国家全体とか、自治体全体とか、そういうレベルでどうしたらいいのかとかはよく分からないです。考えるだに、見知らぬ人たちが多すぎるわけですよね。見知らぬ人たちが多すぎる状況において、その見知らぬ人たち一般について考えるというのはちょっと難しくて、それよりは見知ってる人の見知ってる部分について考える方がいい気がしてます。よく6人繋げていけば世界の誰とでも繋がれるみたいなことを言うじゃないですか。それくらいの感じでゆるく考えるのがいいかなと思う。たとえば、僕が友達の友達の友達のことは大嫌いだとして、でも、僕の友達の友達は、そいつのことが好きなわけですよね。必ずしも「人類皆兄弟」的な繋がり方をする必要はなくて、僕が好きな人を繋いでいったら、コミュニティ全体としては嫌いな奴も混じってくるわけです。僕の好きな奴が僕の嫌いな奴と繋がってくれているっていう状態、そういう感じでいいんじゃないかなと思う。自分が全員のことをどうにかしなきゃいけないとか、共同体全部でどうにかしなきゃいけないって考えると難しいと思うので、そこはもっと身近な人の力を信頼していいんじゃないかな。自分の繋がってる人たちの見る力、接触する力を信じるところから始めてもいいような気がします。
HZ ありがとうございました。最後のお二人の回答はとても面白くて、おそらくお二人とも抽象的な他者についてではなく、具体的な他者との関係性に視線を向けようということをおっしゃっていたんだと感じました。顔の見える他者との部分的つながりを探っていくことで、新たな連関を生み出していく他ないんじゃないか、と。それは差別や排除がすでにある社会で、現状追認的に感じてしまう人もあるいはいるかもしれませんが、最後に逆卷さんがおっしゃっていた「人類皆兄弟」というような大前提のもとに、具体性を欠いた「繋がり」を闇雲に賛美するということが、逆に人々に接続疲れみたいなものを起こしてしまっているように感じられる現状を踏まえると、実践的にも効果があるんじゃないかと個人的には感じましたし、おそらく、それは今日のお話全体に繋がるのだとも思います。まずは「隗より始めよ」ですね。
それでは時間が来ましたので、これにて終了とさせていただきます。みなさん、ありがとうございました。
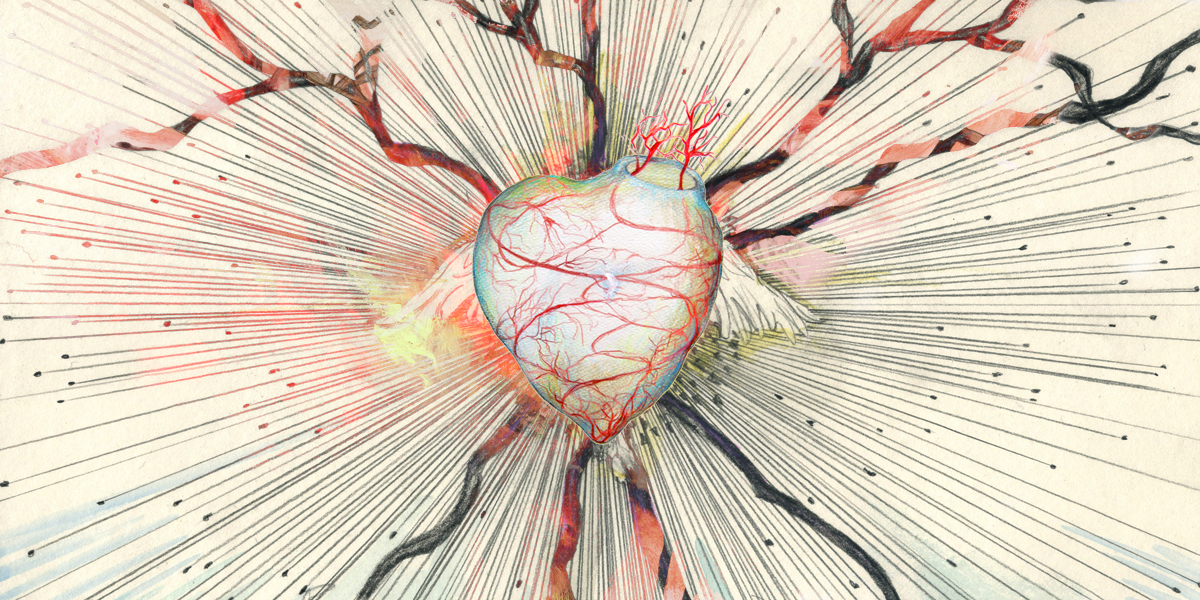
構成|辻陽介
ドローイング|大小島真木
【逆卷しとね・註】
[1] contingere は、「共に、一緒に」(with, together)を意味する接頭辞com- (con-)と、「触れること」(to touch)を意味するtangereの合成語。たとえば、Online Etymology Dictionary https://www.etymonline.com/を参照。辻陽介による趣旨説明文(https://www2.rikkyo.ac.jp/web/katsumiokuno/multi-species-workshop38new.html)の冒頭、聖書からの引用に対応させるなら、現在は、ラテン語聖書「ヨハネによる福音書」20章17節に登場する「われに触れるな」(Noli me tangere)を全面化する状況にあると言えるだろう。
[2] 2020年4月23日23:30の時点で、新型コロナウイルス感染症による国内の死者数は328人(『朝日新聞デジタル』https://www.asahi.com/articles/ASN4S03VRN4RUTIL02K.html)、2020年2月の月間交通事故死者数は509人(警察庁 「交通事故統計月報」
https://www.npa.go.jp/news/release/2020/20200313001jiko0202.html)、同年3月末までの自殺者数は4,749人である(警察庁 「自殺者数 令和2年の月別自殺者数について(3月末の速報値)」https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/R02/202003jisatusokuhouti5.pdf)。
[3] ジュディス・バトラー『アセンブリ――行為遂行性・複数性・政治』(佐藤嘉幸+清水知子訳、青土社、2018年)。
[4] 遺伝子の水平伝播と共生については、拙稿「喰らって喰らわれて消化不良のままの「わたしたち」――ダナ・ハラウェイと共生の思想」(『たぐい』vol. 1 亜紀書房 2019年 55-67頁)と「未来による搾取に抗し、今ここを育むあやとりを学ぶ――ダナ・ハラウェイと再生産概念の更新」(『現代思想』2019年11月号 「反出生主義を考える」209-21頁)を参照。
[5] ウイルスについては、たとえば河岡義裕+堀本研子『インフルエンザ パンデミック 新型ウイルスの謎に迫る』(講談社、2009年、kindle)、武村政春『生物はウイルスが進化させた 巨大ウイルスが語る新たな生命像』(講談社、2017年、kindle)、山内一也『ウイルスの意味論――生命の定義を超えた存在』(みすず書房、2018年)を参照。アクセスしやすいものとしては、谷口清州「ヒトとウイルス」共生と闘いの物語」(インタヴュー構成:飯塚りえ『ヘルシスト』220 https://www.yakult.co.jp/healthist/220/img/pdf/p02_07.pdf)など。
[6] コロナ時代のケアについて論じた浜田明範「新型コロナ「感染者を道徳的に責める」ことが、危機を長期化させる理由 必要とされる「ペイシャンティズム」(『現代ビジネス』 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/71660)と「ようこそケアの世界へ (COVID-19と文化人類学発表資料)」(https://www.academia.edu/42357846/%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%9D%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%B8_COVID-19%E3%81%A8%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BA%BA%E9%A1%9E%E5%AD%A6%E7%99%BA%E8%A1%A8%E8%B3%87%E6%96%99_)、及び
人間世界にとどまらないケアの問題について論じたMaría Puig de la Bellacasa. Matters of Care: Speculative Ethics in More than Human Worlds (U of Minnesota P, 2017)を参考にしている。
[7] 遠隔ビデオ通話の例証は、斎藤帆奈から遠隔通話を介して得た。
[8] HAGAZINE掲載のハラウェイのインタヴューの拙訳(https://hagamag.com/uncategory/4293)、及びその訳註に出てくる文献、とりわけ『現代思想』2017年12月号掲載の「人新世、資本新世、植民新世、クトゥルー新世――類縁関係をつくる」(高橋さきの訳 http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3102)を参照のこと。
[9] Anna Tsing. The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. PrincetonUP, 2015. 邦訳はアナ・チン『マツタケ――不確定な時代を生きる術』(赤嶺淳訳、みすず書房、2019年)。同書の訳者赤嶺淳と辻陽介の対談採録(https://hagamag.com/uncategory/7160)も参照。
【尾崎日菜子・註】
[i] https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200406-00000130-kyodonews-pol
[ii] https://www.google.com/amp/s/mainichi.jp/articles/20200313/k00/00m/010/303000c.amp
[iii] https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/covid-19-nishiura
[iv] 不適切だと指摘があり、西浦は記事の表現について謝罪している。 https://twitter.com/nishiurah/status/1248870244245897216
✴︎✴︎✴︎
逆卷しとね さかまき・しとね/学術運動家・野良研究者。市民参加型学術イベント 「文芸共和国の会」主宰。専門はダナ・ハラウェイと共生論・コレクティヴ。「喰らって喰らわれて消化不良のままの「わたしたち」――ダナ・ハラウェイと共生の思想」(『たぐい vol.1』 亜紀書房)、Web あかし連載「ウゾウムゾウのためのインフラ論」、その他荒木優太編著『在野研究ビギナーズ 勝手にはじめる研究生活』(明石書店、2019 年)、ウェブ版『美術手帖』、『現代思想』、『ユリイカ』、『アーギュメンツ#3』に寄稿。山本ぽてとによるインタヴュー「在野に学問あり」第三回。
尾崎日菜子 おざき・ひなこ/フェミニズム活動家、小説家。ジェンダークィア。小説作品「蜂蜜の海を泳ぐ——地上の小魚」を『吟醸掌篇 vol.3』に寄稿。(https://nohoshobo.stores.jp/items/5dbe52e2220e75763138acad)
✴︎✴︎✴︎
〈MULTIVERSE〉
「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー
フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介
「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄
「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生
「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美






















