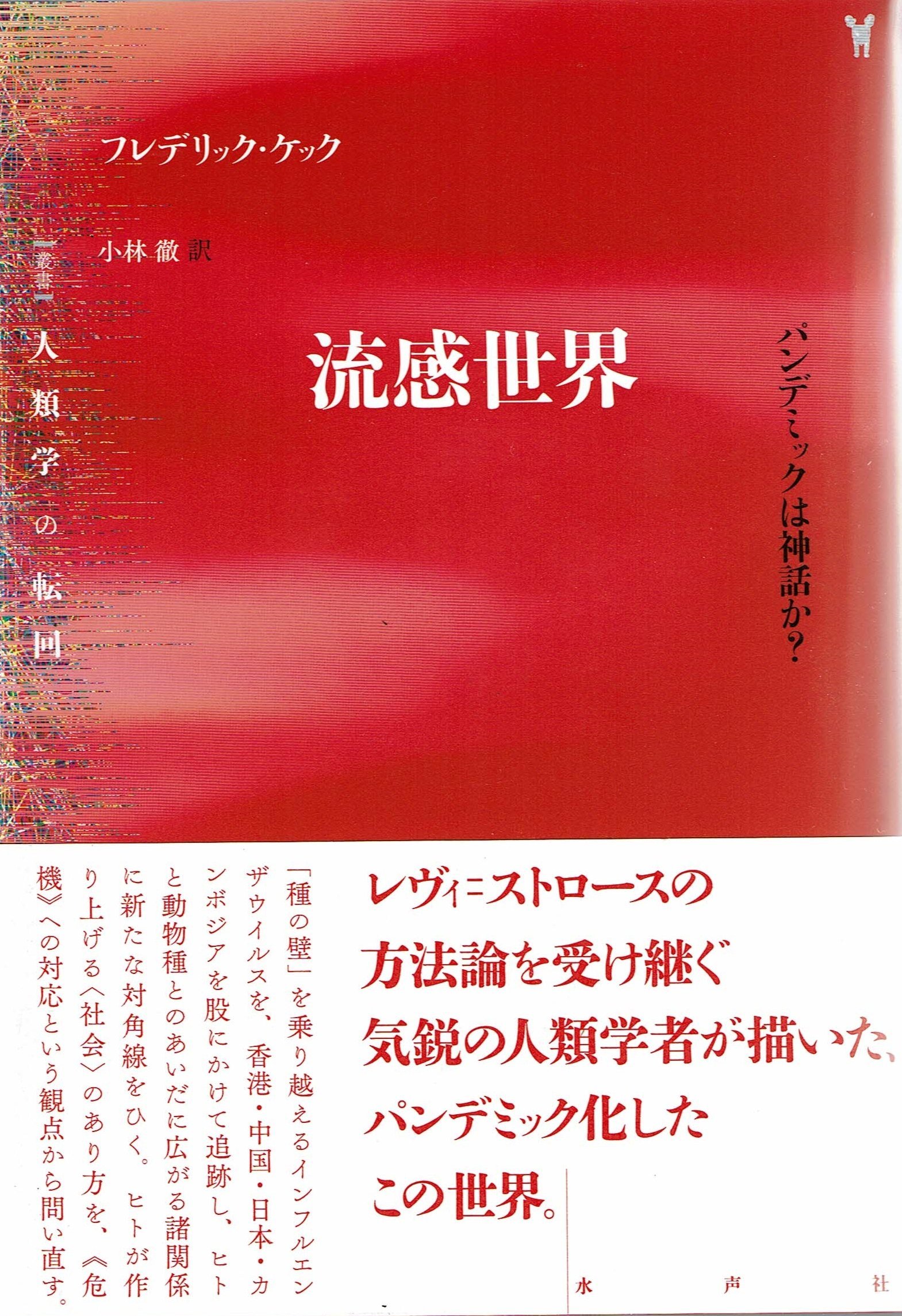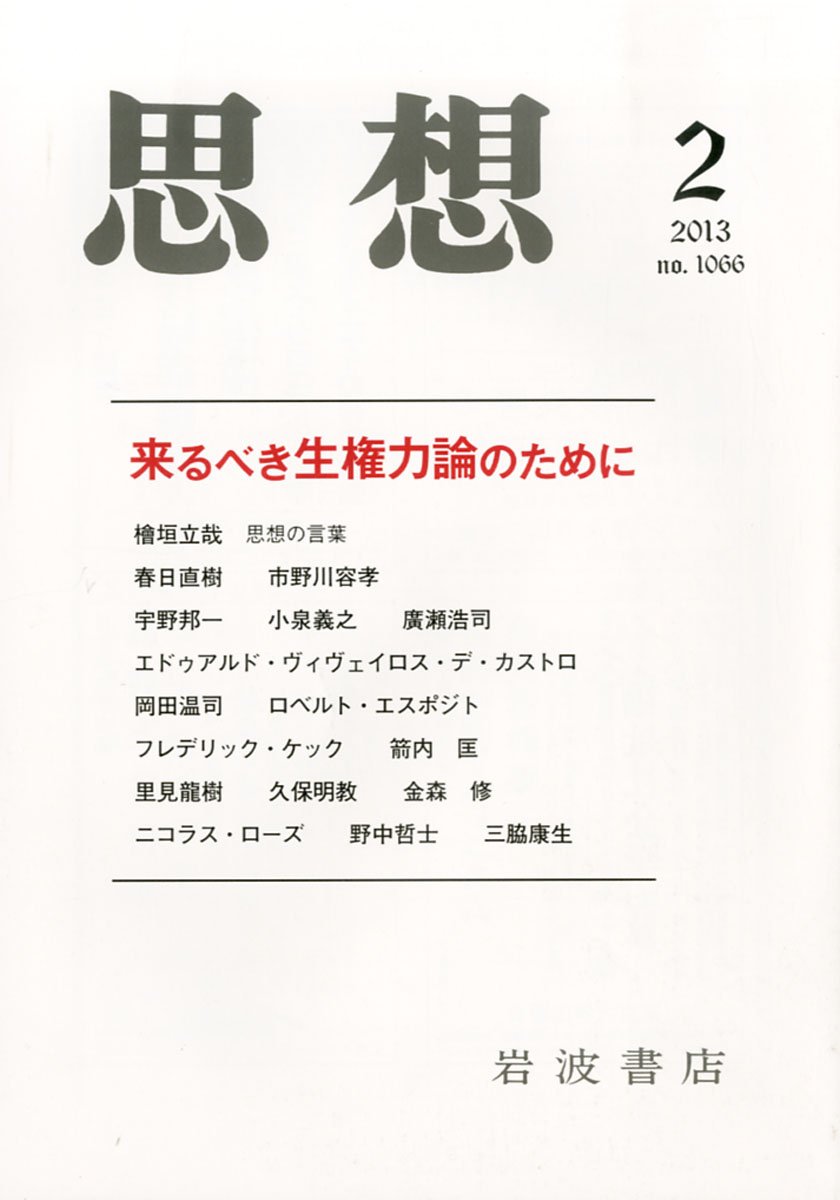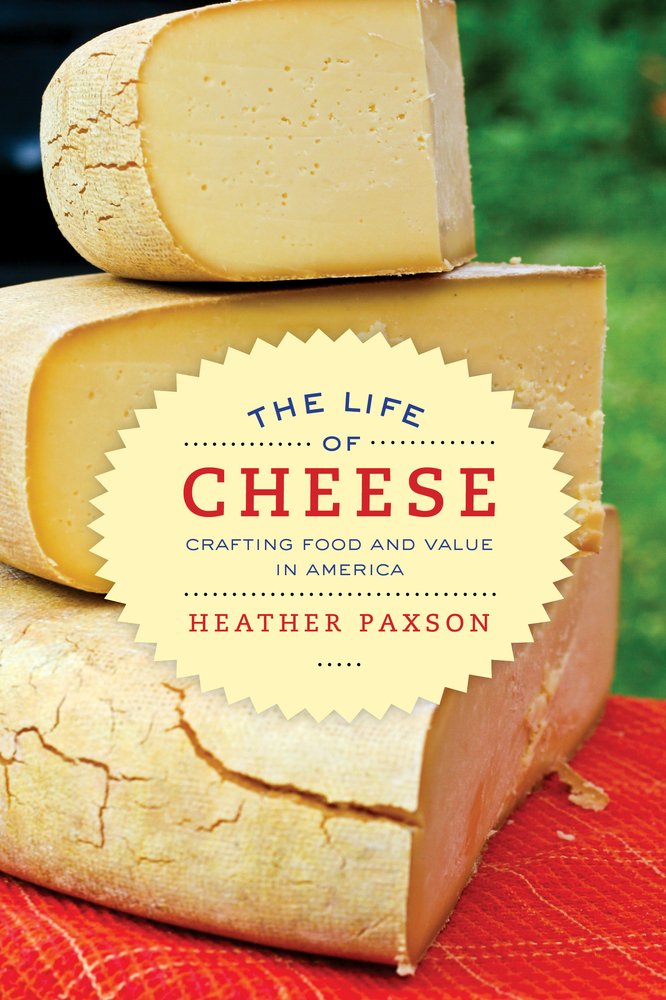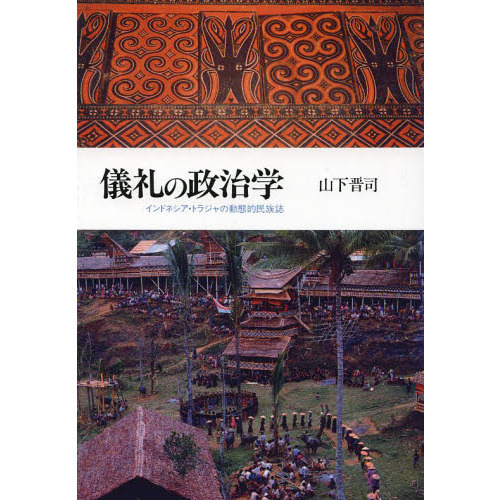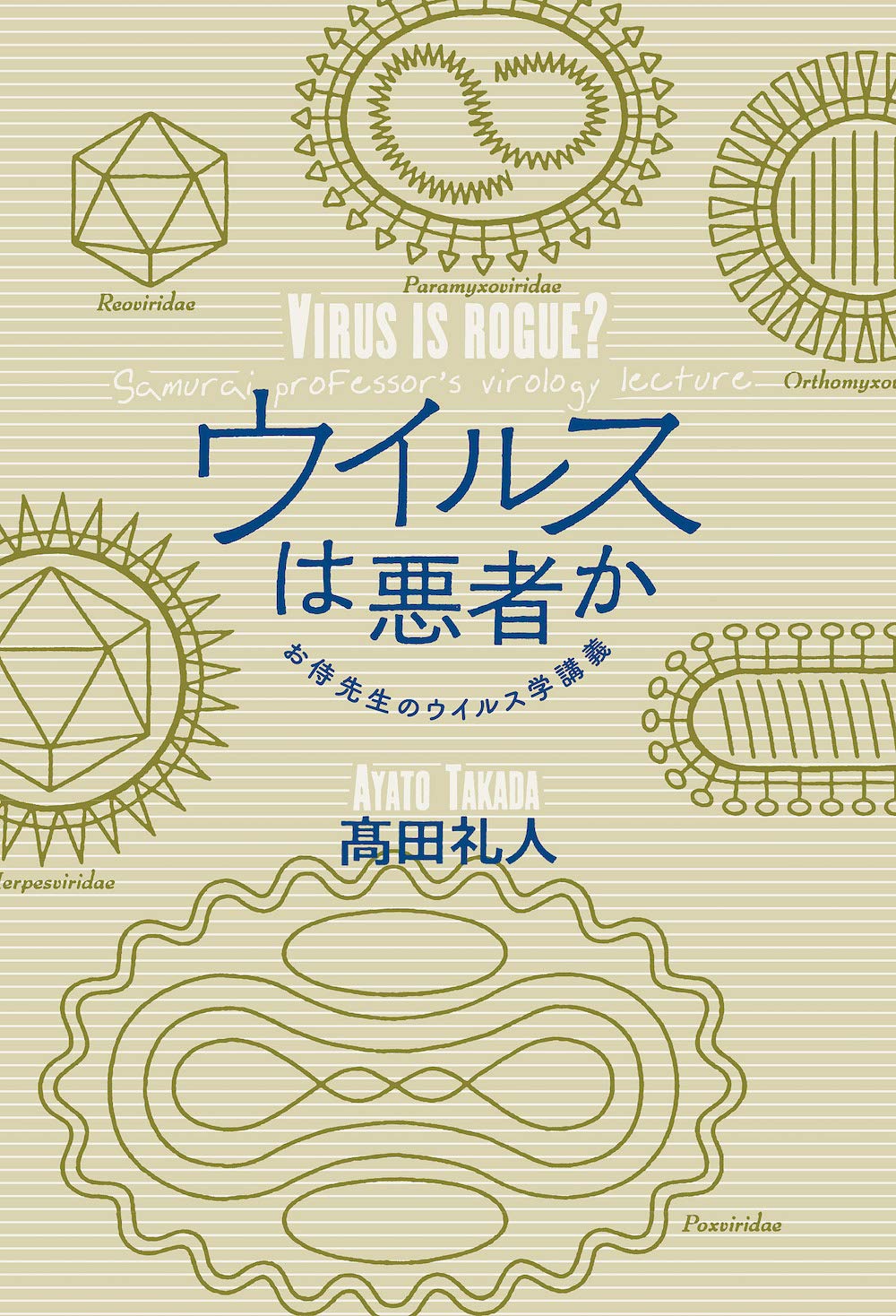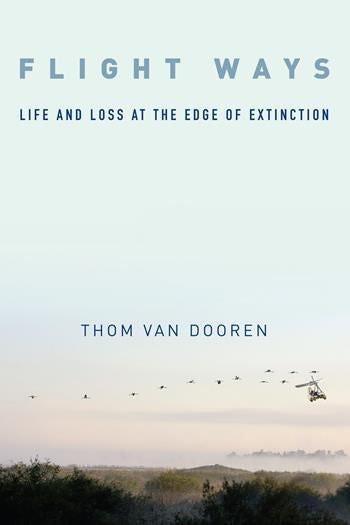シリーズ『COVID-19〈と〉考える』 |TALK 01|奥野克巳 × 近藤祉秋|ウイルスは人と動物の「あいだ」に生成する──マルチスピーシーズ人類学からの応答
マルチスピーシーズ人類学研究会の「 COVID-19を分野横断的に考える 」シリーズ第一弾。新型コロナウィルスを始め、人獣共通感染症と言った時の人間や動物、さらには細菌やウィルスが、マルチスピーシーズ人類学の光源をあてて眺めた時にどのように見えるのかをめぐって。

この記事は、マルチスピーシーズ人類学研究会の「 COVID-19を分野横断的に考える 」シリーズの第一弾として4月2日に行われた、文化人類学者の奥野克巳と近藤祉秋によるビデオ対談(司会:辻陽介)の内容を、記録、再構成、加筆したものです。
学術界において、動物や植物だけでなく、細菌や、場合によってはウイルスなどの微生物もこの生けとし生けるものの範疇に入ると捉えようとするのが、「多種の人類学(マルチスピーシーズ人類学)」です。それらはすべて、他者であり、私たちの隣人です。マルチスピーシーズ人類学は、他者である多種を視野に入れて、人間だけが例外的な世界の住人だとする人間至上主義の見方とは異なる世界の可能性を考えようとします。
連続対談シリーズの第一弾となる今回は、新型コロナウィルスを始め、人獣共通感染症と言った時の人間や動物、さらには細菌やウィルスが、マルチスピーシーズ人類学の光源をあてて眺めた時にどのように見えるのかをめぐって、話し合いました。
Drawing by Maki Ohkojima
Text by Yosuke Tsuji
「人類 vs ウイルス」という図式への違和感
HZ みなさん、おはようございます。HAGAZINEというウェブメディアの編集をしております辻陽介と申します。本日はこれより行います文化人類学者の奥野克巳さん、近藤祉秋さんの対談の司会を務めさせていただきます。お二人は兼ねてより「マルチスピーシーズ人類学研究会」を主宰されてきましたが、今後、数回にわたって行う予定のCOVID-19をめぐる対談シリーズは、マルチスピーシーズ人類学研究会とHAGAZINEの共催によるもので、今回はその第一回目となります。よろしくお願いします。
さて、みなさんもご存知の通り、現在、新型コロナウイルス=COVID-19の世界的なパンデミックに際し、各国政府が出入国に厳しい制限を設け、大型都市をロックダウンするなどの戒厳令を発布する緊急事態となっています。この問題に関しては、ここまで各国首脳が競うように声明を発表していますが、とりわけ個人的に強く印象に残っているのは、ボリス・ジョンソン首相の集団免疫戦略に関する「自粛行動は長期にわたって維持できない。ゆえに社会リスクを疫学的に最小化する」という、つまりは「死を覚悟してほしい」という趣旨の発言であったり、フランスのエマニュエル・マクロン首相による「我々は戦争状態にある」という、あたかも人類とウイルスが全面戦争を行なっているかのような、物々しい宣言です。
確かに、現時点(対談が行われた4月2日の時点)で新型コロナウイルスの感染者数は世界で約830000人、死者数は40000人以上(記事が掲載された4月20日の時点では感染者数は約235万人、死者数は16万人以上)と、予断を許さぬ状況であるのは間違いありません。自分とて人類の一人として「生存」こそを最重要視しなければならないという考え、立場そのものには、いささかの異論もないです。
ただ、「生存」といった時に、果たしてそれが個人としての生存なのか、共同体としての生存なのか、国としての生存なのか、という疑問も同時に生じます。あるいは種としての、さらには多種としての生存という視座もありえることでしょう。このように「生存」という言葉の主体をどう捉えるかによっても、考え方、動き方は大きく変わってくるはずですし、また、マクロン首相の言葉に見られるような、「人類vsウイルス」という対立図式に拘泥することが、果たしてウイルスという生物とも無生物ともつかぬ存在と対峙していく上で、真に有効な見立てなのかどうか、そこにもやや疑問があります。
たとえば、現在においては哺乳類の遺伝子の大半が、実はウイルスからできているということが明らかになっています。一例を挙げれば、哺乳類にとって極めて重要な胎盤の形成には実はウイルスが深く関与しているとされています。あるいはウイルスでなくとも、私たちは大腸菌などの細菌が体内に存在しなければ自力で食物を消化すらできないということも、つとに知られた事実です。こうしたいくつかの例だけを見ても、人類とウイルス、人類と細菌類を単に対立するものとして考えることができないということは明らかでしょう。
また、新型コロナウイルスに関しては、すでに人獣共通感染症であることが分かっています。20世紀以降、社会不安を巻き起こした感染症はインフルエンザ、HIV、エボラ出血熱を始め、多くがこの人獣共通感染症です。要するに、感染症拡大についての物語には、人とウイルスだけでは登場人物が不足しているんです。その物語には本来、非常に多くの生命種、アクターが登場して然るべきであり、「人類 vs ウイルス」という図式は、その上でも単純化された視点だと言えると思います。サイエンスライターのカール・ジンマーが「ウイルスプラネット」と呼んだこの惑星で、この先も人類が「生存」していくためには、安易な対立図式を用いるのではなく、本来、そうしたウイルスを含む多種多様で複雑な種の絡まり合いを、きちんと紐解いていく必要があるのではないか、そうした問題意識もあります。
とはいえ、この場を、いま目の前で生じている被害を無視する形で述べられる理想論のための場にするつもりもありません。この場は、人類がこの惑星で、多種とともにサバイブしていくための強かな戦略会議の場でなければならないとも感じています。その戦略を模索する上でも、先ほど述べたような理由から、まずアントロポセントリック=人間中心主義的な存在論を排する必要があるのではないかと思うのです。そして、まさにその点において、「モア・ザン・ヒューマン=人間以上」の生命の絡まり合いをこれまで考察してきたマルチスピーシーズ人類学の視点が、非常に有用なものとなってくるのではないかと考えています。
あるいは、奥野さんたちがこれまで日本に紹介を続けてきた、人類学の新しい潮流、存在論的転回なども、ウイルスとの向き合い方に関して、多くのヒントを与えてくれるのではないかと感じています。ありていに言えば、我々は多自然主義的な視座に立ち、たとえばエルクを狩るユカギールのように、ウイルスのパースペクティブへとミメーシスする必要があるのではないか。個人的にはそのようなことも思っています(※)。
※人類学の新しい潮流、「存在論的転回」については、HAGAZINE内の記事「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”を参照。
またもう一つ、今回の新型コロナウイルスをめぐっては「インフォデミック」なる言葉も生まれています。この言葉は、SNSなどを通じて正しい情報とフェイクニュースが入り混じって拡散されることで起こる社会的な混乱状態を指すものですが、今日では実際に、人々がウイルスという肉眼では見えないものを恐れ、その恐怖によって、社会そのものが再編されつつあります。目に見えない世界が存在感を強め、人々が真偽を超えて、その世界への恐怖に突き動かされているという状況は、ある種、世界の再魔術化とも言い得るのではないでしょうか。マナや精霊など、不可視なものをめぐる社会関係を調査してきた文化人類学は、こうした面でもその知見を大いに発揮できるのではないかと考えています。
前口上が長くなってしまいましたが、僕としてはそのような問いとともに、この研究会の司会に携わらせていただいています。というわけで、そろそろ対談にうつりましょう。果たして、現在まさに起こっているCOVID-19のパンデミックと、それが引き起こしている社会的混乱に対し、文化人類学はどう接近することができるのか。奥野さん、近藤さん、よろしくお願いいたします。
人類学は「人獣共通感染症」をどう捉えてきたのか──フレデリック・ケックの『流感世界』から考える
奥野 ありがとうございます。まずは今、辻さんが語ってくれたことに関して反応させていただきたいと思います。基本的には全くおっしゃる通りだと感じました。一つは辻さんも指摘されていた「人類 vs ウイルス」という図式への違和感ですね。これについては私自身も非常に不毛だと感じています。現在、COVID-19が雲のように我々を覆っていて、非常に息苦しい日々が続いており、今後ますますそれが加速化することが予想されるわけですが、この対立図式に沿って考える限り、事の本質を見ることはできないでしょう。いかに、この二項図式を乗り越えていくのかというのは、本研究会の一つの大きなテーマだと思います。
もう一つ、辻さんの趣旨説明で気になった点として、「生存」という言葉が何度か出されました。「サバイブ」という言葉も出てきましたね。そこに関して、辻さんは人間の生存を問題化された。私自身も基本姿勢としてそこに異論はないのですが、ただ、ここは丁寧に論じていかないといけないポイントだとも同時に思っています。これは後ほど立ち戻ってみたいと思っていますが、たとえば禅師である内山興正は「生」に関して、「生命的地盤」と「生存的地盤」の二つがあるのだというふうに分けて考えています。この二つの言葉に基づいて内山は語ります。
内山禅師によれば、我々はいつも「生きる」ということを「生存的地盤」で考えています。つまり、生存するためにはどうあるべきか、というふうに。生存ベースで考えていくと、生存にはいい学校を出て、いい会社で働いて…といった様々な我執が起きてきます。それに対し内山は、人間にとってより本質的なのは「生命的地盤」だと言っています。では、「生命的地盤」とは何か。端的に言えば、生を考える場合、死というものが必ず裏側にあるのだ、ということです。生死(しょうじ)、つまり生と死は一体化して、生命なのです。そこのことを考えることが非常に大切であって、それが人間を中心に物事を考える人間中心主義を乗り越える一つの手がかりになるのではないか、と私は考えています。
前置きが長くなりましたが、ここではまず人類学が感染症をどう捉えてきたのか、について話してみたいと思います。辻さんの説明にもありましたが、このCOVID-19は「ズーノシス」、つまり「人獣共通感染症」だと言われています。では、人類学において、この人獣共通感染症がどう捉えられてきたのか。今日、その問題に関して最も影響力のある人類学の研究書の一つに、フレデリック・ケックという人類学者の書いた『流感世界』という本があります。原著が出版されたのは2010年です。それは、感染症をめぐって生じる「生権力」、あるいは「生政治」について(※)どういうふうに考えるのかということに密接に関わっている。まずはこの本を手掛かりとして少し考えてみたいと思います。
※生権力、生政治…フランスの哲学者であるミシェル・フーコーの概念。“フーコーによれば、死に対する権利(殺す権利)を一つの特徴とする古い君主制の主権に対し、近代以降の政治権力は、生を標的として管理・統制を及ぼす生権力に転換した。生権力には二つの形態、つまり工場・学校・監獄などにおいて身体の規律・訓育を目指す「解剖政治」と、出生・死亡率の統制、公衆衛生、住民の健康への配慮などの形で、生そのものの管理を目指す「生政治」が見いだされ、次第に前者から後者へ比重が移ってきたとされる。”(imidas「生権力/生政治」麻生博之 https://imidas.jp/genre/detail/L-101-0045.html)
『流感世界』の概要を紹介しましょう。『流感世界』で調査対象となっているのは、香港で生じた鳥インフルエンザです。香港で鳥インフルエンザが発生したのが1997年、これはイギリスから香港が中国に返還された年です。最初の感染源は中国の広東省だったと言われていますが、1997年に香港で三歳の男児が死亡し、そこから感染が世界中に拡大して、最終的には860人の感染者、そして414人の死者を出したと言われています。
ケックが鳥インフルエンザを調査しに香港に乗り込んだのはその10年後、2007年になります。流行から10年経過した後の香港と中国で、ケックは人類学的手法による調査、たとえば微生物の研究者、行政の役人、医師、農場経営者、市場の小売業者などへのインタビュー、あるいは農場に実際に赴いて実地調査を行ないました。それを元に書かれたのが、この『流感世界』です。
今説明したように鳥インフルエンザの発生と、ケックの調査の間には10年という時間が流れているんですが、その10年の間に中国ではSARSの流行がありました。SARSは2002年から2003年の流行で、その際にも危機があったんですが、ケックによれば、香港では鳥インフルエンザとSARSという二つの危機を乗り越えた経験から、次なる危機に向けて、社会的な備えをしていた。本書でケックは、「香港はインフルエンザやSARSを乗り越えて、次なるパンデミック、カタストロフィーに向けて活気づいている」と表現しています。たとえば大きな音を出して咳をするということが無作法の極みとされたり、中国において伝統的とも言える「不潔さ」と縁を切ろうという動きが、人々の中に活発に見られたようです。
ケックによれば、香港では感染症対策が大きく分けて二つの形で行なわれていました。一つは、いま説明した咳のタブーにつながるような、高度な監視体制が敷かれていること。もう一つは、動物の疫病が生まれた場合に速やかに殺処分を行うということ。この監視と殺処分を交互に行うことで、香港は次なる不安に備えている、ということが本書では述べられています。
また、ケックは香港で何が鳥インフルエンザの感染をもたらすリスクとなっているかについても分析しています。たとえば2007年にケックが調査した時点で、香港には広東省から一日一万羽の生きた鶏が入ってきていたようですが、実はちょうど彼がフィールドに入った時期にも、広東省で鳥インフルエンザが再び発症していたんです。それによって広東省では3000羽のアヒルが死亡して、15000羽の鶏が殺処分されました。その時に香港の新聞各社がどうふうそれを報じたかというと、ウイルスに晒された同胞たる中国人たちの健康を気にするのではなく、9月に控えていた中秋節を祝う祭りのための鶏が中国から輸入されなくなるということを心配していたようです。祭礼には生きた鶏が必要で、それを家族で分ける習慣があるからです。ケックはそうした報道から、そうした習慣が鳥インフルエンザのリスクに香港自体を晒しているという分析をしています。
また、もう一つの事例も紹介すると、香港の仏教徒たちが放生会と呼ばれる、鳥を一斉に空に放つ儀礼を行っています。実際にはスズメが使われているんですけど、年間約30万羽の鳥が、この放生会によって香港では放たれているようです。それは生態系を撹乱させるだけではなくて、スズメを媒介とした鳥インフルエンザの感染リスクともなっていて、鳥類学者などは仏教徒の放生会を非難している。このように、香港では感染症のリスクというものが常に社会問題となっている状況があり、そこに国家当局や宗教、また鶏肉の消費と生産の循環が絡まり合っているということが、この『流感世界』には民族誌的に綿密に描かれています。
果たして、ケックのこの議論をどう考えるべきか。それを探る上で、もう一つ、ケックの論文を参照します。雑誌『思想』の「来るべき生権力論のために」という特集(2013年)にケックが寄稿した「今日の生政治学」という論文です。このタイトルはミシェル・フーコーの提案した「生政治」という概念と、クロード・レヴィ=ストロースの「今日のトーテミズム」という非常に著名な本の、アマルガムです。
ケックはそこで自身の『流感世界』を踏まえ、「司牧権力=パストラルパワー」と「生権力=バイオパワー」という二つの権力について対比的に書いています。まず司牧権力とは何か。これは先ほどの香港の例でいうと、殺処分です。司牧権力とは、動物との連続性において行使されるものであり、供犠のような儀式は、人間が動物との精神的なつながりを回復するために行われるものなのだと言っています。ケックによれば、現代における殺処分もまたそうした司牧権力の行使である、とされます。では、もう一つの生権力はどのように行使されるのか。それについてケックは、動物の群れと人間の人口の監視だ、という言い方をしています。この監視がいわゆるバイオセキュリティによってなされているわけです。つまり、殺処分と監視の二つをこのように対比的に捉え、それが混合したものとして、鳥インフルエンザ以降の香港におけるパンデミックに対する危機管理を分析しているのがケックの議論なんです。
では私自身はケックのこの議論をどう評価しているのかというと、この本のケックの議論は人間中心主義に傾きすぎているというふうに見ています。というのも、ケックは、司牧権力という精神的な権力と、バイオセキュリティを駆使する生権力、この二つが交わるところに、来るべき新興感染症に備える香港の生政治の未来がある、というような言い方をしているからです。結局のところ、彼の視点の中には、人間しかいません。議論全体が人間社会のあり方のみにまなざしが注がれていて、閉じてしまっている。そういう意味で、人間中心主義を脱していません。
と、ひとまずに、どういうふうに人類学者が感染症についてこれまで論じてきたのかという点に関して、ケックの研究を取り上げてみました。批判すべき部分はあるにせよ、ケックが感染症を論じる上で持ち出した生政治という概念は、感染症をめぐる行動を考える上でも非常に重要だという点を付け加えておきたいと思います。
そういえば、この生政治については、今日(4月2日)の朝日新聞に掲載された仲正昌樹さんのオピニオン「疫病と権力の仲」(https://www.asahi.com/articles/DA3S14426193.html)でも言及されてました。仲正さんは「人間の本質があらわになるのは、戦争や自然災害より、むしろペストに象徴される『未知の何か』が人間内部に侵入してくる状況だ」と書かれていて、それがカミュの小説「ペスト」のメッセージだということを言っていました。つまり、自然災害なんかよりも、感染症のアウトブレイクやパンデミックの方が、人間の本質をあらわにするんだ、と。これは非常に示唆深い見方だなと感じています。
とりあえず、私は一旦ここまでです。近藤さん、いかがでしょうか?
マイクロバイオポリティクスとは何か──ヘザー・パクソンの研究
近藤 はい。私の方からは、奥野さんへのリプライを兼ねつつ、このCOVID-19の問題をマルチスピーシーズ人類学的にどう位置づけるのかというところを簡単にお話ししてみたいと思います。
まず奥野さんが紹介されたケックに関してですが、ケック自身はマルチスピーシーズ人類学、マルチスピーシーズ民族誌を必ずしも名乗っているわけではないんですけど、マルチスピーシーズ民族誌に大きな影響を与えている科学技術の人類学の流れを汲む研究をしている人類学者として、かなり共通している部分はあると感じています。その共通性を踏まえた上で、ケックのアプローチとケック以降の人獣共通感染症を扱ったアプローチにどういう違いがあるのかということを考えていかなければいけないと感じていますし、奥野さんが語られていたこともそういうところを視野に入れているのだろうと感じています。
先ほど、辻さんから「目に見えないもの」が今日、存在感を増しているという話がありましたが、科学技術の人類学の特徴の一つに、まさに「目に見えないもの」との関わり、肉眼で見えないものとの関わりへの関心が高いということがあります。伝統的な民族誌の場合は、調査方法的にも人間と哺乳類、人間と鳥との関係などのように、あくまで肉眼で見える世界を扱っていることが多かったんですが、STSでは、フィールドにいる人自身が顕微鏡などの科学的な媒体を使って記録をしている人だということもあり、人間と様々な生物種との関わり合いの中にウイルスであるとか細菌であるとか病原体であるとか、肉眼では見えない様々な存在を含み込んだ民族誌的な記述が出てきている。ケックはそうした科学技術の人類学の潮流に乗っ取った形で議論を進めてきた人物でもあり、マルチスピーシーズとは名乗ってこそいないものの、その重要な祖先の一人として捉えることができると思います。
さらに『流感世界』の原著が出たのは2010年ですが、これはちょうどアメリカの『CULTURAL ANTHROPOLOGY』という雑誌でマルチスピーシーズ民族誌の特集が組まれたのと同じ年でもあります。この特集を監修したのは、S・エべン・カークセイとステファン・ヘルムライクでしたが、その両者とも、科学技術に媒介された世界における肉眼では見えない微小な存在と人々の関わりに関心をもっていました。
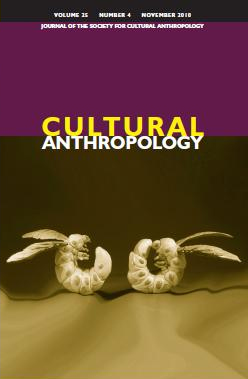
『CULTURAL ANTHROPOLOGY』Volume 25, Issue 4
たとえば、カークセイは、細菌やウィルスを利用したバイオアートの実践者に関する民族誌的な研究を行っていますし、ヘルムライクは海洋微生物学を研究する研究者の調査をしています。その中で自ずと、微生物であるとか、バクテリアであるとか、肉眼では見えないものに焦点が当たるようになっている。こうした研究からは、これまでの、それこそマルチスピーシーズ人類学研究会で私たちがやっているような狩猟民と動物の関係性の研究とは違う話がかなり出てきていて、少なくとも英語圏の議論ではそのような科学技術の人類学をベースとした研究がマルチスピーシーズ人類学を牽引しているというところを、まず確認しておきたいです。
その上で、先ほどの奥野さんの話では、ケックがフーコー的な生政治=バイオポリティクスの議論をベースにしているということだったんですが、私からは、マルチスピーシーズ人類学的な生政治に関する議論の事例として、マイクロバイオポリティクス(microbiopolitics)という言葉を紹介したいと思います。
この概念を提唱したのはアメリカの人類学者であるヘザー・パクソンという方です。この人はアメリカで手作りチーズを作っている職人さんとチーズを作り出している菌類の関わりを研究している人なのですが、彼女のいうマイクロバイオポリティクスという概念の「バイオポリティクス」とは、「生政治」のこと、そして「マイクロバイオ」の部分は「微生物」を指しています。この概念でどういうことが言われているかというと、微小な生物、つまり肉眼では見えないような存在と人間との関係性が、人間同士の関係性、たとえば生活における不和などにも生権力的な影響を及ぼすものであるということです。
たとえばアメリカの手作りチーズ職人が非加熱でチーズを作っていた場合、それが食品安全基準に達していないという理由で製造が規制されていくということが実際に起こるわけですね。人間が微小な生物といかに向き合うかが、食品安全に関する人々のリスク評価の違いによって、人間同士の生き方にも影響を与えていくことがある。
ただ、パクソンの面白いところは、単にそうした人間同士の不協和に焦点を当てるだけでなく、チーズの風味に影響を与えるような、その土地にいる在来の菌類を保全する動きがあったり、職人たちがその土地からもたらされる独特の風味を意味する「テロワール」という言葉を使って、チーズ作りを土地・動物・人の関係として捉えていたりするというような事例も紹介しているところですね。在来菌類の話をしましたが、菌類の場合はウイルスと違って有用な利用方法を考えられますから。このように人間同士の関係だけに焦点を当てるのではなく、人間と微小な生物との様々な関係性のあり方に焦点を当てていくような「マイクロバイオポリティクス」が、マルチスピーシーズ人類学の中で議論されていることは、とても重要だと感じています。
さて、こうしたマイクロバイオポリティクス的な視点を踏まえ、さらにそこに現在の状況を折り重ねて考えてみましょう。目に見えない微小な存在と人がどう生きるかということの人間同士の社会関係への影響が、今日ではただ単に職場や家でどう過ごすか、国や県でどう過ごすか、ということに限らない、地球規模のガバナンスの問題になってきています。それが今日の特徴的な状況なんじゃないかなと思っています。たとえば3月の下旬にゴードン・ブラウンというイギリスの元首相が「この問題に対処するためには世界政府が必要だ」という発言をしていました。このCOVID-19の問題にはグローバルに足並みを揃えて取り組まなければいけない、ということが言われている。あるいは、中国系のメディアも、今日の事態は我々が「人類運命共同体」であることをあらためて認識させてくれているということを、盛んに報道していたりします。要するに、マイクロバイオポリティクス、目に見えない微小な存在といかに生きるかということが、一足飛びに、プラネタリーポリティクス、惑星をどうガバナンスするのか、ということに結びついてしまっている。その是非はさておき、これはグローバリゼーションが当たり前になった現在ならではの現象ではないかと感じています。
供犠と殺処分の連続性──農耕以降の社会における自然の道具化について
HZ ありがとうございます。ケックが『流感世界』で明らかにしようとしていた感染症をめぐる生権力と司牧権力についてのお話、人と微小な世界との関わりが人と人との関わりにも影響を与えていくというパクソンのマイクロバイオポリティクスについてのお話、いずれも興味深かったです。
特に近藤さんの最後のお話は、肉眼では見えない世界への恐怖が、グローバル化した今日の世界においては、直ちにトランスボーダーな管理、統治へと結びついていく危険もあるという指摘だったのではないかと個人的に感じました。そうしたグローバルな管理や統治が必要なのだという議論に対し、前口上でも触れましたが、これまで不可視なもの、目に見えない世界が生き生きと息づいているローカルな社会を調査してきた文化人類学の知見が、あるいはなんらかのオルタナティブを提示できるのではないかと感じています。
というのも今日、COVID-19の感染拡大と、その報道によって、目に見えない微小な世界の存在感が、都市文明においても非常に高まっていて、目に見えないものへの恐怖によって社会が組み直されようとしているわけですが、その中で、そうした目に見えない恐怖を「見える」化しようという方向性がまずあるわけです。不安や恐怖にうろたえるのではなく、科学的なファクトに基づいて、冷静に対処することが大事なのだ、と。フェイクニュースが跋扈する現状を考えれば、この主張はもっともであるとも思うのですが、一方で「見えない」世界をただ「見える」化すればいいという話には、どこか近代的なものに対する過信のようなものも感じてしまいます。
マックスウェーバーが脱魔術化と呼んだ近代化という過程は、一方で不可視なものを可視化していくという流れでもあり、それがすなわち合理化でもあったわけです。しかし、そうした脱魔術化、合理化の中で、自然の外部化、道具化が進み、その結果として起こった大規模な森林伐採、生態系の破壊などにより、様々な新興感染症が新たに誕生し、パンデミックが引き起こされてきたというのも、また事実です。
そうした事態を再び迎えた今日、そこに人類運命共同体としてグローバルに立ち向かおうという視線は、結局、極めて近代的なものであるように感じますし、あるいは歴史を顧みない傲慢な考え方であるように感じるんです。そもそも、人類運命共同体という言葉自体が、まさに人間中心主義的な言葉でもありますよね。倫理的にどうこうという以前に、こうした視線からは結局、自然の制圧、コントロールという考え方しか生まれない気がしますし、そのように自然をコントローラブルなものだとする態度そのものが様々な新興感染症を引き起こしてきたという現実に、あまりに無反省であるような気がします。
ですので、そうした人間中心主義的な管理、グローバルなコントロールとは違う形で、「目に見えない微小な存在」と関係を結んでいく方法を考えることはできないのでしょうか。その上で、たとえば、大規模なパンデミックとは無縁であった狩猟採集社会などにおいて、人々が目に見えない世界とどのように関係性を結んでいたのかが、一つのヒントになるようにも思います。果たして、これまで「目に見えない存在」がどのように社会の中に組み込まれてきたのか、お二人にお伺いしたいです。
近藤 今回のCOVID-19の話に繋げて話すべきかは迷う部分ではありますが、例えば北海道大学に以前勤められていた煎本孝先生の著書『文化の自然誌』によれば、チペワイアンというカナダ森林地帯の狩猟民社会では、季節に応じて移動を繰り返し、生活をしてきました。チペワイアンの人々は、ホチェラスと呼ばれる、毛むくじゃらの野生化してしまった人間について語っていますが、煎本先生によれば、チペワイアンにとって、この精霊的な存在は、野営地で他者との相互依存関係に入ることの不安、他人に対する疑いや警戒心を象徴しているとのことです。狩猟が終わると人々はここら辺は良くない精霊に会うから移動しようと判断して、各自が別の場所へ移動していくことになっていたようです。
この事例は必ずしもウイルスや病原体の話とは直接結びつくものではないかもしれませんが、あくまで抽象的なレベルで、精霊のように普段姿を現さないが人々の傍らでその存在の痕跡を示す「目に見えないもの」と人々がどういうふうに生活を営んできたかということの一例にはなるかもしれません。目に見えない存在について人々が話し合いながら住処を移動させていくということは、マイクロバイオポリティクスとも似ているように思います。
奥野 私はお話を伺ってて二つ思いついたことがありました。一つは近藤さんの話を伺ってのコメントになりますけど、目に見えない微小な存在が、人間世界のある種の生政治だけでなく、地球規模で行われる政治に一足跳びに結びついていくという意味で、マイクロバイオポリティクス、日本語で言うと「微生物生政治」くらいでしょうか、はとても面白いと思います。微小の目に見えない動きを目に見える形で統御しようとういう働きは、仏教でいう「華厳」を連想させます。『華厳経』には「一即多、多即一」という言葉がありますけれど、微小の微塵の中に無限大の宇宙が納まっているということです。たとえ微小なものであっても、それこそが宇宙であって、逆に宇宙というのは極小的な粒のようなものに過ぎない。今起きているCOVID-19を含めウイルスや細菌が、様々な社会的規制に関わる生政治や地球規模での移動制限や外交政策に関わってくるのだとすると、極小のものが巨大なものである、巨大なものが極小であるという仏教的な視点から考えていくこともできるのではないかという気がしました。
もう一つは、ケックの殺処分と供犠に関してです。ケックの議論の念頭にはルシアン・レヴィ=ブリュールやレヴィ=ストロースなどが置かれていると思うんですが、彼は殺処分を供犠と相似的なものとして考えているようなのです。つまり、供儀とは、見えない力が働いて、凶事が起こっており、その力への恐怖、畏怖から荒ぶる力を鎮めるために、神などの力を持った存在に命あるものを捧げることです。それによって、力を鎮め、新しい日常を取り戻していく。殺処分もまた、感染症を拡大させ、人々を恐怖と不安に陥れる目に見えない力を鎮めるための行為であり、それによって秩序を回復していくという意味では、供犠との連続性があるようにも思えます。人類は長らく、そうした形で、自然の背後にある目に見えない世界や存在者と人類社会との調停を行ってきたわけです。
では、辻さんが質問されたような狩猟採集社会においてはどうか。私はボルネオ島の狩猟民プナンの研究を2006年から行っていますが、プナンは供犠をいっさいしません。そもそも儀礼というものをあまりしません。一方、私が1990年代に滞在し調査していた同じボルネオ島の農耕民カリスはひっきりなしに儀礼をしていた。悪い夢を見たら鶏を供犠し、畑では神をよく呼び出して鶏や豚の血を捧げていた。感染症が問題になるのは農耕以降の社会ですが、同様に農耕以降の社会で非常に顕著になってくるのが供犠です。
HZ 今、奥野さんより供犠は農耕社会以降の儀礼である、という話がありました。そして、そこから現在における殺処分へと至るまで、確かな連続性がある、と。しかし、言葉の印象というか、行為の印象として、供犠と殺処分を並べた時に受ける印象にはかなり乖離があるようにも思います。殺処分という行為からは自然の道具化、あるいは自然の搾取というイメージを強く受け取りますが、一方の供儀には、もちろんそうした部分もあるとはいえ、もう少し、自然と人とを巻き込んだ全体的な世界観のようなものを感じます。そこにはまだ、ある種のアミニズムの名残のような、人と他生が連続的に存在している感覚のようなものもあったのではないでしょうか。
奥野 その意味でいうと、おそらく供儀は、狩猟というサブシスタンス(生業)から現代社会の殺処分へ至る中間点に置かれる行為なのかもしれません。たとえば、インドネシアのトラジャという灌漑農耕民の供儀について、人類学者・山下晋司さんが70年代後半に書かれた『儀礼の政治学』という本があります。トラジャは、明確な社会的階層からなるヒエラーキカルな社会です。しかし、インドネシアが近代化の過程で、階層とは関係なく、こぞって都市に出稼ぎに出かけるようになりました。興味深いのはそこからで、出稼ぎ先で儲けたお金を人々が何に使うのかというと、車を買ったりするのではなくて、故郷の葬儀に、供犠に注ぎ込むそうなんです。つまり、故郷で身内が死んだ場合に、水牛を大量に購入して殺すんです。そこで大事なのは、供犠する水牛や豚の数なのです。動物を殺す数が多ければ多いほど、それによって、かつて階層的に下位に置かれていた人が社会的な威信を獲得し、上の階層に行くことができるんです。殺処分と見まがうほどの大量の動物供犠によって、大宴会が続けられ、社会的な序列がひっくり返るのです。
それは言ってみれば、辻さんがおっしゃったような、ある種の自然の道具化であると言えると思います。外部としての自然を利用しながら、自分たちの人間社会の内部を再編成するような動きとして捉えることができます。それは、言ってみれば殺処分と近いように思えます。こうした儀礼の政治学は、供犠から殺処分にいたる中間点に置かれるのかな、という気がします。
HZ なるほど、ありがとうございます。すると、やはり供犠以前、アミニズムにまで遡って考える必要があるのかもしれませんね。おそらく、この後、奥野さんからロージ・ブライドッティのお話があると思いますが、ブライドッティのポストヒューマン論におけるポストヒューマニティもまた、方向性としては非常にアニミズム的なものであるように感じています。果たして、そうしたポストヒューマニズム的な視点からは感染症の問題をどのように捉えることができるのか。お伺いしたいと思います。
人と動物の健康というのは一本でつながっている──「ワンヘルス」の実現に向けて
奥野 ブライドッティの『ポストヒューマン』という本で示されているアプローチというのは、非常にマルチスピーシーズ的だとも言えます。もちろん、標題通り、主題となっているのはポストヒューマニティーズであり、その上で、人間中心主義をどういうふうに乗り越えていくのかという点に視点が注がれています。
これまでの議論と直接的にリンクするところとして、彼女が疾病について触れている箇所があります。彼女が何を言っているのかというと、動物も人間も同じような疾病を抱えている、ということです。心臓病であるとか癌であるとか糖尿病であるとか関節炎であるとか、そうした疾病に人間も動物も同じように罹るものです。また先ほどから触れてきたように動物と人間というのは共通の感染症にも晒されている。動物由来の人獣感染症というのはまさにそういうことです。ブライドッティは、そうした事実が、ポストヒューマニティを考える上でも重要なのではないかということを指摘しています。
その上で、彼女が本書で紹介しているのが「ワンヘルス」という考え方です。このワンヘルスは人獣共通感染症と非常につながりが深い考え方です。そもそも、人獣共通感染症、ズーノシスという言葉を作ったのはフィルヒョウという19世紀の医師、病理学者なんですが、このフィルヒョウは、人間と動物、つまり人獣に共通する疫病の存在を示したにとどまらず、人間と動物の医療というのは同時に行われなければならないとも主張していたんです。その19世紀の提言が、今日の我々が感染症を考えていく上でも非常に重要なのではないかと思うわけです。
つまり、人と動物の健康というのは本来、一本でつながっているはずなんです。それを分けて考えることはできない。それなのに、現在は分かれてしまっている。経験や実践のレベルにおいては、医学と医者の存在というのが一方であり、それとは別に獣医学と獣医が存在している。国際組織もWHOと国際獣疫事務局に分けられている。この隔たりをどうにかして埋めることはできないか。そのために提唱されているのがワンヘルスです。ブライドッティは本書で、健康と疾病をより広く理解するためには、このワンヘルスを実現する必要がある、人と家畜および野生生物の健康達成のためにアプローチを統合する必要がある、ということも言っています。私もこのブライドッティの立場に共感します。
その観点から、再びケックを振り返ってみると、ケックにはまさに、このワンヘルス的な視点がないように読めるんです。アナ・チンの言葉を借りれば、人間だけを他種から隔てられるという前提を持つ、人間例外主義に傾いているように感じます。しかし、先ほど近藤さんがパクソンのマイクロバイオポリティクスを紹介してくださったように、その後の人類学には、こうした人間例外主義を乗り越えるような、ウイルスや感染症をめぐるマルチスピーシーズ的な研究が出てきています。いくつか紹介したいと思います。
一つはナタリー・ポーターの研究です。彼女の「Bird flu biopower」という論文です。今お話したワンヘルスという考えは、2003年のSARS以降にベトナムで導入され、人間–動物のインターフェイスにおける鳥インフルエンザの統制を目指す形で始められているのですが、ナタリーは、ワンヘルス下のベトナムにおける、動物、人間を含む多種からなるコミュニティに行使される生権力の問題を、この論文で論じています。
ウイルス民族誌家を名乗ってるのが、セリア・ロウです。彼女の「VIRAL CLOUDS」という論文を紹介しましょう。この論文ではインドネシアの鳥インフルエンザの感染に関する研究がなされているんですが、野生の鳥、家禽、それから人間、さらにはウイルスを含めた多種の絡まり合いというものが、社会におけるパンデミックに対する備えや、バイオセキュリティ、国民統合のための監視技術とどう結びついているのか、そして、ロウが「CLOUDS」と呼んでいる、人々の不確定で不安定な状況が、いかにして作り出されているのか、そういうことが分析されています。ロウの論文は、主に人間社会の状況について書かれていて、これはケックに近いとも言えます。ただ、彼女の別の論文には「THE VIRAL CREEP」というものもあって、そこではドイツの人類学者ミュンスターと共に、象ヘルペスウイルスと象、そしてその世話をする人間という多種の相互関係、それぞれの存在がいかにして生成するのかということが論じられていて、マルチスピーシーズ的な視座からも非常に面白い論文です。
もう一つ、医療人類学においても顕著な動きがあります。メリル・シンガーという有名な医療人類学者が、人獣共通感染症について論文を書いています。彼女はその論文で、動物を人間社会における外部の要因として取り上げてきたこれまでの医療人類学を破棄し、種間関係に目を向けることで医療人類学を再構築しようとしています。
先ほど説明したワンヘルスというアイディアは医学における実践ですが、そうした動きに併走する形で展開しているマルチスピーシーズの研究の動向を見ると、ケックは人間の生権力の問題だけに集中しすぎているところがあると言えるんじゃないかと思います。言いかえると、ケックは病原体を外部からの未知の変数と捉えることで、人間の世界だけに閉じ篭ってしまっている。ここから言えることは、現在の感染症をめぐる問題に人類学が思想として踏み込まなければならないのは、辻さんの最初の言葉にもあった「モア・ザン・ヒューマン」、つまり人間以上の視野に立って感染症を考えるというポイントにあるのではないかと、私は考えています。
永久凍土の融解が天然痘を呼び戻す──パンデミックは「人新世」の問題
近藤 では、私の方からは、奥野さんがお話しくださった「ワンヘルス」の考え方に関連するような、北方研究の事例についてお話したいと思います。2016年8月のことで世界のニュースでも取り上げられたんですが、西シベリアのヤマル半島というところで、ネネツという牧畜民の集落において炭疽菌の集団感染が起きた話です。なぜ感染が起こったのかについては気候変動の影響によって引き起こされたんじゃないかと言われています。報道によれば、一時期は70人くらいが入院し、死者も出ました。また、この炭疽菌は人獣共通で罹るものとされていて、2千頭以上のトナカイも死んだそうです(※)。
もともと、シベリアでは炭疽菌が存在していたと思われます。しかし、以前はそうした炭疽菌を宿した動物の死体が永久凍土の中に埋められていたので、地表面に出てこないという状況にあったんです。それが、気候変動の影響、特に2016年の夏はとても暑かったということがあり、永久凍土がかなり溶けてしまった。つまり、これまでバッファになっていた永久凍土が部分的に無くなってしまったことによって、地中にいた炭疽菌が地表に出てきてしまったんです。
ただ、炭疽菌が地表に出てきたとしても、それだけであれば人間の居住地にまでは届きません。しかし、ネネツは牧畜民なのでトナカイを飼っていた。そのトナカイが地面に生えている植生を食べることで炭疽菌に感染し、そのトナカイをネネツの人々が食べることで、感染が拡大したという経路が想定されています。
※永久凍土の融解と炭疽菌の感染拡大については以下の記事を参照。「The Siberian Times」Experts warn of threat of born-again smallpox from old Siberian graveyards/「AFP|BB NEWS」解ける永久凍土と目覚める病原体、ロシア北部の炭疽集団発生
これは人々の生業体系と、現在の気候変動が絡まり合う中で起こった人獣共通感染症の事例ですが、現在、これと同じメカニズムで、かつての天然痘なども永久凍土の融解によって戻ってくるのではないか、といった警鐘が専門家によって鳴らされています。これらの事例は今回の新型コロナウイルス感染症の発生とはまた異なる話ではありますが、こうした自然環境の変化によって生じる再興感染症との関わり方は、今後、ますます問われてくるであろう重要な問題だと感じています。
奥野さんのお話においても、人間と動物の「あいだ」、人間と人間の「あいだ」というのを考える必要がある、という話がありましたが、永久凍土の事例を考える上では、さらにまた別の「あいだ」を視野に入れる必要があると感じています。永久凍土とは、過去の世界をも含み込んで凍結している土地であり、それが地表という現在の人間が生活を行なっている場所に影響を与え始めているわけですが、これはどういうことかといえば、これまで存在していた永久凍土と地表の「あいだ」、過去の世界と現在の世界との「あいだ」が、気候変動によって融解することで、危険な混交が起こり始めているということです。こうしたタイプの「あいだ」に感染症が生じてくるということもありえるんです。
そして、こうした一連の現象はいずれも「人新世」の問題であるということを個人的には強調しておきたいと思っています。「人新世」は地質学の言葉ではありますが、この言葉が示している問題とは、ざっくり言えば、地球の資源化が進み、人類全体による地球の支配の拡大、つまりグローバリゼーションがあまりに進みすぎた結果、人間の生存基盤自体が揺るがされるような状況が生じているというところにポイントがあると思っています。すると今日、一つの感染症がこういうふうに世界に拡大し、それによってさまざまな人間のあり方が揺るがされているという状況もまた、「人新世」の問題として捉えていくことができるのではないかと思うのです。少なくとも、そうした視点がマルチスピーシーズ人類学においては重要になってくるのではないかと思っています。
奥野 私からも近藤さんのお話に繋ぐ形でちょっとだけ、お話したいと思います。今、人新世の話が出ましたが、COVID-19を含め、人類共通感染症の流行は、ずばり人新世の問題だと思います。人新世は、人間中心主義的な自然へのアプローチであり、人獣共通感染症の蔓延はその結果だからです。その上で、再びケックの話に戻ると、先ほどから私はケックをずっと人間中心主義な傾向にあると批判的に捉えてきたわけですが、『流感世界』以降、ケック自身も、それを乗り越えるような論を展開しています。たとえば、最近、COVID-19感染拡大初期の2020年3月初めの段階で、ケックが保険会社AXAのインタビューに答えた記事(AXA:When Animal Diseases Spread to Humans/https://www.axa-research.org/en/news/frederic-keck)を読みましたが、彼はそこで以下のように言っていました。
「私の関心は、本当のところは、気候変動、森林破壊、および産業育種によって変化する、私たちと動物との関係性にあります。たとえばウイルスについての一つの関心は、それがコウモリによってもたらされることです。そしてコウモリは森林破壊のためにますます人間の居住地域に近いところにやってくるのです。だから、私たちは、私たちとウイルスの貯蔵庫としてのコウモリとの関係についても考える必要があるんです。コウモリはヨーロッパの国民が田舎から都市に集住してきた19世紀には中世の悪魔として想像されていましたが、今日の田舎では親しい隣人であり、さらに森林破壊のためにより都市圏に近づいてきています。コウモリがどのようにウイルスと共生しているのかについて、もっと多くのことを学ばなければならんないといけないということに私たちは気づいています」
つまり、19世紀までは悪魔として想像されていたコウモリが、現代では人間にとっての親しい隣人となっているというように、コウモリと私たち人間との関係性の変化を追うことが、感染症について考える上でも重要だということです。さらに、コウモリは様々なウイルスと共生しているわけで、ケックは、そうしたコウモリの免疫システムについても我々は学ばなければならないとしている。こうしたケックの視線は、森林破壊や産業育種などを進めてきた人間の、人間中心主義的な思い上がりを乗り越えるための過激な手段となっているのではないでしょうか。森林破壊や産業育種というのは、「人新世」にもダイレクトに繋がるわけですが、ケックもまた、人間が思い上がりを超えて考えていかなければいけないし、そのためには、コウモリと人間の関係、つまり種間関係に注目すべきだと言っているんです。
COVID-19と新たなる「社会的距離」──アラスカ先住民の実践
HZ 今のお二人のお話は共に「あいだ」をめぐるものだったと思いますが、今日まさに新型コロナウイルスのパンデミックに際して取られている「social distancing」と呼ばれる一連の政策は、この「あいだ」の政治をめぐるものですよね。東京都知事の「三密」などもその一部だと思います。ただ、それらはあくまでも緊急対策案的な形で出されているもので、言ってしまえば、今は有事だから特別にこういう対処をしてください、という意味合いになっています。しかし、お二人のお話を聞いていても、やはりもうちょっと根本的なところで、それこそ人と人との関係に止まらない形で「social distancing」というものを日常レベルで再考していく必要があるのではないか、とも感じます。有事としてではなく、平時としての「行為変容」が、もっと問われるべきではないのか、と。その上で、この「あいだ」「距離」をめぐる実践に関して、果たして人類学はどのようなことを言えるのでしょうか。
奥野 私の方から先に応答します。今のご質問に私が想起したのはジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』という本です。この本の11章に、人獣共通感染症のことが書かれている。我々が「あいだ」についてを考える、つまり、今、社会的距離が世界的に問題となっている中で、それを一時的な政策としてではなく、我々のハビトゥスとしてどのように身につけることがなされるべきなのかということを考える上で、彼の議論は非常に示唆に富んでいると感じます。
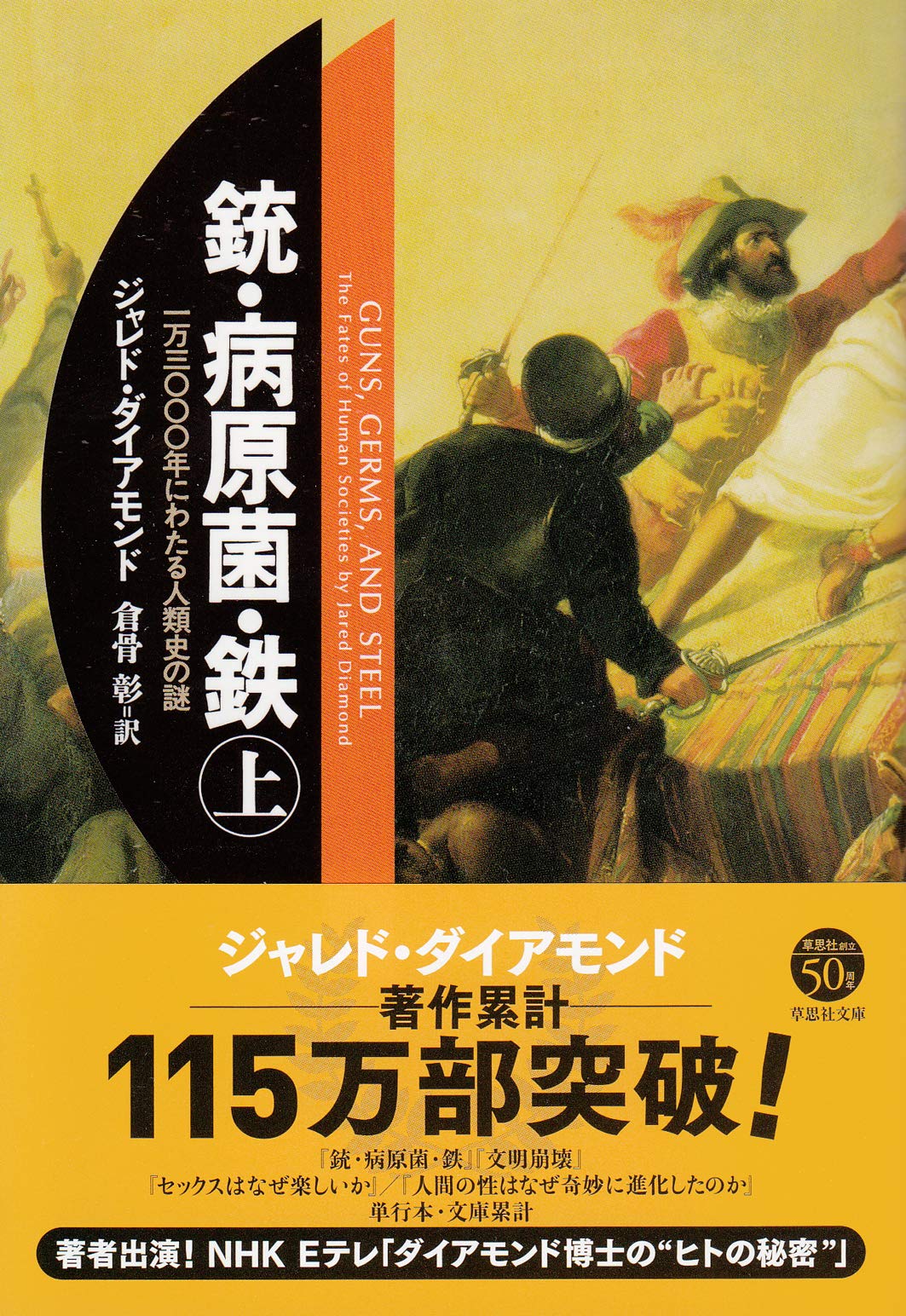
『銃・病原菌・鉄』(著・ジャレド・ダイアモンド、訳・倉骨彰/草思社文庫)
ダイアモンドは、集団感染症というものは狩猟採集民や焼畑農耕民の社会でははびこらなかった、と言っています。また、感染症というものが少人数の集団に登場するのは、それが外部からもたらされた時だ、という言い方もしています。そして、これはおそらく正しい。というのは、私はボルネオ島の狩猟民プナンの集落を2006年から調査し続けているんですが、私が調査を開始する前年、2005年に、私がその後に行くことになる調査地のプナンが13人ハシカで死亡しているんです。さらに、隣のコミュニティでは18人が死亡した。これはプナンの社会にとって、とても大きな出来事でした。そして、そのハシカの集団感染がなぜ起こったのかというと、イバンという近隣の農耕民が持ち込んだとされています。要するに、外部の集団から持ち込まれてきたんです。
これはまさにダイアモンドが言っている、狩猟民社会には外部から感染症がもたらされるという話に符合する事例です。そこから考えると、一般によく知られている感染症が出てきたのは、人類史においてはほんの最近のこと、今から一万年くらい前に農業が始まり、人口の密集集落ができ、やがて都市ができ、加速度的に人口が増え、それ以降のことなんです。たとえば、天然痘は、紀元前1600年頃のエジプトの記録が最古のものです。おたふく風邪は紀元前400年頃、ハンセン病は紀元前200年頃、そして時が現在に近づくにつれて、どんどんと多様な新興感染症、エマージングウイルスが出てきています。
逆に、狩猟採集民社会には、ほぼ感染症がなかったと言われています。ダイアモンドによれば、病原体、菌、ウイルス、寄生虫などは排泄物の中に含まれていることが多く、定住していると、そうした排泄物への接触頻度があがりますが、狩猟採集民というのはその場に長い間とどまらないため、基本的にあまり接触することがない。つまり、農耕革命を病原体の視点から考えてみれば、とてつもない繁殖環境を獲得したのだとも言えるんです。それが都市化によって加速化し、さらにはグローバル化によって人の行き来が激しくなることによって、「あいだ」というものが縮まっていった。その結果、今回のような世界的なパンデミックが起こっている。
では、そのような事態において、我々にはどのような「あいだ」の実践が可能なのか。近藤さん、いかがでしょう。
近藤 一つの例として、内陸アラスカ先住民の方々がどう現在の状況に対応しているのかというところをお話してみたいと思います。今彼らが行おうとしていることをざっくり言うと、二重の社会的距離化だと言えます。彼らの暮らしは、歴史を辿れば小さい集団単位で一つの川筋に暮らすというもので、そこに非先住民、つまりヨーロッパ系アメリカ人との接触があり、それによって村に住むようになり、そこから現在では都市に出ていく人も増えているんですが、その歴史を遡り、原点に戻ってやり直す、つまり、積極的に閉じるということが、今、彼らが行っていることなんだと思います。
その具体的な内容として、一つは、現状で彼らは都市と村の間を飛行機で行き来しているんですが、その便数を非常に絞っています。本当に必要最低限の食料や薬を運び込むためだけの便数に制限して、都市と村の間を切り離したんです。そして、もう一つ、村と都市部だけではなく、村と野営地、狩猟のためのキャンプをも切り離そうという意見があります。つまり、村にたくさん人が集住している状態が危ないという認識のもと、みんながそれぞれ、かつて使っていたキャンプに戻るべきなんじゃないか、という考えが出てきているんです。これが実際にどの程度行われるかは分かりませんが、現在、そういうことが盛んに言われるようになっています。村と街の切断、そして、もしキャンプへの大規模な移動が実際におこなわれれば、村自体の解体、この意味で社会的距離化が二重になっているんです。
とはいえ、実際にキャンプに人々が分散してしまうと、もし重症者などが出てしまった場合には困ります。だから、これがいいことなのかどうかは私には分かりません。ただ、彼らは真剣に、都市と村の間を切り離し、そこから村の集住を避けるため、元々の伝統的な生活形態に戻る、ということを考えているんです。個人的に興味深いと感じたのは、実はこうした対策というのは1918年のスペインかぜ流行の際に彼らの祖先がやったものだそうで、そうしたことが村の中で語り継がれていると言うことです。スペインかぜの時は、基本的にはヨーロッパ系アメリカ人がアラスカにもたらすような経路となっていため、彼らは一年間キャンプにこもり、交易所などには行かないという暮らしを過ごしたらしい。そこにヒントを得て、現代においてもそういうことをやろうと考えている人が増えているんです。
あるいは、こうした状況下で、今まで都市に出ていた人の中からも、キャンプに戻ろうと考える人が出てくるかもしれない。様々な集団の中で、過去の集合的な記憶のようなものが呼び覚まされるかもしれない。そうした中で人々の伝統のようなものが再文脈化され、再び活性化するような状況に、私たちは立ち会っているのかもしれないとも思います。このことについては、文化人類学者としても、より詳しく調べていきたいと思っています。
人と動物の「あいだ」に生成するもの──ウイルスは悪者か?
HZ ありがとうございます。今、近藤さんより二重の社会的距離化という話がありましたが、このパンデミックに反応しているのは、おそらくアラスカの先住民の方々だけではありませんよね。都市的な暮らしをしている人々の中からも反グローバリゼーションの意識などが盛り上がってきているように感じています。その中で、たとえば歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリは、COVID-19下で盛り上がりつつある反グローバリズムに対して警鐘を鳴らすようなメッセージを発していました。しかし、この状況下で境界線が見直され、「あいだ」のありようが問われていくということ自体は、単に人間社会の政治的なレベルを超えて、必要なことではないかと思います。もちろん、それがレイシズムやマイノリティの排除に短絡するようなことがあってはならないわけですが。
そこで思ったのは、語られるべき距離には二種類あるのではないか、ということでした。今、近藤さんがご紹介してくださったアラスカの事例などにおける物理的な距離をとっていくという時の距離がまず一つ。もう一つは、奥野さんが紹介してくださったケックのインタビューにおける、コウモリと人間との関係に目を向けていく態度のような、存在論的な距離です。森林破壊、過剰な人の行き交いなどによる物理的な距離の縮小は控えつつ、一方で存在論的には距離を縮小していく。遠ざかりつつ近づきながら、ワンヘルスを目指していく。そういう態度が求められているのではないかと感じました。
奥野 今のお話についてもそうですが、「あいだ」が重要なキーワードとなってくるように感じます。これについて、最後にもう少しだけ考えてみたいと思います。先ほども述べましたが、人獣共通感染症に関しては、まず一つ、人間と動物の「あいだ」というのが非常に重要になってくると思うんですね。人間がそれまで住んでなかった場所に入りこむようになり、森林であるとか、自然を開発して、そこに住むようになることで、野生動物との距離が縮まる。それだけじゃなく、野生動物もまた住むところがなくなって人間が住んでいる場所に出てくる。それによって動物にとっては共生可能だったウイルスが、人に感染して猛威を振るうというような状況が生まれている。
言ってしまえば、感染症の脅威というのは、人間のエゴによって作り出されているということになる。冒頭の話に戻れば、そうであるにもかかわらず、我々はウイルスを敵であるとか、脅威であるとか、呼んでいるわけです。これは非常に滑稽だと思います。人獣共通感染症というのは、ヘーゲルの主奴の弁証法、つまり、主人である人間が、奴隷である自然を、弁証法的に、支配、コントロールしていこうとした中で、生まれてきたものであるわけですから。
その点に関して言えば、こういう本があります。『ウイルスは悪者か』。端的にいうと、これは反語で、ウイルスは悪者ではないということが言いたいわけで、北海道大学の人獣共通感染症センターの高田礼人さんが書いた本です。安倍首相にせよ、小池都知事にせよ、ウイルスを敵だというふうに言っていますが、この方はそうではない。そういうふうに見なすのは行き過ぎだ、と言っています。私も、それは大事な視点ではないかと思います。つまり、ウイルスを敵だとか脅威とみなさないというのは、人間だけを例外視するのではなく、人間、動物、病原体を同列に考えるということであり、それはすなわちワンヘルスの見方にも繋がるんです。その観点から、病原体を含むあらゆる存在者の動きを、善悪以前、脅威とか悪者とか敵とかの判断以前の次元で、生と死が絡まり合った生命現象として描きだすことが、とりわけ、マルチスピーシーズの観点からは大切なんじゃないかと思っています。
そこに「あいだ」の問題が重要になってくる。つまり、ウイルスのような微小な存在が人間と野生動物の「あいだ」に生成してくると考えたほうが分かりやすいんじゃないか。実際、人獣共通感染症における病原体というのは、野生動物から人間に、関係性を通じて移される。「あいだ」が十分にある時には転移しない、縮まることによって、病原体が転移する確率が高まるわけです。精神科医の木村敏は、「あいだ」というのは単に「あいだ」じゃないんだ、と言っています。「あいだ」を表面に出ている人やモノ、現象に、裏面から作用を及ぼす力の場として考えています。「あいだ」を消極的なものとしてではなく、積極的なものとして捉えています。この見通しを踏まえて、最後に環境哲学者のヴァン・ドゥーレンのマルチスピーシーズ研究の『Flight Ways』という本を紹介したいと思います。
牛へのジフロフェナク投与がまわりめぐって炭疽菌と狂犬病ウイルスを拡散させる
奥野 『Flight Ways』の一章は、インドのハゲワシについて書かれた本ですが、そこに登場するのはハゲワシだけではなく、人間、牛、犬、それから病原体、具体的には炭疽菌と狂犬病ウイルスが登場します。少し概要を説明します。
インドにはかつてハゲワシがたくさんいました。川岸に放置された動物の死体や人間の死体にたかり、その屍肉を食べていたんです。ところが、そのハゲワシが今日いなくなってしまった。ベンガルハゲワシはこの数十年で99パーセントが死滅したと言われています。なぜ死滅してしまったのか。かつて、インドでは牛という動物が、耕作や搾乳、重労働のために使役される存在であって、肉として人に食べられることはなかったんです。そのため牛の死骸は捨てられ、その死骸を食べるハゲワシにとっては、まさに理想の生息環境となっていたんです。毎年500万~1000万頭の牛、ラクダ、水牛が、ハゲワシの世話になっていたと言われます。百羽くらいのハゲワシが一頭の牛の死骸を30分ほどで綺麗に片付けていたそうです。
近藤さんの話にも出てきましたが、炭疽菌という菌は主に草食動物に蔓延し、それによって動物は死に至るんですけれど、通常、その死骸において炭疽菌は増殖するんです。インドの牛も炭疽が感染していましたが、ハゲワシは30分くらいで死体を片付けてしまうので、炭疽菌の芽胞が形成される前に全て組織を取り除いてしまうんです。これによって、炭疽菌の拡大が食い止めてられていました。
もう一つ、インドのハゲワシは人間の死体も食べていました。ムンバイのパルシー教徒にはかつて鳥葬の風習がありました。彼らは、ハゲワシに死体をついばませていたんです。言ってしまえば、パルシーの人たちは自分たちの生の中にハゲワシの居場所を作っていたとも言えます。このように、かつてのインドではハゲワシ、牛、炭疽菌、人が相互に絡まり合って、ある種のバランスを形成していたんです。
ではなぜハゲワシが絶滅してしまう方向に進んだのか。これは抗炎症薬のジフロフェナクという薬が原因でした。ジフロフェナクは1960年代から人間に使われていたんですが、やがて貧困層において牛にも使われるようになったんです。牛の歩行困難、乳腺炎や出産困難の際に、このジフロフェナクを投与することで、強引に働かせ続けた。彼らは貧しかかったため、そうせざるをえなかったんです。すると、牛の体内にジフロフェナクの成分が残る。そして、その成分が牛の屍肉を食べるハゲワシに腎炎をもたらすことになり、バタバタとハゲワシが死んでいったんです。
こうしてハゲワシがいなくなってしまったことでまず問題になったのは炭疽菌です。さっき説明したように、ハゲワシが炭疽菌の拡大をそれまで防いでいたのに、いなくなってしまった。これによって、炭疽菌が蔓延するようになりました。もう一つ、変化がありました。ハゲワシの減少に反比例するように野良犬が増えたんです。これは牛の死骸がハゲワシによって解体されず、野良犬にとっての食料となったことが原因です。ただ、犬も牛の死骸を片付けはするものの、そんなにスピードが早くない。さらに炭疽菌のような疫病を封じ込めることもない。
さらに犬の増加はまた別の問題も巻き起こしました。町中を野良犬がウロつくことで、人間、あるいは他の哺乳類に狂犬病ウイルスを撒き散らすようになったんです。統計によれば、年間インドでは1700万人が犬に噛まれていて、そのうちの75%が貧困層、さらに狂犬病にかかるのはそのうちの96%。世界に起こる狂犬病による死のうちの約6割がインドで起きていて、年間25000人~30000人が死亡しているようです。死者のうち90%が貧困層で、成人男性がほとんどであることから、遺族の経済的な貧困度合いはさらに高まります。このように、牛へのジフロフェナクの投与が、まわりめぐって、ハゲワシを死滅させ、さらには人々に貧困と痛みと死をもたらすようになったんです。
この事例は、人間と動物、あるいは菌やウイルスは、それぞれ別個に生きてるんではなく、食べ、食べられ、使役し、使役され、影響を与え、与えられ、相依しながら、絡まりあって生きているという、世界のありようを示しています。牛の死、ハゲワシの死が病原体を広く解き放ち、人間への狂犬病ウイルスの感染を引き起こした。病原体というのは、まさに人間と、人間と共にある動物の「あいだ」に生じるんです。その「あいだ」とは異なるものたちが出会う空間であり、その空間というのは常に動因をもった力の場としてある。「あいだ」に現れた病原体というのは転移された個体の中で増殖し、やがて個体に死をもたらすかもしれない。我々の住まう世界は、ヴァン・ドゥーレンが描き出したような、人間や動物たち、あるいは動物たちが保有する病原体が、生まれ、生き、死んでいく世界なんですね。ヴァン・ドゥーレンはこういうふうに言ってます。
「生と死というのは、こうした関係性の内側で起きている」
これは冒頭で紹介した禅師・内山興正が「生命的地盤」という言葉で言おうとしていたこととも繋がります。つまり、人間、動物、病原体が絡まり合い、入り乱れ、死が生を支え、さらには生がいつの間にか死を産むという、常ならざる「モア・ザン・ヒューマン(人間以上)」の世界の根源的な探求というのが、私たちの前にある問いの本質なのではないか。病原体、人間、動物の相互作用を、生と死を丸ごと含めて探ること、つまり生死(しょうじ)の問題こそが私たちの次なる課題ではないのか。
最後にこういうふうに言い換えることもできます。我々が今問題にしているのは、病原体が人間の世界に侵入してきて「以降」の話ばかりなんです。そして、ある意味でその存在に対してうろたえている。そうではなく、もっと遡って考えなければならないと思うんです。モア・ザン・ヒューマンの世界で、病原体、人間、動物たちが絡まり合って生きている姿を理解し、そして気遣うべきではないのか。私からは以上です。
切断の時代における新しいつながり──トラデジタルとドムス化
近藤 私からは最後に、辻さんが指摘されていた、反グローバリズムに対する懸念が起こっている、ということに関して、二つの側面からお話したいと思います。
まず一つの側面として、社会的距離化によって連想されるのは孤立かもしれませんが、私は必ずしもそうではないと思っています。この状況下においても、デジタル技術を介した新しいつながりというものが生まれ得ると思うんです。それこそ、この研究会自体が、このようにZOOMを利用してオンラインで行われているように。つまり、社会的距離化の時代に、デジタル技術を介した新しいつながりをどう考えるのか。そして、それは人間同士の関係でもあるし、人間と情報技術、機械との関係でもある。その両面から考えなくてはいけないと思っています。人間と動物との関係だけではなく、人間と機械との関係というのも、マルチスピーシーズ人類学が扱うべきテーマですから。
まず人間同士の関係について言うと、たとえばカナダ先住民の人たちが最近になって盛んにビデオ会議をやるようになっているんです。カナダでは先住民運動がとても盛んなのですが、COVID-19の感染拡大下における今日ではカナダ内の違う地域に住む人々がビデオ会議で互いをつなぎ、この事態を先住民コミュニティでいかように受け止めていくのかということが活発に議論されていたりします。私は関心を持っているのが食文化の話なので、こういう状況下で村からもう一度野営地に戻って、たくさん狩猟して食料を確保しなければいけないということを言う人が増えていることを面白く感じるんですが、一方で、そうした伝統を強く意識して生きている先住民族が、そのまさに伝統の受け継ぎ方をめぐる議論を、デジタル技術の媒介の中で話しているということが、とても現代的だなと感じています。デジタル技術に媒介されるような形で伝統が再定義され再文脈化されているというのは、非常に興味深い現象です。
最近、先住民学の中では「トラデジタル」(tra-digital)という言葉も使われています。つまり、トラディショナルであり、かつデジタルであるということです。デジタル技術によって媒介されるような伝統のあり方、これは新型コロナによって社会的距離化をしなければならないという事態においても、単なる孤立とは異なる、新しいつながりかたの一つとして、個人的に関心を持っていることです。
もう一つの側面、これは外出自粛の流れと関係しますが、今、生活空間である家や部屋を考えた時、そこにも新しい「あいだ」が生まれているのではないかと感じるんです。個人的にはICT、つまり情報技術と人々の相互ドメスティケーションが起きているんではないかと見立てています。この時のドメスティケーションとはどういうものか。情報技術は「動物」ではないので厳密に飼育しているというわけではないと思うんですが、しかし、私は今、パソコンを始めとする情報技術に取り囲まれて暮らしながら、実際にそれらに飼育されているような気分を感じているんです。ここで私が前提としているのは、デイヴィッド・アンダーソンらの人類学者が提起している「ドムス化」としての「ドメスティケーション」論です。
もともとラテン語において、ドメスティケーションの語源となった「ドムス」とは家屋や家庭のことなんですね。ですので、ドメスティケーションとは、もともとは家の家内経済の中に動物とか植物とかを招き入れるという意味だったんです。アンダーソンらはそこに着目し、ドメスティケーションというのは、自分たちのドムス、つまり住まい、生活圏内の中に動植物を組み込み、組織化することだと語っています。この話がどのように革新的かというと、これまでドメスティケーションの話は、人間と動物の関係という二者関係として考えられてたのに対して、そもそも人間と動物の飼育関係を可能にするような媒介、インフラストラクチャーに着目しなければいけないんだ、というところを指摘した点です。その中で、インフラストラクチャーとしての情報技術と、人がどのような相互ドメスティケーションの関係にあるのかということが考えられなければならなくなったんです。
実際、私の家は今急にデジタル化が進んでいまして、これまでがアナログすぎただけというのもあるんですが、いきなりビデオ会議を介して日常的に人々とやりとりするようになりましたし、プリンターも新しく買いましたし、スマホとラップトップと大きなデスクトップパソコンでFacebookをチェックしたりしながら暮らすようになってしまったわけです(笑)。このように私のドムス、つまり自宅が再組織化されていっているわけですが、その新しい情報環境の中で知的生産をしなければいけないということに、私自身が直面している。これを一体どう考えるべきなのか。これもまた、社会的距離化時代において考えなければならないことなのではないかと感じているんです。
つまり、人獣共通感染症を考える上では人間と動物の「あいだ」を考えなければいけないし、人同士の社会的距離についても考えなければならないんですが、もう一つ考えなければならないこととして、在宅時間が増えることで存在感を増しているICTと私たちとの「あいだ」という、「あいだ」もあるのではないか。私からは以上になります。
HZ ありがとうございます。ICTに関して、僕は時々、スマートフォンが僕の拡張身体なのではなく、僕がスマートフォンの拡張身体なのではないか、と感じることがあります。それと同様に、ウイルスに関しても、生物をウイルスの拡張身体として想像することもできるかもしれないと思ったりもします。実際に最近では、ウイルスとウイルス粒子を分けて考え、ウイルス粒子が寄生した細胞をウイルス本体として考えるヴァイロセル仮説という考えもあるようです。この時、細胞はウイルスが効率的に増殖するための装置のようなものとして考えられるわけですが、すると、その細胞の寄せ集めからなる人間である自分とは一体、どういう存在なのか。あるいは自分の身体もまた常に再組織化されつつあるドムスのようなものなのかもしれない、そんなことを思いました。
いずれにしても、大変興味深いお話でした。時間になりましたので、これにて終了となります。ありがとうございました。

大小島真木「THE HEART—HIBERNATION」
構成|辻陽介
ドローイング|大小島真木
✴︎✴︎✴︎
奥野克巳 おくの・かつみ/1962年生まれ。立教大学異文化コミュニケーション学部教授。主な著書として、単著に、『「精霊の仕業」と「人の仕業」:ボルネオ島カリスにおける災い解釈と対処法』『帝国医療と人類学』『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』、共編著に『文化人類学のレッスン:フィールドからの出発』『セックスの人類学』『人と動物の人類学』『改定新版 文化人類学』『Lexicon 現代人類学』などがある。共訳書にエドゥアルド・コーン『森は考える:人間的なるものを超えた人類学』、レーン・ウィラースレフ 『ソウル・ハンターズ:シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学』、ティム・インゴルド『人類学とは何か』など。
近藤祉秋 こんどう・しあき/1986年生まれ。北海道大学アイヌ・先住民研究センター助教。共編著に『犬から見た人類史』、論文に「ボブ老師はこう言った:内陸アラスカ・ニコライ村におけるキリスト教・信念・生存」(『社会人類学年報』四三号所収)、「赤肉団上に無量無辺の異人あり:デネの共異身体論」(『たぐい』vol.2所収)などがある。
✴︎✴︎✴︎
〈MULTIVERSE〉
「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー
フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介
「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄
「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生
「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美