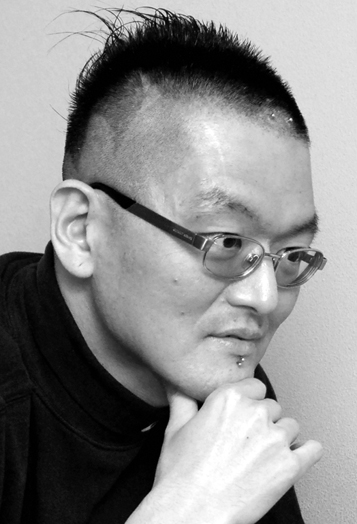ケロッピー前田 『クレイジーカルチャー最前線』 #16 昨今の縄文ブームは“縄文ルネサンス”という文化現象だった── 縄文イメージの変遷から現代の縄文アーティストたちの台頭へ
驚異のカウンターカルチャー=身体改造の最前線を追い続ける男・ケロッピー前田が案内する未来ヴィジョン。現実を凝視し、その向こう側まで覗き込め。未来はあなたの心の中にある。

「森の聲」に耳を澄まして
筆者とタトゥーアーティスト・大島托との縄文タトゥー復興プロジェクト「縄文族 JOMON TRIBE」の作品が、2020年7月11日から8月16日まで、新潟県津南町の地域博物館「なじょもん」の展覧会「森の聲―Papua×Jomon×Art」にて展示された。

https://www.najomon.com/page_top/index.php
https://www.najomon.com/page_kikaku/index.php?id=1590547555&view_year=2020
この展覧会は、縄文文化からインスピレーションを得たアート作品、パプアニューギニアの民族資料、本物の縄文土器とを同じ展示空間で見せることで、それぞれに共通する“森の聲”に耳を澄ませてみようというものである。
自分たちの作品が縄文土器とともに展示してもらえるというのは感無量だ。現代の縄文アーティストの方々との共演も大変嬉しい。展示内容に関しては、改めてレポートしたいが、この21世紀の日本にあって、「縄文」というもののイメージが刷新され、現代の作家たちに大きなインスピレーションを与えていることがよくわかる展示となっていた。

展覧会「森の聲―Papua×Jomon×Art」@なじょもん
拙著『縄文時代にタトゥーはあったのか』(国書刊行会)にも書いているが、大島托とのアートプロジェクトを5年ほど前に始めたきっかけは、昨今の縄文ブームに触発されたところもあった。
では、昨今の“縄文ブーム”とはどんなものであろうか?
そんな素朴な問いに真っ向から挑んでいるのが、昨年12月に刊行された古谷嘉章氏の著書『縄文ルネサンス』(平凡社)である。古谷氏は、「昨今の縄文回帰は、一時的な“ブーム”でなく、日本における文化の大きな転換期である」といい、それを「縄文ルネサンス」という言葉で表している。今回は、この『縄文ルネサンス』という本を導き手に縄文イメージの変遷を振り返ってみたい。
ちなみに、古谷氏とは、昨年11月、東京藝大で開催された「藝大で縄文の話をしよう」というトークイベントでご一緒させていただいている。このイベントは、土器修復を専門とする石原道知氏の主催によるもので、作品制作を通じて従来の縄文イメージを超えていこうという作家たちがその活動のプレゼンテーションをするというもので、古谷氏が提唱する「縄文ルネサンス」を体現するものであった。僕らもその仲間に加えてもらったことは非常に誇らしいことである。
縄文ルネサンスの3つのポイント
さっそく、『縄文ルネサンス』のページを開いてみよう。
冒頭で、古谷氏は人類学者としてのフィールドワークのためにブラジルを訪れた際、アマゾン下流の都市ベレンに10ヶ月ほど滞在し、先史土器風の土器について調査をしたと書いている。そこで彼が発見したのは、観光土産用に先史時代の土器をコピーしたものが大量に作られていること、それらの土器が地域アイデンティティとも結びつき日常的に利用されていること、さらに本物の先史時代の土器が無造作に日常生活のなかで使われている実例などであった。その状況について、古谷氏は「考古学者が考える学術的価値」を越えた「先史文化の現代的利用」であると驚嘆し、さらに進んで「現代の日本社会においては、縄文文化はどのように活用されていくのだろうか」という疑問を投げかけている。
この本は、古谷氏がアマゾンで得た着想を現代の日本における縄文文化の再発見という文化現象を通じて、検証しようというものである。
とはいえ、その調査領域はかなり広範に及んでおり、考古学の縄文研究史、縄文遺跡の世界遺産登録や遺物の国宝指定から、実際の遺跡や博物館の訪問を経て、縄文関連書籍の急増や「縄文まつり」などのフェス&イベントの開催、土偶キャラや縄文グッズのマーケティングにまで及んでいる。それぞれのジャンルについて、具体的な資料や情報も豊富に詰まっており、文化現象としての「縄文ルネサンス」の全体像を具体的に描き出そうという野心的な試みとなっている。
この本の内容全体を俯瞰すると、3つの重要ポイントが見えてくる。
第一のポイントは、この本のメインテーマともいえる縄文イメージの変遷である。古谷氏は、参考文献として山田康弘の2冊の著書『つくられた縄文時代』(新潮社、2015年)と『縄文時代の歴史』(講談社新書、2019年)をあげている。それらを踏襲しながら、まさにいま日本で起こっている「縄文ルネサンス」という文化現象を解説している。

『つくられた縄文時代』(新潮社)
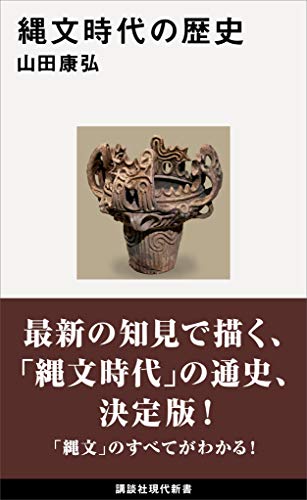
『縄文時代の歴史』(講談社新書)
「縄文土器」という名称は、1877年、エドワード・S・モースが大森貝塚を発見し、そこで見つけた「縄で文様をつけた土器(cord marked pottery)」をそう名付けたことから始まっている。日本における考古学研究もまたそこから始まったが、戦前においては「縄文時代」や「縄文文化」といった認識はなく、縄文土器を使用した人たちが生きた時代は「石器時代」と呼ばれ、日本人の起源についての議論が盛んだった。アイヌ説、コロボックル説などが論争となったが、発掘された人骨そのものを調査する形質人類学的研究から、現代の日本人の直接的な先祖は、縄文土器を作った石器時代人であると結論付けられた。
戦後には、美術家・岡本太郎による縄文の美の発見(1951年)という事件があったが、一般的には縄文時代は原始的で貧しい暮らしをしていたとずっと考えられてきた。だが、そんな従来の縄文イメージが覆るきっかけとなったのは、1994年、青森市の三内丸山遺跡で大型掘立柱建造物跡が発見されてからである。
そのことから、縄文時代に「長期的に大規模な定住生活を維持していた豊かな社会」があり、埋葬法や副葬品に差異が見え始めることから「階層化」も進んでいたとも考えられた。経済的にも栄え、文化的にも豊かな、新しい縄文のイメージが登場することとなったのだ。
第二のポイントは、縄文遺跡の世界遺産登録や縄文遺物の国宝指定を通じて見えてくる「縄文ルネサンス」である。それらを通じて、縄文が世界に誇る日本文化として海外へと発信されていくと同時に、日本各地で「縄文」が新たな地域復興のキーワードとしても浮上してくる。ちなみに、先に紹介した三内丸山遺跡を含む、「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、2019年に世界遺産への推薦が決定し、2021年の登録を目指している。
現在、縄文の遺物で国宝となっているのは、土偶5点と土器群1点の計6点である。1995年、最初に国宝指定された長野県茅野市の《縄文のビーナス》が出土したのが1986年、他の4点の国宝土偶の出土年と指定年を見ていくと、函館市の《中空土偶》出土1975年(指定2007年)、八戸市の《合掌土偶》出土1989年(指定2009年)、舟形町(山形県)の《土偶の女神》出土1992年(指定2012年)、茅野市の《仮面の女神》出土2000年(指定2014年)となる。また、縄文土器として唯一国宝となっている新潟県十日町市笹山遺跡の《火焔型土器》14点と《王冠型土器》3点を含む《深鉢形土器》57点ほかは出土1982年(指定1999年)である。

笹山遺跡(新潟県十日町市)
古谷氏は、国宝遺物のすべてが最近出土したものであることを指摘した上で、国宝土偶が多い理由として、2009年、ロンドンの大英博物館で開催された『土偶の力』展の大成功があると強調する。凱旋した土偶たちは帰国後すぐに東京国立博物館で『国宝土偶展』として展示され、複数の土偶の国宝指定へとつながった。
そして、改めて、上記の国宝遺物が勢ぞろいする形で実現したのが、2018年7月、東京国立博物館で開催された『縄文―1万年の美の鼓動』展である。この年の3月、古谷氏は「縄文ルネサンス」という文章を『西日本新聞』に七回連載しており、それらがこの本のベースになっている。2018年は、古谷氏が提唱する「縄文ルネサンス」という文化現象がわかりやすい形で顕在化した年と言えるだろう。
第三のポイントは、縄文文化と現代のアートとのかかわりである。
『縄文ルネサンス』の表紙を飾っているのは、現代アートと考古学の融合を目指している堀江武史氏の《ウルトラ・スカルプチャー》で、秋田県漆下遺跡出土土器をモデルにしている。
この本に帯文を寄せているのは、縄文考古学を代表する小林達雄氏である。小林氏は、国学院大学名誉教授であるとともに、故郷であることから新潟県立歴史博物館の名誉館長も務めている。新潟といえば、信濃川流域に出土する火焔型土器がよく知られており、それは新潟の縄文文化を代表するばかりでなく、最も広く知られた縄文土器のアイコンとしても定着している。
ここで注目すべきは、小林氏は「縄文を現代に活かす」という発案から、縄文をテーマとした現代のアーティストたちの作品にも関心が高く、2000年、新潟県立歴史博物館の開館特別展『[火焔土器的こころ]ジョウモネスク・ジャパン』では、現代の作品を考古資料と同じ会場で展示する試みを行っている。
その後、火焔型土器が出土するのがほぼ新潟県内に収まることから、いくつかの自治体が連携して「火焔型土器のクニ」復興運動が盛り上がり、2009年、小林達雄氏が理事長となって、NPO法人「ジョーモネスク・ジャパン」が設立されている。

新潟県立歴史博物館の火焔型土器コレクション
縄文からJOMONへ
このように見てくると、縄文文化と現代のアートとのかかわりもまた、「縄文ルネサンス」という文化現象のなかで進んできたことがわかってくる。
この本の終盤で、古谷氏は「『縄文ルネサンス』が、この十年ほど本格化しているのは、けっしてまったくの偶然ではないし、誰かが周到に仕組んだものでもなく、それなりの理由がある」として、いくつもの推論を展開している。そんななかでも強く共感できるのは、「縄文からJOMONへ」という地球規模で縄文文化を再発見しようというグローバルな視点や、現代の「縄文ルネサンス」関連の品々を未来の考古学者はどのように解釈するのかを想像する長いスパンの時間感覚である。
改めて、『縄文ルネサンス』を通じて、僕らの縄文タトゥー復興プロジェクト「縄文族 JOMON TRIBE」もまた、そのような文化現象から大きく影響され、時代の要請という“必然”を持って生まれ出てきたことを確認するとともに、今後の活動についても大いに励ましてもらったことに感謝したい。
今年の夏、「縄文族 JOMON TRIBE」の「なじょもん」での展覧会もまた、日本から世界に発信する新しい文化現象につながるものであろう。21世紀における「縄文ルネサンス」はまだ始まったばかりなのだから。
【INFORMATION】
ケロッピー前田『縄文時代にタトゥーはあったのか』
大島托(縄文タトゥー作品)
国書刊行会 2020年3月19日発売

本体価格2400円(定価2640円)https://amzn.to/38OTAfb
漆黒でオーバーオールな古代の和彫が近現代の鎖を断ち切り日本を日本に戻す。菊地成孔氏(音楽家・文筆家)推薦!!
土器や土偶にえがかれた線、円、点、螺旋といった我々を魅了する幾何学的な文様。これらがもしも太古の人体にきざまれていたとしたら――。世界中に残る痕跡をたどり、太古に失われたタトゥーを現代人に彫り込み「モダン・プリミティブズ」へと身体のアップデートを目指す壮大な試み。
〈MULTIVERSE〉
「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー
フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介
「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄
「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生
「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美