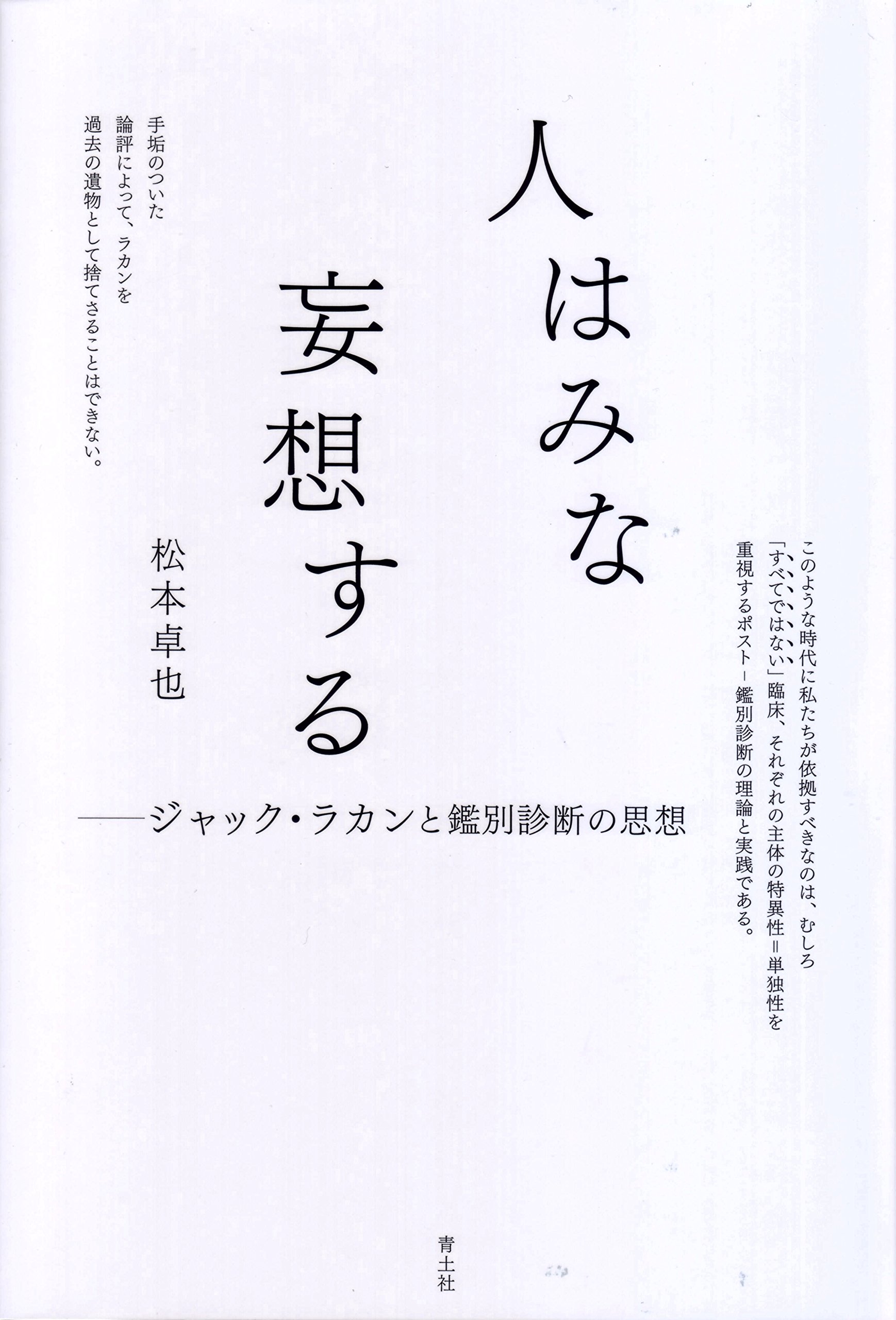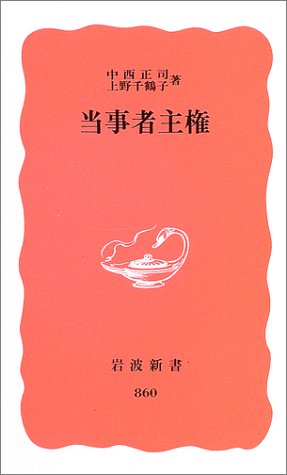今、戦略的に「自閉」すること──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー
ともすれば、過剰に「開かれ」すぎてしまったがゆえのディスコミュニケーションが目立つ現在、あらためて「自閉」という状態の持つ可能性を探る。精神科医・松本卓也氏インタビュー。
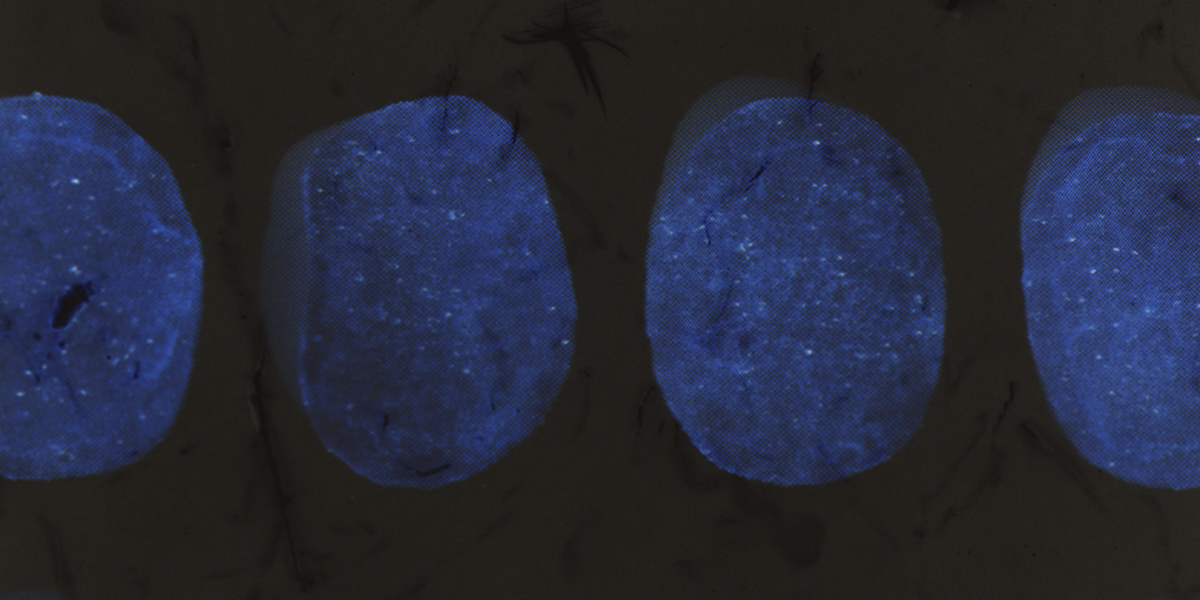
一般に主体のあり方をめぐっては、外に向かって「開かれ」ている方がより望ましく、逆に自らのうちに「閉じて」しまうことは望ましくないという、なんとなくの印象がある。言い換えれば、よりコミュニカティブであることが素晴らしく、そうでないことは悪いことであるという、うっすらと、しかし広く蔓延した信念のようなものが存在する。
近年、精神分析においても注目を集めている「自閉症」や「アスペルガー」が治療すべき病、定型的な主体モデルから逸脱した異常性として捉えられている背景には、おそらく、そうした常に「開かれ」ていることへの、そして「開かれ」ていることこそが正しいのだという、ある種のオブセッションがある。あるいは「コミュ障」や「コミュ力」なる言葉が広く流行し、カジュアルに用いられている背景にあるものも、それと同じものかもしれない。
しかし、果たして本当にそう言い切ってしまってよいのだろうか。いや、そもそも、外に向かって「開かれ」ている状態がコミュニカティブであり、自らのうちに「閉じて」しまっている状態はコミュニカティブではないという見立ては、本当に妥当な見立てだと言えるのだろうか。あるいは、そうした見立ては、逆説的にコミュニケーションの多様性を疎外し、人々を孤立させてしまうものとも言えないだろうか。
「現在一般にコミュニケーションであると考えられている仕方とは異なるつながり方があるのか。現在の自閉症研究が、その一つの試金石になっているように思っています」
精神科医であり、ラカン派の精神分析の研究者である松本卓也氏は、「自閉」のもつポジティブな可能性について、そう語る。また、その可能性を探る上で鍵となるのは「水平的な小さなグループ」を形成することであり、そうした小さなグループが起こす「ローカルな革命」こそが現代において大事なことなのではないか、とも。
ともすれば、「開かれ」てしまいすぎたがゆえのディスコミュニケーションが目立っているようにも見える現在、あらためて「自閉」という状態の持つ可能性を探る、ロングインタビュー。
(INTERVIEW & TEXT_Yosuke Tsuji)
(PHOTOGRAM_Masashi Mihotani)
HZ ようやくお会いできました。松本さんとは2017年に雑誌『STUDIO VOICE』に寄稿のお願いをして以来、原稿のやりとりこそさせて頂いてきましたが、ずっとメールのみでの会話でしたから。
松本卓也(以下、松本) 最初に寄稿したのはジャック・ラカンの「まなざし」についての原稿でしたね。今日ははるばる京大まで来てくださり、ありがとうございます。あとで吉田寮も見ていくといいですよ。ご案内しますので。
HZ 吉田寮は大学側との裁判などもあって、何かと話題ですよね。先ほど、少しだけ外観を覗いてきました。実は京大に来たのはこれが初めてなんです。ちょっと驚いたんですが、キャンバス内に喫煙所が一つもないんですね。タバコ呑みにはつらいなあ、と(笑)
松本 京大もだいぶ変わってしまいましたからね。それこそ吉田寮の問題にも表れているように、「学生自治」というこれまでギリギリ残っていたものがかなり脅かされている。もちろん、それが残っていたこと自体が珍しいのですが……、で、今日のインタビューはどういうテーマでしたっけ。
HZ 今日は「自閉」についてお話を聞きたいと思っています。ラカン派(※)の精神分析研究者として、松本さんはここ数年、従来の精神分析においては等閑視されてきた自閉症スペクトラムに注目し、「自閉」について精神分析的に捉え直すアプローチをされてきました。今日は、この「自閉」という状態が持つ積極的な価値について、松本さんにお話を伺いたいんです。
※ジャック・ラカン……フランスの哲学者、精神分析家。ジークムント・フロイトの精神分析を構造主義的に発展させ、ポスト構造主義思想に大きな影響を与えた。1981年没。
「自閉症」は社会が変化していく中で照らし出された症状
HZ 現在、「自閉」という言葉は非常にネガティブな言葉として用いられている印象があります。ある対象を「自閉的」だと形容する時、それは、その対象が外との交流を持たず、閉ざされている、ともすれば、自己完結的であり排他的であるといったニュアンスが強く、実際、「自閉的」という言葉が用いられる際、それは批判や揶揄としてがほとんどです。
しかし、僕は闇雲に「自閉」が悪いこととされてしまっていることに違和感があります。そもそも、あらゆる文化、表現の前提にはある種の自閉状態があり、その状態を経たからこそ生まれてきたものだとも言えます。それは古典的な文化のみならず、現代的なポップカルチャーについても同様でしょう。
もちろん、他者と「つながる」ということは重要だと思いますが、それと同程度に「自閉」することも重要なのではないか。あるいは、「開かれている」ことばかりを過剰に追求した結果、むしろ現代は「つながり」が極めて希薄化してしまっているようにも僕は感じています。そうした現状を踏まえた上で、あらためて「自閉」をある種の必要なプロセス、人や集団にとって必要な段階として、捉え直すことはできないのだろうか。今日はそのようなことをお話ししたいと思っているんです。
松本 それはとても重要な論点ですね。ただ、今おっしゃったような文化や集団における「自閉」について考えていく前に、まずは整理も兼ねて、精神医学の観点から症例としての「自閉」について、少し順を追ってお話してみたいと思います。
そもそも、精神医学において「自閉」という言葉が最初に提唱されたのは、1910年頃、「統合失調症」という概念を作り出した精神科医のオイゲン・ブロイラーによってでした。当時、ブロイラーは「自閉」という状態を「外の世界から撤退する」というイメージで語っていましたが、それと同時に、「自閉」することはある種の「内面生活の豊かさ」を伴うということも強調していました。この2つがセットになっているということが重要です。つまり、「自閉」のポジティブな側面というのは、初めから想定されていたことだったんです。
その後、「(幼児)自閉症」という疾患が発見されたのは1943年のことで、発見したのはレオ・カナーという医師でした。先ほども説明したように、自閉という言葉自体はそれ以前からあったものの、レオ・カナーによって疾患としての「自閉症」が発見されるまでは、「自閉」は統合失調症の一つの症状として捉えられていたんです。
では、この1943年まで、現在でいう「自閉症」と同じ症状を持つ人たちがどのように扱われていたかというと、知的障害などと混同されていた可能性が高いと考えられます。言い換えれば、レオ・カナーは当時、知的障害とされていた子どもたちの中から、ちょっと様子が違う特殊な一群がいることに気づき、彼らを「自閉症」と名指したんです。これは、そうした症状がこの時に誕生したというのではなく、医師たちの物の見方が変化したということです。
しかし、当時はまだ自閉症は幼児期に特有のものとして考えられていました。いまでは自閉症と連続的なものと考えられている「大人のアスペルガー症候群」というものが見出されるようになったのも、ようやく1980年代に入ってからです。「アスペルガー症候群」自体は子どもに見られる自閉症類縁の疾患として1944年に発見されたものだったんですが、80年代に、成人になるまで特に何の診断もされてこなかった人の中に、うまく周囲とコミュニケーションが取れない人たちがいることがわかった。それでよくよく調べてみたら、そういった人たちはアスペルガー症候群と呼ばれていた子どもと同じ特徴をもっていることがわかったのです。それ以降、実は自閉症やアスペルガー症候群の人は思っていた以上に社会に多くいる、という話になっていったんです。
HZ 現在は自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群などの症例名も、一般に広く浸透していますよね。しかし、たとえば精神分析において分析モデルとしてきた人格モデルは、長らく主に神経症と統合失調症の二つでした。近年になり、ようやく自閉症やアスペルガーが子どもに限定されない症例として発見され、また新しい人格モデルとしても注目されるようになったのはなぜなんでしょう?
松本 おそらく、そうした症状が発見されるようになった理由としては労働環境の変化があると思います。20世紀の後半、第三次産業が圧倒的に増えた。これは、他者とのコミュニケーションが常に要請されるような労働環境で働く人の数が増えたということです。そうした中で、これまでは目立つことのなかったそうした症状が目立つようになったのではないでしょうか。また、社会の中でコミュニケーションが重視されるようになると、それを前提に教育を行う学校空間の中でもそうした症状が目立つようになり、診断が下されるケースが増えた。だから、基本的には社会が変化していく中で照らし出されたものだと言えるでしょう。もちろん、社会情勢の変化によって、症状の出やすさ、主体形成のあり方も少しは変わっているという可能性もありますので、一概に「単に発見されるようになっただけ」とも言い切れませんが。
HZ なるほど。決着はついてないとはいえ、基本的には主体のあり方が大きく変わったのではなく、社会環境の変化によって、その存在が気づかれるようになったということですね。松本さん自身は、このように自閉症やアスペルガー症候群が大きな注目を集めるようになった現状について、どうお考えですか。
松本 先ほども言ったように、「自閉」には「内面生活が豊かになる」という側面があることが最初から指摘されていました。しかし、いかに内面生活が豊かであろうと、外部とコミュニケーションを取らない以上、その豊かさは外に表れづらい。その豊かさが認識されないという不幸な状況が長らくあったわけです。しかし、近年、自閉症やアスペルガー症候群が注目されるようになったことで、自閉症スペクトラムをもつ人々のアート作品なども注目されるようになっていますよね。
ただ、現在、彼らに注目が集まってしまっているというのは、現代社会において、コミュニケーションこそがいいものと見なされている、つまり、他者と円滑に言葉を交わし、相互に理解するという形の繋がり方こそが素晴らしく、あたかもそれ以外にコミュニケーションの形がありえないかのように捉えられている、ということの裏面でもあるわけです。それこそ「コミュ障」という言葉が流行したり、SNSなどを通じた「つながり」が過剰に賛美されたりというのも、その一環でしょう。「コミュニケーション」や「つながり」を重視することそれ自体が悪いというわけではありませんが、あるひとつの定型的なやり方で繋がることばかりが重視されてしまっているように思います。その繋がり方にうまく乗れない人たちが「自閉的」であったり「アスペルガー」だと名指されているとも言えるわけです。ここに一つの問題があると思います。
先ほど、現在は開かれすぎているがゆえに「つながり」が希薄化しているという指摘がありましたが、では、現在一般に「コミュニケーション」であると考えられている仕方とは異なる「つながり」方があるのか。現在の自閉症研究が、その一つの試金石になっているように思っています。
変化不能で共有不可能なマテリアルなもの
HZ ありがとうございます。いま自閉症が精神分析の中でスポットライトを浴びるようになった背景についてを説明していただいたわけですが、ところで、こうした近年の精神分析の動向、関心の変化は、他の諸ジャンルの最近の動向ともリンクしているように感じています。大雑把にいえば、現在、他者理解のモードが領域横断的に大きく更新されつつあるのではないか、と。これは松本さんがいまおっしゃった、現在一般にコミュニケーションだと考えられている仕方とは異なる「つながり」方を考える上でも、とても重要な点だと思います。
これは松本さんが以前、雑誌『atプラス』(atプラス30/臨床と人文知)でお話しされていたことですが、従来の精神分析では、表面に出ている症状にはもっと深い症状の真理があるという前提があり、その深層の真理を分析によって暴いていくことが可能だと考えられていたわけですよね。ようするに、患者のトラウマを発見することが、長らく精神分析の主な目的とされてきた。しかし、自閉症者には、そうした深い症状の真理というものが見当たらない。病因がより身体的で、偶発的なものであり、すると、もはや分析などできないのではないか――大雑把にまとめると、そういうお話でした。
これはつまり、解釈可能性をめぐる問題とも言えますよね。かつては人の精神とは解釈によって理解可能なものだとされていたわけですが、実は人の精神を完璧に解釈するなんてことは本当はできないのではないか、と考えられ始めている。この解釈不可能性への着眼は、たとえば近年、文化人類学において注目を集めている「存在論的転回」などとも、重なっているように思います。
存在論的展開の旗手とされているヴィヴェイロス・デ・カストロは、多文化主義に対して「多自然主義」という言葉で、西洋近代的な形とは異なる文化観、自然観について説明しています。これまでの西洋的な多文化主義においては、自然そのものは一つしかないが、しかし、その一なる自然を解釈する文化は多様に存在するのだと考えられていた。これは一般に文化相対主義と呼ばれる見方です。
一方、ヴィヴェイロスのいう多自然主義においてはこれが逆転し、自然が一つしかないのではなく文化こそが一つなのだとされます。しかし、文化は一つと言ってみても、他種を含めた私たちはそれぞれに異なる仕方で世界を捉えている。これはどういうわけなのかというと、自然が多数あるからだ、というわけです。ここでいう自然とはつまり、物理的な身体のことです(※)。
※多自然主義についてのより詳細な解説は、HAGAZINE内の別記事「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”にて読むことができる。
文化の差異とは異なり、身体の差異は言葉を通じた解釈によっては理解することができません。この転回は精神分析の自閉症への着目とも同じ方向を向いているように感じます。極端な言い方をすれば、今日の領域横断的な潮流は、私たちはそれぞれに特異な身体によって自閉した存在であり決して理解し合うことなどできないということを、あらためて私たちに突きつけているように思います。すると、やはり重要になってくるのは、そうした理解に頼らない「つながり」方はどういうものなのか、ということになるわけです。
松本 そうですね。今、現代思想を含むさまざまな領域で何が起こっているかを大枠で捉えるなら、それは「社会構築主義に対する揺り戻し」かもしれません。あるいは相対主義に対する揺り戻しといってもいいでしょう。ポストモダンの思想においては、「何かしらの文化的ファクター、経済的ファクター、言語的ファクターが世界の認識を作っているがゆえに、世界はそれぞれ相対的なものだ」という見立てが主流でしたし、それが革命のイマジネーションを形づくってもいました。相対的であるということは、今ある形と違う形で社会を作ることができるのだ、ということでもありますから。だからこそ、ポストモダン思想は政治思想にも応用されえたわけです。
だけど、今日において気付かれつつあるのは、いかに社会的に構築されていると言ってみたって、その根幹には、変化不可能なマテリアルなもの、そして他人とは分かち合えない共有不可能なものがあるだろう、ということであるように思います。その気付きは様々なジャンルを横断する形で起こっていて、たとえば哲学であれば思弁的実在論がそうですよね。あるいは人類学の存在論的転回なども、僕はあまり詳しくないですが、文化相対主義とは違う仕方で、自然そのものを多数的なものとして考えようとしている。また、フェミニズムにおいても似たことが起こっていると言えるかもしれません。第二波フェミニズムは、いわゆる「女らしさ」というのは社会的に構築されたものであると考えたわけですが、第三波フェミニズムや、なかでもポストフェミニズムと呼ばれる人たちにおいては、やはり身体というマテリアルな次元が問題とされるようになっており、かつてなら「社会的に構築されたもの」として考えられていたような性的なあり方を主体的に選択する女性の欲望などについて問われるようになっている。
あるいは障害をめぐる議論についてもそうした流れがあります。「障害の社会モデル」という考え方において、障害はどこにあるかといえば、私の身体にあるのではなくて、社会の側にあるのだ、とされていました。つまり、街から段差をなくしてバリアフリーにすれば障害はなくなるのだ、という考え方ですね。これはまさに障害に関する社会構築主義であると言えます。確かに、理屈としてはそれで解決するように思えるんだけれども、しかし、やはりそれは頭の中だけでの解決だと言うこともできる。実際、バリアフリーになったところで、自分の足がうまく動かないという事実は変わらない。また、身体障害に比べて、自閉症スペクトラムのような障害は見えにくいものですから、見えるバリアをなくすことだけでは生きづらさを減らすことが難しい。だとすれば、実際に自分の身体や脳にどのようなマテリアルな問題があるのかについてをあらためて考え直さなければならないということになる。
HZ 松本さんは現在のこうした潮流をどう評価されているんでしょう?
松本 マテリアルなものを考え直さなければならないということ自体は、正しいと思っています。ただ、その上で注意しなければならないこともある。最近、そうした流れに乗っかる形で、変なことを言う人たちがたくさん出てきているでしょう。いわゆるバックラッシュの人たちです。たとえば、近年よく売れた新書で、人種間のIQの差はやはり明らかにあるだとか、男女にはこのような本質的な差があるとか、まるで社会構築主義という考えなどこれまで存在しなかったかのように「これこそが事実なのだ」ということを「エヴィデンス」にもとづいて指摘するようなダークな知性がありますね。あの著者は、人種差別をなくそうという動きがずっとあったにもかかわらず、白人と黒人のあいだのIQの差が埋まらないという「事実」から、生来的なIQの格差が「実在」すると主張しています。しかし、「ブラック・ライヴズ・マター」の運動などをみればわかるように、現在でも人種差別ははっきりと存在しており、やはり社会構築主義的な視点から物事をみなければいけないことも多いはずです。しかし、バックラッシュの人たちはそこを無視した上で「事実」を主張するんです。思弁的実在論に影響を与えた人物として、ニック・ランドがいますが、彼に象徴されるように、そうしたバックラッシュ的な流れと、新しい知の流れとの区別がつきづらくなっているということは、危ないと感じていますね。
HZ その危うさは非常に感じます。僕も昨今の流れ、マテリアルな部分や身体的な部分をもう一度、再評価していくということは、非常に重要なことだと感じているのですが、しかし、そうした立場から自分の主張を組み立てていこうとすると、期せずして排外主義的な一部の保守系の人たちに部分的に似てきてしまう。まさに今日の「自閉を再評価する」というテーマ設定自体、あらぬ誤解をされてもおかしくはないわけで(笑)。もちろん、きちんと見ていけば明らかに方向性は違うわけですが、たとえばSNS上などにおいては、どうしても断片的な言葉だけが飛び交うことになるので、区別がつきづらい。実際、今話してきたような流れにある議論は、右なのか左なのか、一見するとどっちつかずで、両方から攻撃されがちでもあります。そういう状況が割と目につく。
松本 この潮流をどっちの領土にするかみたいな話ですよね(笑)。ここは本当に難しいところだと思います。だから、「自閉」についてを語る上でも、少し迂回しておきましょう。「自閉」に関連して、僕が最近興味を持っているのは、「当事者」という言葉なんです。
孤立による他者叩きを回避し、本当の意味での当事者性を立ち上げる
松本 日本で「当事者」という言葉が大きく注目を浴びるきっかけとなったのは、上野千鶴子と中西正司が岩波新書から共著で出した『当事者主権』という本です。この本によって、「当事者主権」という言葉が一気にメジャーになりました。ようするに、外部があれこれ言っていることよりも、当事者の言っていることの方が大事なのだ、という考えが登場した。当事者こそが一番大事でしょう、と。もちろん、これは大事な考えです。しかし現在、この「当事者主権」がややおかしな方向に向かっているように僕には見えるんです。
上野と中西の本の中で「当事者」として想定されていたのは、たとえば女性や障害者でした。しかし最近、当事者の声として強く聞こえるようになったのは、いわゆる「非モテ男性」の人たちだったりします。弱者男性論の文脈で、当事者性が強く指摘され始めているんです。もちろん、男性が当事者性を主張すること自体はとても大事なことです。それ自体に問題があるわけではない。しかし、なぜか目立っているのは当事者性を盾にした女性叩きだったりする。たとえば「女性が下方婚をしないことが問題だ」とか「女性専用車両は男性差別だ」といったようなことを彼らは言うわけです。これは明らかに戦う方向を間違っています。本来、男性が男性性で苦しんでいるのであれば、性別役割分業を批判するフェミニズムと連帯ができるはずですし、トロフィーワイフ的に女性を物として捉えていることが結果として自分たち自身を困難な状況に追い込んでいることを無視している。
思うに、「当事者」という概念は、上野と中西の『当事者主権』の後、どこかで捻じ曲げられてしまったのでしょう。実際、震災後に佐々木俊尚の『当事者の時代』という本が話題になりましたが、あの本で彼は「マイノリティ憑依」という言葉を使って、「当事者のことを他の人が代弁すべきではない」という点を強調した。それによって、「当事者にこそ主権がある」という箇所だけが「当事者」という概念の価値だと考えられるようになってしまったのではないかと思うのです。そこから、弱者男性論のような当事者の主張が強さをもつようになる土壌がつくりあげられてしまったのではないか。しかし、このような「当事者」概念は、当初考えられていた「当事者」概念の半分の側面しか見ていません。だから、僕は「当事者」という概念をリブートしなければならないと思っているんです。後で話しますが、これは「自閉」の話にも繋がってきます。
HZ たしかに、弱者男性論に限らず、SNSによって「当事者」の声が直接的に発信されるようになったことで、当事者がこうと言っているんだからこうなんだ的な、ある種の思考停止が起こっているような印象はあります。もちろん、一方で外部の人間が推測だけであれこれということは問題ではあるものの、これではどこか身も蓋もない感じがする。その上で「当事者」という概念をリブートするとは、一体どういうことなんでしょう。
松本 そもそも、上野千鶴子らが『当事者主権』で話していたことは、単に「当事者が主権を持っている」という話ではありません。また、「当事者という人が最初からいるのだから、その人たちに主権を渡そう」という話でもなかったんです。あの本において、もっとも大事なポイントは、「人は最初から当事者であるわけではなく、当事者になる」ということです。つまり、当事者になること、当事者への生成が大事だということなんです。
近頃言われているような「当事者の意見が大事」という時の当事者とは、実はまだ当事者ではない。そこにある要素が入ってこないと、人は当事者にはなれない。では、そのある要素とは何か? それは、自分とよく似た人々からなるグループ(集団)なんです。たとえば女性の大学進学を例にとってみましょう。現在、大学の進学率は50パーセントくらいですよね。僕が勤めている京大の生徒でも、田舎出身で、特に女子であったりすると、地元では「東大京大とかそんなのやめときなさい、女の子なんだしそもそも短大にしなさい」みたいなことを言われてきた学生がいます。そのように言われて育つと、「そんなものかな」と思って、大学進学というものが自分にとって当事者性のないものになってしまいます。むしろ、田舎の慣習に従って生きていくことが当たり前になって、そのことに疑問をもたずに育ってしまう。
では、そのときに当事者性を持つために何が大事かというと、自分と似た境遇にいる人たちのグループに入ることなんです。そして、もう一つ大事なことは、そのグループの中に「ちょっと上の先輩」がいるということ。たとえば田舎出身なんだけど、大学に行って、今は何らかの研究や仕事をしている、というような人ですね。そういう人がいることで、一つのロールモデルができ、「自分にもこういうことができるんだ」と思えるようになる。そこで初めて「自分も大学に行ってみたい」という気持ちが生まれ、大学進学ということに関しての当事者になるわけです。
障害者についても同じです。重度障害の人で、周囲から「施設で暮らしたほうがいい」と言われていると、自分自身、施設に入った方がいいものだと思いがちです。しかし、同じ重度障害の人のグループに参加して、同じ障害を抱えているにもかかわらず一人暮らしをしている人たちのことを知ることで、初めてこの問題の当事者になれる。「一人暮らしにチャレンジしてみよう」という切実な気持ちが生まれる。これが非常に重要なことだと思うんです。上野千鶴子はそのことを「ニーズはあるのではなく、つくられる」と表現しています。この言葉の裏を返せば、「ニーズが発生しなければ、人は当事者になれない」ということでもある。そして、ニーズの発生のためには、お互いをエンパワーメントするようなグループが必要なんです。
先ほどの弱者男性論の人たちには、そうした意味でのグループが機能していないように感じます。語りの中で自分自身がエンパワーメントされている感じがしない。だから、他者をディスエンパワーメントする流れに走ってしまう。実際、弱者男性論の言説はなぜかフェミニズムに対する批判に向かいがちですが、それは、女性たちが運動の成果として獲得してきたものに対して、「自分たちも同じようにエンパワーメントされたい」ではなく、「エンパワーメントされてきた女性たちを引きずり下ろしたい」という態度になるからでしょう。ついでに言えば、彼らが好きな言葉に「反転可能性テスト」がありますが、この言葉はつねにフェミニズムの主張に対するディスエンパワーメントのために使われていますね。このような傾向は、「ネトウヨ」と呼ばれる人たちにも指摘できるかもしれません。彼らには自分たちの力を高めていくように機能するグループがなく、数はたくさんいてネット上でつるんでいるようには見えるけれども、「当事者」という概念からみると、実は孤立している。だから、グループの力によってエンパワーメントに成功しているように見える他者やマイノリティを叩くことが語りの中心になってしまう。
実は自閉症においても、このグループの力が重要なんです。最近、國分功一郎さん、熊谷晋一郎さん、千葉雅也さんらと自閉症の研究会をやっていて、そこでも議論していることなんですが、自閉症スペクトラムの人は相対的に人口が少なく、つまりはマイノリティであるため、自分と似た人に出会える確率が低いんですね。すると、自閉症スペクトラムに特有の何らかの認知の特性を持って生まれてきた人にとっては、身の周りにいる人が、自分と同じような仕方で世界を見ていないということが常態化する。だから、ちょっとしたコミュニケーションにおいても齟齬が生じ、通じ合えなくなってしまう。すると、いま自閉症スペクトラムの症状だと考えられているもののいくつかは、自分とよく似た人とのグループの作りにくさや、グループをつくる機会の相対的損失やそこから来る孤立の結果であると考えられるかもしれないのです。
だから、自閉症の人たちがそういうグループを形成する環境を確保しなければならない。実際にそういう実践を行なっているところもあります。自閉症の子どもを集めて、電車が好きな人たち、地図が好きな人たちという風に分けてグループを作り、そこに通ってもらう。すると、普段は周囲とうまくコミュニケーションが取れない子どもでも、そこであればコミュニケーションが取れるというようなことが起こる。
このように、現実に顔を突き合わせて会うような、自分と似たような人がいるグループを作ることが、孤立による他者叩きを回避し、本当の意味での当事者性を立ち上げる上では重要なんです。また、そのグループには、「ちょっと上の先輩」はいたほうがいいのですが、「偉い人」がいてはいけない。要するに、権力関係のない水平的なグループでないといけない。こうしたグループの形成が、自閉症に限らず、今後は大事になってくるんだろうと思います。
HZ 同質性の高いグループを形成するというのは、まさに輪になって「閉じる」ことでもありますよね。一方、孤立しているとは、ある意味で全方位的に開かれているということだとも言えます。つまり、「自閉」することにも種類があり、群れずに一人で自閉してしまうことは、逆に「閉じる」ことを難しくしてしまうのかもしれません。いま松本さんがおっしゃっていたグループ形成というのは、ある種の小集団的自閉と呼べるものではないかと思いました。
平準化に抗する水平的なグループを形成せよ
HZ ところで、今、松本さんは「水平的なグループ」とおっしゃいましたが、この水平性についてもいくつかの種類があるように思います。たとえば、バラバラに孤立した人たちからなる水平的な関係となると、これは「出る杭は打つ」というような形になりやすい気がします。それこそ、先ほど松本さんが例に出した、弱者男性による女性叩きのような形です。一方、そこになんらかの垂直性があると、目標のようなものが生まれ、上向きの切磋琢磨が起こりやすいと思うんですが、しかし、それもまたバラバラに孤立した人たちを前提とすると、ある種の全体主義のような、極端な超越に向かいがちです。
だから、同質性が比較的に高い小さめのグループであることが大事なんだと思いました。先ほどの「ニーズ」の話でいうと、グループの中で「ニーズ」が共有されることで、その水平的な関係性においてグルーヴ感が生まれ、緩やかな上昇が生じていくといいますか。
松本 そこがとても重要ですね。というのも、これまで水平性については、その片側しか顧みられてきませんでしたから。そもそも、こういう文脈で使われる水平性という言葉は、明らかにキルケゴールに由来しています。キルケゴールが『現代の批判』と題した文章の中で、現代社会は水平化(Nivellering)されていると論じた。ここでいう水平化とは、つまり平準化(Einebnung)のことです。キルケゴールの危惧の背景には、当時、社会が工業化されていく中で、みんなが同じ既製品を使い、同じような消費生活を送るようになったことがありました。
これは現在でも同じです。たとえば、今であればみんなiPhoneを使っている。まるで人民服のように。それなのに、なぜかiPhoneが個性を表すものだと思い込んでいる。キルケゴールはこの平準化を「水平化」と呼び、批判したわけです。たしかに、その批判は有効ではあるんですが、しかし、これは本来、水平性の一面にしか過ぎません。
こうしたキルケゴールの一面的な水平化=平準化論を真に受けたのがハイデガーでした。ハイデガーは、人間の横の関係というのは平準化に帰結してしまう、そこに埋没してしまうのではいけないと言っています。だからこそ、自分が死にゆく存在だということを自覚して、垂直的な理想に目覚めよ、と主張したわけです。しかし、その結果、ハイデガーが向かったのはナチスであったわけですから、水平性を嫌って極端な垂直性を求めるのは、やはり危険なんです。
もっとも、ポストモダン以降、「大きな物語の終焉」という言葉に代表されるように、垂直性にはほとんど可能性がないように思えます。だとすれば、水平性がもつ、平準化ではないもう一つの側面を評価していく必要がある。平準化が貧しい水平性であるとすれば、豊かな水平性があるのではないかと考えるのです。たとえば、先ほど説明した当事者によるグループはまさにそれではないでしょうか。似た者同士が小さく集まりつつ、水平的な関係性の中で相互にエンパワーメントしていく。しかも、それによってみんな一緒になってしまう(平準化されてしまう)というわけではない。逆に水平的であるからこそ、ちょっとだけ垂直的に突出できることがある。そういう動きを支援する水平性というのものがありえる。だから、平準化と水平化を区別すべきだというのが僕のテーゼなんです。ハイデガーが水平化=平準化を非本来性と結びつけたことと反対に、むしろ水平性に本来性を結びつけることができないか。それは、平準化のように見えているものの中から、いかにして本来的な水平性を取り出していくか、ということです。
では、具体的にどのようなグループであれば豊かな水平性を実現できるか。病院やケアの現場を念頭に置いて話せば、そうした水平性を確保するためには、時間をゆっくりと取り、すぐに決断を迫られないということが大事です。最近は決定力が大事、といったような思想が世界を覆っていますが、決定しなくていいという自由が担保される必要がある。あとは上から何かを押し付けられないで済むということ、そして、雑多なものがその辺にたくさんあるということも大事です。水平性の関係がクリーンになりすぎてしまうと平準化に近づいていってしまうので、気を散らせることができる状況が必要なんです。
統合失調症や自閉症の患者さんが行う作業療法などの現場について考えてみましょう。そこでは、どうしても、効率的な治療プログラムを考え、そこにいる患者さん一同に同じことをさせようとしてしまいがちです。しかし、そのようにしてしまうとちょっとした逸脱が許されなくなってしまい、患者さん自身を一つの工業製品のように扱ってしまう状況が作られてしまう。だから、作業をやらせるにしても、一つの作業をみんなにやらせるのではなく、たくさんの作業があるということが大事になる。あるいは、何もしてなくてボーッとしているだけの人がいてもいい。そういう緩やかな空間が確保されることで、何か突出したものが生まれて可能性が生まれるのです。
精神分析家のフェリックス・ガタリも似たことを言っています。自閉症的な人は常同行為といって、ずっと同じことを繰り返し行い続けるという傾向があるんですが、ガタリいわく、その繰り返しがある極点を超えると芸術作品が生まれる。これは、自閉症者の例を出さなくても、なんとなく分かりますよね。たとえば職人技などもその類です。包丁研ぎのような一見すると単純な作業を何十年もずっとやっていて、それがある域値を超えると、ロボットなどには絶対に真似できない芸術になるわけです。
そして、おそらくそれは一人じゃできないんです。ずっと同じことを続ける時に、周りに同じようなことをしている人がいる必要がある。だからと言って、それはコミュニケーションが重要だということでもない。コミュニケーションは、取ってもいいし、取らなくてもいい。むしろ、世の中で「コミュニケーション」と呼ばれているものではないコミュニケーションをそこで新たに発明することができるような空間です。僕は臨床現場に限らず、そういう空間を世の中にたくさん作るべきだと思っています。もちろんこれは簡単なことではありません。人は、ほうっておいても権威をつくり、ヒエラルキーをつくり、そのヒエラルキーのもとでメンバーを管理しようとしてしまいます。つまりは、水平的なグループは容易に平準化されてしまう。だからこそ、こういった現場には、平準化に抗する耐えざるメンテナンスが必要なのであって、それは過酷なものであると言ってもいい。
HZ 非常によく分かります。話したり、話さなかったりしつつ、ただ一緒にいるということ、言い方を変えれば「ゆるくつるむ」ということは、まさにマテリアルなつながり方であり、相互理解とはまた異なる身体の出来事ですよね。そこでいうと、松本さんは以前、そうしたグループを多様に形成することを「部族化」と呼んでいましたが、その言葉選びに僕はすごくしっくりきたんです。ただその上でも、その部族は、ある程度、外部から切断されていなければならないですよね。部族の規模が大きな規模になってしまうと、すぐに平準化が起こってしまいますから。
松本 そうですね。平準化に抗する水平的な集団というのは、おっしゃる通り、ある程度の小ささじゃないといけないんです。少なくとも、ある程度の大きさになってしまったグループを平準化させないための技法を、僕たちはまだよく知らない。だから、その水平的な小さなグループが隣のグループと統合してより大きなグループになって、さらに大きなグループになって、と向かってしまったとしたら、グループとしては不完全になる。その先にあるのは国家であり、さらには帝国主義かもしれませんから。つまり、グループの巨大化は必ず権威を発生させてしまうんですね。
そうなってしまえば、せっかくの水平性がダメになってしまう。だから小さな小集団のままでいい。そこで特異的な実践ができればいいんです。身も蓋もないですが、たとえば政治について言えば、そうした小集団の形成によって、国家の形や世界の形が一変するかと言えば、そんなには変わらないでしょう。小さな集団の力はたかが知れています。ただ、それでも、必ず効果は発揮するはずなんです。外山恒一風に言うと「奴らはビビる」です(笑)。たとえ小さなコミューンみたいなものだとしても、そこですごく変わった特異的な実践がなされていれば、それに気づく人が出てきて、なんらかの影響を受けることになる。別にその小集団で最終的に権力を奪取しようなんて考える必要はなくて、そういう存在があることで、どんな人たちもその実践に降りてこれるようになる。彼らが別のグループを作れるようになる。そこに「ニーズ」が生まれ、新たな当事者が生成するんです。
政治の話になると、すぐ政権交代や、場合によっては革命だ、なんていう言葉が聞こえてきますが(笑)、せっかくつくった水平性の中にいきなりそんな大きな垂直性を置く必要はないんです。いまのところはただ奴らをビビらせてやればいいんです。
ジャック・ラカンの「パス」——水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ
HZ (笑)。それで言うと、統合し、巨大化し、権力構造が生まれてしまうことを回避する上でも、文化相対主義的な解釈による相互理解をいったん退ける必要があるのだろうと思いました。異なる小集団を解釈によって包摂することをやめ、「わからない」を前提にする。「わかる」ためには少なくとも身体を共にするということを倫理としていくことで、グループ同士の過剰な接続を防ぐ。
僕にとって集団の一つのモデルは部活動や公立中学校なんです。悪い言い方をすれば、様々な部活同士、学校同士には、あまりシリアスではない軽微な紛争があるじゃないですか。「第一中学の連中はチャラい」「第二中学の連中はダサい」みたいな、あのノリです。実際に仲が悪いというわけでもないし、相互に交流もあるんだけど、儀礼的にディスり合ってる。そうした紛争そのものが目的化したような紛争が、実は重要な役割を果たしている気もするんです。というのも、この軽微な紛争すらないと、たちまち集団は巨大化してしまいますから。
松本 縄張りみたいなイメージですよね。あるグループとあるグループが、それぞれの縄張りを代表してラップバトルするような。遊びに近い、マジじゃない喧嘩くらいがちょうどいいんだと思います。そこで高みを目指しすぎると、どうしても統合や権威に向かっていくことになりますが、そんなことは目指さない方がいいんです。ローカルな横のつながりの現場の革命をまずはやるべきで、そのためにはまずはあまり高さのことを考えない方がいい気がします。
実は僕は、ジャック・ラカンが考えていたことも、実はそういうことだったと解釈する余地があるのではないかと思っているんです。ラカンはある時期に国際精神分析協会というところから破門されているんですが、ラカンは国際精神分析協会の非常にヒエラルキー的な性質に批判をくわえるようになった。当時の国際精神分析協会は、フロイトから精神分析を受けた人がもっとも偉くて、その人から精神分析を受けた人が次に偉い、といった具合に、ピラミッド型のヒエラルキー構造をとっていた(※)。すると、自然とグループで一番偉いのは、存命中で一番歳をとってる分析家だということになる。だから、「精神分析とは上から教わるものだ」ということが常態化していたんです。教育分析というのは、権威ある上の世代から下の世代に向けて行われるものですよね。
※国際精神分析協会において精神分析家として認められるためには、すでに精神分析家である人物から精神分析(教育分析)を受ける必要がある。
それに対し、ラカンは1967年に「パス」という装置を提案したんです。この「パス」でラカンが何をやろうとしたかというと、「精神分析とは上から教わるものだ」という考えを逆転して、「最も若い分析家にこそ最も大きな可能性がある」という考えを行き渡らせようとしたのです。「現在において精神分析とは何か」と言う問いに答えることができるのは誰かというと、普通に考えると一番年配の分析家がそうだと考えてしまうわけですが、ラカンはまったく反対のことを言っていて、今まさに自分の分析を終えようとしている人物、要するにまったくの駆け出しの人物こそが、「現在において精神分析とは何か」について語る権利があり、その人物が精神分析家のグループに「精神分析とは何か」を教えるのだ、と主張したのです。
こうしてラカンは精神分析家のグループがもつヒエラルキーを脱構築したわけですが、その際に、最も若い分析家の分析経験がグループに教えるに値するのかどうかを判断するために提案されたのが「パス」という装置だったんです。「パス」においてラカンが重視したのが特異性という概念でした。ラカンによれば、一人一人の分析経験は特異的であり、誰とも共有することはできない。しかし、その特異的な分析経験は伝達され、共有されることがありうる。こういう逆説をラカンは言っていたんですが、その伝達が起こったのかどうかを確かめる装置が「パス」だったんです。
具体的にどうするかというと、まず自分の分析経験が終わりに近づいている人物Aが、別の人物Bに自分の分析経験について話すんです。そして今度は、そのBが承認審査委員会というところで、Aの経験を話す。A本人は委員会に直接話をしないわけです。言ってしまえば伝言ゲームのようなものなのですが、こうした伝言ゲームを経ても、そのAの分析経験の特異性がちゃんと伝わるのかどうかを試す装置が「パス」だったのです。
ちなみに伝言の仲介をする人物Bは「パサー」と呼ばれているんですが、そのパサーは、この「パス」を行う人物Aと、だいたい同じくらい分析が進んでいる人から選ばれます。ここでもやはり、自分と似た状況の人の存在が重要なのです。自分と似た状況の人に自分の経験を話すことによって、何かが伝達される。他の人とは異なる個々の特異性は、類似した人とのあいだで伝達され、グループ全体で共有されうる。そういったことをラカンは考えていたんです。
まとめると、まず垂直的なヒエラルキーを問い直し、最小化することによって、精神分析を「上から教わる」ものではなく、「下から教える」ものに変える。しかし、「下から教える」と言っても、「誰でも当事者である」わけではないのと同じように、誰もが学派に教えることができるわけではない。では、誰ならいいのか。その人物の分析経験の特異性が水平的な横の関係において伝達されることが確認された人物でなければならない。それによって、初めてその人物がグループに教えることができるというわけです。つまり、水平的な横の関係を確保した上で、ちょっとだけ垂直的に立つことが大事だというわけですね。
ラカンは分析家の語りは資本主義からの出口だと考えていました。「パス」の提案はまさにその実践だったのかもしれません。もっとも、その話はお互いに顔を知っているくらいの小さな分析家のグループには妥当するとしても、それが国家規模においても資本主義の出口だと言えるかどうかは別の話でしょう。しかし、ラカンは分析家のグループ内のローカルな革命だけをやることでいいと思っていたようなのです。そういうグループがあることによって、たぶん何らかの影響を世の中に与えられると考えていたのかもしれません。
HZ 非常に面白いお話ですし、どこかアナキズムにも近い実践的態度のように思いました。結局は、それぞれがそれぞれの場所でグループを形成し、それぞれの実践を粛々と行なっていく他ない。大きく何かを変えていく上でも、まずは局所的に小さな革命を起こしていこう、と。
さて、色々と伺ってきましたが、最後にこのインタビューをまとめる形で話を「自閉」に戻せば、やはり現在は「開く」ことよりも「閉じる」ことが重要な局面になっているような気がしています。もちろん、端的な排外主義などには断固として抗っていく必要はありますが、「開く」ことが必ずしも「つながる」ことに帰結するとは限りません。今日のお話によって「自閉」しながらも「つながる」ことの可能性が垣間見えたような気がしています。
松本 そもそも、自閉症ではない人たちがコミュニケーションだと思い込んでいるものなんて、実は大したコミュニケーションでもないんですよ。「おはよう」って言われたから「おはよう」って返そう、ついでに天気の話でもしておくか、みたいなもので、そこに含まれている情報量なんて実際にはほぼゼロだったりする。我々は普段、ただコミュニケーションをしていると思い込んでいるだけだとも言えるんです。
一方、自閉症の子どもたちを見ていると、ものすごいマニアックな話を挨拶も一切せずに始めたりするんです。はたから見るとびっくりしてしまうんだけど、それで十分に彼らのコミュニケーションは成立しているんです。
HZ 自閉症に限らず、子どものコミュニケーションは面白いですよね。以前、作家の石丸元章さんがお話しされていたんですが、息子さんがまだ幼稚園生の頃に、友達たちと砂場遊びをしている姿を眺めていたそうなんです。その時にハッと気づいたそうなんですが、一見すると子どもたちは一緒に砂を掛け合ったりして遊んでいるように見えるものの、よくよく見ていると、それぞれの子どもたちがそれぞれのルールで動いているだけで、実際はバラバラの遊びをしていることに気づいたそうなんです。だけど、表面的にはコミュニケーションは成立している。あたかも小さな砂場の上にマルチバース宇宙が相互干渉的に展開しているかのようなイメージです(笑)
松本 子どもはそうなりますね(笑)。それと、コミュニケーションはコミュニケーションをしないことを含めてコミュニケーションなんです。一時的に一人でなにか同じ動作をずっとし続けるといったことも非常に重要で、そうしたことを可能にする上でもグループが大切なのだと思います。
最後に、キング・クリムゾンのギタリストのロバート・フリップの話をしておきましょう。彼は「ギター・クラフト」という一種のギター学校も運営していたのですが、その学校の生徒に関して彼が面白いエピソードを話していたことがありました。なんでも、そのギター学校で、ある一音だけをただ淡々と弾き続けている生徒がいたそうなんです。周りの生徒たちはメタルの早弾きみたいな練習をしている中、同じ音だけをずっと弾いていたんですね。やがて早弾きの練習をしていた一人の生徒が、その一音だけを鳴らし続けてる生徒に「そんなので練習になるのか?」と聞いたそうなんです。すると、その生徒は「俺は自分の音を見つけた。お前はまだ自分の音を見つけていないんだろ」と言ったらしい。フリップは、まさにその生徒のようなあり方を重視していたのですが、ある共通点を持ったグループが同じ空間にいるだけで、こういうちょっとした特異性が生まれてくることができる。早弾きの練習をしている人たちはイングウェイ・マルムスティーンみたいな早弾きの権威が好きで、「もっと早く」という垂直的な方向ばかりにいきがちなんですが、そんな中でも横にズレたやり方をする人が出てくるんです。
HZ 突如、名もなきアート・リンゼイが現れるわけですね(笑)
松本 そうそう(笑)。そういうことにこそ可能性を見出していきたいですよね。
HZ そう思います。今日はどうもありがとうございました。
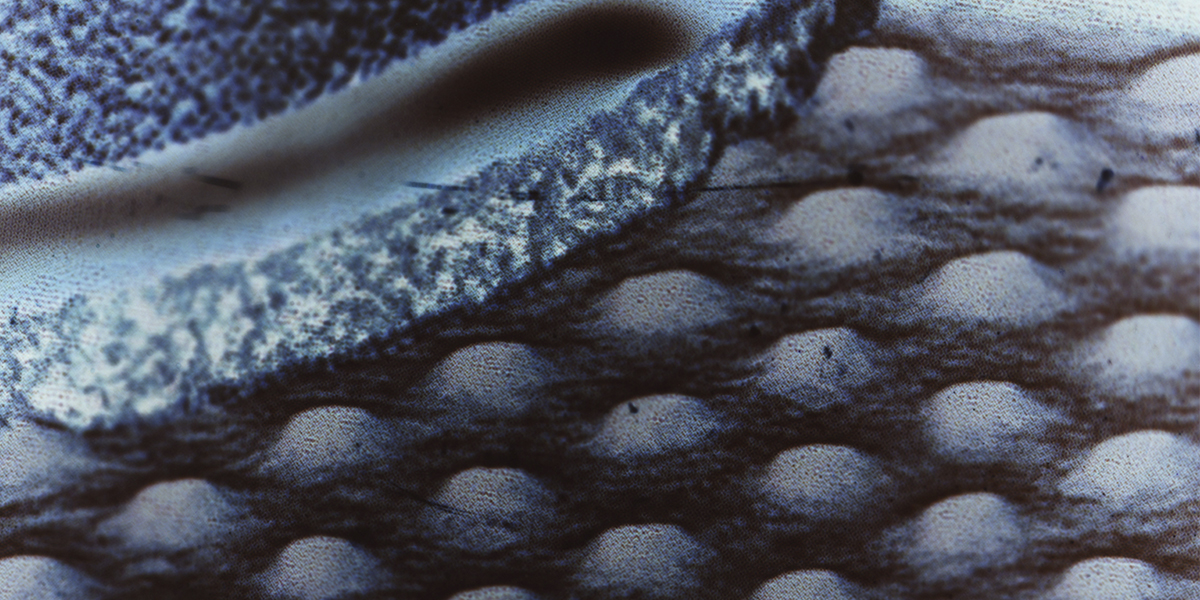
(INTERVIEW & TEXT_Yosuke Tsuji)
(PHOTOGRAM_Masashi Mihotani)
✴︎✴︎✴︎
松本 卓也 まつもと・たくや/1983年、高知県生まれ。高知大学医学部卒業。自治医科大学大学院医学研究科博士課程修了。博士(医学)。現在、京都大学大学院人間・環境学研究科准教授。専門は、精神病理学。主な著書に、『人はみな妄想する』(青土社)、『享楽社会論』(人文書院)、『〈つながり〉の現代思想』(共編、明石書店)、『症例でわかる精神病理学』(誠信書房)など。主な訳書に、ヤニス・スタヴラカキス『ラカニアン・レフト』(共訳、岩波書店)など。
✴︎✴︎✴︎
〈MULTIVERSE〉
「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美