檀廬影×菊地成孔 『エンタシス書簡』 二〇一九年十一月/檀→菊地「ユングの曼荼羅と三十歳の夏」
元SIMI LABのラッパーであり小説家の檀廬影(DyyPRIDE)と、ジャズメンでありエッセイストの菊地成孔による往復書簡。
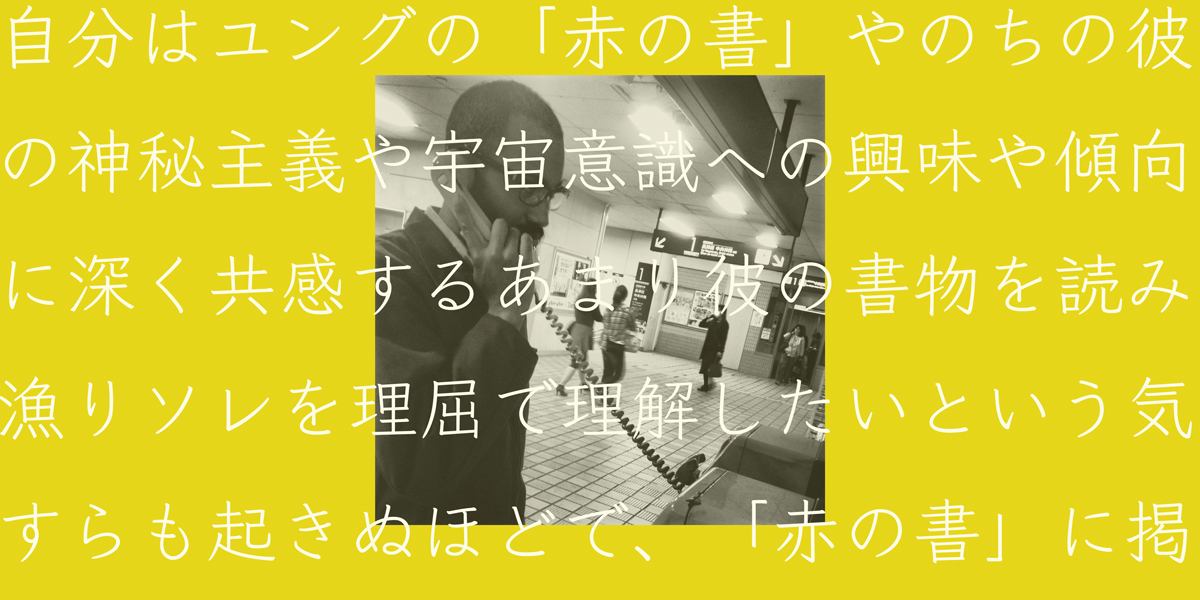
✴︎✴︎✴︎
安易な質問ではありますがフロイトの魅力とはなんでしょうか?
同じ心理学者ならば自分はユングの「赤の書」やのちの彼の神秘主義や宇宙意識への興味や傾向に深く共感するあまり彼の書物を読み漁りソレを理屈で理解したいという気すらも起きぬほどで、「赤の書」に掲載されている曼荼羅のような彼の描いた絵をぼんやりと眺めているだけで「ああ、こういう感じだろ、わかるわかる」といった具合に抽象観念で彼と共鳴し分かったような気になって満足してしまうのです。
幼き成孔様が治療を受け演技する姿を想像すると悲しくも笑いが止まりませんでした。同時に好奇心旺盛で早口でまくしたてる活発な成孔少年に会ったような気がいたしました。或いは本当に会っていたかもしれません。というのも自分の小説「僕という容れ物」で主人公「僕」の前世の人物「ギン」が若き日々を過ごしたのが1970年前後の横浜や新宿周辺です。この文章に綴った過去の日の内容がもし事実に近いものであったなら幼き日の成孔少年に当時会っていても不思議ではなかったという不条理なようでいて自分にはほとんど血が通う肉にでも触るようなリアルな妄想を部屋の窓の外を足早に過ぎ去っていく雲に投影してみたりしました。
✴︎✴︎✴︎
三十歳の夏。
この夏は物入りで、レストランのアルバイトに付け加え、家電量販店の大型家電配送のアルバイトを掛け持ちし、八月の休日は二日間でした。一日は雑用に奔走し、休日と言っていい日は一日のみ、唯一の休日を何をして過ごしたか全く記憶にないのも少し不思議ですが、眠っては起き、ひがなぼんやり過ごしていたのでしょう。
後半からは苦痛も何も感じなくなり、思考は停止し何も考えることができなくなりました。幸福もなければ苦痛もなく、ただただ160キロある冷蔵庫を屈強な男と二人一組で担ぎ、この肉体の脆さや儚さを微かに感じながらも、思考は真っ白、頭は空っぽで普段あれこれ考えすぎる癖があるわたしには却って好都合に思え、この虚空の時間が永遠に続けばいい、とさえ思いましたが夏も終わりに近づくと肉体は悲鳴をあげるかのように、夜、一日で唯一の食事を済ませると全身にじんましんが出るようになりました。二の腕の裏の刺青に至っては皮下に入っているインクが青く醜く腫れ上がり、九年前の精神病の症状が最も酷く酒浸りでもあった時分に入れた諺の刺青が「今こそこのように生きよ!」と主張しているかのようでした。顔半分の筋肉が痙攣しいつもの何倍も瞬きし、これを止める為に無に向かって満面の笑みを作る。この体調が治るまでに九月の一ヶ月間まるまる要し、その間何かをまともに思考したり自然な会話をするのも不可能に思われました。人に話しかけられても吃って挙句に場違いな返事をし、「おい何故わざわざ今そんな事を言うんだ。何の脈絡もないじゃないか?」「今の返事をしたのはお前じゃないのか?」「僕か? 僕が言ったのか?僕にもわからない」と脳細胞間でざわざわと言い合っているのを聞くような具合です。
夏になると何処からともなく御囃子の音がきこえて来るのは周知の風物詩ではありますが、この音を聞くとなぜか意識がぼんやりと滑らかな飴玉に包まれたような気分になってその音の源をこの目で確かめたくてしょうがない気持ちになるのです。どんな場所でどんな人々がどんな表情を浮かべて円陣を組んで盆踊りをしているのかを考えるといてもたってもいられない気持ちになりました(檀少年には危険な事ほど思い立ったら、いてもたってもいられずにやってしまう強迫性衝動がありましたのでこれは最も安全な強迫観念と言っていいでしょう)。
その音が出ている場所をこの目で見たいというイメージのそのまま真っ直ぐ先には幼少期の記憶に繋がっているのですが、いくら思い返してみても家族や友人と祭りに出かけた記憶がほとんどないのです。夏祭り会場に着くと遠巻きから眺め、それで一瞬気の済むような気がするのですが、街灯に吸い寄せられる蛾の如く、夏の蒸し暑い空気に浮かぶ提灯のおぼろな光に、少しひび割れた盆踊りの音楽に吸い寄せられて人混みに溶け込んで夏の日の人々を見て回りました。家族連れで金魚すくいをやってる人や小学生同士でつるみ射撃をしてはしゃぐ少年たち。出し物や食べ物を買うでもなくその場の空気に浸りきると、ちぢれた後ろ髪を引かれるような思いで帰路につくのでした。
なぜ祭りでは一人でいる記憶しかないのか考えてみると。
思えば片親の母は俺を産んでからすぐに長い間現場仕事をしており神奈川の自宅から都内や遠方の建築現場にもよく行っていたので帰りが遅い為、俺も早く帰ったところで家には誰もいないので、幼少期より五時のチャイムが鳴って友達が一人、また一人と帰って行った後、学校の校庭を徘徊して古い校舎の裏手に行くと金髪で長丈のベンチコートを着た中学生くらいの兄ちゃんたちがガスパン片手に奇声を上げて幼い俺を追いかけ回してきて退散、公園に行ってぼんやりと過ごしたり駅やスーパーやおもちゃ屋、駄菓子屋などを散策して、気が付くと出ている月をぼーっと眺めているうちに帰るタイミングを見失い、そんな日に限って母が早く帰っていたりすると怒られて。日々日頃そんな生活をする小学生でしたから夏休みの夕方は道草を食って帰るにはうってつけでした。
大人になってからは盆踊りの音を聞いた後に訪れる衝動への出席率は一割ほどに減少いたしました。
未解凍の冷凍ナンをかじりながら外を裸足で歩きまわり、裸足のダンと呼ばれ、雨が降れば水たまりで泳ぎ、ガイジンの呼び声には腕力で応え、保護者たちに嫌われる野生児でした。成孔様のネグレクトとはまた少し異なりますが、どうやら俺は鍵っ子になるには少し元気が良すぎてしまったようです。
成孔様は三十歳の夏の日をいかが過ごされておりましたか?
✴︎✴︎✴︎
〈MULTIVERSE〉
「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美























