亜鶴 『SUICIDE COMPLEX』 #08 僕が作品を展示する理由、あるいは展示という行為のもつ過剰な暴力性について
タトゥー、身体改造、ボディビル、異性装……絶えざる変容の動態に生きるオイルペインター亜鶴の、数奇なるスキンヒストリー。第八回は亜鶴が作品を展示する理由、そして展示という行為がもつ暴力性をめぐって。

<<#07「作品制作という行為はいかなる特権性をも持つ行為ではない」を読む
絶望的に埋めがたい他者との距離
僕が今の制作スタイルに落ち着いてから6年ほどになるだろうか。僕のスタイルとは、不特定の人物の正面からの顔をひたすらキャンバスに大写しで描き続ける、というものだ。周囲からは「アズ君デッサンうまい。描写力がある」なんて非常に有り難い評価を頂くこともあるが、それは事実ではない。僕はそもそもデッサンが大の苦手なのだ。
さらに言うと、僕は「これは何らかの障害なのでは」と疑うほど図面というものが読めない。折り紙の本、刺繍の本などをいくら読んでも「わぁ!図だぁ!」としか思えなく、冗談抜きにひとつも理解できないのだ。
思い返せばピアノだって10年近くも習っていたのに譜面が読めなかった。譜面上の各音に自分が決めた色を塗り(ドは赤、レは黄、ミは緑など)、色の配置として一小節ごとにデータとして頭に叩き込み、暗譜し、弾いていた記憶がある。
学校でデッサンや写生をした際も、大量の枝の生えたマングローブの原生林の様な図を描いてしまい怒られたことがあった。自分の中では見たものを見たとおりに描いているつもりなのだが画面の中で形成されていく図と現実の目の前にある光景が明らかに違ってきてしまう。違ってきていることにはさすがに途中で気づくので、その瞬間どうでも良くなってしまって描けなくなる。
そんな僕が正面から見た人の顔、しかもあえて表情を作らない顔を描くと言うことを続けているのにはそれなりに理由がある。

ニライカナイ(亜鶴/2019)
端的に言うと、人が好きだからだ。ただひたすらに、僕は人間が好きなのだ。
しかし、好きであるがゆえにどうしようもない距離を常に感じてしまう。その距離はなぜ生まれてしまうのか。この連載においても再三書いてきているように、僕はそれは身体を包んでいる皮膚ゆえだろうと考えている。
親にしてもそうだし、友達にしてもそうだ。長年一緒に過ごしてきた相手にしたって変わらない。同じ風景を見ているその瞬間にだって、そこには僕が見ている風景と相手の見ている風景、僕の感想、相手の感想がそれぞれ別個に存在する。そのズレは通常、言葉を介すことで調停が試みられる。介した言葉がお互いの距離を埋め、その時の共感度が近いもの同士が惹かれ合い、様々な形態のパートナーとなっていくのだろう。しかし、そうとはいえ言葉による共感にも限度がある。結局、どれほど言葉を尽くしても絶望的なまでに距離を感じてしまう。
あるいは、そうした距離を少しでも縮めようと、セックスをすることになったとしてもそうだ。そこにも頑然と皮膚の壁が存在する。これは身体の構造の問題なのでどうしようもないが、男の身体はこの点において、少なくともヘテロセクシュアルである限りにおいて、非常に不都合だろう。僕のペニスは堅牢な皮膚によって覆われている。一方、そのペニスを包むのは女性パートナーの柔らかな粘膜である。皮膚がどこまでも堅牢であり続けることに対し、粘膜は半皮膜であり、柔和だ。内外を行き来できるその粘膜の構造を、僕はいつも非常に羨ましく思う。
僕は何を以てしても何一つ体内に取り込むことは出来ず、いつも皮膚が邪魔者として存在している。本当であればドロドロに溶けてしまい。完膚なきまでに一体化もしたい。あるいは小宇宙の塵となって一緒にコスモの中を浮遊したいとも思う。食人が可能なのであれば相手を食べることで、せめても我が体内に、皮膚の内に相手を取り込みたい、なんて気持ちにもなる。それが不可能なのであれば、最初から血のつながった家族であったならどれだけか良かったのに、と思うことも多々ある。
そうありたいのにそうあれないというアイロニーが、多分、僕をキャンバスという画面へと向かわせ続けているのだと思う(あれ、ここまで書いてみて思ったのだけど、その線で考えるのなら、前回に一蹴した「キャンバスは皮膚の再現である」という論調も、あながち間違いではないのかもしれない)。そして、相手ともっと深く共感したいと僕が感じるとき、あるいは相手の知りえない心象を想像するとき、僕がその手掛かりとしてきたのが顔なのだ。
幼少のころから人の顔をよく見ていた記憶がある。自宅に訪れた業者のおじさんの作業する手元ではなく、僕はその顔を見ていた。母の開いているトールペイントの教室に通っていたマダム達の絵よりも顔に興味があった。誰かが何かをしている最中の表情に、僕は今も昔も単純に惹かれている。心象から表情を想像するのではなく、表情から心象を想像することに僕は興味があり、だから僕の描く顔はいつも無表情なのだと思う。

Night Walker(亜鶴/2019)
また、身も蓋もないことを言えば、僕が正面からの顔を描き続けるようになった当時、インスタグラム上のとある絵画系のプラットホームアカウントでは顔をモチーフとした筆致の荒い絵画が日々ポストされ、言ってしまえば流行っていた。
僕は元より物体として顔というモチーフが好きだったことから、そういったTLを眺めるのも好きだった。しかし自分自身が顔を描くにはデッサン力があまりになくうまく描けないというジレンマもあった。だからこそ、なおのこと、それを描けるようになりたいと思ったというのが、僕が今のモチーフに向き合う具体的なきっかけだ。かつ、ハードルは高い方が好きという性格のため、描くからにはあえて難しい正面形の顔のみを描くことを選んだ、というわけである(空間表現における単純なテクニックなので理解してもらえるとは思うが、図像を描く、イメージする際は正面形でなく、たとえば横向きや少し斜めに向ける事で陰影が付き、立体に奥行きがもたらされる。それに対して正面からの直視の図像というのは描くにあたって込められる情報がどうしても少なくなる)。
現代美術というものを主戦場にするようになり、やれコンセプトだ、やれステートメントだ、というものが必要とされるようになったが、そうしたものはいずれも後付けに過ぎない。闇雲に制作を続けてきた結果、様々な発表の機会を得ることが増えてきて、自分にとっての「点」として分散させてきた事がやっと「線」として回収されてきているという感じだろうか。しかし本音では、大きなキャンバスに大きな顔! とても赤い! といったような、デカイものはデカイ、よってかっこいい! みたいな単純な話の方をより好んでいる。この辺りもアイロニカルと言えるかもしれない。
へたくそなルービックキューブ
ここで、僕の作品制作のプロセスを少しだけ説明しておく。
僕のアトリエスペースは劇的に狭い。写真の通り、作業出来る範囲は2畳に満たない。そこに様々な画材をぶちまけ、ゴミ屋敷の住人としてその空間を支配している。狭いこと自体は慣れているし、苦にはならない。ただ、一方で現実的な問題として、引きの視点で制作物を見ることができないとという問題もある。

そこで、まずはひたすらに手作業で絵具、スプレー、パステルと画材を使い分け、画面を組み上げていく。そのアナログな工程の中で描きかけている画面の屋台骨がある程度見えてきた段階で画面を写真に撮る。その写真をアプリで反転させる。
アナログ作業の中で唯一システマチックな作業を組み込むのがこの瞬間だ。
人間の目とは不思議なもので見ているモノのズレ、ブレを知らない間に脳内補完する機能を持っている。デッサン力のない僕にとって、この脳内補完は不必要、というか余計な機能だ。だから、iPhoneを使い画面を反転させる事で補完されている脳内図像を再度、元のブレている状態に戻す。そうすることで、デッサン力の欠落を補うのである。
反転された画像と実際の画面を見てそのブレを探す。探しながら実際の画面上の図像修正のために奔走する。そして次の一手を加えていく。
ある程度の段階になると、この一連の行為の繰り返しとなる。そのため、僕の携帯のカメラロールにはパッと見ただけでは何がどう変わっているのかは分からない程度の差しかない、ほぼ同じ画像が連続して並ぶこととなる。このように、ひたすらに画面と交渉を続けていく。
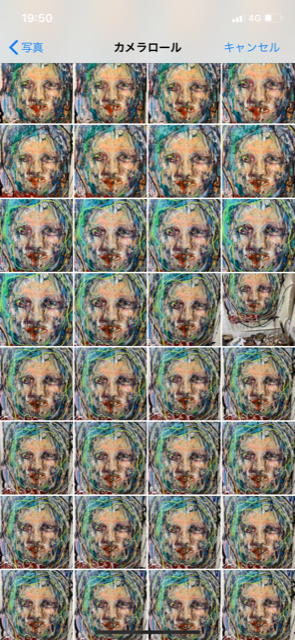
その過程のある段階でメインモチーフである顔から離れ、今度は背景となるサブモチーフにも注力し始める。もちろんその最中だって反転作業は延々と繰り返される。
追加されるモチーフは様々だ。花であったり、その時々の心象風景であったり、文字であったり、とにかく僕の皮膚内に堆積させていたアイテムを僕というブラックボックスを通して出力していく。メインモチーフを正面向きの不特定の個人の顔と定めてしまっている以上、制作はかなりの縛りプレイである。もちろん、僕なりの規範を毎度壊さなくてはならない。しかし、ルーティンからどのようにズラしていくかは、描き始める前には決まっていない。

唯、巻き込む事でしか生きられず、尚も狂う事さえ出来ず(亜鶴/2019)
僕は制作を開始するにあたって、最終完成形などを想定したことがない(想定したってまったく違う終着点にしか辿り着けないのは知っているし)。あるいは、アタリだって画面の中に丸を1つ描くだけだ。エスキースだって作ったことがない。
よく他人に制作工程を説明する際に使う表現なのだが、僕の制作のプロセスはへたくそな人のやるルービックキューブのようなものだと思う。一辺の色を揃えてしまったらそこにどうしても固執してしまいがちだ。だからこそ、アプリを用いることで、あえて強制的にシェイクしていくのだ。
制作を開始した瞬間におおよそ完成の形が分かる、完成のタイミングが読めてしまうという人もいるだろう。
しかし僕は6年ほど同じスタイルで、顔という同じモチーフを使い制作をし続けているというのに、いまだに目の高さの位置も間違うし、鼻梁の高さだって誤ってしまう。陰影の付け方もイマイチ分かっていない。なんなら毎度同じところで失敗していて、その失敗にだって画像反転することでやっと気づけるのだ。しかし、もし自分自身で僕の手癖を理解してしまえば、僕の怠慢な性格上、テクニカルなところに引っ張られてしまうだろうし、さらにはテクニカル一辺倒になってしまえば、逆に僕のテクニックのなさが、白日の下に曝け出されてしまうだけだろう。
だから、今のままできっと良いはずだ。
そう信じて、明らかに崩れたデッサンの構図から、どのように図像を立ち上げなおしていくかということを、延々と繰り返している。
メインモチーフ(顔)を先に置き、サブモチーフを描く。そこからメインとサブとの関係性を心地よい範囲にまで昇華する。周囲との関係を調整しつつも過剰に組み上げていく。時にお気に入りだったにしても一気に消してしまって全てを下地として再度組み込みなおしてしまう事だってある。そう思えばこの制作方式自体が僕の生き方とほぼ同じなのかもしれない。

Life(亜鶴/2019)
展示という行為のもつ拭えぬ暴力性
前回と今回の二回にわたり、絵について書いてきたが、自分にとって絵を描くということが何なのかはいまだに分からないままだ。ではなぜ制作をするのか。いや、制作をするだけでなく、なぜわざわざ発表の場を設けたりもするのか。制作の欲動の源泉が自己メディテーションを目的とするのであれば、粛々と自室内で制作をし続けるだけでよいのではないか。
多分、僕は制作を通し、モノを作り発表をすることによって、他者との間に何らかの関係性を強制的に持とうとしているのだと思う。強固かつ堅牢に守られた皮膚の内側から何かしらを外界に発することによって、要は強引に自身の制作物を見せつけることによって、相手の「LIFE」の一部に僕の制作物、果ては僕の「LIFE」を取りこませよう、「見せつける」という手法によって干渉させてしまおうというわけだ。前回、鑑賞の瞬間に僕は存在しなくて良いと述べたが、そうとはいえ、確実に作品の背後に僕は存在してしまっている。だからこそ展示という行為は、否応なく過剰な暴力性を帯びている。
その意識は刺青を彫る上においても同じだ。刺青もまた暴力性を伴う。そうした暴力性を踏まえた上でも、他人の「LIFE」に干渉をしたいのは、きっと僕自身が干渉されたいからに他ならず、要するに僕はずっと皮膚内の孤独から解放されたいと願っているのだ。
そしてもし僕が誰かに干渉するのであれば、その相手の持つ何らかの悩みであったり、苦であったりを全て焼き切り、僕が全てを抱え込んで死にたい、だなんて途方もないことさえ思ったりもする。しかし、現実というものは難しい。逆に僕自身が周囲の悩みの種になってしまっているということも痛いほどに理解している。そう思うと、ただ苦しくて、自分を恨めしく思う。ただ、こればかりは頭を抱えていても仕方ないのだ。粛々と制作をし続けるしかない。
僕はもとよりかなりのアナログ人間である。泥臭いのが似合っているとも自負している。だからこそ一手一手、非常に手間のかかる方法を以て、僕自身の世界を皮膚内から少しずつ拡張し、恥ずかしながらも世間に干渉しようと足掻いている。果たして、この先どうなることやら。

The Vase(亜鶴/2019)
〈INFORMATION〉
亜鶴・個展「Pachydermata」
2019.11/4〜13(会期中無休)@MEDEL GALLERY SHU
亜鶴の個展”Pachydermata”が2019年11月4日より10日間、東京は有楽町の帝国ホテル内のギャラリー【MEDEL GALLERY SHU】にて開催される。キュレーションは飯盛希。初日である4日は亜鶴も在廊予定。https://medelgalleryshu.com/
〈MULTIVERSE〉
「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー
「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー
「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”
「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー
「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る
「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎
「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美






















