神本秀爾 『History Hunters ラスタファーライの実践』 #02「キングストンから15キロ、《ボボ》のコミューンを訪ねて」
文化人類学者・神本秀爾によるジャマイカ・レゲエの旅。ラスタファーライの歴史と実践を追う。大学を卒業し院生となった神本は、再び訪れたジャマイカで、下界から切り離されたラスタ宗派《ボボ》のコミューンを訪問した。

過激で敬虔なラスタ宗派「ボボ」
そうこうしているうちに4回生になった。学部に入学する前から大学院には進学してできることなら大学に残りたいと思っていたのだけれど、専攻した美学とか芸術学の関心はかなり自分のものとはズレていたので、美学とか芸術学を続けるのは正直厳しいと思っていた。
結局、僕は学部卒業から2年後の2005年に大学院に進学し、文化人類学の講座に所属した。文化人類学にも他の分野と同じようにいろんな関心や側面があるのでひと言では言えないが、当時の僕にとっては、西欧近代批判とか自文化中心主義批判とか、世間の常識と距離をとっているように見えたスタンスが良かった。なにより、興味のあるところに堂々と長くいることができる学問だというのが一番の魅力だった。指導教員は南インドの宗教をはじめ、セクシュアリティや軍隊など色々なことをやる人だったのだが、研究室に相談に行ったときに、対象はなんでもいいと言っていたこと、修了生にはタンザニアのラスタのことをやった先輩がいたのが決め手だった。
修士課程は2年間だが、そのうち半年ぐらいはフィールドワーク(現地調査)をすることが期待されていた。修士1回生のときは授業をある程度取らなければならないので、たいていの学生は夏季休暇に、来年度の本調査に向けて予備的な調査をおこなう。
僕が調査の対象にしたかったのは、正式名称をEthiopia Africa Black International Congress、通称ボボと呼ばれるラスタ宗派だった。だいたいのラスタはドレッドをこれ見よがしにしているのだが、ボボのラスタはドレッドをターバンで覆っていて、そういう「他と違う」ところが好みだった。そして、ボボを自称していた(一般にもボボと理解されていた)SizzlaやCapleton、Anthony Bといったシンガーたちの音楽も好きだった。
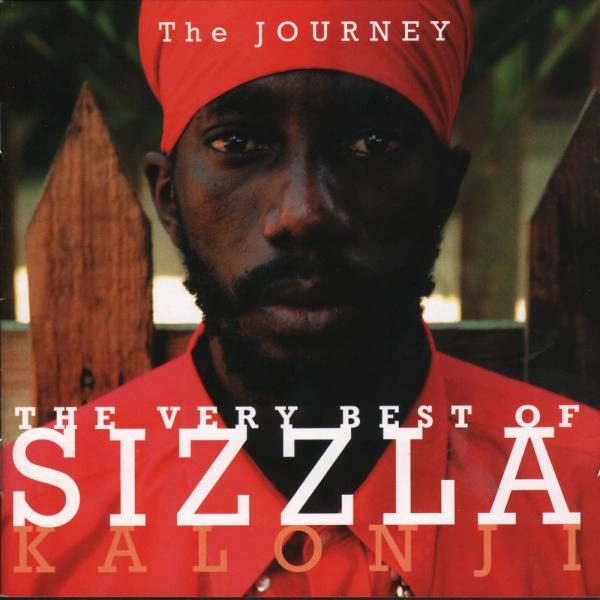
The Journey – The Very Best Of Sizzla Kalonji
彼らが、ハイレ・セラシエの偉大さを称えるメッセージと、「バビロンを燃やせ」というような過激な言葉を織り交ぜた歌を次々リリースしていたことや、DVDなどで見た、観客の盛り上げ方などもとても魅力的だった。「宗教的な敬虔さと過激さは、どのような関係にあるのだろうか」というのが僕の素朴な疑問になった。そういうこともあって、まずは、SizzlaのBobo Ashantiというアルバムを通じて知っていた、ボボのコミューンで受け入れられ、彼らの世界を知っていきたいと思っていた。
2回目のキングストン
2005年の8月末、2回目のキングストンに行った。あまりに準備と知識が不足していた2001年の反省を生かして、効率よくキングストンの情報を集めるために、日本人向けのゲストハウス、アイシャハウスに滞在することにした。
夏は長期休暇を取りやすいので、10ぐらいあった部屋はたいてい満室だった。コンクリートの建物は、昼間は当然暑く、夜は夜で熱がこもって、天井のファンだけでは寝苦しい夜が続いた。水不足とのことで、しばらく昼間は水も使えなかった気がする。客は男中心でサウンドマンと学生が多かった。網シャツもとても流行っていた。サウンドマンも、たいてい普段は別の仕事をしている場合が多いが、ここではサウンドマンというアイデンティティを全面に出しながら過ごしているように見えた。日本食を持ち込んでいる人が多かったので、近所のスーパーで買った食材と合わせてカレーをつくって大勢で食べたことなどもあって、合宿のような気分になることもあった。
ボボのコミューンは、キングストンの中心部から15キロほど海沿いの道を東に行ったあたりの山際にある。ボボ・ヒルとも呼ばれていた。ただ、ボボ・ヒルにいきなり行っても何ができるかわからなかったし、いきなり行って受け入れられなかったら、院に進学した第一の目的を見失いかねない。なにより調査計画を練り直す羽目になる。そう思ったので最初はあせらず、街中をぶらぶらしてはラスタっぽい人に話しかけて、ボボ・ヒルについての情報を集めはじめた。決められたエリアを行き来するルート・タクシーやハイエースを改造したミニ・バスの乗り方も覚え、ダウンタウンやパピンなど、ターミナルになっているエリアにも行くようになった。パピンは観光客にとっては用事があるところではないけれど、近くにあるUWI(The Univerisity of the West Indies、西インド大学)の図書館や本屋に用事があった僕はよく行った場所のひとつだ。
UWIには、ラスタに関する書籍を出版していたBarry Chevannesがいた。彼のRastafari: Roots and IdeologyやRastafari and Other African-Caribbean Worldviewsは院試の準備をしている頃には手に入れていて、研究計画書の作成にも参考にしていた。彼と面識のある先生は日本にいたので、紹介をお願いした方が良かったのかもしれないけれど、彼には直接会いに行った。
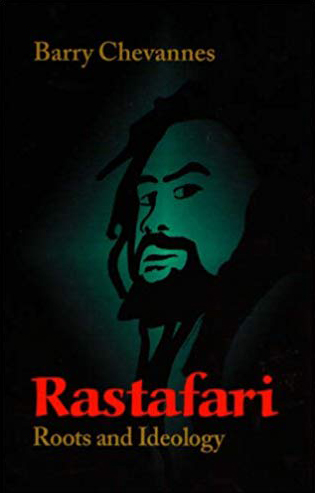
『Rastafari: Roots and Ideology』by Barry Chevannes
文化人類学のフィールドワークには問いを探しに行くような側面がある。どれだけ現地に関する資料を読み込んで想像をたくましくして、今後やりたい議論のことを考えたとしても、現地に身を置かないことには、机上の空論になってしまいかねない。予備調査とは、もちろん、ある程度関連資料は読んでから行くものだが、現地の空気のなかで、自分に解決できそうな問いを見つけるという面が強い。そういうこともあり、Chevannesに会ったときは、自分が何をしたいともはっきり言えず、簡単な自己紹介程度で終わった気がする。ただ、彼に会ったことで、研究者として、ラスタあるいはボボにちゃんと向き合いたいと宣言したような気分になって、オフィスを出たあとは、すがすがしい気分だった。
下界からは遮断されたボボ・コミューン
ジャマイカ滞在をはじめて10日ほど経って、ボボ・ヒルへ行った。ボボ・ヒルの最寄りのバス停、ナイン・マイルまでは簡単に行けるのだが、バスを降りてコミューンまでの1マイルほどの道が危険だと聞かされていたので、最初はタクシーで行った。街なかを抜けて、島の南側の海沿いの道に出て、ノーマン・マンレー空港のある右側に折れず、そのまままっすぐ海沿いを走る。左手に広がる、山の木々の力強い緑色は、やはり自分が南の国に来ていることを実感させた。
バス停をこえたあたりで左折すると、コンクリート造りの家のあいだに、トタンを壁としても使っている簡素なつくりの掘っ建て小屋のような家が立ち並んでいる。その1マイルほどをまったく無関係の外国人がいきなり歩くのはたしかに不自然で、場合によっては危険だ。そんなことを思いながら年季の入った日本車のタクシーで家々のあいだを通り抜け、最後、乾いた川沿いの急な山道をのぼり切ったところで視界が開け、少し先にボボのコミューンはあった。

当時の門。数年後にははるかに立派なものになっていた。
ラスタ・カラーで塗り分けられた建物や柵はとてもきれいだった。まわりもとても静かで、空気が違うように感じた。単純に「下界とはまったく違う」という感想を覚えた。キングストンの喧騒のなかにしばらくいたことや、タクシーでは大きな音で音楽がかかっていたことも関係しているだろうけど、それだけではない。ふもとの住宅地とは比べものにならない、明らかに別の世界が目の前に存在しているという興奮を覚えた。初めて実感として目の前に聖なるものを見たからこそ、「下界」とはどのようなものを指すのか、逆説的に理解させられた瞬間だった。
連れて来てくれたドライバーが門を叩き、中に入れてくれと言ってくれた。しばらく経ってターバンで頭頂部を覆ったラスタが顔をのぞかせた。彼らは一般的な英語とは違う現地の言葉、パトワでやり取りをしていたので、彼らが何を話していたかあまり理解できなかったのだが、割とすんなり入れてもらえそうだということは分かった。
いちばん手前に建つゲート・ハウス(門衛所)に恐る恐る入った。広くない建物の奥に受付のような場所があり、そこからこちらを見ているラスタがいた。名前や住所を聞かれ、その答えがノートに書きこまれていく。日本の住所なんか書いても何にもならないように思ったが、そうするのが決まりだということだった。用件を聞かれたが、なかに住んでいる誰かに会いに来たというわけでもないので、自分はラスタについて勉強している学生で、中を見学させてほしいと答えた。この先、良い関係が築けるかどうかわからないし、なにより目の前にいる人に対して、研究(research)という言葉は不適切だとも感じて、勉強(study)という言葉を使った。
ただ、1996年に出版されたバレットの『ラスタファリアンズーレゲエを生んだ思想』のあとがきで柴田佳子さんが書いているように、ボボへの観光客や見学者、研究目的での訪問者というのは少なくなく、80年代から彼ら目当てに小商いをするラスタもいたようなので、ゲート・ハウスのラスタにとって、僕はたまに来る観光客のひとりぐらいに見えたのだろう。
プリンス・エマニュエルの独創性
敷地の中を案内してくれるというラスタが出てきたので、ゲート・ハウスで荷物を預け、彼についていくことにした。ラスタは好きじゃないと言っていたドライバーは、ゲート・ハウスのソファに座って待っておくと言った。傾斜のある細い道を彼について歩く。ゆっくり歩いても、真夏の日差しにさらされているので、信じられないくらい汗をかいた。ロイヤル(royal)・キッチン、ロイヤル・レストラン、オフィス、エルサレム・スクールなどと紹介される。一部きれいな建物もあったが、そのあたりで切ってきたような木とトタンなどの廃材を組み合わせて作った建物が、ロイヤル(王の、王国の)をつけて呼ばれているのを聞いて、そのギャップに驚いた。

コミューンからは海が見える。
途中で何人かとすれ違った。僕を案内してくれたラスタはそのときに、何か言い、たまに左手を曲げて自分の右胸の上のあたりにあてたり、額の前に手を当てる敬礼のようなポーズをとったりしていた。彼が口にした言葉のいくつか、”Love”とか”Honorable”と言っているのは聞き取れた。”Love”の意味は愛で、”Honorable”は尊称なので、いくつかの建物に”royal”をつけていたのと同じように、彼らが自分たちや自分たちのいる空間に自分たちを高めるような緊張感を帯びさせているように感じてさわやかな気分になった。このようにして、僕は、それまでの自分の想像の範囲をこえた次元でまわっている世界の入り口に来たことを実感した。
それでは、この世界は、その他の世界とどのように異なっていたのだろうか。まず、コミューン自体がラスタのルールを前面に出した聖なる空間として外界と分けられている点で異なる。しかし、ボボには、他のラスタとも大きく異なる世界観があり、その世界観がボボのコミューンをより一層他の世界から浮き上がらせている。
この世界観は、この宗派を創始したプリンス・エマニュエルという極めて独創性をそなえたラスタの思想に由来している。その独創性の現れのひとつが、前の方で書いた、ボボのラスタはドレッドをターバンで覆うという決まりだ。同じように視覚的にわかる違いとしては、ラスタ・カラーの並びが違うこともあげられる。ハイレ・セラシエの治めたエチオピア国旗と同じように、上から緑、黄、赤という並びが一般的なのだが、ボボの場合は上から赤・黄・緑と逆である。そして真ん中に五芒星がある。これは、ガーナ国旗の柄である。

ボボの崇拝対象(左からガーヴェイ、エマニュエル、セラシエ)
別の回にあらためて詳しく説明するが、このような差異の根源を辿っていくと、ボボでは、ハイレ・セラシエだけでなく、プリンス・エマニュエル、マーカス・ガーヴェイも崇拝しているという点にたどり着く。ガーヴェイはセラシエの戴冠を予言したというのが、ラスタの世界では定説なので、他のラスタもガーヴェイを崇拝とは言わないまでも重視している。つまり、エマニュエルの崇拝という点が、ボボを他のラスタと分ける根本にある。ボボのコミューンはエマニュエルの世界観が具現化した空間なのである。
文字にすると500字にも満たないこれぐらいのことも、最初はほとんど分からなかった。ただ、やはりこの世界をもっと深く知りたい、とあらためて思いを強め、その日はコミューンを後にした。

正装のひとつを見せてくれた信徒。
〈MULTIVERSE〉
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「REVOLUCION OF DANCE」DJ MARBOインタビュー| Spectator 2001 winter issue
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”





















