遠迫憲英 『神々のセラピー|サイケデリック精神医学』 第一回「先生が暴れたら誰が先生をブチ込むんだ?」
精神科医・遠迫憲英が精神世界の迷宮を描いた虚構手記。音楽とドラッグと精神分析。交錯する現実と妄想。閉鎖病棟では今日も患者たちが踊っていた。
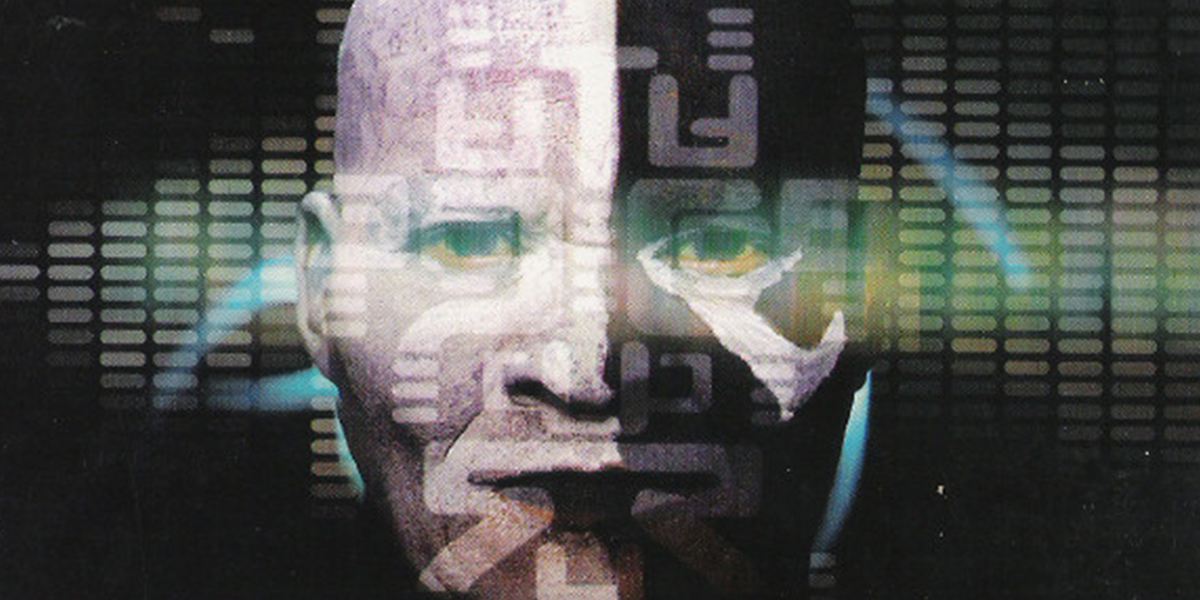
この物語はフィクションである。
そしてこの世界も仮想現実(フィクション)である。
この世界が、俺の想像の産物でしかないのなら、この文章は結局この認識主体である俺に向けて書かれたものに違いない。ここに書かれた世界は、ただ閉じた俺という宇宙の、泡のように生まれては消えてゆく、無限の可能性の一現実に過ぎない。あなたの宇宙が、あなたの死とともに誰にも気づかれず終わりを迎えるように、俺の世界のリアリティも、俺の消失とともにあなたとは関係なくこの世から消え去るかもしれない。
ただもしかするとこの世界は、俺一人の孤独な一人舞台ではなく、あなたとどこかで出会い、俺の記憶を受け渡せる愛の持てる世界かもしれない。そのために書いている。
ある幻覚をみたことがある。いまこの世界は俺の主体が形成している世界なのだが、あまりにその主体の頭が悪いために、この世界は愚鈍さに満ち溢れた世界になっている。ナルシズムに満ちた俺は、自分の自己愛のために他人を利用した世界を生きている。治療者としての仮面を被りながらしたり顔をして。高位の賢者たる友人たちは、その愚鈍さに憂い、俺とこの世界を見守ってくれているというヴィジョンだ。
世界は俺の愚鈍さの程度に自由であり、俺の愚鈍さは世界中の人々の苦しみの源である。この世界の誕生と消失の中で苦しみ成長しながら今生を全うすることが、俺への神々のセラピーであるという気付きだ。それは絶望的に優しい。
果たして俺は狂っているだろうか?
彼らと我々を隔てるもの
自分のことを語りたい、しかし語りたいことなどなにもない。ただ意識の独白的な思考の流れをこの世に繋ぎ止めたいだけなのだ。すでに客観性などは体の良い言い訳をするための手段に過ぎぬとうっちゃってしまった。この世に存在する自意識という牢獄からのレポート。俺に綴れるとしたら、そのようなものしかないのだ。
しかし、その牢獄の格子越しの眼差しも、人類の数だけあるのであって、それぞれの人生の独自性の中には他人が面白いと感じるものもあるかもしれぬ。俺の名前は須佐現、精神科医だ。俺が日々相手にする狂気を内包する人々、そして彼らを眺める俺の眼差しの牢獄からのレポートも、他人には物珍しく、興味深いと感じられるかもしれない。
今牢獄といったが、実際はそのような重いものでもなく、頭蓋骨から両目で眺めるこの世界の認識の話をしているのであって、たとえば俺の自意識はドラッグで自他との境界が完全に崩壊したことがある程度には自由を知っている。だからコミュニケーションの断絶を憂いているというわけではなく、話したいのはもっと愛に満ちた交流の話だ。俺とあなたがこころの底で繋がれるような可能性に満ちた話をしたい。それが幻想であろうがなかろうが、そんな気持ちになれる相手と出会いたい。
俺の仕事は毎日訪れる数十人の精神疾患を有した人々と交流し、一緒に絶望し、希望を与えることだ。希望とは具体的な言葉のによって与えれるのではない。患者の目の前に現れる精神科医という存在が示す根拠のない生への自信に満ちた態度によって与えられる。俺が患者の前で狂気にひるまず、今朝食べたハムエッグの外観や滋味について語り合うように、患者と語り合える事が重要だ。なぜなら、苦痛に満ちたその妄想の、パニックの、抑鬱の背後に広がる家族関係や人間関係、トラウマや隠匿された秘密の、複雑に絡み合った物語の糸をたぐりながら、その隙間のもつれをほどき、シンプルな物語に変換し、患者と俺の間で取り組み可能なものに再構成する必要があるからだ。
よく患者との交流について負担ではないかと聞かれることがある。おそらく質問者の心理には、この普通ではない仕事に対する覗き見的関心と、自分がそういう面倒な立場に陥りたくないという気持ちが入り混じっているのであろうが、実際はあまり負担ではない。むしろ楽しんでいると言っていい。もちろん解決しようのない問題を独りよがりに持ち込んで、協力して治そうとするつもりもない無礼な患者もいるので、そういった方には丁寧にお帰りいただくとして、大概は自分もまた相手の立場に入り込んで相手の人生のトラブルを追体験している。医師として適切な表現であるかは分からないが、それは実に刺激的な体験であり、楽しいことなのだ。もちろん、それは単に俺が追体験しているつもりになっているだけとも言えるが、その思い込みが治療の重要な鍵になってゆく。
他人の人生を追体験してゆくこと、目の前の相手の身体に自分が乗り移り、相手の感情や立場、状況をバーチャルに体験しようとすることの面白さが、この仕事の醍醐味だ。自分と相手の間に展開する互いの内的世界が交流する治療空間。俺がそのチューニングを行う上で手掛かりにしているのは、ドラッグによる変性意識状態と、ドラッグのバッドトリップによる様々な精神疾患の疑似体験の経験値だ。疑似体験といったが、実際に病になっていたのだ。ありとあらゆる精神疾患に。ドラッグによって自分の中に闇を取り込んで、それを乗り越えることで成長しようとする。ジャンキーとはそういう生き方のことだ。
20数年前、イクイノックスのレイブで、JUNO REACTORの神がかったライブに吹き飛ばされ、アシッド3枚とスピードとマリファナをチャンポンして完全に精神病状態になった。アシッドによる意識の拡張と自他境界の崩壊がスピードによって加速され、スピードが切れたことで急激にバッド・トリップに突入、自分が誰であるかがわからなくなった。同時に、周囲は自分の人生のすべての秘密を知っており、今自分が思考している内容、その恥のすべてについて共有されていて、そのネットワークの根幹をなす、コミュニケーションの隠された秘密については、自分にだけ秘匿されているという感覚に襲われた。すべての秘密は開示されているのに、自分だけがその秘密を理解できない、という惨めさに打ちひしがれた。限りなく落ち込み、誰も信じられず、生きていることさえも耐え難く、しかし青い空には入道雲がもくもくと立ち込め、様々な巨大な動物の姿をして虹色に踊っている。完全に狂っていた。
後にそれが妄想知覚、被害関係妄想だと知り、それを自己治療することが自分の精神科医としての最も最初の作業だった。その作業には数年を要したが、その数年間に統合失調症の患者達と過ごした時間は自分にとってかけがえのない体験になった。解体した思考の中、妄想世界を精神病院の保護室の中で過ごす彼らと、同じ保護室の中で過ごし、彼らの宇宙の中で語らい、同じ時間を共有することが、当時の自分にとって必要な時間であったのだ。
彼らが抱く妄想や幻覚とは彼らの内的な不安の外世界に対する投影である。不安のあまりの強さによってそれが自我のキャパシティを超えて外部に投影され、外部から襲ってきているように体験されているのだ。これは単なる分析ではなく、実際に自分の肌身で実感したことである。さらに、彼らと関係性を構築するためには、彼らの世界と自分の内的世界をクロスオーバーさせ、彼らの世界を旅し、彼らの世界に俺の安心の基盤を挿入する必要があった。そうして互いにとって掛け替えのない存在になることで、彼らが次第に正気を取り戻してゆくということも知った。それは医者から一方的に与えられるものではない、まさに医師と患者の相互作用によるものだった。
そういった患者たちをその当時は100人くらいは担当していた。保護室に隔離されるような、最重症の患者も10人程度いただろう。そんな時間が10年以上続き、その間に俺は癒やされていた。レイブ明けのバキバキの頭で病棟で仕事をすることも多々あった。男性の慢性統合失調症患者が50人収容されている閉鎖病棟を担当していたこともあったが、そのサイケデリックに高密度な病棟は、もっとも優れたトランスパーティのフロアの中心と全く同レベル、あるいはそれ以上にテレパシックな空間であったことを告白しておこう。
ところで、こう書くと彼らがあたかも極めて特殊な連中かのように思われるかもしれないが、実際のところ、そんなことはない。実は狂気のレベルにおいてさえ、彼らと我々を隔てるものはなにもないのだ。互いに対する無理解と恐怖がコミュニケーションを寸断する。そしてその恐怖は相手に投影され、恐るべき対象として認知される。それはこちら側の内面にある未熟な問題にすぎない。精神病患者のほうが我々よりも実はオープンだ。
考えてみてほしい、50の独自の妄想宇宙をもった患者たちが閉鎖された空間で毎日を過ごす状況を。彼らは互いの宇宙を否定、侵犯せず、互いを認めあって生活している。他人の宇宙については限りなく寛容だ。それはイコール自分の宇宙の安全を保証されることであるからだ。彼らの世界ではそれが理解できないと生きてくことができない。俺は医師というもっとも権力や権威を持った存在としてそこに参入するので、彼らと同一の目線でとはいかなかったかもしれないが、精神の深い部分において他者との交流の秘密を彼らから学んだ。
ある時、患者から言われた言葉がある。
「俺たちは狂って暴れたら、保護室にブチ込まれるけど、先生が暴れたら誰が先生をブチ込むんだ?」
俺がもっとも患者たちに潜っていた頃の話だ。
※この物語はフィクションです。読者に違法薬物の使用を勧めるものではありません。日本における違法薬物の使用は、麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法、大麻取締法によって処罰されます。
〈MULTIVERSE〉
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「REVOLUCION OF DANCE」DJ MARBOインタビュー| Spectator 2001 winter issue
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”






















