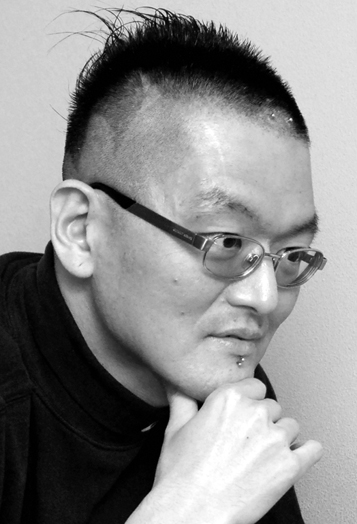ケロッピー前田 『クレイジーカルチャー最前線』 #01 カウンターカルチャー視点から読み解く『ホモ・デウス』 人工知能台頭で現実味を増すサイボーグ時代の到来
驚異のカウンターカルチャー=身体改造の最前線を追い続ける男・ケロッピー前田が案内する未来ヴィジョン。現実を凝視し、その向こう側まで覗き込め。未来はあなたの心の中にある。

人類の歴史を再び読み直すこと
過去において、歴史といわれるものの多くは、政治や経済、あるいは文化と呼ばれるものの変遷を辿っていくことで描かれてきた。
冷戦終結と東西ヨーロッパ統一を経て、世界のグローバル化に伴い、歴史そのものをもっと大きな人類史として描き直そうという動きがあった。そんな中で、世界的なベストセラーとなったのが、ジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』だ。そこでは西洋人が世界の覇権を握ることになった理由を文化や人種の優劣でなく、地理的気候的な条件や科学的な見地から読み解いていた。たとえば、植民地政策に伴い、中南米で多くの先住民が西洋人が持ち込んだ病原菌で死に絶えたことについて、免疫を作るために重要な役割を果たす家畜を持っていたのかがどうかが、生き残りの大きな分かれ道となったとする見解など、非常に斬新であった。また、表記言語を持たなかった部族・民族の歴史についても注目している点で、遺伝子分析による人類史の研究が活かされていた。
ご存知の通り、世界規模の人類の遺伝子分析から、我々、ホモ・サピエンスがアフリカで誕生し、そこから世界中に拡散していったことが立証されている。また同時に、ホモ・サピエンスの拡散とともに世界中に存在したサピエンス以外のホモ種がことごとく絶滅してしまったことも事実である。ホモ・サピエンスが他のホモ種を皆殺しにしてしまったというのか?
そのようなホモ・サピエンスの強権的ともいえる生き残りの方法を読み解き、全世界で500万部以上を売る大ベストセラーとなっていたのが、ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』であった。ハラリにかかれば、農耕も貨幣も宗教も、すべてがホモ・サピエンスが唯一生き残るための戦略であった。
確かにそのことでホモ・サピエンスは現在のような繁栄を勝ち取ったが、同時にまた現代的な不幸も背負い込んでいる。つまり、「我々、人類は果たして幸福なのか?」という視点である。そして何より『サピエンス全史』の最も注目すべき点は、過去の歴史を総覧するばかりでなく、未来に待ち受けるであろう出来事にまで言及していることだ。そこで語られるのは、人類を超えるような人工知能、人類そのものの生物学的な改変、あるいは人類と機械の融合によるサイボーグの登場であり、その未来は一般的な現代人の想像力を超えている。では、我々は一体どうすればいいのか?
ホモ・サピエンスの身体に秘められた潜在能力

『ホモ・デウス』
(著・ユヴァル・ノア・ハラリ/訳・柴田裕之/河出書房新社)
世界が待ち望んだハラリの続編『ホモ・デウス』は、そうした人類の未来に焦点を置いて書かれたものである。
ハラリは、冒頭で人類は飢餓と疫病と戦争を克服したと解説する。そしてそれらが克服された今、人類の新たな目標は人工知能を完成させることによって人類自らが神のような存在になることだという。
もしもそのようなことが可能だとするならそれを実現することを止めることは誰にもできないだろう。とはいえ、いくつもの不安がつきまとう。
人工知能が人類を追い越してしまうとするなら、人類は機械の奴隷になるのか? あるいはいつか不要なものとして全滅させられてしまうのか? そして何より人類のこれからの命運を誰が決めていくいくと言うのか? 結局は人知を超えた人工知能に人類の総意を託してしまうことになりはしないか?
最終的なところで、ハラリは非常に楽観的だ。それはシンギュラリティの提唱者レイ・カーツワイルに似ている。恐るべき未来の到来を予言しながら、その暴走を警告しながらも、テクノロジーの進歩のさらなる加速を止めることはできず、日常的な態度や行動の変化でその進む道をより良く修正していくしかないという。確かに彼ら自身に本当の意味での脅威が及ぶことはないだろう。しかし、実際に人工知能に翻弄されるのは、もっと立場が弱く、社会の末端で生きる人たちである。
だが少なくとも未来において、今にも増して現実はもっと複雑でもっと過酷なものとして我々の目の前に立ちはだかってくる。その問題を国家や社会や企業が解決してくれるとはまったく考えられない。
自分たちの幸福は各自がそれぞれの責任において勝ち取らなければいけないだろう。そのためには、ハイテクノロジーな未来世界において、ハラリがいうところの「虚構」としての社会システム、つまりは農耕や貨幣や宗教が登場する以前の原始的な感性を取り戻していかなければならない。たとえるならば、ウィリアム・ギブスンが『ニューロマンサー』で描いたサイバーパンク、あるいはファキール・ムサファーが『モダン・プリミティブズ』という言葉で提唱したものである。
最後に言えるのは、これからの短い年月の間に想像を絶する大きな変化が人類に及ぶかもしれないということである。そんな時代を困難な現実として悲観するより、その行く末を見届けるためにも、我々自身がホモ・サピエンスの一員として、自分の身体に秘められた潜在能力に賭けてみても良いのではないかと思う。そういう意味では、『ホモ・デウス』は未来を明るく照らし出してくれているとも言える。とにかく、未来を楽しもう。
Homo Deus: A Brief History of Tomorrow with Yuval Noah Harari

『クレイジーカルチャー紀行』
(著・ケロッピー前田/角川書店)
Photo by Ryan O’Shea, Grindhouse Wetware/ノーススター
〈MULTIVERSE〉
「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性
「REVOLUCION OF DANCE」DJ MARBOインタビュー| Spectator 2001 winter issue
「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”